家督相続とは、旧民法に基づく遺産相続方法で、1人の長男もしくは長女が家のすべての財産を引き継ぐ制度です。現在では家督相続の制度は廃止されているものの、個別の事情によって家督相続のような遺産相続を望む人がいることも事実です。本記事では、家督相続の概要や現在の遺産相続との違い、家督相続のような遺産相続をする方法について詳しく解説します。家督相続を主張する人がいる場合の対処法も解説しているため、ぜひ参考にしてください。
地元の専門家をさがす
家督相続とは
家督相続とは、一家の財産をすべて長子が引き継ぐ相続の制度です。1898年(明治31年)から1947年(昭和22年)までの間に施行されていた旧民法で定められていましたが、現在すでに家督相続の制度は廃止されています。
しかし、なかには現在でも慣習として家督相続を続けたり、長男・長女が家督相続を主張したりするケースがあります。
家督相続についての理解を深めるために、下記のポイントを確認していきましょう。
- そもそも家督相続とは
- 現在の遺産相続と家督相続の違い
- 現在でも家督相続を適用するケース
詳しく解説します。
そもそも家督相続とは
1898年(明治31年)から1947年(昭和22年)まで施行されていた旧民法で定められていましたが、1947年(昭和22年)に施行された民法改正によって廃止されています。
そもそも家督相続とは、長男や長女などの長子が一家の財産をすべて引き継ぐ制度です。財産のなかには、戸主としての地位と権利、義務が含まれています。
不動産や金銭などの遺産についても長子にのみ相続が認められており、他の兄弟姉妹や被相続人の配偶者には相続する権利が認められていませんでした。
家督の考え方は鎌倉時代から定着し、長子による家督相続は江戸時代に確立されたと考えられています。ただ、家督相続は武家用の制度だったため、現代に合う制度とは言い難いでしょう。
ただし、地域や家系によっては、「財産は長男が引き継ぐべき」という考えも残っていることも事実です。
現在の遺産相続と家督相続の違い
現在、民法改正によってすでに家督相続の制度は廃止され、家族が亡くなると遺産相続をおこないます。
家督相続と遺産相続との違いを表にまとめました。
| 家督相続 | 遺産相続 | |
|---|---|---|
| 相続順位(相続する人) | 長子(長男または長女) | 原則、法定相続人 |
| 相続するもの | ・戸主としての地位と権利、義務 ・不動産や金銭などの財産 | 不動産や金銭などの財産 |
| 相続するタイミング | ・戸主が死亡したタイミング ・戸主が隠居生活を始めるタイミング ・女性戸主の入夫婚姻・男性戸主の婿入り婚のタイミングなど | 被相続人が亡くなったタイミング |
| 相続放棄の有無 | 容認されない | 容認されている |
より詳しく違いを理解するために、ここでは相続順位(相続する人)の違いと相続するタイミングの違いについて解説します。
相続順位(相続する人)の違い
家督相続と遺産相続においての大きな違いは、相続する人の優先順位が定められている相続順位です。
家督相続の時代、現在の民法と違って相続順位は下記のように第5位まで定められていました。
- 第一順位:被相続人の直系卑属で、原則長男または長女。年長男子を優先する
- 第二順位:被相続人が生前に指定した者、もしくは遺言で指定された者
- 第三順位:被相続人の父母または親族会が同籍の家族から指定した者
- 第四順位:被相続人の父母・祖父母など直系尊属
- 第五順位:被相続人の親族会が親族・分家の戸主、あるいは分家の家族などから指定した者
一方、現在の遺産相続における相続順位は、下記の通りです。
- 常に相続人となる者:被相続人の配偶者
- 第一順位:被相続人の子どもや孫などの直系卑属
- 第二順位:被相続人の父母や祖父母などの直系尊属
- 第三順位:被相続人の兄弟姉妹
このように、配偶者の立場が重視され、子どもが複数人いる場合には平等に財産を分け合うことが基本となりました。

相続するタイミングの違い
家督相続と遺産相続では、相続発生のタイミングや手続きにも違いがあります。
家督相続の時代、現在とは違って戸主の死亡以外でも家督相続が認められていました。具体的には、下記のようなケースです。
- 前戸主が60歳になって隠居となったタイミング
- 女戸主が入夫婚姻をして相手の男性が戸主となるタイミング など
入夫婚姻とは、女戸主と結婚した男性が夫として妻の家に入ることです。入夫が戸主となるケースも少なくありませんでした。
なお、前戸主の隠居によって家督相続をしたとしても、前戸主が死亡するまでは所有者変更のための登記はできませんでした。
一方、現在の遺産相続が開始するタイミングは、被相続人が亡くなったときです。登記手続きは、遺言書があればすぐに開始でき、遺言書がない場合は法定相続人との遺産分割が終わってから始めることができます。
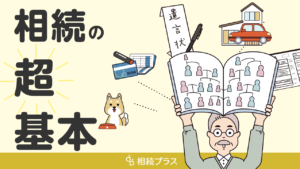
現在でも家督相続を適用するケース
昭和22年の民法改正によって、すでに家督相続は廃止されています。しかし、現在でも家督相続の考えを用いる場合があります。
それは、旧民法が適用された期間の相続登記が完了していない場合です。
相続登記が完了していない場合
旧民法が適用されていた期間中に相続が発生し、不動産の相続登記が未了のままの場合は、当時の相続関係に基づいて家督相続の形で登記手続きが行われるケースがあります。
現在の民法に従って相続登記をしようとすると、権利関係者が複数人にわたり遺産分割協議ができない可能性が大いに考えられます。しかし、旧民法の適用期間になるため、現在の民法に従った遺産分割が難しい場合には、家督相続の制度に従って相続登記を完了させることが可能です。
なお、家督相続によって不動産を取得する場合、遺産分割協議書の作成や相続人全員の同意の必要がありません。一般的な相続登記よりもスムーズに手続きを進められるでしょう。
家督相続に近い遺産相続をするための方法
相続事情は家族や資産の状況によって個別に考える必要があります。何かしらの事情によって長男や長女にすべての財産を引き継ぎたいという家督相続のような遺産相続をしたいと考えるケースもあるでしょう。
ここでは、家督相続に近い遺産相続をするための方法についてご紹介します。
- 遺言書を作成する
- 家族信託制度を利用する
- 遺産分割協議にて他の相続人の同意を得る
- 家督相続のような相続では遺留分に注意する
家督相続はすでに民法では認められていません。複数人子どもがいる場合には平等に財産を分けることが大原則であることを前提に、家督相続に近い遺産相続の方法について確認しましょう。
遺言書を作成する
遺言書では、所有している財産の引き継ぎ先について意思表示することが可能です。遺言書は、「誰にどれだけの財産を分けるのか」を決める法的効力を持っています。
遺言書がなければ、原則民法で定められている法定相続分通りに遺産分割されると考えておきましょう。しかし、遺言書では「長男にすべての財産を相続させる」などと指定することが可能です。
ただし、遺言書に法的効力を持たせるには、書式を守らなければなりません。特に、自筆証書遺言や秘密証書遺言で遺言を残す場合、作成日や自筆の署名、押印がなければ法的効力がないものとみなされてしまいます。
より確実に遺言を残したいのであれば、公証人の立ち会いのもと作成される公正証書遺言で作成することをおすすめします。
いずれにしても、遺言内容によっては法定相続人が納得せずに、他の遺産分割方法を話し合う可能性があるため、遺言書の作成前に専門家へ相談するようにしましょう。
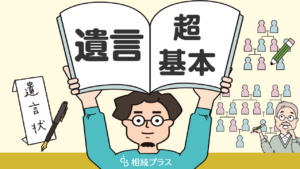

家族信託制度を利用する
家族信託制度を活用して、長男や長女に財産を集中させる方法もあります。家族信託制度とは、家族などの受託者に自分の財産管理を任せる契約のことです。
将来、認知症や障がいによって自分の財産が管理できなくなったときに備えるために活用されるケースが多いです。たとえば、父親が委託者となって子どもを受託者として財産を預け、父親が受益者となって利益を受け取るという設定ができます。
家族信託では受益者が亡くなったときの定めを設定でき、「長男を受益者として指定する」などと財産を集中させたい人を契約のなかで定めることが可能です。特に定めがない場合は、通常の相続財産と同様に相続されます。
ただし、家族信託の設計は難しく、家族や親族とのトラブルの原因になりかねません。当事者だけで内容を決めて契約を交わすのではなく、家族信託の実務経験が豊富な専門家に相談することをおすすめします。

地元の専門家をさがす
遺産分割協議にて他の相続人の同意を得る
被相続人がすでに亡くなっている場合に家督相続のような遺産相続を実現したいのであれば、遺産分割協議にて他の相続人の同意を得るために説得しましょう。
遺産分割協議とは、被相続人が残した遺産を法定相続人全員でどのように分割するかを話し合うことです。
たとえば、長男が家業を継ぐなどの理由で遺産をすべて引き継ぎたいということがあるかもしれません。このような場合、他の法定相続人が納得し、合意したことを証明する遺産分割協議書を作成する必要があります。
つまり、法定相続人のなかに1人でも反対する人がいると、家督相続のような遺産相続はできません。他の法定相続人が納得せざるを得ない理由がなければ難しいでしょう。
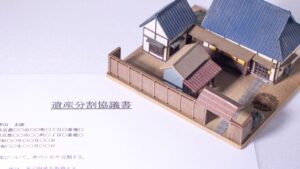
家督相続のような相続では遺留分に注意する
家督相続のように1人の相続人へ財産を集中させたい場合、遺留分に注意しましょう。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に対して民法で最低限保証されている遺産の割合です。遺言があったとしても遺留分が優先され、法定相続人に一定の遺産が保障されています。
たとえば、被相続人に配偶者と長男・次男の3人の法定相続人がいるにもかかわらず、被相続人が残した遺言書に「長男に全財産を相続させる」と記載されていると仮定します。
しかし、配偶者と次男にはそれぞれ最低限保証されている遺留分が受け取れていない状態です。これを遺留分の侵害といいます。
遺留分の侵害があった場合、遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。例の場合、遺留分を侵害された配偶者と次男は、長男に対して遺留分侵害額請求を行うことが可能です。このとき、配偶者と次男に対して長男は遺留分を金銭で支払わなければなりません。
1人の相続人に財産を集中させたい事情があったとしても、他の相続人の遺留分を侵害しない程度にとどめておくよう配慮すると相続人同士のトラブルを回避できるでしょう。

家督相続を主張する相続人がいた場合の対処方法

相続発生後、家督相続を主張する相続人がいた場合には下記の対処方法を実践しましょう。
- 遺言書の有無を確認する
- 遺言書がある場合は内容の確認をする
- 話し合いが進まなければ遺産分割調停をする
- 遺言書に基づき家督相続に近い相続がされた場合は遺留分侵害額請求を行う
基本的には、上記の1から4の順番に対処していくことをおすすめします。それではステップごとに、詳しく解説します。
遺言書の有無を確認する
遺言書には法的効力があるため、まず遺言書の有無を確認しましょう。遺言検索システムを利用するほか、自宅や貸金庫などに遺言書が残されていないか捜索します。
遺言書があれば原則遺言書通りの遺産分割を行い、遺言書が見つからなければ法定相続人全員で遺産分割協議を行います。なお、遺言書の内容に納得いかない場合、法定相続人全員の合意のうえ遺産分割協議を行って改めて遺産分割の内容を決めることも可能です。

遺言書がある場合は内容の確認をする
遺言書が見つかった場合、内容を確認しましょう。
自筆証書遺言書保管制度を利用している場合や公正証書遺言書が残されている場合を除いて、自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかったときには家庭裁判所における検認が必要です。
自宅や貸金庫で遺言書を見つけて勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料を課される恐れがあるため注意しましょう。
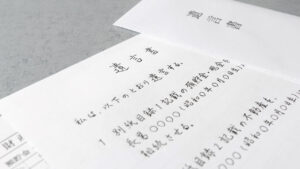
話し合いが進まなければ遺産分割調停をする
遺産分割協議を行っても、法定相続人同士で決着がつかない場合もあるでしょう。
たとえば、長男は代々引き継がれてきた家督制度を重んじるべきだと主張する一方、他の兄弟姉妹は現代の考え方に合わせて遺産を均等に分割するべきだと主張している場合、話の折り合いがつけられません。
当事者同士の話し合いで決着がつかない場合は遺産分割の調停をし、裁判所で決着することになります。なかには遺産分割調停に発展する前に、相続に強い弁護士に入ってもらうことで解決する場合もあります。
世間一般的な考え方や過去の判例を提示しながら冷静な話し合いができるため、家督相続制度ではなく今の民法に従った判断を促しやすいでしょう。


遺言書に基づき家督相続に近い相続がされた場合は遺留分侵害額請求を行う
「すべての財産を長男へ相続させる」などと一方的で不利な内容の遺言である場合、遺留分侵害額請求で遺留分を主張しましょう。
遺留分侵害額請求を行う場合、下記の順番で進めていきます。
- 相手方との交渉
- 相手方への遺留分侵害額請求の通知
- 調停
- 訴訟
話し合いによって合意に至った場合、合意書を作成しておくと安心です。一方、話し合いでは解決できない場合、遺留分侵害額請求する旨を通知し調停・訴訟を検討しましょう。
調停の申し立て手続きの依頼や調停での主張を有利に進めるために、相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。

家督相続は現在廃止されている制度
家督相続は1898年(明治31年)から1947年(昭和22年)まで施行されていた旧民法における制度で、現在廃止されています。
当時では長男や長女などの長子が家の財産をすべて継承することが当然のこととされていました。
不動産登記において家督相続が適用される場合があるものの、現在では配偶者の存在が重視され、子どもが複数人いる場合は平等に遺産を引き継ぐこととなっています。
さまざまな個別な事情によって家督相続のような遺産相続をしたい場合、相続人同士でのトラブルの原因になりやすいです。生前に対策ができていれば理想的ですが、対策されないまま相続が開始した場合は相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。
相続プラスでは、相続に強い弁護士をエリア別・悩み別に検索することが可能です。ぜひ、弁護士の力を借りて、円満な遺産相続を行いましょう。
地元の専門家をさがす


