「不動産を相続したけど権利証がない」昔からある不動産を相続した場合、そのようなケースは珍しくありません。権利証が無くても相続登記は可能です。また、権利証が必要な場合でも対応方法はあります。この記事では、権利証を紛失してしまった際の相続登記について、わかりやすく解説します。
地元の専門家をさがす
権利証・登記識別情報とは?
権利証とは、正式には登記済証と呼ばれる不動産の所有者や抵当権の債権者などを証明する書類です。
建物を新築した場合は所有権保存登記、土地や建物を購入した場合は所有者移転登記、また、土地や建物を担保に入れて抵当権を設定した場合には抵当権設定登記が必要になります。これらの登記手続きが完了した際に、登記した人(登記名義人)に渡される書類を登記済証と呼びます。
登記済証は、登記名義人だけが所持し、所有権などの権利を第三者に公的に証明する書類です。そのことから、登記済権利証を権利証と呼ぶことがあります。
また、権利証は、現在は登記識別情報に変更されています。登記識別情報とは、登記済証に代えて発行されるアラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号(パスワード)のことです。
以前の登記簿は登記簿という名の通り、紙の台帳として保管されていました。登記簿の内容を記した登記済証も、紙に登記済の印判を押印されて発行されていました。
しかし、平成17年から登記簿の情報は順次データ化されており、データ化できなかった一部の不動産を除いて、現在は、権利証の代わりに登記識別情報という符号が発行されます。
権利証と登記識別情報は、法的には同じ立ち位置となります。紙で発行された権利証は現在でも有効です。権利証の場合は、登記済証の印判が押された紙(原本)自体に効力があるため、必要書類として提出する際には原本を提出することになります。
一方、登記識別情報は符号に効力があります。そのため、符号がわかればコピーや符号を書き写した紙でも効力があります。
権利証・登記識別情報は、両方とも不動産の権利を公的に証明する大切な書類です。一度紛失すると再発行はできないため、入手後は大切に保管するようにしましょう。
ただし、紛失したからと言って不動産の権利までなくなることはないので安心してください。
権利証なしで相続登記はできる?
結論から言えば、相続登記は権利証なしで手続き可能です。昔から所有している不動産の場合、権利証を紛失している可能性も少なくないでしょう。
権利証は一度紛失すると再発行ができないため、いざ相続が発生し登記が必要という時に紛失していることで困る方もいるものです。しかし、相続登記に必要な書類に権利証は含まれません。
不動産売買の場合、第三者に不動産を売却するため売却する不動産が本人(売主)のものであることを証明する必要があります。
加えて、登記の際に買主・売主双方が共同申請することで、権利の移動が正当に行われたことを証明しているのです。そのため、売買時や売買後の所有権移転登記では、権利証の提出が必要になります。
一方、相続登記は売買による所有権移転とは、状況が異なります。相続登記は、登記簿上の所有者である被相続人が死亡していることから、登記手続きは相続人のみによる単独登記です。
相続人による登記の正当性を示すためには、遺言書や被相続人の戸籍謄本などで証明できるため、権利証が必要とならないのです。
ただし、相続登記でも例外的に権利証の提出が求められるケースがあります。
次のようなケースでは、権利証が必要になります。
- 被相続人の最後の住所と登記簿上の住所の一致を証明できないケース
- 遺贈により第三者が不動産を取得するケース
登記簿は、所有者の氏名や住所の変更がある際には変更登記の手続きが必要です。しかし、変更登記は令和5年12月時点では義務化されていないため、怠っているケースも珍しくありません。
そのため、被相続人の最後の住所と登記簿の住所が異なることがあります。相続登記の手続きでは、被相続人の氏名だけでなく住所まで一致してようやく本人と確認されます。
被相続人の住所が異なる場合は、現時点までの住所の変遷を住民票の除票や戸籍附票などで確認する必要があるのです。
役所の前住所情報の保存期間が過ぎているとその情報は廃棄されるので、以前の住所とのつながりを証明できる書類を取得できなくなる恐れがあります。その場合は、権利証の提出が必要になるのです。
また、被相続人の死亡により不動産を取得する方法には、相続以外に遺贈もあります。遺贈とは、遺言書などで相続人以外が相続財産を取得する方法です。
遺贈を理由にした所有権移転登記では、被相続人と不動産を取得する人の共同申請が必要になるため、権利証の提出が必要になります。


再発行ができない権利証がどうしても必要な場合はどうする?

例外的に権利証が必要な相続登記で権利証がない場合でも、代替えとなる方法を利用することで相続登記が可能です。
権利証を紛失した場合の対応としては、次の3つの方法があります。
- 事前通知制度を利用する
- 司法書士などに依頼して本人確認情報を作成してもらう
- 公証人に本人確認してもらう
事前通知制度を利用する
事前通知制度とは、権利証が提出できない登記申請の場合、法務局からの通知で本人確認する制度です。
権利証を添付せずに登記を申請すると、法務局から「登記申請の内容」「本人が申請した申請内容が真実である旨」の内容が記載された通知が送付されます。
この通知に対して相違ないことを確認したうえで署名と実印を押印することで、登記手続きを進めることが可能です。事前通知制度では、通知が送付されてから2週間以内に、法務局に提出する必要があります。
回答期限を超えてしまうと、登記申請は却下されるため、通知受け取り後は速やかに回答し、法務局宛に返送することが大切です。
事前通知制度は、別の書類を収集する必要がなく費用も掛からないため、権利証がない場合に最初に検討するとよいでしょう。
ただし、郵送で通知のやりとりを行うので手続きに時間がかかる点には、注意が必要です。売却など期限が迫っている登記の場合、期限に間に合わない恐れもあるので、早めに手続きするようにしましょう。
司法書士などに依頼して本人確認情報を作成してもらう
司法書士など資格者に本人確認情報という本人確認をしたことを証明する書類を作成してもらうことで、権利証の代替えにできます。
マイナンバーカードなどの本人確認書類の提出と、資格者の面談によって所有者であることを証明してもらう方法です。提出する本人確認書類などの資料は、資格者によって異なるので事前に確認するようにしましょう。
司法書士に依頼すればそのまま登記手続きも代行して貰えるため、スムーズな手続きができます。


公証人に本人確認してもらう
資格者による本人確認同様に、公証人に本人確認してもらうことが可能です。公証人での本人確認の場合、必要書類を揃えて公証役場で手続きを行います。
公証人の立ち合いのもと登記申請書などに署名捺印し、公証人から本人確認の認証を付与してもらうことで、その申請書を利用した登記であれば権利証の提出なしでも手続きできます。
公証役場での手続きは、司法書士の本人確認よりも手続きや必要書類が厳格です。事前に公証役場に出向いて、手順や必要書類の確認をしておくことをおすすめします。
相続登記に必要な書類は?
相続登記するには、いくつかの必要書類が必要です。必要書類は、相続方法によって異なるので注意しましょう。
ここでは、「遺産分割協議」「法定相続」「遺言」それぞれの場合の相続登記で必要な書類を解説します。
遺産分割協議による場合
遺産分割協議で相続した場合の相続登記の必要書類は、下記の通りです。
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産の所有権を取得する者の住民票など
遺産分割協議は、遺言書のない相続・遺言書に記載のない遺産がある・遺言書と異なる割合で相続したい場合・遺言書がなく法定相続分以外で相続する場合で必要です。
また、遺産分割協議で話がまとまらず家庭裁判所で調停・審判になるケースでは、家庭裁判所で作成される調停調書などが遺産分割協議書の代わりとなります。

法定相続分による場合
法定相続分で相続する場合の相続登記で、必要な書類は下記の通りです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産の所有権を取得する者の住民票など
遺言書がない相続であっても、法定相続分で相続する場合は遺産分割協議は必要ありません。また、相続人が1人しかいないケースも遺産分割協議は不要です。
法定相続分は、相続人と被相続人の関係性により異なるので注意しましょう。主な相続割合は下記の通りです。
| 相続人 | 相続割合 |
|---|---|
| 配偶者と子ども | 配偶者2分の1・子ども2分の1 |
| 配偶者と直系尊属(父母・祖父母) | 配偶者3分の2・直系尊属3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1 |
遺言の指示による場合
遺言による相続での相続登記では、下記のような書類が必要です。
- 遺言書
- 被相続人の死亡時の戸籍謄本(除籍謄本)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 不動産の所有権を取得する者の住民票など
遺言書がある場合、他の相続登記に比較し収集する戸籍の範囲が狭くなり必要書類は少なくて済みます。ただし、遺言書が自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合、家庭裁判所の検認済証明書の添付も必要な点には注意しましょう。なお、法務局に保管されていた自筆証書遺言については検認は必要ありません。
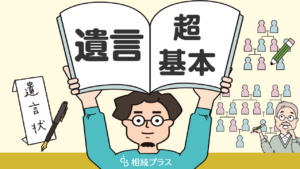
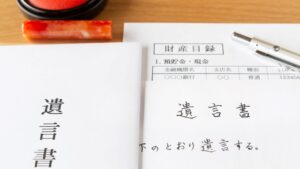
相続登記は権利証は不要だか速やかな手続きが必要
相続登記では、例外的なケースを除いて基本的に権利証なしで相続登記が可能です。
権利証が必要なケースであっても、事前通知制度などの権利証に変わる手段を用いることで相続登記はできます。
司法書士の本人確認を利用すれば、そのまま相続登記手続きも依頼できるので相談してみるとよいでしょう。
権利証が必要ないケースであっても、司法書士なら相続登記を含めた幅広い相続手続きのサポートに対応してくれます。相続登記は令和6年4月1日に義務化されたため、速やかな手続きが必要です。
信頼できる司法書士を見つけて相談することで、スムーズな相続登記ができるようになるでしょう。
地元の専門家をさがす



