相続分の指定とは、遺言書で相続人に対して引き継ぐ遺産の割合を指定することです。法定相続分よりも優先されるため、遺言書の内容に戸惑った方もいるのではないでしょうか。本記事では、相続分の指定があったときの遺産分割方法や、法定相続分との違いについて詳しく解説します。相続分の指定があったときの対応方法を知り、スムーズに相続手続きをすませましょう。
地元の専門家をさがす
相続分の指定とは
相続分の指定とは、遺言書で被相続人が相続人の引き継ぐ遺産の割合について指定することや、第三者に相続分の割合を決めることを委任することです。たとえば、遺言書に「妻に60%長男・次男にそれぞれ20%ずつの財産を残す」と残されていれば、相続分の指定に該当します。
具体的にどのように相続分の指定がされるのか、詳しく確認しましょう。
相続分の指定とは遺言書によって相続する財産の割合を指定すること
相続分の指定は、被相続人が相続人に対して法定相続分通りの相続をさせたくない場合に行われます。たとえば、以下のようなケースにおいて相続分の指定がされます。
- 苦楽を共にした配偶者により多くの財産を残したい
- 家業を継ぐ長男に多くの財産を残したい
- 妻・長男・次男の3人に平等に財産を残したい
相続分の指定をするには、遺言書に指定したい割合を明確に記載しなければなりません。相続人は、原則遺言書通りの割合で相続をします。
ただし、相続人全員が納得すれば遺産分割協議を行って、指定された相続分と異なる割合で遺産分割を行っても問題ありません。
相続分の指定パターンは様々
相続分の指定パターンは様々ですが、以下のような相続分の指定をイメージすることが多いと思います。
- 妻・長男・次男に3分の1ずつ
- 妻に70%、長男・次男に15%ずつ
しかし、以下のように相続人すべてに対する割合が指定されてなくても問題ありません。
妻に遺産の70%を与える
このような指定の場合、妻に遺産の70%だけを与えるのか、残り30%に対する法定相続分も与えるのかは一概に解釈できません。
また、以下のように、合計しても100%に満たない遺言が残される場合もあります。
妻に50%、長女と次女に20%
このような指定の場合、残りの10%は5:2:2の割合で分配するケースが一般的です。
さらに、被相続人が相続分を指定せずに、相続分を決める人物を遺言で指定することもできます。
相続割合について、友人である〇〇に一任します
このような指定の場合、指定された友人が相続分を指定できます。ただし、委託された人は委託を拒否することが可能です。
相続分の指定があった場合の遺産分割
遺言書によって相続分の指定がされている場合、法定相続分より優先されるため指定された相続分通りに遺産を分割します。
相続分の指定だけをされた場合は、指定された割合に基づいて遺産分割協議する必要があります。なぜなら、誰がどの財産を引き継ぐかが決まっていないからです。
妻・長男・次男に3分の1ずつといった指定相続分があったとしても、遺産は金銭だけだとは限りません。土地や建物、預貯金など、それぞれの最終的な帰属先を確定するために遺産分割協議を行います。
一方、遺産分割の指定があった場合でも、相続人全員で遺産分割協議を行って遺言書と異なる方法で遺産分割をすることができます。もちろん、相続分の指定に関しても、相続人全員が納得していれば、指定の割合以外で分割しても問題ありません。
より相続分の指定について理解を深めるために、法定相続分や遺産分割方法との違いについて詳しく確認しましょう。
法定相続分と相続分の指定の違い
法定相続分とは、相続人が2人以上いる場合に民法で定められている相続人ごとの相続割合のことです。法定相続分は、被相続人との関係ごとに以下のように定められています。
| 法定相続人の内訳 | 法定相続人 | 法定相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者 | すべて相続 |
| 配偶者+子ども・孫など | 配偶者 | 2分の1 |
| 子ども・孫など | 2分の1 | |
| 配偶者+両親 | 配偶者 | 3分の2 |
| 両親 | 3分の1 | |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者 | 4分の3 |
| 兄弟姉妹 | 4分の1 |
相続分の指定や遺産分割方法の指定のある遺言書がなければ、法定相続分通りの割合で遺産分割を行うことが一般的です。相続人全員で行う遺産分割協議を行う際にも、多くのケースでは法定相続分を軸にして話し合いが進められます。
一方、相続分の指定には決まりがなく、被相続人が考えた通りの割合を指定できます。ただし、法定相続分から大きくかけ離れた割合が指定されていると不公平に感じやすく、相続トラブルを招く原因になりかねません。
「法定相続人」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

相続分の指定と遺産分割方法の指定の違い
相続分の指定に似た言葉に「遺産分割方法の指定」という言葉があります。
遺産分割方法の指定とは、遺産をどのように分けるかを決めることです。不動産や自動車など物理的に分割できない遺産が含まれている場合に指定されることがあります。
たとえば、「配偶者に自宅の土地・建物と〇〇銀行の預貯金すべてを、残りを長男に相続させる」などと指定されているのであれば、遺産分割方法の指定に該当します。
また、以下のような遺産分割の方法を指定することも可能です。
| 現物分割 | 財産をそのまま各相続人が相続する分割方法 ※例:不動産は長男、預貯金は次男が相続する |
|---|---|
| 代償分割 | 特定の相続人が財産を相続する代償として、他の相続人に対して金銭を支払う分割方法 ※例:長男が不動産を相続する代わりに、長男が次男に代償金を支払う |
| 換価分割 | 財産を売却して売却代金を分ける分割方法 ※例:不動産を売却し、売却で得た利益を長男と次男で分ける |
一方、相続分の指定は、あくまでも相続させる財産の割合を指定するだけです。個別の財産内容や遺産の分割方法を指定する場合は、遺産分割方法の指定に該当します。
遺言では、相続分と遺産分割方法の両方を指定することも可能です。
地元の専門家をさがす
相続分の指定について知っておきたいこと・注意点
相続分の指定があった場合に知っておきたいことや注意すべきポイントがあります。
以下の5つの項目ごとに、知っておくべきことについて解説します。
- 相続分の指定と相続登記
- 相続分の指定と債務
- 相続分の指定と債権
- 遺留分は相続分の指定より優先される
- 特別受益があったときの考え方
1つずつ詳しく確認し、スムーズに相続手続きを済ませましょう。
相続分の指定と相続登記
相続分の指定があった場合、一般的に遺産分割協議書を作成し、合意した内容に基づいてそれぞれの相続人が登記を行います。すべての相続人が署名・押印した遺産分割協議書があれば、遺産分割協議書に記載されている通りの内容で相続登記の手続きが進められます。
もちろん、遺産分割を行う前に指定相続分による共同相続登記を行い、遺産分割後に改めて不動産を取得した相続人への持分移転登記も可能です。この場合、遺産分割を原因とした持分移転登記ができます。
「相続登記」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

相続分の指定と債務
相続分の指定があり、その指定通りに遺産分割を行ったとしても、債権者に対して指定された相続分について主張することはできません。そのため、債権者に法定相続分に従った割合で返済を要求される可能性があります。
なぜなら、相続分の指定はあくまでも相続人に対する意思表示であり、債権者の合意は得られていないと考えられているからです。
たとえば、長男と次男の相続人に対して、「長男4分の3、次男に4分の1相続させる」と遺言書を残したとしましょう。借金1000万円が残っていたとき、長男は750万円、次男は250万円の借金を引き継ぐこととなります。
しかし、債権者は相続分の指定に従わずに、長男・次男の双方に500万円ずつ請求できます。
ただし、相続人の間では相続分に応じた負担割合だと考えられるため、指定相続分に基づいて求償することが可能です。
そもそも多額の借金が残っている場合、借金の返済義務を引き継がないために相続放棄する選択肢も検討しましょう。
「相続放棄」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

相続分の指定と債権
債権を相続する場合、指定された相続分にしたがって分割し、それぞれの相続人に帰属することが一般的です。
たとえば、1200万円の債権を長男・次男・三男の3人で相続すると、法定相続分通りであればそれぞれ400万円ずつ相続します。しかし、被相続人によって、長男に2分の1、次男・三男に4分の1ずつ」と定められていれば、長男は600万円、次男・三男はそれぞれ300万円ずつ相続することとなります。
遺留分は相続分の指定より優先される
遺留分は、相続分の指定よりも優先されます。遺留分とは、被相続人の配偶者や子どもなどに認められた最低限受け取れる遺産の割合です。
遺留分より少ない相続分を指定された相続人は、遺産を多く引き継いだ相続人に対して遺留分侵害額請求を行えます。
たとえば、「長男に9割の遺産を相続させる。残りの1割を次男・三男で分けること」といった内容の遺言書が残っている場合、次男・三男は遺留分を下回る相続分を指定されているため不公平に感じるでしょう。
遺留分侵害額請求を行うと、請求する側と請求される側との関係に亀裂が入りやすく、親族関係のトラブルに発展する可能性があります。被相続人の遺言だったとしても、円満な親族関係を続けるために、遺産分割協議を行って法定相続分に近い割合で遺産分割することをおすすめします。
もちろん、遺留分が侵害されたからといって、かならずしも遺留分侵害額請求を行使する必要はありません。「家業を継ぐ長男に財産を残したのだろう」と他の相続人が納得していれば、遺留分を侵害した相続分で遺産を引き継いでも問題ありません。
「遺留分」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
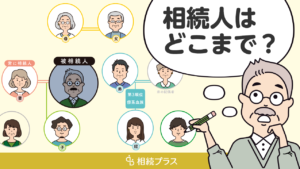
特別受益があったときの考え方
被相続人から特定の相続人に対して生前贈与や遺贈が行われた場合、特別受益があったとみなして実際の相続財産に合算して、相続分を決める必要があります。これを特別受益の持ち戻しと呼びます。
しかし、相続分の指定がある場合、特別受益を加味したうえで相続分が指定されていると解釈し、特別受益の持ち戻しを免除することが多いようです。
被相続人の明確な意思表示として、遺言書で特別受益の持ち戻し免除の意思表示がなされる場合もあります。
「特別受益」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

相続分の指定をした遺言書の書き方
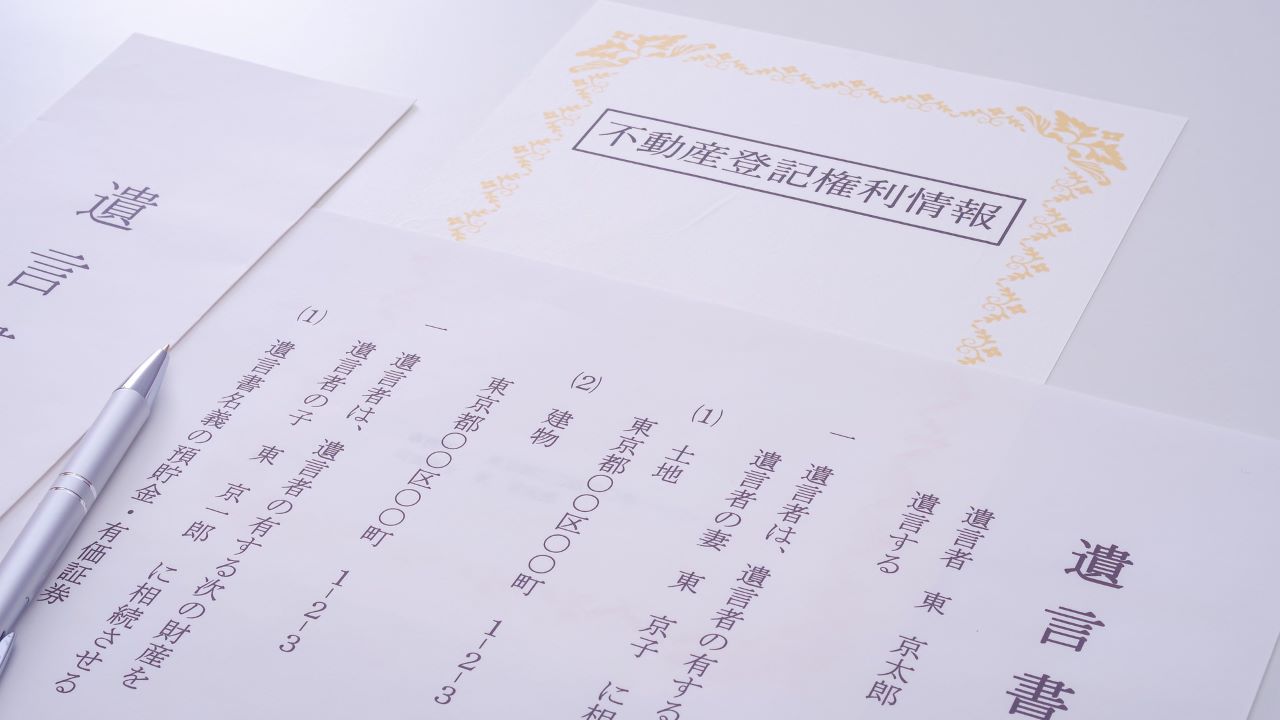
相続人に対して相続分の指定をしたい場合、誰が見ても理解できるようにそれぞれの相続人の取り分を遺言書に明記する必要があります。
具体的な記載例は、以下の通りです。
遺言者 相続太郎は、次の通り各相続人への相続分を指定する
妻 相続花子(昭和20年9月21日生) 3分の2
長男 相続一郎(昭和45年2月15日生) 6分の1
次男 相続二郎(昭和47年5月18日生) 6分の1
上記のように遺言書を作成すれば、それぞれの相続人の相続分を指定して財産を引き継ぐことがきます。ただし、相続分の指定だけでは遺産分割方法について相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
残された家族の負担を少しでも軽くし、意思通りに遺産分割をしてもらうためには、遺産分割の指定まで行うことをおすすめします。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼すれば、財産状況や家族関係を考慮して希望を叶えられる遺言書を作成するためのサポートをしてくれます。遺言書の書き方に詳しい専門家に相談しましょう。
「遺言書の書き方」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

相続分の指定があると法定相続分より優先される
遺言書によって相続分の指定がされている場合、法定相続分よりも優先されます。被相続人の意思を尊重し、指定された相続分通りに遺産を引き継ぐことが一般的です。
しかし、遺留分を侵害している場合や多額の借金が残っている場合、相続人同士で不公平に感じることもあるでしょう。このような場合は、遺産分割協議を行って相続人全員が納得した割合で遺産を引き継ぐことも可能です。
なかには遺言書が原因となって、相続トラブルに発展するケースもあります。金銭が絡むことで、今まで仲の良かった兄弟姉妹の関係に亀裂が入ったといった話は珍しくありません。
相続に関するトラブルを防ぎ、円滑に相続手続きを終わらせるためには弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。過去の事例や個別の事情を踏まえて、最適なアドバイスをしてくれるでしょう。初回は無料で相談に乗ってくれる事務所も多いため、ぜひ気軽に専門家の力を頼ってみてください。
地元の専門家をさがす


