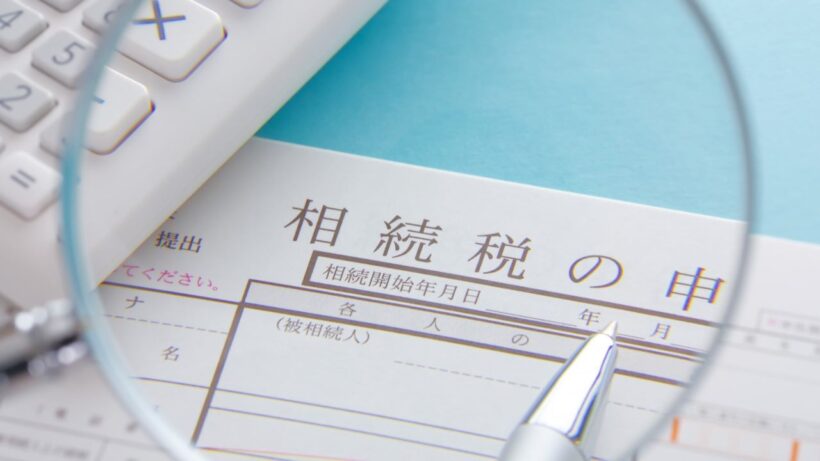相続税についてのお尋ねとは、相続税が発生する可能性のある相続人に対して税務署から送付される文書です。同封されている相続税の申告要否検討表を記入すると、相続税を納める必要があるかどうかを判断できるようになっています。本記事では、相続税についてのお尋ねが送付される理由や、税務署から届いたときの対応方法について詳しく解説します。対応にお困りの場合は、ぜひ参考にしてください。
目次開く
地元の専門家をさがす
相続税についてのお尋ねとは?
「相続税についてのお尋ね」とは、亡くなった方の遺産を相続する相続人に対して税務署から送付される文書です。相続税が発生する可能性の高い人に対して相続税の申告・納税の義務について説明する書類や、遺産内容を確認して相続税が発生するかどうかの回答を求める書類が税務署から送付されます。
2014年(平成26年)までは「相続税についてのお尋ね」という名称の書類が送付されていました。しかし、現在では様式が変わっており、下記の書類を「相続税についてのお尋ね」と呼ぶ場合があります。
- 相続税についてのお知らせ
- 相続税の申告等についてのご案内
本記事においても、便宜上、上記の書類のことを「相続税についてのお尋ね」と呼んで説明します。
相続税についてのお尋ねの送付時期は、被相続人が亡くなってから6〜8か月程度経った頃の場合や数年経った頃の場合などさまざまです。
相続税についてのお尋ねが届くと、相続税の申告について不正や脱税が疑われているのではないかと不安に思うかもしれません。しかし、税務署に疑念があるから届くわけでなく、遺産の内容を確認し、必要であれば相続税の申告・納税をしてくださいねという催促の書類のため安心してください。
ただし、相続税の申告期限は、被相続人が亡くなってから10か月後です。お尋ねが送付されたタイミングによっては申告期限が迫っていたり、すでに期限を過ぎていたりするケースもあります。そのため、申告の必要があるのであれば、早急に準備を開始しましょう。
また、相続税についてのお尋ねについて、回答を提出する義務はありません。しかし、回答を返送しておきましょう。なぜなら、回答をせずに無視していると、税務署が状況を確認するために追加調査を行う可能性があるからです。
お尋ねが送付されているからといって必ずしも相続税の申告・納税義務があるとは限りませんが、税務署は相続税を申告する義務があるのではないかと見込んだうえでお尋ねを送付しています。お尋ねに回答しないと、財産隠しや税逃れを疑われる可能性があります。
なかには、なぜ税務署が被相続人が亡くなったことや財産状況について把握しているのか疑問に思う方もいるかもしれません。相続税についてのお尋ねが届く理由や意義を深堀りするために、下記のポイントを詳しく確認しましょう。
- なぜ税務署は相続の発生や相続財産を把握しているのか
- お尋ねが来なくても相続税申告が不要とは限らない
順番に解説します。
なぜ税務署は相続の発生や相続財産を把握しているのか
税務署は、相続税が課税される人を高い精度で把握することができます。なぜなら、下記のような情報を得る手段を持っているからです。
- 死亡に関する情報
- 生前の所得に関する情報
- 金融機関の預金口座に関する情報
- 有価証券(証券会社)に関する情報
- 不動産に関する情報
- 海外の資産に関する情報
- 過去の相続税申告書の情報
どのようにして税務署が情報を入手するのかについて詳しく確認しましょう。
死亡に関する情報
まず、被相続人が死亡した事実は各市区町村役場から税務署に通知されます。
家族が亡くなると、死亡を知った日から7日以内に死亡届を市区町村役場に提出しなければなりません。戸籍法と相続税の関係によって、死亡届を受理した市区町村役場から税務署に死亡の情報が届けられるという流れです。
生前の所得に関する情報
当然、税務署は被相続人の過去の確定申告の情報を把握しています。
亡くなった方が会社員などで年収500万円以上の場合や、源泉徴収が必要な報酬を受けている場合には、税務署に源泉徴収票が提出されるため、確定申告されていない所得・収入に関する情報も持っています。
また、税務署は、亡くなった方の所得情報を遡って死亡時の財産状況を推測することが可能です。
金融機関の預金口座に関する情報
金融機関の預金口座の情報は、死亡をもって即座に税務署へ通知されることはありません。しかし、税務署は亡くなった方の預金口座の残高や明細を照会する権限を持っています。
生前の所得状況から死亡時の財産状況を推測し、相続税申告の義務があると思われる方の口座情報を取得することが可能です。
有価証券(証券会社)に関する情報
証券会社の有価証券に関する情報は、特定口座年間取引報告書が証券会社から税務署へ提出さるため把握されています。
特定口座年間取引報告書とは、証券会社の特定口座で管理されている1月1日から12月31日の譲渡損益額・配当等の金額が一覧になった書類です。この報告書によって、税務署は亡くなった方が保有していた有価証券について把握することができます。
不動産に関する情報
不動産に関する情報について、税務署は法務局から登記情報を毎月取得しています。税務署が自然と得られる情報は所有権移転に関する情報のみです。
取得者・取得日・移転原因が分かるため、不動産を購入・売買した情報はもちろん、贈与や相続によって所有者が変わったことも税務署に把握されていると認識しておきましょう。また、被相続人名義の土地や建物について、税務署が市区町村役場から情報を得ることも可能です。
海外の資産に関する情報
海外に財産を移していたとしても、海外にある財産についても税務署は把握に力を入れています。
たとえば、100万円を超える海外送金がある場合、金融機関から税務署に国外送金等調書が提出されます。2014年1月からは国外財産調書制度が施行されており、海外で保有する資産が合計5000万円を超える方は、毎年税務署に対して国外財産調書を提出する義務があります。
このように、国内の納税者が海外へ財産を移したとしても課税される制度が整っており、海外の資産状況も税務署が把握していると考えておきましょう。
過去の相続税申告書の情報
被相続人が過去に行った相続税申告の情報も、当然税務署は把握しています。被相続人の配偶者や両親がすでに亡くなっており、被相続人が相続した際に相続税申告をしていた場合は、その記録が税務署に残されています。
被相続人の生前の所得に加えて、相続した財産の状況も税務署は把握しているため、どれほどの資産を保有していたのかの推測が可能です。
お尋ねが来なくても相続税申告が不要とは限らない
相続税についてのお尋ねが届かないことが、すなわち相続税が発生しないとは限りません。
ご説明した通り、税務署はさまざまな情報から相続税が発生する可能性のある人について調査をしています。しかし、税務署がすべての国民の財産状況を完璧に把握しているわけではありません。そのため、相続税が発生する可能性がある場合であっても、相続税についてのお尋ねが届かないケースもあります。
相続税についてのお尋ねが届かなかったからといって遺産内容を把握せず、相続税の申告・納税の義務を怠ることは許されません。期限に遅れてしまったり、無申告のまま放置したりすると、ペナルティとして延滞税や加算税が発生する場合があります。
遺産総額が相続税の基礎控除額を超えていないか、早めに調査しましょう。
相続税についてのお尋ねが届いたら税理士に相談した方が良いケース
相続税の申告義務がないと思っていたにもかかわらず、相続税についてのお尋ねが届くと不安に感じるでしょう。
まずは冷静に回答を返送することが好ましいですが、下記のケースに当てはまるのであれば税理士に相談することをおすすめします。
- 相続税が発生するほどの財産に心当たりがないケース
- 相続税の申告期限まで日数が少ない・過ぎているケース
- 相続税の申告が必要かどうか判断できないケース
3つのケースについて詳しく確認し、当てはまる場合は相続税に強い税理士に相談しましょう。
相続税が発生するほどの財産に心当たりがないケース
相続税が発生するほどの遺産がないように思っていたところ、相続税についてのお尋ねが届いた場合は税理士に相談したほうがよいでしょう。
なぜなら、家族や親族に伝わっていない財産がある可能性があるからです。たとえば、家族には知られていない隠し口座を持っていたり、不動産を購入していたりするかもしれません。
税務署側は相続税が発生する可能性があると推測してお尋ねを送付しています。そのため、改めて財産調査を行うとよいでしょう。的確かつスピーディーに対応するためにも、相続税に強い税理士への相談がおすすめです。
相続税の申告期限まで日数が少ない・過ぎているケース
相続税についてのお尋ねをきっかけに相続税申告が必要だと気づいたとしても、申告期限までに日数が少ない場合や、すでに期限を過ぎている場合は税理士に相談しましょう。
相続税の申告・納税の期限は、相続開始から10か月以内と定められています。期限を過ぎると、延滞税や加算税などのペナルティが課される可能性があります。しかし、自分で財産の評価額の計算や控除の計算をすると、間違った申告をしてしまう可能性を否定できません。
スピーディーに、正確な相続税申告を行うために、税の専門家である税理士の力を借りましょう。
相続税の申告が必要かどうか判断できないケース
相続税の申告が必要かどうか判断できないときは、税理士に相談するほうが確実な手続きができるためおすすめです。
たとえば、遺産総額が基礎控除額に近い場合や、不動産の評価額があいまいな場合などが当てはまります。申告義務の有無の判断が難しい場合は、相続税に強い税理士に相談して判断をしてもらいましょう。
相続税についてのお尋ねが届いたらどうすればいいか
相続税についてのお尋ねが届いた場合の対応について、下記のケースごとに解説します。
- 相続税の申告の予定がない
- 相続税の申告の予定がある
詳しく確認しましょう。
相続税の申告の予定がない
相続税についてのお尋ねが届いた時点で相続税の申告をするつもりがなかった場合、相続税に強い税理士に相続財産の調査から依頼しましょう。家族や親族に伝わっていない財産が見つかるかもしれません。
もし、遺産が想像以上に多く、相続税の申告義務がある場合には、そのまま税理士に申告も依頼すると心強いでしょう。
相続税の申告の予定がある
相続税の申告の予定がある場合、そのまま準備を進めましょう。
ただし、相続税の申告には相続開始から10か月以内という期限があります。法定相続人の確認や相続財産の把握に手間や時間がかかるため、相続税についてのお尋ねが届いた時点で準備を始められていないのであれば、税理士に相談することをおすすめします。
地元の専門家をさがす
相続税についてのお尋ねの書き方

相続税についてのお尋ねに同封されている「相続税の申告要否検討表」の返送は義務ではないものの、回答することをおすすめします。回答がなければ税務署は隠し財産や税逃れを疑い、独自に調査を行う可能性があるためです。
なお、相続税の申告要否検討表は、国税庁の公式サイトからダウンロードすることが可能です。
万が一紛失した場合でも、上記よりダウンロードして返送しましょう。
ここでは相続税の申告要否検討表の記入方法について、下記の項目ごとにご紹介します。
- 故人の住所・氏名・生年月日・逝去日
- 故人の職業・勤め先の名称
- 相続人の数と続柄
- 故人の不動産
- 故人の有価証券
- 故人の現預金
- 故人の生命保険金・死亡退職金
- その他の財産
- 相続時精算課税を適用した財産の贈与について
- 故人が亡くなる前3年以内の相続時精算課税以外の財産の贈与について
- 教育資金または結婚・子育て資金の一括贈与について
- 故人の債務と葬式費用
- 相続税申告が必要かどうかの検討
- 提出者の情報
詳しく確認し、正しく記入しましょう。
①故人の住所・氏名・生年月日・逝去日
まず、故人の住所・氏名・生年月日・逝去日を記入します。記入者本人の情報ではないため、間違いのないように注意しましょう。
②故人の職業・勤め先の名称
亡くなる直前とそれ以前の主な職業について記入します。たとえば、現役時代は会社員で、亡くなる直前には退職して年金生活をしていたのであれば、下記のように記入しましょう。
- 亡くなる直前:無職
- それ以前の主な職業:会社員
会社員と記入した場合は、右横の「お勤め先の名称」に会社名も記入します。
③相続人の数と続柄
次に、相続人についての情報を記入します。相続人の氏名・フリガナ・住所・続柄について全員分記入し、表下部の「相続人の数」の箇所に相続人の数を記入します。相続放棄をした人の情報も必要となるため、注意しましょう。
また、被相続人に離婚歴がある場合、現在の親族が認識していない法定相続人がいる可能性があります。トラブル回避のために、相続人調査を依頼することも検討しましょう。
④故人の不動産
つづいて、被相続人名義の不動産について記入します。不動産の種類・所在地・面積・路線価等・倍率・評価額の概算について記入し、表下部の「合計額」の箇所に不動産の総額を記入しましょう。
路線価や倍率については、国税庁が公表している「路線価図・評価倍率表」から確認できます。もし、路線価が定められていない場合は、固定資産税評価額を記入すれば問題ありません。
評価額の概算は、「路線価×面積」もしくは「固定資産税評価額×倍率」で算出できます。
⑤故人の有価証券
故人が保有していた株式・公社債・投資信託等について記入します。銘柄・数量・金額を記入し、評価部の「合計額」の箇所に合計額を記入しましょう。
銘柄や数量については、証券会社から被相続人宛てに送付される取引報告書や取引残高報告書などの書類から確認できます。また、金額は亡くなった日付で記入する必要があるため、取り扱い先の証券会社などに問い合わせましょう。
⑥故人の現預金
故人が持つ預貯金と現金について、預入先・金額を記入します。預入先には支店名も一緒に記入しましょう。被相続人が亡くなった日における金額を記入する必要があるため、通帳や取引明細があれば参考にしてください。
また、現金の欄には財布や金庫、タンスに置いてあるすべての現金の金額を記入します。もし、葬儀費用として直前に現金を引き出していた場合、現金の金額に加算する必要があります。
⑦故人の生命保険金・死亡退職金
故人の生命保険金と死亡退職金について、記入します。生命保険金については保険会社等の名称と金額を、死亡退職金については支払い会社等の名称と金額を記入しましょう。
生命保険金と死亡退職金は、相続人の数に応じて非課税となる額が変わります。表下部にある注意書き部分に生命保険の総額と死亡退職金の総額、相続人の数を記入して、課税額を計算しましょう。相続人の数×500万円の方が金額が高い場合には、「0」と記入します。
また、ホ+への金額には、生命保険金の課税額と死亡退職金の課税額の2つを合算した金額を記入します。
⑧その他の財産
その他の財産には、④〜⑦に該当しない遺産について記入します。
たとえば、骨董品や自動車、貸付金などの財産が該当します。財産の種類・数量等・金額と、記入した財産の合計額を記入しましょう。該当する財産がない場合、記入は不要です。
⑨相続時精算課税を適用した財産の贈与について
相続時精算課税とは、相続税と贈与税を一度に課税する制度です。
生前の贈与が2500万円までは贈与税は非課税となりますが、贈与した方が亡くなるとこれらの財産も相続税の課税対象です。贈与を受けた相続人の氏名・財産の種類・金額と贈与を受けた財産総額を「合計額」の欄に記入しましょう。
⑩故人が亡くなる前3年以内の相続時精算課税以外の財産の贈与について
相続時精算課税以外で贈与を受けた財産であっても、故人が亡くなる前3年間(2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から4年間〜7年間)に贈与を受けていた場合、相続財産に持ち戻して相続税の計算を行わなければなりません。
贈与を受けた方の氏名・財産の種類・金額と贈与を受けた財産の総額を「合計額」の欄に記入しましょう。
⑪教育資金または結婚・子育て資金の一括贈与について
故人から教育資金、または結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の適用を受けた人がいる場合、管理残額を記入する必要があります。
該当する場合、贈与を受けた人の氏名・資金の種類・管理残額と、その合計額について記入しましょう。一定の金額までは相続財産に加算されない特例制度が定められています。
⑫故人の債務と葬式費用
銀行やカードローンなどからの借入金や未納となっている税金、葬式費用などについて記入します。これらは、相続財産の額から差し引かれて相続税の額が算出されます。
⑬相続税申告が必要かどうかの検討
②〜⑫までに記入した内容から、相続税の課税対象額を概算します。あくまでも配偶者控除や小規模宅地等の特例などを適用させずに、遺産総額から基礎控除額を差し引くだけの計算です。
また、ここで記入した不動産や美術品などの財産の評価額も概算に過ぎません。実際に相続税の申告義務があるか、相続税が発生するかは相続税に強い税理士に判断してもらいましょう。
⑭提出者の情報
最後に、相続税の申告要否検討表を記入している方本人の氏名・住所・連絡先を記入します。もし、税理士に相談しているのであれば作成税理士の氏名・事務所所在地・電話番号を記載しますが、相談していなければ作成税理士は空欄のままで問題ありません。
もし、税理士に相談しているのであれば作成税理士の氏名・事務所所在地・電話番号を記載しますが、相談していなければ空欄のままで問題ありません。
記入できたら税務署に返送しましょう。
相続税についてのお尋ねに関するよくある質問
相続税についてのお尋ねに関するよくある質問についてまとめました。
- 回答・提出期限はある?
- 無視したらどうなる?
- お尋ねに嘘を書いた場合はどうなる?
- 相続財産と基礎控除額が近い場合は返送しなくていい?
- 相続税の申告をするかどうかはどう判断すれば良い?
Q&A形式でお答えしています。ぜひ、最後まで読んで疑問を解消しましょう。
回答・提出期限はある?
相続税についてのお尋ねに対する回答には、期限が設けられています。届いた書類に記載されている回答期限までに届くように返送しましょう。相続発生後数年が経過してから届いた場合は即時返送することをおすすめします。
また、相続税申告を行う場合には申告期限に間に合うよう準備を進めましょう。相続税申告の期限についても送付された書類に記載されているため確認してくださいね。


無視したらどうなる?
相続税についてのお尋ねを無視して回答を返送しなければ、財産を隠していると怪しまれるかもしれません。
税務署が調査の対象であると判断し、税務調査をしようとする可能性があります。もちろん、確実に相続税が発生しないと判明している場合やすぐに申告する予定がある場合、すでに申告が終わっている場合などは、放置しても問題ありません。
しかし、税務調査が実施されると、80%以上の割合で追徴課税が課せられます。また、自宅に調査官がきて調査を行うため、対応に疲弊してしまうこともあるでしょう。このような理由から、お尋ねが届いたら無視せずに、早めに回答を返送することをおすすめします。
お尋ねに嘘を書いた場合はどうなる?
相続税についてのお尋ねに嘘の回答をしてしまったとしても、そのことに対してのペナルティは特にありません。
ただし、実際には相続税の申告・納税義務があるにもかかわらず、わざと財産を少なく記入して相続税の申告を期限内にしなかった場合、大きなペナルティが与えられる場合があります。
納税調査の実施によって財産隠しが発覚すると、相続税に加えて15〜20%の無申告加算税や40%の重加算税などが課される恐れがあります。
あくまでもペナルティを受けるのは相続税の申告をしなかった場合や嘘の申告をした場合に限られ、お尋ねに嘘・虚偽の回答をしたとしても正しく申告を行えば問題ありません。

相続財産と基礎控除額が近い場合は返送しなくていい?
相続税の申告要否検討表に指示通り記入した結果、相続財産の総額と基礎控除額が同額に近い場合、相続税の申告義務があるかどうかの判断を慎重に行わなければなりません。
なぜなら、相続税の課税対象となる財産の評価額を正確に判断する必要があるからです。また、みなし相続財産は誰が受け取ったかによって非課税枠が使えない場合もあります。
相続税の申告義務があるかどうかを正確に判断するには、相続税について詳しい税理士に相談しましょう。
地元の専門家をさがす
相続税の申告をするかどうかはどう判断すれば良い?
相続税の申告が必要かどうかは、相続した財産の総額が基礎控除の額を超えるかどうかで判断しましょう。基礎控除の額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で算出できます。
最終的な判断が難しい場合は、税理士に相談することをおすすめします。
「相続税についてのお尋ね」が届いたら専門家に相談しよう
いきなり相続税についてのお尋ねが届くと、税務調査対象になったのかと焦るかもしれません。しかし、税務署が持っている情報から相続税が課税される可能性のある人に相続税の申告要否検討表を送付してほしいというお願いに過ぎず、過度な心配は不要です。
ただし、お尋ねが届いたということは、高確率で相続税の申告・納税義務があるということです。申告するつもりがない場合、家族や親族が知らない財産が残されているかもしれません。
自己判断で申告しないで放置していると、税務調査が行われてペナルティが課されたという事例もあります。
そのため、相続税についてのお尋ねが届いたら相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。財産調査や相続税の申告が必要かどうかの判断などを依頼することが可能です。
積極的に専門家の力を借りて、相続税に対する不安を払拭しましょう。