「お金を掛けずに、家族のために法的に有効な遺言書を書きたい」と考えている方は「自筆証書遺言」を検討してもよいでしょう。ドラマや映画の中で、登場人物が遺言書を書くシーンが出てくることもあるため、「遺言書のイメージ」として思い浮かべる人も多いかもしれません。
地元の専門家をさがす
《基本》自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言は、どのような特徴を持つ遺言なのでしょうか?他の遺言方法や、法務局にて新たに開始された保管制度などを踏まえて、自筆証書遺言の特徴を徹底解説していきます。
自筆証書遺言は、費用が少なく手軽に書ける遺言
自筆証書遺言とは、遺言を書く「遺言者」本人が自分の手で書いた遺言のこと。自分で遺言書を一貫して作成するためほとんど費用が掛かりません。遺言を残そうとしている人の年齢が15歳以上に達しており、紙とペンがあれば作成できます。ただし、後述の通り「財産目録」はパソコンやワープロで作成することもできます。
ただし、法律に関する専門家のチェックを通さないため、書き間違えや必要要件を満たさず無効になる恐れがあります。また、遺言者の自宅で保管され、作成時に立ち会う証人もいないため、遺言書の紛失・改ざん・偽造のリスクがあることも挙げられます。
遺言書は自筆証書遺言以外にも2種類ある
遺言書の形式は、自筆証書遺言以外にも、公正証書遺言と秘密証書遺言という2種類の遺言が存在しています。自筆証書遺言への理解をさらに深めるために、公正証書遺言と秘密証書遺言の特徴を簡潔に解説します。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場にいる公証人に作成してもらう遺言のこと。
公証人とは、法律の専門知識に長けており、国の公務である公証事務を担当する人のことで、実質的に公務員とみなされています。遺言書を公正証書にすると、極めて高い証拠力を持つようになります。
公正証書遺言の作成方法は、証人(立会人)2名の前で遺言者が話した内容を公証人が聞き取り、その内容を証人に間違いないか確認しながら、法律上の要件を満たすように正しく作成されます。
そのため、形式の不備によって無効になるという可能性が極めて低くなるといえます。さらに、厳重なシステム下の公証役場にて保管されるため、改ざんや紛失の心配がほとんどないというメリットもあります。
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、存在だけを公証役場で証明してもらい、遺言の内容を誰にも知られない遺言を指します。公証役場にいる公証人と、立ち会ってくれる証人2人の前で、封がされている自分の遺言書の存在を証明してもらい、公証役場に遺言を作成したという記録だけを残します。亡くなった後に遺言書が相続人に発見されないことや、遺産が国に帰属してしまうなどのリスクを防げます。
秘密証書遺言の作成方法は、遺言書本文を含め、内容すべてが自筆である必要がありません。パソコンで作成したり、第三者が代筆したりしても問題ありません。
ただし、注意点として、内容や形式に不備があった場合に要件を満たさず無効になってしまうことや、遺言者本人が保管することによる紛失、悪意のある第三者による改ざんのリスクが挙げられます。
自筆証書遺言用に新たな保管制度がスタート
自筆証書遺言を取り巻く環境は変化しています。令和2年7月より、法務省管轄の「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。
自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言の原本と画像データを法務局に長期間保存できる制度です。この制度を利用した場合と利用しない場合で、どのような違いがあるのかを下記の表にまとめました。
| 保管制度を… | ||
|---|---|---|
| 利用しない | 利用する | |
| 保管場所 | 本人 | 法務局 |
| 遺言の内容を知る人 | 本人 | 本人及び、法務局の職員 |
| 偽造や紛失のリスク | あり | なし |
| 検認の有無 | 必要 | 不要 |
| 保管申請手数料 | なし | 3900円 |
| 死亡時の通知 | なし | あり |
自筆証書遺言書保管制度が創設された背景として、相続人などに発見されなかったり、改ざんされたりする自筆証書遺言のデメリットを抑えることが挙げられます。同制度を活用すれば、保管場所が法務局になり、遺言書原本とその画像データが、適切に長期間保存されます。
預けた遺言書を閲覧する場合も手数料が発生し、モニターで遺言書画像を閲覧する場合は1400円、原本を閲覧する場合は1700円の手数料がかかります。
自筆証書遺言書保管制度の保管申請件数は、制度開始の令和2年7月から令和6年7月までで累計7万9128件にのぼっています。特に令和6年だけでも年間で2万3382件を記録し、前年の1万9336件から大きく増加しました。「自宅よりも安心できる場所に保管したい」「死亡したら通知が相続人に届くようにしたい」とお考えの場合は、自筆証書遺言書保管制度の利用を検討してみてもよいでしょう。
ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用する上での注意点もあります。同制度を使用しても、自筆証書遺言として、遺言内容が無効になってしまうリスクは変わらないということ。
同制度の申請時、遺言書の形式については、要件を満たしているか遺言書保管官のチェックを受けられます。しかし、遺言内容が要件を満たすかまではチェックされません。したがって、遺言内容の法的有効性を高めたいのであれば、弁護士などの専門家に遺言内容の要件の確認を依頼するか、公正証書遺言で作成することをオススメします。
弁護士などの専門家に依頼する前に、初回までは無料相談ができる事務所もあります。こうした事務所をうまく活用して、要件を満たす有効な遺言書を作成するように心掛けましょう。
参照:12 法令・関連情報・リンク集|法務省/自筆証書遺言書保管制度のご案内|法務省/01 遺言書保管制度とは?|法務省
「遺言書の書き方」についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

自筆証書遺言のメリットとデメリット
3種類ある遺言方法の中でも、とくに手軽に始められる「自筆証書遺言」には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?こちらの段落にて、徹底解説していきます。
【3選】自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言について、次の3つのメリットを解説します。
- 自分1人で手軽に書ける
- 費用がほとんどかからない
- 遺言書の内容とその存在を秘密にできる
それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。
1. 自分1人で手軽に書ける
自筆証書遺言のメリットは、遺言者が単独で作成できる身近な遺言方法であるということ。紙とペンがあれば作成可能で、書き方や要件に注意していれば、費用や手間を掛けずに何度でも書き直しができます。
公正証書遺言では、必要な準備をしてから公証役場に出向き、遺言者の発言を公証人が聞き取って遺言書を作成します。秘密証書遺言でも、存在を証明して記録に残すために公証役場に行かなければなりません。
自筆証書遺言では、公正証書遺言と秘密証書遺言で発生するこうした公証役場での手続きや費用が発生しないため、単独で手軽に遺言書を作成できるメリットがあるといえます。
2. 費用がほとんどかからない
遺言書を作成するにあたって、遺言者本人が費用を負担することはほとんどありません。
公正証書遺言と秘密証書遺言は、ともに公証人や法務局への費用と手数料が発生します。それぞれの費用相場を見ると、公正証書遺言は2~5万円程度、秘密証書遺言は一律1万1000円掛かります。
3. 遺言書の内容とその存在を秘密にできる
自分が死亡するまで、誰にも遺言書の存在と内容を知られたくない場合に、自筆証書遺言は有効な遺言方法の1つだといえます。
公証証書遺言では公証人と証人2人に存在とその内容を、秘密証書遺言では公証人と証人2人に存在を確認してもらいます。遺言書の内容だけではなく、存在までも秘密にしておきたいと考えているならば、自筆証書遺言にメリットがあります。
【4選】自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言のデメリットについて解説します。手軽に作成できる自筆証書遺言だからこそ、次の4つのデメリットがあるといえるでしょう。
- 自分で書く手間がかかる
- 無効になる場合もある
- 死後に発見されない、内容を偽造される恐れがある
- 相続人が検認手続きをする必要がある
それぞれのデメリットについて詳しく見ていきましょう。
1. 自分で書く手間がかかる
自筆証書遺言は、文字通り自筆で書かなければなりません。「財産目録」はパソコンやワープロで作成することもできますが、本文は自分で一言一句間違えないように、書式や要件を満たすように書かねばなりません。また、体力低下・病気・障害などで手が不自由になってしまい、自筆することがが難しくなってしまう場合もあります。
2. 無効になる場合もある
自筆証書遺言は、遺言内容や形式に対して法律の専門家のチェックを受けていなければ、無効になってしまう場合があります。遺言を法的に有効にするためには、関する複雑な内容を厳格な書式に則って作成する必要があります。したがって、遺言内容や書式、要件に不備がある場合、その遺言は無効となってしまうおそれがあります。
3. 死後に発見されない、内容を偽造される恐れがある
自筆証書遺言は、基本的に遺言者本人が管理し、保管する必要があるものです。
たとえば、身近な保管場所だと自宅が選ばれるケースが多いです。その場合、紛失したり、相続人が保管場所を忘れたりすることが考えられます。遺言書の偽造や改ざんの危険性も同様です。悪意のある相続人が遺言書の内容を書き換えてしまう危険性も、完全に排除できるわけではありません。
このように自筆証書遺言では、遺言書を書いても死後発見されない、または遺言書の偽造や改ざんという恐れが付きまとってしまいます。そのため、安全に遺言書を保管できる場所を確保し、その場所を信頼できる人に伝えておくことが大切です。
それでも不安が残るのであれば、前述した「自筆証書遺言書保管制度」の利用を検討してみましょう。法務省の管轄する安全な保管場所に原本と画像データが保存され、さらに遺言者の死亡後に相続人に通知が届くため、先の発見されないという懸念点を解消することができます。
4. 相続人が検認手続きをする必要がある
自筆証書遺言は、死後相続人に発見されて開封される前に、家庭裁判所による「検認」手続きが必要です。「検認」とは、相続人に遺言の存在と内容を知らせて、遺言書の偽造・変造を防止する手続きを指します。
相続人などが自筆証書遺言を発見した場合、基本的に遺言書を開封する前に家庭裁判所に申し立てて「検認」を行いましょう。収入印紙代や郵便切手代、検認済証明書の交付手数料など、あわせて数千円程度が検認費用が発生します。
自筆証書遺言では、相続開始後に家庭裁判所での手続きが発生してしまうというデメリットが挙げられます。
検認の手続きを経ずに勝手に遺言を開封した、遺言書の内容を執行をした場合は、5万円以下の過料に処せられることがあります。
自筆証書遺言の作成方法の流れ

自筆証書遺言の作成方法の流れを解説します。自筆証書遺言にも所定のルールが定められているため、その形式や要件に従って相続人・相続財産の配分について書かなければなりません。自筆証書遺言の作成方法は、大まかに次の4つのステップに分けられます。
- 必要となる書類を用意する
- 財産目録を作成する
- 遺産分割の内容を考える
- 遺言者本人の自筆で遺言書の全文を書く
自筆証書遺言を作成するまでの4つのステップについて解説していきます。
1. 必要となる書類を用意する
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合を除き、自筆証書遺言を作成するにあたり必要となる書類は、法律でとくに指定されていません。しかし、遺言者が所有する財産について、その財産価額を確認・証明できる書類が実質的に必要になると想定されます。
不動産関係書類をはじめ、主に以下のような書類が必要となるでしょう。
- 登記簿謄本など(不動産関係の書類)
- 証券会社の残高証明書など(有価証券関係の書類)
- 各銀行の残高証明書など(預貯金関係の書類)
- ゴルフ会員権の証書
- 生命保険証書
- 絵画や骨董品などの明細書
不動産関係の書類とは、権利などの物件を特定できるものを指し、「登記簿謄本」以外に「固定資産税評価証明書」「売買契約書」が該当します。
預貯金の関係書類では「各銀行の残高証明書」以外に、「貯金通帳」の写しや、ネット銀行であれば「残高確認ページ」などです。
保有している株式が未上場である場合、市場価格が分かりません。無料相談を活用しつつ、税理士といった専門家に依頼して、保有する株の評価をしてもらいましょう。

2. 財産目録を作成する
遺言書だけでは、遺産に関する情報としては不十分で、遺言書とあわせて「財産目録」を作成し、一緒に添付する必要があるのが一般的です。「財産目録」とは、遺言者の所有する資産・負債の区分・種類について一覧にしたリスト。遺言書はこのリストの財産の分割方法を指定する書面だからです。
令和元年の法改正で、添付される財産目録の作成方法だけは、手書きである必要がなくなり、ワープロやパソコンによる作成が認められるようになりました。さらに、財産目録の書き方については、遺言者本人が作成する必要もなくなったため、家族や第三者が作成することも可能です。
土地や建物といった不動産に関する固定資産税評価証明書、金融機関の残高証明書のコピーを財産目録として使用することが認められています。
財産目録の書き方における注意点は、各ページに遺言者本人の署名捺印を必ず行うこと。各ページに署名捺印を行う以外に、財産目録の形式や要件など書き方に関する指定はとくにありません。相続人が相続税の申告などで困らないよう、見やすさに配慮しながら、自由な書式で財産目録を正確に作成しましょう。
3. 遺産分割の内容を考える
遺言で財産を渡したい相手や、その遺産の配分を考えます。遺言書を作成すれば、配偶者や子どもなどの法律で定められている相続人である「法定相続人」以外にも、自分の遺産を指定して遺贈することができます。また、遺贈先は個人だけでなく、慈善団体やNPO法人、介護施設などの団体でも問題ありません。
ただし、遺産分割の内容を考える際の注意点として挙げられるのが「遺留分」です。法定相続人には、最低限受け取れる遺産の割合である「遺留分」という権利が法律で保障されています。そのため、遺産相続でトラブルにならないよう、相続人となる予定者の「遺留分」を侵害しないように、遺言書の書き方に配慮した方がよいでしょう。
4. 遺言者本人の自筆で遺言書の全文を書く
要件を満たすように、用意した紙に全文を自筆で書きましょう。書き方については、縦書き・横書きの指定はありません。自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、紙はA4サイズと指定されていますが、利用しない場合は紙の種類やサイズに指定はありません。
遺言書の作成日付を明記し、署名捺印を行うため印鑑が必要になります。また、自筆で書くため、文字を間違えてしまうこともあるかもしれません。その場合は、見本などを参考にしながら、所定のルールに従って訂正しましょう。
「遺言書の書き方」についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

自筆証書遺言を作成する際の注意点について
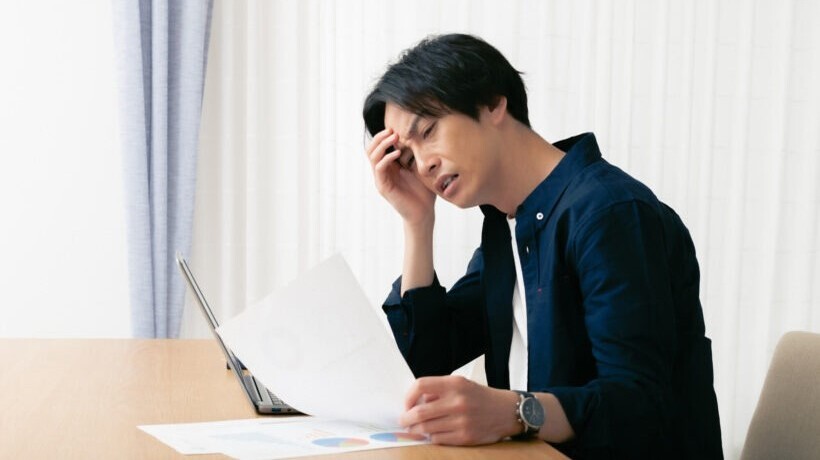
自筆証書遺言を作成するときの注意点を解説します。書式の要件以外にも作成時の注意点を理解していないと、相続トラブルの原因になったり、過料というペナルティを支払わなければならなくなったり、最悪の場合は遺言が無効となってしまうこともあります。自筆証書遺言を作成するときの注意点は、下記の6つが挙げられます。
- ビデオレターなど音声・動画で代用しない
- 複数人による共同遺言を作成しない
- 認知症など判断能力が不十分な状態で作らない
- 遺言書が複数ある場合は古い方が無効になる
- 遺産分割についてあいまいな表現をしない
- 遺留分を考慮した内容にしていない
1. ビデオレターなど音声・動画で代用しない
これまで解説した通り、遺言の形式は基本的に法律で書面で残すことが定められています。そのため、スマートフォンやボイスレコーダーなどで録画した音声や動画は、そもそも遺言としての要件を満たさず、法的効力を持たない無効なものとなります。
ただし、亡くなった人の表情や想いが動画や音声を通して、相続人に伝えられると想定されるため一定の効果は期待できます。したがって、あくまでも要件を満たした遺言書を作成した上で、遺言書では伝えきれない遺言者の想いや感情を相続人に伝えたい場合は、ビデオレターなどを作成してもよいでしょう。
2. 複数人による共同遺言を作成しない
民法975条で「共同遺言の禁止」と定められているため、2名以上が同一の遺言を遺すことが禁止されています。
つまり、遺言書は1人につき、1つしか作成できないのです。たとえば、夫婦が共同して形式通りに遺言書を作成したとしても、その遺言は要件を満たさないため、無効になりますしたがって、複数人でまとめて連名で遺言を作成するのではなく、1人につき1つの遺言書を、要件を満たすように別々に作成してください。
3. 認知症など判断能力が不十分な状態で作らない
遺言書は、遺言者の本人に「遺言能力」がある前提で作成されるものです。「遺言能力」とは、遺言者本人が遺言内容や遺言の結果を弁識(理解)できる判断能力のこと。したがって、認知症などで本人の遺言能力がないにもかかわらず、作成された遺言書は無効となります。
もしも被相続が認知症になってしまい、十分な判断能力(遺言能力)に欠けているような状態であるならば、遺言書を作るよりも、まずは専門家に相談することを検討しましょう。
また、認知症や意思能力に不安がある方は「成年後見制度」や「家族信託」という制度の活用を、検討してもよいかもしれません。
「成年後見制度」についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

「家族信託」についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

4. 遺言書が複数ある場合は古い方が無効になる
自筆証書遺言は、遺言者自身が保管するため、遺言書の管理が行き届いていないこともあります。そのため、過去にすでに遺言書を作成したにもかかわらず、うっかり新しい遺言書を作成してしまうことがあります。
このようにして、同じ遺言者の遺言書が2通存在してしまうことになります。2通の内容が矛盾している場合、どちらの内容に従って遺産相続をすべきか、相続人は混乱してしまうでしょう。
この場合は、形式にかかわらず作成日付が新しい方の遺言書が有効になり、古い方が無効になります。たとえば、遺言書を2通発見した場合、新しい方が「自筆証書遺言」、古い方が「公正証書遺言」であったとしても、新しい遺言書である「自筆証書遺言」の内容が有効になります。
自筆証書遺言は何度も作り直しがきく遺言方法であるため、こうした事態を招いてしまうことがあります。したがって、遺産相続時に問題が起きないよう、遺言者は遺言書をしっかりと保管・管理しておく必要があります。
5. 遺産分割についてあいまいな表現を避ける
たとえば、「あとは任せる」など、相続人や財産が具体的に特定できないあいまいな表現で書かれた遺言内容は、相続トラブルの原因になりかねないため、避けた方がよいでしょう。
こうなると、遺産相続について相続人同士で、遺産分割協議書を作成しなければならなくなり、相続手続きの負担も増えてしまいます。
財産目録を活用しながら、「誰に・どれを・どのくらい」相続させるのか、あるいは遺贈するのかをしっかりと明記するよう、遺言書の書き方に注意しましょう。
6. 遺留分を考慮した内容になっていない
遺産相続では、遺言書があれば基本的に遺言書の内容に従って相続が行われます。しかし、すでに解説した通り、遺言書の内容が相続人の「遺留分」を侵害する内容であった場合は、その内容通りに相続されず、トラブルに発展する可能性があります。
遺留分を侵害された相続人が遺留分を放棄しない場合、自分が相続するはずだった遺産を請求するために、他の相続人に対して裁判を起こすことも考えられます。相続人が複数いる場合、相続人同士の相続トラブルにならないように、遺言書は遺留分を考慮した遺言書にしておくとよいでしょう。
「遺留分」についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
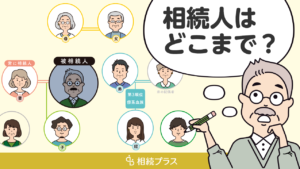
手軽で身近に始められるのが自筆証書遺言
ここまで自筆証書遺言の基礎知識や、実践的な知識について解説してきました。
相続が一度発生すると、「遺産額の大小にかかわらずもめてしまった」という声も聞かれます。また、「故人の遺言書があると、相続人同士で仲が悪くても冷静に話し合いに臨める」という声もあり、遺産相続時における遺言書の存在は非常に大きいといえます。
自筆証書遺言は他の遺言方法と異なり、1人でも作成できるためすぐに書き始められます。「転ばぬ先の杖」ということわざがあるように、遺産を渡す側ともらう側で相談しながら、手遅れになる前に遺言書の作成を一度検討してみてはいかがでしょうか。
地元の専門家をさがす



