「自分には相続人がいないかもしれない」「相続してくれる人がいないときに遺産はどうなるのだろう」とお悩みではありませんか。亡くなった方の遺産を相続する方が誰もいない状態を相続人不存在といいます。本記事では、相続人不存在になるケースや遺産がどうなるのかについて詳しく解説します。相続発生後の手続きの流れや注意点も解説しているため、ぜひ参考にしてください。
地元の専門家をさがす
相続人不存在とは
相続人不存在とは、亡くなった方が残した遺産を相続する方が誰もいない状態です。具体的には、下記のようなケースに相続人不存在となります。
- 法定相続人がいない
- すべての法定相続人が相続放棄をしている
- 相続欠格・相続廃除により相続人がいなくなっている
3つのケースについて詳しく確認しましょう。
法定相続人がいない
亡くなった方に法定相続人がいない場合、相続人不存在となります。
法定相続人とは、民法で定められた亡くなった方の財産を引き継ぐ権利のある人のことです。ご本人が亡くなった時点で、下記の人が誰もいない場合に法定相続人はいないということです。
| 順位 | 続柄 |
|---|---|
| 必ず法定相続人になる | 配偶者 |
| 第一順位 | 子ども(亡くなっている場合には孫) |
| 第二順位 | 両親(亡くなっている場合には祖父母) |
| 第三順位 | 兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪) |
上記に当てはまる人がすべて法定相続人になるわけではなく、法定相続人には優先順位が決まっています。配偶者がいれば常に配偶者は法定相続人です。
子どもがいれば子どもが法定相続人になりますが、子どもがいなければ第二順位の両親、両親もいなければ第三順位兄弟姉妹が法定相続人となります。
また、第一順位の子どもや第三順位の兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子どもである孫や甥姪が代わりに相続できる代襲相続となります。
つまり、配偶者や第一順位から第三順位までの人、代襲相続できる人がいない場合に法定相続人がいない状態です。このとき、法定相続人が誰もいないため相続人は不存在となります。

すべての法定相続人が相続放棄をしている
法定相続人がいるものの、すべての法定相続人が相続放棄の手続きをすると相続人不存在となります。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべての遺産を引き継がない相続方法です。相続放棄をすると、法定相続人としての立場を失うことになります。
相続放棄をすると、法定相続人の次順位の人が法定相続人となります。たとえば、すべての子どもが相続放棄をすると、次順位である両親(亡くなっている場合は祖父母)が法定相続人です。
しかし、借金が多くて引き継ぎたくない場合やすべての財産を寄付する場合など、すべての相続人が相続放棄するケースもあります。このとき、法定相続人の立場を持つ人が誰もいないため、相続人不存在となります。

相続欠格・相続廃除により相続人がいなくなっている
法定相続人がいる場合であっても、相続欠格・相続廃除によって法定相続人がいなくなると相続人不存在となります。
相続欠格・相続廃除とは、亡くなった方に対して危害を与える行為を行った人から相続の権利を剥奪すると定められた民法のルールの1つです。具体的には、下記のような行為をした人が当てはまります。
<相続欠格>
- 被相続人や他の相続人を殺害、または殺害しようとし刑を受けた
- 相続人が殺害されたことを知っていたのに黙っていた
- 被相続人を騙したり脅迫して遺言書を書かせたり変更させた
- 被相続人を騙したり脅迫して遺言書の変更を妨げた
- 遺言書を偽装したり勝手に書き換えた
<相続廃除>
- 被相続人に対して虐待をした
- 被相続人に重大な侮辱を加えた
- 上記以外に、被相続人に対して著しい非行があった
相続欠格に該当すると、相続する権利を自動的に失います。一方、相続廃除は、ご本人の意思によって排除することが可能です。
ただし、相続欠格・相続廃除のいずれの場合においても、代襲相続は認められます。つまり、相続欠格・相続廃除に該当する法定相続人に子どもがいる場合は、相続する権利が子どもに引き継がれます。
相続欠格・相続廃除によって法定相続人がいなくなり、代襲相続も発生しないときに相続人不存在となる点に気をつけましょう。

相続人不存在の場合に財産はどうなる?
相続人不存在の場合、亡くなった方の遺産がどのように扱われるのか気になりますよね。ここでは、下記の順番に遺産の取り扱いについて詳しく解説します。
- 遺言書がある場合
- 特別縁故者がいる場合
- 最終的には国庫に帰属される
詳しくみていきましょう。
遺言書がある場合
遺言書が残されている場合、遺言内容にしたがって財産が引き継がれます。
遺言書では、個人または法人・地方自治体などさまざまな引き継ぎ先を指定できます。たとえば、生前お世話になった人やビジネスパートナーはもちろん、生まれ育った地方自治体やお世話になった介護施設などの指定が可能です。
また、近年は「最後に世の中の役に立ちたい」という思いから、社会問題の解決のために活動するNPO団体や公益財団法人などへ遺贈寄付を検討する方が増えています。
家族や親戚がいなくて、自分の財産がどのように使われるのか不安を感じる方は遺言書を作成するとよいでしょう。
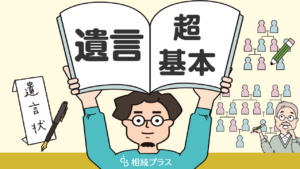
特別縁故者がいる場合
特別縁故者がいる場合、特別縁故者が遺産を引き継ぎます。特別縁故者とは、法定相続人がいない場合に特別に相続できる人のことです。
特別縁故者として認められる可能性のある方は、下記の通りです。
- 亡くなった方と生計を同じとしていた者
- 亡くなった方の療養看護に努めた者
- その他亡くなった方と特別の縁故があった者
たとえば、内縁の配偶者や事実上の養子、報酬を受けずに亡くなった方の看護・介護に尽くした方などが挙げられます。
ただし、上記の方すべてが特別縁故者として認められるわけではありません。特別縁故者として遺産を引き継ぐためには、家庭裁判所にて申し立てを行って、認定を受ける必要があります。

最終的には国庫に帰属される
遺言書が残されておらず、特別縁故者もいない場合、遺産は国庫に帰属されて国のものになります。また、特別縁故者が遺産の一部だけを引き継ぐ場合もあり、残りも国庫に帰属されます。
相続人不存在の場合に国庫へ帰属することは民法959条に定められており、年々額が増えていることが現状です。生前築いた財産が国のものになってしまうことに違和感を感じる方は、遺言書を作成して財産をどのように使ってもらいたいのかを明確にすることをおすすめします。
相続人不存在の場合の手続き

相続人不存在の場合、どのような手続きが行われるのか気になりますよね。ここでは、下記の2つについて順番に解説します。
- 相続人不存在の財産は相続財産清算人が管理する
- 相続人不存在の手続きの流れ
詳しく確認しましょう。
相続人不存在の財産は相続財産清算人が管理する
相続人が不存在のとき、財産は相続財産清算人が管理することになります。
相続財産清算人とは、亡くなった方の財産を管理・清算する人のことを指します。相続財産清算人が担う役割は、下記の通りです。
- 亡くなった方の受遺者や債権者へ支払いをする
- 特別縁故者へ相続財産分与の手続きをする
- 精算後に残った財産を国庫へ帰属させる
相続財産清算人になるために必要な資格はありませんが、相続財産を中立的に清算しなければならないため弁護士や司法書士など専門家が選ばれることが一般的です。
相続人不存在の手続きの流れ
相続発生後、相続人不存在によって財産が国庫へ帰属されるまでの手続きの流れは、下記の通りです。
- 相続財産清算人の選任
- 債権申し立ての公告
- 相続人不存在の確定
- 特別縁故者への財産分与の申し立て
4つのステップに分けて、詳しく確認しましょう。
相続財産清算人の選任
まず、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所は、利害関係者や検察官などの請求を受けたうえで相続財産清算人を選任します。利害関係者とは、亡くなった方の債権者や特別縁故者などです。
相続財産清算人には地域の弁護士や司法書士など専門家が家庭裁判所から選任されることが一般的です。選任後、相続財産清算人選任のお知らせと、本当に相続人不存在であるかどうかを確認するために、被相続人の死亡を官報で6か月以上の期間を定めて公告します。
この期間に相続人の申し出があった場合には、遺産はその相続人へ承継されるため、相続財産清算の手続きは終了です。
債権申し立ての公告
相続財産清算人選任および相続人捜索の公告に加え、家庭裁判所は亡くなった方の債権者や受遺者がいる場合には届出をするように公告します。これを債権申し立ての公告と呼びます。
公告の期間は2か月以上です。期間満了後、届出のあった債権者や受遺者に対して遺産から弁済されます。弁済によってすべての遺産がなくなった場合、相続財産清算手続きは終了します。
相続人不存在の確定
相続人捜索の公告期間が満了し、その間に相続人を名乗り出る人がいなければ相続人不存在が確定します。相続財産清算人の選任から確定までにかかる期間は、最低6か月です。
法改正される令和5年4月1日より前は、相続人不存在確定までに公告手続きを段階的に行わなければならなかったため、相続人不存在の確定までに最低でも10か月以上かかっていました。
しかし、令和5年4月1日の法改正施行によって、相続財産清算人選任の公告と相続人捜索の公告、債権者申し立ての公告の3つの公告を並行して行えるようになったため最低6か月に短縮されています。
特別縁故者への財産分与の申し立て
特別縁故者を主張するには、相続人不存在の確定から3か月以内に家庭裁判所に対して特別縁故者の申し立てと財産分与の請求を行わなければなりません。
家庭裁判所は、申立人を特別縁故者として認定するか、認定する場合にはどれほどの財産を分与するのかを決定します。財産分与の審判の確定後、相続財産清算人は特別縁故者に対して財産分与の手続きを行います。
ただし、すべての財産を特別縁故者が引き継ぐとは限りません。残った分は相続財産清算人の手続きによって国庫へ帰属されます。
また、相続人不存在の確定から3か月以内に申し立てがない場合や、申し立てが却下された場合、亡くなった方の財産はすべて国庫へ帰属されます。
地元の専門家をさがす
相続人不存在の注意点
相続人不存在である場合の注意点は、主に4つあります。
- 行方不明の相続人がいる場合は相続人不存在ではない
- 財産に不動産が含まれる場合は売却して国庫に納められる
- 特別縁故者は不動産の共有者より優先される
- 特別縁故者には相続税が発生する
詳しく見てみましょう。
行方不明の相続人がいる場合は相続人不存在ではない
法定相続人のなかに行方不明者がいる場合、相続人不存在に該当しないとされています。
法定相続人に行方不明者がいるとき、まず行方不明者について不在者財産管理人を選任し、選任された不在者財産管理人が代理で遺産相続手続きを行います。
このように、法定相続人本人は行方不明ではあるものの、あくまでも存在していることを前提に相続手続きを行うため、相続人不存在にはなりません。
ただし、相続開始時に失踪宣告がされていれば、その行方不明者は死亡したものとしてみなされます。つまり、この場合は相続人不存在となります。
しかし、失踪宣告は申し立てから死亡とみなされるまでに1年程度かかるため、相続開始から失踪宣告の申し立てをすることは現実的ではありません。あくまでも相続開始時点で失踪宣告されているかどうかで相続人不存在になるかどうかを判断します。
財産に不動産が含まれる場合は売却して国庫に納められる
相続財産に不動産が含まれる場合、最終的に売却したのちに国庫に納められます。
相続人が不存在の場合、相続財産は自動的に法人化され、その法人を相続財産法人と呼びます。相続財産清算人が選任されたときに、相続財産に不動産が含まれる場合、その不動産登記の名義人を相続財産法人に変更しなければなりません。
また、不動産のままでは国庫に帰属させることはできず、相続財産清算人は不動産を売却して金銭に換価してから国庫に納めるという流れになります。
ただし、民法255条では、「共有者の1人がその持分を放棄したとき又は死亡して相続人がいないときは、その持分は他の共有者に帰属する」と規定されています。つまり、亡くなった方の持分が含まれる相続財産の不動産は、持分移転登記を行うことで、他の共有者のものになります。
特別縁故者は不動産の共有者より優先される
特別縁故者がいる場合、相続財産に含まれる不動産の持分は自分が引き継ぐ権利があると主張するでしょう。
しかし、民法255条で定められているとおり、亡くなった方が残した不動産の持分は相続人不存在だと他の共有者のものになります。
このとき、特別縁故者と不動産の共有者のどちらが優先されるのかという点に疑問が生じます。結論からいうと、最高裁判所の判断では、相続財産に含まれる不動産に共有者がいて、さらに特別縁故者がいる場合、特別縁故者を優先するとしています。
優先順位としては、下記の通りです。
- 相続債権者や受遺者に対する清算手続きを行う
- 特別縁故者に対する財産分与を検討する
- 特別縁故者がいない場合に不動産の共有者へ持分を帰属させる
つまり、特別縁故者がいなくても相続債権者や受遺者への清算によって、不動産の持分が他の人の名義になる可能性もあります。
特別縁故者には相続税が発生する
特別縁故者が相続財産から財産分与を受けた場合、相続税が発生する場合があるため注意しましょう。なぜなら、分与された時点における時価に相当する金額を被相続人からの遺贈によって取得したとみなされるためです。一方、国庫に帰属する場合には課税の心配はありません。
また、特別縁故者が受け取った財産に対して課税される相続税は2割加算されます。
相続税の2割加算とは、被相続人の配偶者や1親等の血族以外が遺産を受け取ったときに、相続税が2割加算される税のルールです。特別縁故者は法定相続人ではないため、2割加算の対象となります。なお、兄弟姉妹が相続した場合にも相続税の2割加算が適用されます。
相続人不存在とは遺産を相続する方が誰もいない状態
相続人不存在とは、亡くなった方が残した遺産を相続する方が誰もいない状態です。民法で定められている法定相続人がいなかったり、法定相続人全員が相続放棄したりした場合などが該当します。
近年は生涯独身の方や子なし夫婦も増えており、相続人不存在となる方が増えてきました。相続人不存在となると遺産は原則国庫へ帰属されます。
しかし、お世話になった方や社会活動をしている団体に財産を遺贈して役立てたいと考える方が多いことも事実です。せっかく築いた財産が国のものになることに違和感がある場合は、財産の譲り先を遺言書で指定することをおすすめします。
遺言書作成で不安を感じる方は、相続に強い弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。相続人不存在であることや財産を譲り渡したい先への思いを伝えると、的確なアドバイスがもらえます。
相続プラスでは、相続に強い専門家を悩み別・エリア別に検索できます。ぜひ活用し、今抱えている悩みを解決しましょう。
地元の専門家をさがす


