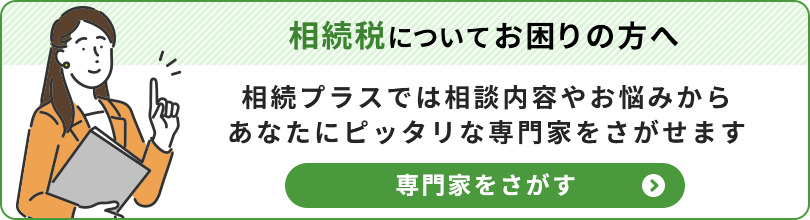土地を相続や贈与で取得したときに評価額を計算するために用いられる書類が「財産評価基準書」です。財産評価基準書を見れば、ご自身で概算の評価額を計算することができます。この記事では、財産評価基準書の概要や相続した土地の評価方法について詳しく解説します。路線価図や評価倍率表の読み方も解説しているため、相続財産のなかに土地が含まれている場合はぜひ参考にしてください。
財産評価基準書とは
財産評価基準書とは、相続税や贈与税を計算するために用いる路線価や倍率などが記載された文書です。土地を相続・贈与によって引き継いだ場合に、土地の評価額を算定するために欠かせない情報が詰まっています。
そもそも、土地には下記のように目的によって5つの異なる価格が設定されています。そのため、土地は「一物五価」と呼ばれることがあり、路線価を基準として評価する場合は「一物四価」とも言われます。
| 価格の種類 | 価格の内容 |
|---|---|
| 実勢価格 | 実際の市場で売買される価格 |
| 公示地価 | 国土交通省が毎年3月に発表する全国約2万6000の基準値となる価格 |
| 基準地価 | 都道府県が毎年9月に発表する全国約2万の基準値となる価格 |
| 相続税路線価 | 国税庁が毎年7月に発表する価格(公示地価の約80%の価格) |
| 固定資産税路線価 | 市区町村が3年に1度発表する価格(公示地価の約70%の価格) |
これらは相互に影響しているものの、異なる価格がつけられています。実勢価格が決定されるときに公示地価を軸に決定していることは事実です。しかし、土地の特徴や周辺環境、売り主・買い主の個別の事情も考慮されています。
財産評価基準書に掲載されている路線価や評価倍率表は相続税路線価に関する内容のため、ここからは路線価を中心に説明していきます。
財産評価基準書について理解を深めるために、下記のポイントをおさえましょう。
- 財産評価基本通達とは
- 財産評価基準書とは
詳しく解説します。
財産評価基本通達とは
財産評価基準書に似た書類に「財産評価基本通達」という書類があります。財産評価基本通達とは、財産評価に関するルールがまとめられたマニュアルのようなものです。
相続税法では、「相続や遺贈、贈与により取得した財産の価額は、取得時における『時価』による」と定められていて、この財産の価格を基準として相続税や贈与税を計算します。
しかし、相続したときの時価を評価することは一般人にとって非常に難しく、評価の方法を間違えると評価額に大きな差額が生まれてしまいます。
そこで、「財産評価基本通達」にまとめられた一律に財産を評価するルールに従って土地を評価することで、公平な課税を実現しているのです。一部の財産を除き、相続財産の多くは財産評価基本通達に基づいて評価方法が定められています。
財産評価基準書とは
相続や贈与で取得した土地の評価についても、財産評価基本通達において路線価方式や倍率方式などの評価方法が規定されています。
評価方式で用いられる路線価や評価倍率表など、具体的な評価基準が記載されている書類こそが財産評価基準書です。つまり、財産評価基本通達で定められたルールに従って相続・贈与で取得した土地を評価するために、財産評価基準書に記載された基準を用いて具体的に算出するという使い方をします。
財産評価基準書は毎年各国税局(沖縄県は沖縄国税事務所)で作成されており、誰でも国税庁の公式サイトから確認することが可能です。
相続した土地の評価額を算出する方法
土地を相続した場合、相続税を算出するために土地の評価額を算出しなければなりません。
土地の評価方法は、基本的には相続した土地の地目ごとに異なります。下記の順番に、地目ごとの評価額計算方法についてご紹介します。
- 宅地の評価方法
- 田・畑の評価方法
- 山林の評価方法
- 地目がわからない場合の調べ方
詳しく確認しましょう。
宅地の評価方法
相続で引き継ぐ土地のなかで最も多い地目は、宅地でしょう。
宅地とは地目の1つで、建物の敷地、及びその維持・効用を果たすための土地のことを指します。例えば、住宅や店舗などの建物を建てるための土地や建物に関連する庭や私道などが該当します。
宅地を評価する方法は、路線価方式か倍率方式かのどちらかです。路線価が設定されている場合、路線価図の数字を基準として、地積や補正率を考慮して評価額を算出することになります。一方、路線価がない場合は、評価倍率表に記載されている数字を固定資産税評価額に乗じて評価額を算出します。
貸宅地である場合は借地権割合の分だけ評価額が減額されるため、路線価図で借地権割合をチェックしましょう。
田・畑の評価方法
相続した土地が田・畑の場合、区分によって評価方法が異なります。田・畑は、都市部の近さに応じて4つの区分に分けられています。それぞれの評価方法を表にまとめました。
| 農地の区分 | 概要 | 評価方法 |
|---|---|---|
| 純農地 | 農業の生産性が高く、宅地に転用することがほとんど不可能とされる農地 | 倍率方式 |
| 中間農地 | 許可を得られれば宅地への転用が可能で、売買できる可能性のある農地 | 倍率方式 |
| 市街地周辺農地 | 市街化傾向が強いエリアにある農地 | その土地が市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する額 |
| 市街地農地 | 市街化区域内にある農地や、すでに農地以外への転用許可を受けている農地などとして都道府県知事の指定を受けている農地 | 宅地比準方式、または倍率方式 |
市街地農地の評価額算出に宅地比準方式を用いる場合、下記の計算式で評価額を導きます。
- 市街地農地の評価額=(その農地が宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額−1㎡の造成費)×農地の地積
計算式に出てくる造成費は、その農地を宅地に転用するときに発生する費用のことです。
田・畑を相続した場合は、まずどの農地に該当するかを確認するようにしましょう。
山林の評価方法
山林とは、樹木や竹が生育する土地のことです。
相続した土地が山林の場合、区分によって評価方法が異なります。山林は、都市部の近さに応じて3つの区分に分けられています。それぞれの評価方法を表にまとめました。
| 農地の区分 | 概要 | 評価方法 |
|---|---|---|
| 純山林 | 市街地から遠く離れたエリアにある山林 | 倍率方式 |
| 中間山林 | 純山林と市街地山林の中間にある山林 | 倍率方式 |
| 市街地山林 | 市街地にある山林 | 比準方式、または倍率方式 |
市街地山林で用いられる比準方式を用いる場合、下記の計算式で評価額を導きます。
計算式に出てくる造成費は、その山林を宅地に転用するときに発生する費用のことです。
なお、市街地山林が所在するエリアが評価倍率表において倍率方式を用いて山林の評価を行う区域に該当する場合、比準方式であっても倍率方式で評価を行います。
地目がわからない場合の調べ方
地目がわからない場合、土地の登記簿を確認すれば解決できます。登記簿は、法務局の窓口で発行してもらうか、郵送やオンラインでも請求することが可能です。
登記簿には、通常「地目コード」が記載されています。地目コードは1〜23まであり、どの土地もいずれかの地目に分類されています。
ここでは、相続や贈与でよく見る地目の番号について表にまとめました。
| 地目コード | 地目 |
|---|---|
| 1 | 田 |
| 2 | 畑 |
| 3 | 宅地 |
| 7 | 山林 |
なお、実際の利用状況と一致しない場合もあります。登記簿上の地目と現況が異なる場合、現況が優先されるため注意しましょう。
また、固定資産税納税通知書にも地目が掲載されていますが、これはその年の1月1日の現況の地目とされていて、課税地目と呼びます。
財産評価基準書の読み方

財産評価基準書は、国税庁の公式サイトから閲覧することが可能です。ここでは、財産評価基準書の読み方を下記の4つのステップに分けてご紹介します。
- 相続の年分・土地がある都道府県を選択する
- 評価方法を選択する
- 土地がある地域を選択する
- 評価額を読む
詳しく確認し、財産評価基準書の見方をマスターしましょう。
参考:財産評価基準書|国税庁
相続の年分・土地がある都道府県を選択する
まず、「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」へアクセスし、ページ上部から調べたい年分を選択して、日本地図の中から調べたい都道府県を選択しましょう。
選択する年分は、相続によって取得した土地については被相続人が亡くなった年、贈与の場合は贈与を受けた年を選択します。
評価方法を選択する
都道府県を選択すると、土地の評価方法を選択する画面に移動します。
調べたい土地が路線価方式で評価するエリアであれば「路線価図」、倍率方式で評価するエリアであれば「評価倍率表」を選択します。どちらか判断できない場合は、「評価倍率表」から「一般の土地用」を選択しましょう。
土地がある地域を選択する
つづいて、相続・贈与によって取得した土地のある市区町村を選択します。すると、選択した市区町村の路線価図、あるいは評価倍率表が表示されます。
評価額を読む
最後に、表示された評価額を見ていきましょう。路線価図と評価倍率表とで読み方が異なるため、それぞれ読み方をご紹介します。
路線価図の場合
路線価図は「120D」「105G」などのように、数字+アルファベットで表示されます。
数字は、その道路に面する標準的な土地の1㎡あたりの価格を1千円単位で表しています。
また、アルファベットは借地権割合を表しています。借地権割合とは、土地の更地評価額に対する借地権の割合です。土地の権利のうち借地権が占める割合を30〜90%の範囲で定めています。
書かれているアルファベットが示す借地権割合は、下記の表の通りです。
| 路線価図のアルファベット | 借地権割合 |
|---|---|
| A | 90% |
| B | 80% |
| C | 70% |
| D | 60% |
| E | 50% |
| F | 40% |
| G | 30% |
例を挙げると、「120D」と書かれている場合、1㎡あたり12万円の土地で借地権割合は60%いう意味になります。
評価倍率表の場合
評価倍率表を開くと、町名または大字名が五十音順に並べられている表が表示されます。まず、調べたいエリアに該当する場所を見つけましょう。
表の左側に「固定資産税評価額に乗ずる倍率等」と書かれた部分があるため、該当する土地の地目から倍率を確認します。
相続した土地が宅地であれば、宅地に書かれている数字が倍率方式に用いる数値です。
ただし、なかには「路線」「比率」「中42」などと表示されている場合があります。路線と書かれている場合、「路線価が出ているため路線価方式で評価する」という意味合いです。
また、田・畑の欄に「比準」と書かれていれば宅地比準方式で評価すること、「中+数字」と書かれていれば中間農地であることと倍率方式で評価することが示されています。
相続した土地の評価額に関するよくある質問
最後に、相続した土地の評価額に関してよくある質問についてご紹介します。
- 相続した土地の評価額を専門家に算出してもらうことはできる?
- 相続した土地が路線価図で「個別評価」となっているが、どういう意味?
- 貸し出している土地はどのように評価額を算出する?
- 国税庁の路線価と全国地価マップの路線価に違いはある?
Q&A形式で疑問にお答えしているため、最後まで確認しましょう。
相続した土地の評価額を専門家に算出してもらうことはできる?
相続した土地の評価額を専門家に算出してもらうことは可能です。
財産評価基準書の読み方を知っていれば、相続した土地のおおまかな評価額の算定はできます。しかし、正確な評価を行うには単純に計算するだけでなく、土地の形や周辺環境も考慮しなければなりません。
評価額が間違っていると相続税を余分に納めてしまったり、あとから追徴課税されたりする可能性があるため、相続した土地の評価額は、専門家に相談して算出してもらうことをおすすめします。専門家に相談することで、より精度の高い評価が期待できます。
相続した土地の評価額算定の依頼ができる専門家は、税理士と不動産鑑定士です。
相続や贈与に強い税理士に相談すると、財産評価基準書に従って正しい評価額を算出してもらえます。相続税や贈与税の申告もまとめて依頼できるため、おすすめです。
一方、不動産鑑定士は鑑定評価をしてくれます。財産評価基準書より時価が安い場合、相続税評価を下げられる可能性があり、節税につながる可能性があります。
例えば、土地がいびつな形をしている場合や、土壌汚染がある場合など、土地の価値を引き下げる要因があるのであれば、不動産鑑定士に評価してもらうとよいでしょう。
相続した土地が路線価図で「個別評価」となっているが、どういう意味?
路線価図をみていると、「個別評価」と記載されている土地があります。
個別評価の多くは、土地区画整理事業の施行区域、もしくは市街地再開発事業の施行区域です。路線価がつけられていないため、路線価方式で土地の評価ができません。また、倍率方式でも評価できない土地です。
個別評価と記載されている土地を相続した場合、税務署に対して個別評価を申し出る必要があります。申告の方法は、国税庁の「個別評価申出書」を作成し、所定の添付書類を担当税務署に提出します。
個別評価申出書は、下記よりダウンロードが可能です。
提出先はかならずしも納税地を管轄する税務署とは限らないため、注意しましょう。
また、個別評価の申し出から評価結果が出るまでに1か月程度かかります。相続税や贈与税の申告期限に余裕を持って申し出を行うようにしましょう。
貸し出している土地はどのように評価額を算出する?
人に貸し出している土地を相続した場合、評価方法が少し変わります。
他人が使用する権利を持っていない自用地と比べると、人に貸し出している賃宅地や賃家建付地は土地の評価が減額されます。なぜなら、土地や建物の借主には一定の権利が付与されており、土地所有者の判断で自由に土地を利用することができないためです。
賃宅地か賃家建付地かによって評価額を求める計算式が異なるため、それぞれ見てみましょう。
まず、賃宅地とは、他人に貸し出しており、そこに他人所有の建物が建てられている土地のことです。賃宅地を相続したときに評価額を求める計算式は、下記の通りです。
- 相続税評価額=自用地としての評価額×(1-借地権割合)
次に、賃家建付地とは、賃貸マンションや賃貸アパートなどの自己所有の建物が建設されており、その建物を他人に貸している土地のことです。
賃家建付地を相続したときに評価額を求める計算式は、下記の通りです。
- 相続税評価額=自用地としての評価額×{1-(借地権割合×借家権割合×賃貸割合)}
自用地としての評価額は、これまで説明してきた通りに路線価方式や倍率方式などで求めます。
また、借地権割合は路線価や評価倍率表に記載されています。なお、賃家建付地の評価で用いる借家権割合は、全国一律で30%です。

国税庁の路線価と全国地価マップの路線価に違いはある?
一般財団法人資産評価システム研究センターが掲載している「全国地価マップ」からも、路線価を確認することは可能です。
国税庁の路線価と全国地価マップの路線価の違いは、路線価の検索方法と最新の路線価が反映されるタイミングです。
国税庁では地図から調べたいエリアを選んで路線価を確認しますが、全国地価マップでは検索窓に市区町村か郵便番号を入力するだけで路線価の確認ができます。国税庁と比べて利便性が高いといえるでしょう。
ただし、最新の路線価が反映されるタイミングは国税庁の方が早いです。そもそも路線価は国税庁が公表するデータのため、全国地価マップへの反映に時差が発生します。
毎年7月に国税庁から公表されますが、それから数か月後に全国地価マップが更新されるため注意しましょう。
財産評価基準書だけでは相続した土地の適正評価額はわからない
相続や贈与によって土地を取得した場合、相続税や贈与税の算定のためには土地の評価額を算出する必要があります。財産評価基準書を見ればおおまかな評価額を概算できるものの、正確な相続税評価はわかりません。
なぜなら、正確な相続税評価を算定する際には土地の形や周辺環境などを考慮する必要があり、専門的な知識が不可欠だからです。万が一、間違った評価額で相続税や贈与税を申告すると、税金の納め過ぎが起きたり追徴課税を請求されたりするかもしれません。
相続や贈与によって土地を取得する場合は、専門知識を持ち合わせている税理士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家の力を借りて、正しい土地の評価額を知ったうえで税申告をしましょう。