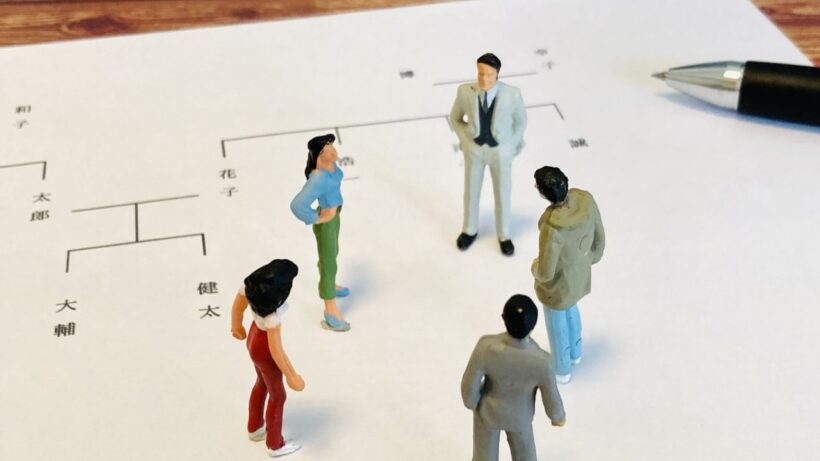相次相続控除とは、10年以内に二次相続が発生したときに、同じ財産に対して短期間で2回発生する相続税の負担を軽減できる制度です。短い期間に何度も相続が発生すると税負担が重くなるため、公平性を保つために設けられています。本記事では、相次相続控除が適用される要件や控除を受ける方法、注意点について詳しく解説します。
地元の専門家をさがす
相次相続控除とは
相次相続控除とは、相続開始前10年以内に、被相続人が相続・遺贈・相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を引き継ぎ、その際に相続税が課されていた場合に、その財産に対する二次相続の相続税から一定の金額を控除する制度です。
そもそも、相次相続とは短い期間に相続が重なることを指します。「相次いで発生する相続」と考えるとわかりやすいでしょう。
例えば、両親の片方が先に亡くなったときに発生する相続を一次相続、そのあとに存命だった方が亡くなったときに発生する相続を二次相続と呼びます。
短い期間で立て続けに相続が発生すると、大きな相続税の負担が発生する可能性があります。仮に、父親が亡くなったときに相続税が発生し、そのあとすぐに母親が亡くなって相続税が発生した場合、同じ相続財産に対して重複して課税されてしまうことになりかねません。
そこで、重複課税を防止する目的として、要件を満たした場合に相次相続控除という税負担を軽減する制度が設けられています。相次相続控除は一次相続における相続税申告では受けられず、二次相続における相続税申告で控除を受けることが可能です。

相次相続控除を受ける方法
相次相続控除を受ける方法について、下記の3つのステップごとに解説します。
- 相次相続控除が適用される要件を確認する
- 控除の金額を計算する
- 控除を受けるための書類を提出する
相次相続控除が適用されるかどうかも含め、詳しく確認しましょう。
相次相続控除が適用される要件を確認する
まず、相次相続控除が適用される要件を満たしているか確認しましょう。
相次相続控除が受けられる人は、下記のすべての要件に当てはまる場合に限られます。
- 被相続人の法定相続人であること
- 一次相続から10年以内に二次相続が発生していること
- 二次相続における被相続人が一次相続で財産を取得し相続税が課税されていること
それぞれ詳しく解説します。
被相続人の法定相続人であること
1つ目の要件は、被相続人の法定相続人であることです。法定相続人とは、民法で定められている相続する権利を持つ親族のことです。
そのため、相続放棄をした人や、欠格・廃除によって相続する権利を失った人は対象になりません。
なお、一次相続および二次相続において、遺言書によって財産を譲り受けた人であっても法定相続人には該当しません。
一次相続から10年以内に二次相続が発生していること
2つ目の要件は、一次相続の開始から10年以内に二次相続が発生していることです。「一次相続の開始」とは、一次相続における被相続人が亡くなった日を指します。
一次相続の開始日から起算する相続税申告の期限とは異なるため注意しましょう。
例えば、2021年(令和3年)4月10日に一次相続が発生した場合、2031年4月10日までに二次相続が発生した場合に相次相続控除適用の対象となります。
二次相続における被相続人が一次相続で財産を取得し相続税が課税されていること
3つ目の要件は、二次相続における被相続人が一次相続で法定相続人として財産を取得しており、相続税が課税されていることです。
そのため、二次相続における被相続人が一次相続で財産を相続していたとしても、遺産総額が基礎控除額を超えていない場合や、配偶者控除などの適用により相続税が0円になった場合には、相次相続控除は適用外です。
あくまでも、一次相続において「相続税の申告をしたか」ではなく、「相続税を納税したか」が焦点となるため注意しましょう。
控除の金額を計算する
続いて、相次相続控除の金額を計算することになります。控除額は、一次相続で二次相続における被相続人に課税された相続税の額を元に算出します。
この一次相続で課税された相続税の額に対して、1年あたり10%減額した金額を二次相続で発生する相続税の額から控除します。
具体的な計算式と計算例について詳しく確認しましょう。
相次相続控除の金額の計算式
それぞれの相続人が受けられる相次相続控除の金額の計算式は、下記の通りです。
相次相続控除の金額=A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10
※ただし、C/(B-A)の割合が100/100を超える場合は100/100として計算
アルファベット部分には、下記の要素が該当します。
| A | 二次相続における被相続人が一次相続の際に課せられた相続税の額 ※相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額 |
|---|---|
| B | 二次相続における被相続人が一次相続の際に取得した財産の額 ※「取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務および葬式費用の金額」で算出 |
| C | 二次相続において相続・遺贈・相続時精算課税にかかる贈与によって取得したすべての人が取得した財産の合計額 |
| D | 相次相続控除を適用する相続人が二次相続において相続・遺贈・相続時精算課税にかかる贈与によって取得した財産の額 |
| E | 一次相続から二次相続までの年数 ※1年未満の期間は切り捨て |
この例を用いて、それぞれの場合の計算例を説明していきます。
相次相続控除の金額の計算例
ここでは、下記のような場合における相次相続控除の金額について計算例をご紹介します。
- 法定相続人:長男・次男の2人
- 一次相続:父親が令和2年1月30日に死亡。このとき母親が12億円の財産を相続し、2億円の相続税を課税された。
- 二次相続:母親が令和6年10月20日に死亡。長男は純資産価額6億円相続し、次男は純資産価額3億円相続した。
このとき、二次相続で受けられる長男と次男それぞれの相次相続控除の額は、下記の通りです。
<長男>
A:2億円
B:12億円
C:9億円(6億円+3億円)
D:6億円
E:4年(1年未満は切り捨て)
控除額:2億円×9億円/(12億円-2億円)×6億円/9億円×(10-4)/10=7200万円
<次男>
A:2億円
B:12億円
C:9億円(6億円+3億円)
D:3億円
E:4年(1年未満は切り捨て)
控除額:2億円×9億円/(12億円-2億円)×3億円/9億円×(10-4)/10=3600万円
計算の結果、長男は7200万円、次男は3600万円ずつ相続税額を控除できます。
控除を受けるための書類を提出する
相次相続控除を受けるには、税務署に提出する相続税申告書と一緒に下記の書類の作成と提出が必要です。
また、一次相続の相続税申告時に提出した書類も一緒に添付すると、わかりやすくなります。
- 第1表 相続税の申告書
- 第11表 相続税がかかる財産の明細書
- 第11表の2 相続時精算課税適用財産の明細書など
※相続時精算課税制度の対象となる生前贈与がある場合のみ
- 第14表 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額などの明細書
※暦年課税制度の生前贈与加算の対象となる贈与がある場合のみ
- 第15表 相続財産の種類別価額表
相次相続控除を受けるための手続きは相続税の申告と一緒に行うため、相続開始の日の翌日から10か月以内に書類を準備しましょう。被相続人の最後の住所地を管轄する税務署の窓口に直接提出するか郵送、あるいはe-Taxを利用した電子申告にて手続きができます。
なお、相次相続控除を適用させて相続税が0円になる場合、相続税の申告は原則不要です。書類の提出や税務署に出向くなどの必要もありません。
ただし、相続税の申告が不要であっても、相続税申告をした方がよい場合もあります。控除の適用方法や申告すべきかどうかがわからないときは、積極的に税理士に相談して個別に解決してもらうことをおすすめします。
地元の専門家をさがす
相次相続控除が適用される場合・されない場合

ここからは、相次相続控除が適用される場合と、適用されない場合について、それぞれ解説していきます。
- 相続放棄をしていると控除を受けられない
- 一次相続で相続税が発生していない場合は適用できない
- 同時死亡の場合は適用できない
- 相続税の申告後でも控除を受けられる
- 相続財産の分配方法が確定していなくても適用できる
- 3回目以降の相続でも適用できる
詳しく確認していきましょう。
相続放棄をしていると控除を受けられない
一次相続・二次相続のいずれかで相続放棄をしていると、相次相続控除の適用を受けることができません。
例えば、父親が死亡した一次相続時に、長男へ事業を継がせるために母親が相続放棄をしていたとしましょう。相続放棄をしても父親の生命保険金は受け取れるため、遺贈として受け取っていたと仮定します。
しかし、一次相続において母親は相続放棄をしたため法定相続人ではなく、相次相続控除の要件である「被相続人の法定相続人である」を満たしていません。そのため、母親が亡くなった二次相続が発生しても、二次相続における相続人は相次相続控除の対象外です。
なお、相続人欠格・廃除の場合にも対象外となります。一方で、法定相続人であれば兄弟姉妹間の相続でも適用することができます。
一次相続で相続税が発生していない場合は適用できない
控除の目的は二重課税の負担減少のため、一次相続で相続税が発生していなければ控除を受けられない点に注意しましょう。申告をしたかどうかではなく、納税したかどうかがポイントとなります。
例えば、配偶者控除を使えば1億6000万円まで、もしくは配偶者の法定相続分までであれば相続税は課税されません。ほかにも、小規模宅地等の特例や障害者控除などを適用させて相続税が0円になっていたのであれば、二次相続での相次相続控除は適用外です。
同時死亡の場合は適用できない
交通事故や震災などによって、同時に死亡した場合には原則相次相続控除の適用ができません。例えば、両親2人が同じ震災に巻き込まれて亡くなった場合、亡くなる前10年以内に相続人として財産を取得しておらず、相続税の課税もないからです。
ただし、過去10年以内の相続で父親か母親が相続人となっており、相次相続控除の要件に当てはまる場合は控除を受けることができます。
相続税の申告後でも控除を受けられる
相次相続控除の適用を忘れて相続税の申告をしていた場合でも、申告期限から5年以内であれば相次相続控除の適用を受けられます。実際には、更正の請求によって納め過ぎた相続税の還付を求めることが可能です。
更正の請求と同様に、相続税の過少申告をしていた際に正しい相続税の金額を申告し直す修正申告の際に相次相続控除を適用することもできます。ただし、修正申告にかかる延滞税や過少申告加算税などについては、相次相続控除は適用できません。
相続財産の分配方法が確定していなくても適用できる
相続税の申告期限である相続開始の日の翌日から10か月以内に相続財産の分配方法が確定していなくても、相次相続控除の適用を受けられます。
遺産分割の内容が決まっていない場合、法定相続分で相続したものと仮定して、相続分の申告を行います。この際に相次相続控除の適用が可能です。
ただし、申告を後日やり直す必要がある点に注意しましょう。
3回目以降の相続でも適用できる
3回目の相続であっても、相次相続控除の適用が可能です。3回目の相続で亡くなった方が前回・前々回の相続において法定相続人として相続税を納めていることや、一次相続から10年以内に相続が発生していることなどが要件となります。
例えば、父親・母親・長男・次男の4人家族のうち、父親が亡くなり、次に母親が亡くなり、さらに長男が亡くなったとき、長男に子どもがいなければ、次男がすべての相続において法定相続人となって相次相続控除を受けられる可能性があります。
相次相続控除を受けるときに知っておきたい注意点
相次相続控除を受けるときに知っておきたい注意点は、2つあります。
- 相次相続控除で相続税が0円になっても申告をしたほうが良い場合がある
- 相次相続控除の額は相続人の間で自由に分配できない
詳しく確認しましょう。
相次相続控除で相続税が0円になっても申告をしたほうが良い場合がある
原則、相次相続控除を適用させて相続税の額が0円になるとき、相続税の申告は不要です。しかし、二次相続で取得した相続財産を相続開始から3年10か月以内に売却するつもりなら相続税申告をしておくことをおすすめします。
なぜなら、取得費加算の特例を適用させられる可能性があるからです。
取得費加算の特例とは、相続財産の売却益に課せられる譲渡所得税の計算において、売却した相続財産の対価の額から控除する取得費にその財産に対して発生した相続税額も加算できる制度です。
取得費に加算する相続税は、相次相続控除を適用させる前の税額を元に計算します。つまり、相次相続控除によって相続税が0円になったとしても、譲渡所得税を減税できる可能性があります。
しかし、取得費加算の特例を活用するには、相続税の申告をしていなければなりません。そのため、相続財産を売却するつもりなのであれば、将来の税負担を軽減させるためにも相続税の申告をしておきましょう。
相次相続控除の額は相続人の間で自由に分配できない
相次相続控除を適用させる二次相続において、相次相続控除の額を相続人の間で自由に分配することができません。
例えば、相続税の未成年者控除や障害者控除は、本人が使いきれなかった控除額について、扶養義務者全員で協議をして他の相続人への分配割合を決められます。
しかし、相次相続控除は、それぞれの相続人が取得した財産の額によってあん分されるため、控除額を他の相続人に分配することができません。あくまでも、相続人ごとに相次相続控除の額を計算する点に注意しましょう。
相次相続控除は複雑なため税理士に相談しよう
相次相続控除の適用を受けるには、細かな要件を満たす必要があるうえに、控除額の算出方法がとても複雑です。更に間違った申告をすると、ペナルティを受ける場合があります。
また、相続税には相次相続控除の他にも適用できる控除がたくさんあります。相続税が発生する可能性がある場合は税理士へ相談しましょう。申告書や税の計算に対応してくれることはもちろん、節税の相談にも対応出来ます。
積極的に税理士の力を借りて、さまざまな控除や特例を活用して相続税の負担を軽減させましょう。
地元の専門家をさがす