土地を相続する場合、どれほどの相続税が発生するのか気になりませんか。相続財産のなかに土地が含まれている場合、一般的に相続税路線価を用いて相続税評価額を算出します。本記事では、相続税路線価の基礎知識から調べ方、土地評価額の計算方法について詳しく解説します。相続税の計算例や路線価の注意点も解説しているため、ぜひ参考にしてください。
路線価とは
路線価とは、国税庁が発表する道路に面した土地の1㎡あたりの評価額です。毎年1月1日時点に算定された評価額が発表されます。
一般的に「路線価」というと「相続税路線価」を示し、相続税や贈与税を算定する際に用いられます。
相続税評価額の概算額の計算方法は、下記の通りです。
相続税評価額(概算)=路線価×土地の面積
実際の相続税評価額は土地の形や接している道路の数などによって、奥行価格補正や側方路線影響加算を行って補正しなければなりません。
また、路線価には固定資産税や不動産取得税などを計算するときに用いられる「固定資産税路線価」を示す場合もあるため注意しましょう。
さらに、路線価以外にも、土地の価格を決めるために公示地価や実勢価格が用いられる場合もあります。路線価は公示価価格の8割程度となっており、税負担が少なくなるように設定されています。
より路線価について理解を深めるために、下記の順番に詳しく確認していきましょう。
- 相続税路線価と固定資産税路線価
- 路線価以外の土地の価格(公示地価・実勢価格)
順番に解説します。
「令和6年度の路線価」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
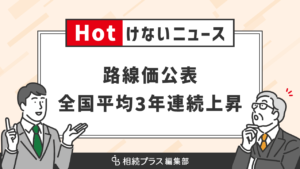
相続税路線価と固定資産税路線価
相続税路線価と固定資産税路線価の大きな違いは、評価を行う機関です。
相続税路線価は国税庁によって評価されますが、固定資産税路線価は市区町村(東京23区は東京都)によって評価されます。相続税は国税である一方、固定資産税は市区町村が管轄する地方税であるためです。
ほかにも違いがたくさんあるため、それぞれの違いを下記の表にまとめました。
| 項目 | 相続税路線価 | 固定資産税路線価 |
|---|---|---|
| 評価主体 | 国税庁 | 市区町村 (東京23区は東京都) |
| 求められる評価額 | 土地の相続税評価額 | 土地の固定資産税評価額 |
| 利用される税金の種類 | 相続税 贈与税 | 固定資産税 登録免許税 不動産取得税 都市計画税 |
| 評価頻度 | 毎年 | 3年に1度 |
| 価格時点 | 1月1日 | 基準年の1月1日 |
| 発表される時期 | 毎年7月頃 | 基準年の4月頃 |
| 価格水準 | 公示価格の80%程度 | 公示価格の70%程度 |
相続税路線価は毎年評価され、価格がその度に更新されます。相続税を計算する際は、相続が発生した年の1月1日に評価された路線価を使わなければなりません。
一方、固定資産税路線価は3年に1度しか評価の更新がないため、価格も3年に1度の更新となります。これから土地を取得する方は、基準年に発表された固定資産税路線価を活用して固定資産税評価額を推測できます。
ただし、土地所有者には毎年送付される固定資産税納税通知書で正確な固定資産税評価額を知ることができます。そのため固定資産税路線価を調べる機会は少ないでしょう。
相続税評価額も固定資産税評価額も、それぞれの路線価に土地面積を乗じると概算額が求められます。正確な評価額を計算するには専門的な知識が必要となるため、専門家に相談することをおすすめします。
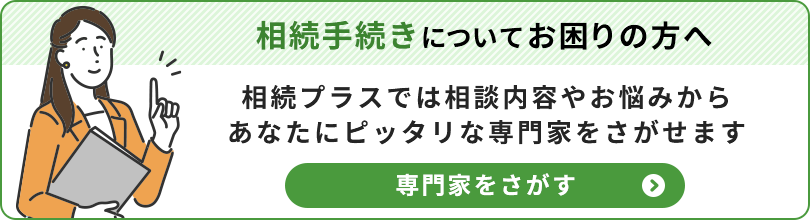
路線価以外の土地の価格(公示地価・実勢価格)
路線価以外にも、公示地価や実勢価格などのように基準となる土地の価格が設定されています。
まず、公示地価とは、全国2万6000地点の土地の単価です。国土交通省が発表している価格で、土地取引や資産評価を行うときの目安として活用されています。公示地価も、毎年1月1日に評価され、毎年発表されます。
一方、実勢価格とは、実際に土地取引がされている相場水準の価格です。公示価格は実勢価格の50~90%程度となっており、公示価格よりも実際には高い価格で土地の売買取引が行われていることがわかります。
「不動産評価額の計算方法」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

相続税路線価の調べ方と土地評価額の計算方法
ここからは、相続税路線価の調べ方と土地評価額の計算方法について下記の順番に解説します。
- 相続税路線価の調べ方
- 相続税路線価図の見方
- 路線価の補正
- 土地評価額の計算方法
詳しく確認しましょう。
相続税路線価の調べ方
相続税路線価は、下記のWebサイトより調べることができます。
どちらのWebサイトからでも、地図をクリックして目的の土地を指定すれば路線価がわかります。
国税庁のWebサイトは、紙ベースの路線価図がもととなってWebサイトにアップロードされているため、慣れていなければ町名やページ番号から目的の土地を探すことが難しいかもしれません。
資産評価システム研究センターのほうが分かりやすいと感じる方は多いため、ぜひ活用しましょう。
相続税路線価図の見方
目的の土地を指定すると、指定したエリアの地図に「150D」「420B」などのように数字とアルファベットが表示されています。路線価を知るには、数字の部分を確認しましょう。
表示されている数字を1000倍したものが、その土地の路線価です。たとえば「150D」と書かれている場合、150×1000=15万円の路線価が設定されているとわかります。つまり、この道路に面している土地の1㎡あたりの価格は、15万円です。
また、数字のあとに表記されているアルファベットは、借地権割合を示しています。A〜Gまでのいずれかが割り当てられており、下記のように設定されています。
| 表記されているアルファベット | 借地権割合 |
|---|---|
| A | 90% |
| B | 80% |
| C | 70% |
| D | 60% |
| E | 50% |
| F | 40% |
| G | 30% |
借地権割合とは、土地の貸主と借主の権利の割合です。借地権割合が大きいと、借り手側の権利が大きくなります。賃貸物件や人に貸している土地の評価額の計算に活用します。
路線価の補正
単純な四角形の平らな土地であれば、路線価を土地面積に乗じるだけで概算額を求めることができます。
しかし、実際にはきれいな四角形の土地は少なく、一般利用のしづらい部分に対して減額の補正をかけなければ正しい評価額が導き出せません。
土地の形にもとづいて減額させる路線価の補正には、以下の5つの種類があります。
| 補正 | 内容 |
|---|---|
| 奥行価格補正 | 土地の奥行が一般的な土地と比較して長い・短い場合に行う補正 |
| 不整形地補正 | 台形や三角形など、土地の形がいびつな場合に行う補正 |
| 間口狭小補正 | 道路に面している間口が狭い土地の場合に行う補正 |
| 奥行長大補正 | 間口の幅が狭いにもかかわらず奥行きが長い土地に行う補正 |
| がけ地補正 | 平坦な部分と通常の用途に利用できないと認められるがけ部分が一体となっている土地に行う補正 |
該当すれば、すべて適用させて補正をかける必要があります。
一方、複数の道路に接している土地は利用価値が高く、路線価を増額させるための補正を行います。接道の状況に応じた路線価の補正の種類は、下記の2つです。
| 補正 | 内容 |
|---|---|
| 側方路線影響加算 | 交差点や道路の角地で複数の道路に接している土地に行う補正 |
| 二方路線影響加算 | 2つの道路に挟まれている土地に行う補正 |
それぞれの補正率は条件によって異なり、国税庁の公式サイトから確認しましょう。
ただし、専門的な知識がなければ、正確な評価額を算出することは簡単ではありません。なぜなら、間口と奥行きのバランスや、がけのある方角など、細かな条件が設定されているからです。
誤った認識で土地評価額を算出してしまうと、相続税が低く見積もられてしまい、いざ納税を行う際に「予想以上の支払いが必要だった」と慌てなければなりません。
早めに専門家に相談し、相続税の申告・納税に備えましょう。
土地評価額の計算方法
土地評価額の計算方法は、目的の路線価と補正率を調べたうえで下記の計算式に当てはめます。
土地の相続税評価額=相続税路線価×土地面積(㎡)×補正率
たとえば、路線価520Eの立地で120㎡の土地を相続し、その土地が奥行価格補正0.95%の条件に当てはまるとき、相続税評価額は下記の通り算出します。
土地の相続税評価額=52万円×120㎡×0.95=5928万円
補正によって評価額は大きく変わるため、専門家に正しい補正率を確認してもらいましょう。
路線価を使った相続税の計算例

相続財産に土地が含まれているとき、路線価を活用して相続税評価額を算出して相続税を計算する必要があります。
実際に支払う相続税がいくらになるのか、下記のような相続が発生したときを例に計算方法について確認しましょう。
- 相続した土地の条件:路線価400D、面積150㎡
- 他の相続財産(預金)の合計:1億円
- 相続人:妻・子ども2人
- 相続割合:妻が60%、子ども2人が20%ずつ
まず、相続税の計算をするために相続税評価額を計算しましょう。ここでは分かりやすいように、補正の必要のない土地とします。
土地の相続税評価額=40万円×150㎡=6000万円
土地の相続税評価額がわかったため、相続財産の総額を算出します。
相続財産の総額=1億円+6000万円=1億6000万円
次に、基礎控除額について計算します。
基礎控除額=3000万円+(600万円×3人)=4800万円
基礎控除額が分かったため、相続税の課税対象額を算出しましょう。
相続税の課税対象額=1億6000万円–4800万円=1億1200万円
1億1200万円に対して相続税が課税されるため、相続税の税率を乗じて相続税額を算出します。まずは、法定相続通りに相続したと仮定して、それぞれの相続人の課税額を計算します。
- 妻の課税額=1億1200万円×2分の1=5600万円
- 子ども2人の課税額=2800万円ずつ
それぞれの課税額に応じた税率を乗じ、控除額を適用させて相続税額の合計を計算しましょう。
- 妻の相続税=5600万円×30%−700万円=980万円
- 子ども2人の相続税=2800万円×15%−50万円=370万円ずつ
それぞれの相続税額の合計を足した1720万円が相続税の総額です。相続税の総額である1720万円を実際に相続した割合を乗じて、それぞれが負担する相続税額を算出します。
- 妻が負担する相続税額=1720万円×60%=1032万円
- 子ども2人が相続する相続税額=1720万円×20%=344万円ずつ
上記が実際に負担する相続税の内訳となります。実際には、配偶者控除や小規模宅地等の特例などを活用して税負担を大幅に軽減できます。
土地の相続税評価額や相続税の計算はとても複雑です。専門知識がなければ間違った申告をしてしまうことになりかねません。正しい相続税の申告・納税を行うためにも、専門家に相談することをおすすめします。
「相続税の計算」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
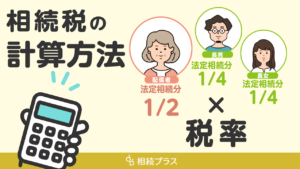

路線価に関して知っておきたいこと・注意点
路線価に関して知っておきたいこと・注意点は、4つあります。
- 2つの道路に面している土地の相続税評価額は表面路線価を決定する
- 路線価がない土地は評価倍率表を用いる
- ケースに応じた適切な補正が必要
- 相続や贈与のあった年の路線価を使用する
順番に確認しましょう。
2つの道路に面している土地の相続税評価額は表面路線価を決定する
間口と奥行き、2つの間口など、2つの道路に面している土地相続税評価額は表面路線価を決定して計算する必要があります。
たとえば、下記のような土地を相続するときの相続税評価額について詳しく確認しましょう。
- 土地のある場所:普通住宅地区
- 接道条件:東側20m・南側8m
- 土地面積:160㎡
- 路線価:東側150D・南側200D
原則として、土地に面する路線の路線価に奥行き価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線が正面路線です。
- 東側:路線価15万円×補正率1.00=15万円
- 南側:路線価20万円×補正率0.97=19万4000円
今回のケースでは、上記のように南側の方が高い路線価となるため、南側が正面路線、東側が側方路線となります。
ここからは、土地の相続税評価額を求める方法について見ていきましょう。
まず、側方路線である東側について、側方路線影響加算率から正面路線価に加算する価格を算出します。
路線価15万円×奥行き価格補正率1.00×側方路線影響加算率(角地)0.03=4500円
最後に、土地の相続税評価額を計算します。
土地の相続税評価額=(正面路線価20万円+4500円)×160㎡=3272万円
このように計算が複雑となるため、注意しましょう。
参照:正面路線の判定(1)|国税庁/奥行価格補正率表(昭45直資3-13・平3課評2-4外・平18課評2-27外・平29課評2-46外改正)・側方路線影響加算率表(平3課評2-4外・平18課評2-27外改正)|国税庁
路線価がない土地は評価倍率表を用いる
都市部や大きな道路には路線価が設定されていますが、郊外や山間部の道路のなかには路線価が設定されていないケースもあります。
路線価が設定されていないエリアの相続税評価額を計算する場合、倍率方式を活用します。「国税庁のWebサイト」から、「評価倍率表」の「固定資産税評価額に乗ずる倍率等」から「1.2」「1.4」などの数値の確認が可能です。
倍率方式で相続税評価額を計算する場合、下記の計算式を用います。
相続税評価額=固定資産税評価額×評価倍率
下記のような土地の相続税評価額を求めてみましょう。
- 土地の固定資産評価額:1200万円
- 評価倍率:1.2
計算式は、下記の通りです。
相続税評価額=1200万円×1.2=1440万円
相続した土地に路線価がなくても、焦らず対応しましょう。
ケースに応じた適切な補正が必要
土地面積のみで相続税評価額を簡単に計算できるケースはほとんどありません。土地は1つとして同じ条件のものがなく、同じ路線価の同じ土地面積であっても、使い勝手の良さ・悪さが考慮されて相続税評価額が変動します。
たとえば、同じ道路に面している土地であっても、奥行きが長すぎたり短すぎたりすると使い勝手が悪いため補正で減額されます。一方、角地であれば使い勝手が良い土地のため、加算するための補正をしなければなりません。
土地の条件によって適切な補正が必要となるため、路線価から相続税評価額を計算するには一定の専門知識が必要です。専門家に計算してもらい、正しく相続税の申告・納税をしましょう。
相続や贈与のあった年の路線価を使用する
相続税や贈与税を計算する際は、相続や贈与のあった年の路線化を使用することがルールとなっています。申告する年の路線価ではないため、注意しましょう。
たとえば、令和元年10月1日に相続が発生したときの相続税申告・納税の締め切りは令和2年8月1日です。このとき、令和2年の路線価ではなく、令和元年の路線価を用いて相続税評価額を算出しなければなりません。
また、相続税路線価は毎年1月1日時点で評価され、7月頃に更新されます。1月から6月までの間に相続や贈与があったとしてもすぐに路線価を調べることができず、路線価が発表される7月以降までは相続税や贈与税の金額を確定させられません。
路線価が発表されるまでに掲載されている最新の路線価は、前年の価格のため注意しましょう。
相続税路線価の計算は複雑なため専門家を頼ろう
相続税路線価の調べ方がわかると土地の相続税評価額が計算できるようになります。ただし、多くの土地では補正をする必要があり、専門知識が欠かせません。あくまでも、相続税路線価に土地面積を乗じた数字は概算額であると理解しておきましょう。
また、土地の評価額の計算だけでなく、相続税の計算も複雑です。控除や特例を活用すれば大幅な節税に結びつきますが、専門知識がなければ正しい申告は難しいでしょう。
早めに相続の専門家に相談しておくと安心です。相続プラスでは、相続に強い専門家をエリア別・悩み別に検索することができます。ぜひ、活用してください。


