「婚姻によって姓が変わり、実家の戸籍を抜けて配偶者の戸籍に入った娘は遺産を相続できない」といったことを言われ、困惑している方がいるかもしれません。しかし、現行の民法では嫁に行った娘であっても、法定相続人として遺産の取り分が認められています。本記事では、嫁に行った娘が親の遺産を相続できないと言われる理由や、相続できないと言われたときの対処法をご紹介。嫁に行った娘が相続するときの注意点も解説しているため、ぜひ参考にしてください。
目次開く
地元の専門家をさがす
嫁に行った娘も遺産を相続できる
「嫁に行った娘には相続する権利はない」と親や兄弟姉妹から言われると、信じる方がいるかもしれません。
しかし、嫁に行った娘も親の遺産を相続する権利を持っています。なぜなら、子どもは法定相続人の第一順位となり、嫁に行ったとしても父・母の子どもであることに変わりはないからです。
たとえ、婚姻によって姓が変わり、実家の戸籍を抜けて配偶者の戸籍に入ったとしても、実の両親との親子関係に影響はありません。
より理解を深めるために、下記のポイントについて詳しく解説していきます。
- 子どもは法定相続人の第一順位
- 結婚して苗字が変わっても相続人の権利は変わらない
- 夫の両親と養子縁組をしても相続人となる
順番に見ていきましょう。
子どもは法定相続人の第一順位
現行の民法では、子どもは法定相続人の第一順位に位置付けられています。法定相続人とは、民法で決められた相続する権利を持つ人です。
法定相続人には相続できる順位が決まっており、子どもは第一順位です。先に子どもが亡くなっている場合は、その子ども(被相続人から見た孫)が相続人となります。
そもそも子どもがいない場合は第二順位である父母、父母もいなければ第三順位である兄弟姉妹が法定相続人になります。なお、被相続人に配偶者がいる場合は、かならず相続人です。
実の父母との関係は結婚してもしなくても変わりありません。つまり、結婚しているかどうかにかかわらず、娘も息子も等しく相続する権利を持っています。
そのため、父もしくは母が死亡した際には、原則として嫁に行った娘も相続人となります。当然、結婚の有無や性別によって遺産を相続できる割合の差もありません。

結婚して苗字が変わっても相続人の権利は変わらない
結婚して戸籍や苗字が変わったとしても、原則として法定相続人の権利は変わりません。
なかには昔ながらの考えや地域における慣例によって、「嫁に行った娘には相続権がない」と考える人もいます。しかし、嫁に行った娘も、相続順位は第一順位のままです。
結婚して夫の姓になった場合も同様に相続権を失いません。現行の民法においては、ほかの兄弟姉妹と同じ相続割合で遺産を引き継ぐことが可能です。
夫の両親と養子縁組をしても相続人となる
娘が夫の両親と養子縁組をしていた場合でも、実の両親と親子関係があることには変わりないため、娘は実の両親の相続人のままです。
夫の両親と養子縁組をしている場合、法律上の親子関係となるため夫の父・母が被相続人となる場合にも相続人になります。
ただし、特別養子縁組をした場合は実の両親との親子関係が解消される点に注意しましょう。特別養子縁組とは、実の両親との親子関係を法的に終了させたうえで、養父母との間で実の子と同等の親子関係を結ぶ制度です。そのため、特別養子縁組をした場合は、実の両親の相続人にはなれません。
特別養子縁組をするには子どもが原則15歳未満でなければならないため、嫁に行くタイミングで特別養子縁組をすることはできないと考えておきましょう。
嫁に行った娘に相続権がないと思われる理由
ここまでに説明したように、嫁に行った娘にも実の両親の遺産を相続する権利は原則的にあります。しかし、なぜ「嫁に行った娘には相続権がない」と言う人がいるのでしょうか。
その理由として、旧民法における家督相続が影響していると考えられます。
ここでは、嫁に行った娘に相続権がないと思われる理由の理解を深めるために、家督相続について下記のポイントについて解説します。
- 旧民法の家督相続では相続権がなかった
- 家督相続は廃止され均分相続へ
詳しく確認しましょう。
旧民法の家督相続では相続権がなかった
現行の民法では嫁に行った娘にも相続権がありますが、旧民法の家督相続では嫁に行った娘に相続権はありませんでした。
明治31年から昭和22年までの旧民法では、家長制度・家督相続が採用されていました。家長制度とは、一家の主人である戸主が家族を統率し、ほかの家族は戸主に服従する制度です。
家長制度においては、戸主が亡くなると戸主権を持つ長男(いない場合は長女)がすべての財産を相続する家督相続が行われていました。そのため、嫁に行った娘はもちろん、長男がいる場合は妻や娘、次男、三男にも相続する権利がありません。
さらに、男子や年長者が優先されていたため、非嫡出子の男子と嫡出子の女子がいる場合には非嫡出子の男子が優先されて相続することが一般的でした。このように、結婚の有無にかかわらず、娘には相続権がないに等しい時代があったのです。

家督相続は廃止され均分相続へ
現在では家長制度や家督相続は廃止されています。終戦後に日本国憲法が制定され、その内容に即して昭和22年に民法が大幅に改正、昭和23年1月1日から施行されました。
この改正民法で、現行の民法と同様に「兄弟姉妹はすべて遺産を均等に相続する」という均分相続がされるようになりました。
ただし、現在においても「財産は長男がすべて継ぐもの」という考え方を重んじる人がいることも事実です。そのため、どのように遺産を分割するかは現行の民法に合わせながらも、個別に決めていくとトラブルが生じにくいでしょう。
嫁に行った娘には相続権がないと言われた際の対処法

もし、実家の家族や親戚から「嫁に行った娘には相続権がない」と言われたとしても、実の父・母が亡くなった場合には原則相続する権利を持っています。
ここでは、相続権がないと言われたり、相続放棄をするように指示されたりした場合の対処法を3つご紹介します。
- 現在の相続制度を説明する
- 専門家に相談する
- 遺産分割調停・審判で遺産の分け方を決める
順番に確認し、自分の相続権を主張しましょう。
現在の相続制度を説明する
まずは現在の相続制度を当事者に説明することから始めましょう。
親や兄弟姉妹などが現行の民法で定める相続制度を正しく理解していない理由で、家督相続を実現しようとしている可能性があるからです。
現在の相続制度では、結婚の有無にかかわらず兄弟姉妹が均等に相続する権利を持っていることを丁寧に説明し、納得してもらうよう努めましょう。
専門家に相談する
もし、当事者間の話し合いでは納得してくれないのであれば、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談しましょう。たとえ同じ内容の説明であっても、第三者で法律に詳しい専門家から説明を受けることで納得してもらえる可能性が高まります。
専門家に依頼する際は、トラブルの可能性がなければ司法書士、トラブルの可能性がある場合や既にトラブルが起きている場合は弁護士に相談するとよいでしょう。
さらに、相談した専門家を交えて遺産分割協議を行うと法的なアドバイスをもらいながら話し合いを進められます。

遺産分割調停・審判で遺産の分け方を決める
専門家から現行の民法についての説明を受けても納得してもらえない場合や、遺産分割協議で合意に至らない場合は遺産分割調停・審判を行いましょう。
遺産分割調停とは、遺産の分割方法について家庭裁判所の裁判官と調停委員が双方の主張を聞き取って、相続人全員の合意を目指す手続きです。調停が不成立となった場合は、家庭裁判所が遺産分割の方法を決定する審判へと移ります。
ただし、遺産分割調停・審判は、話し合いが進まないときの最終手段として考えておくべきです。なぜなら、相続人の間で禍根が残ってしまい、今後の親戚付き合いに影響が出るかもしれないからです。そのため、できることなら話し合いでの解決が望ましいでしょう。
どうしても遺産分割調停・審判を行うなら弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば調停や審判に向けてのアドバイスだけでなく、当事者の代わりに代理人として家庭裁判所へ出廷してくれます。


地元の専門家をさがす
嫁に行った娘の相続で知っておくべきこと
最後に、嫁に行った娘の相続について知っておくべきことを5つご紹介します。
- 遺産分割協議書への押印は慎重に
- 他の相続人による遺産隠しへの対処法
- 嫁に行った娘を除外して行われた遺産分割協議は無効
- トラブルを避けるために相続放棄も検討する
- 嫁に行った娘に相続させたいがトラブルが予想される場合の対処法
詳しく確認しましょう。
遺産分割協議書への押印は慎重に
他の相続人が作成した遺産分割協議書へ署名・押印を行う際は、慎重に行いましょう。なぜなら、署名・押印をしてしまうと合意したとみなされるからです。あとから納得できない内容だったことに気づいても取り消しは難しいと考えておきましょう。
そのため、しっかりと内容を確認し、遺産分割の内容に納得できるかどうかを確認する必要があります。なかには「嫁に行った娘は相続権を放棄する」といった内容が含まれているかもしれません。記載されている内容に納得できるのであれば、合意の証として署名・押印をしましょう。
納得いかない場合は、法定相続人としての相続分があることを主張し、再協議を提案すべきです。
他の相続人による遺産隠しへの対処法
実家の兄弟姉妹などの他の相続人が「嫁に行った娘だから遺産を知らせないでおこう」と遺産隠しをしているケースがあります。実家を離れて暮らしていると、遺産隠しに気づかないまま遺産分割協議を行ってしまうかもしれません。
本来であれば公平に遺産分割するために、遺産分割協議はすべての財産を開示した状態で行う必要があります。
他の相続人による遺産隠しを疑う場合は、下記のような対処法を実践しましょう。
- 銀行口座の残高証明書を取り寄せる
- 銀行に名義人が死亡したことを知らせる
- 法務局で不動産の登記簿の確認や市区町村役場で固定資産台帳の開示を行う
金融機関は、口座の名義人が死亡したことを知ると基本的にその口座を凍結し、相続手続きが完了するまでは口座から引き出しができないようにします。そのため、他の相続人が口座引き出しをしないようにするためには、名義人の死亡を知らせることが効果的です。
個人で調査することが難しい場合は、弁護士に隠し財産の調査を依頼することも可能です。物理的に実家が離れている場合や時間を割けない場合には、弁護士を頼ることも選択肢に入れて検討しましょう。
嫁に行った娘を除外して行われた遺産分割協議は無効
もし、嫁に行った娘以外の相続人で遺産分割協議を行った場合、遺産分割協議で合意に至ったとしても無効になります。なぜなら、遺産分割協議は法定相続人全員で行わないと成立しないと定められているからです。
また、無断で本人のふりをして署名・押印をすることは、文書偽造や有印私文書偽造罪などの犯罪に問われる場合があります。
嫁に行った娘に相続させたくない場合でも、遺産分割協議には法定相続人全員が参加し、全員の署名・押印がされた遺産分割協議書を作成する必要があります。
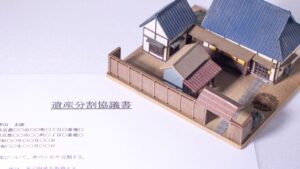
トラブルを避けるために相続放棄も検討する
ほかの相続人とのトラブルやマイナスの財産相続を回避するために、相続放棄をすることも選択肢に入れて検討しましょう。
相続放棄とは、法定相続人が家庭裁判所にて申述することで、相続人としての立場を失う手続きです。一度相続放棄をすると後から撤回することはできず、プラスの財産も一切相続できなくなります。
また、相続放棄は相続発生から3か月間の熟慮期間中に手続きをしなければなりません。熟慮期間を過ぎると相続放棄できなくなる可能性が高まるため、注意しましょう。

嫁に行った娘に相続させたいがトラブルが予想される場合の対処法
嫁に行った娘に相続させたい思いがあるものの、地域や家族の価値観からトラブルが予想される場合の対処法をご紹介します。
ご自身の遺産を嫁に行った娘に相続させるには、下記の対処法が有効です。
- 嫁に行った娘の取り分を明記した遺言書を作成する
- 相続以外の手段として生前贈与や家族信託を検討する
資産状況や家族関係などによって、嫁に行った娘に財産を受け渡すための最適な方法は異なります。相続に詳しい弁護士や司法書士などに相談し、個別にアドバイスをもらうことをおすすめします。
嫁に行った娘には親子関係があるため相続できる
嫁に行った娘も、他の息子や娘同様に相続権を持っています。現行の民法では、同じ第一順位の相続人と均等な遺産分割が認められています。
しかし、年代や地域によっては家督相続の価値観を大事にしている人がいることも事実です。話し合いで現行の相続制度について理解してもらえればよいですが、納得してもらえないなら弁護士から説明してもらうことをおすすめします。
それでも納得してもらえない場合には、遺産分割調停・審判を検討しましょう。遺産分割調停・審判では、弁護士にサポートしてもらうとスムーズに手続きを進められます。
相続プラスでは、相続に強い弁護士や司法書士を一覧で確認できます。エリア別・悩み別で検索することも可能なため、ぜひ活用してください。
専門家の力を借りて、正当な自分の権利を主張しましょう。
地元の専門家をさがす


