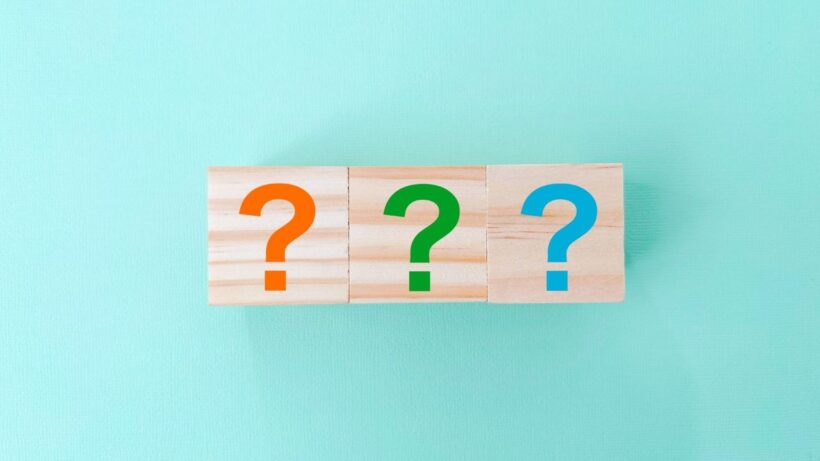相続登記の義務化が令和6年4月1日にスタートし、相続や遺産分割協議の成立から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料が科される可能性があります。しかし、代々相続登記されていない土地がある場合、「相続人が誰かわからない」「手続きが難しい」と問題点を感じることでしょう。本記事では、相続登記義務化における問題点とその解決策について詳しく解説します。相続登記していない不動産を持っている方や、これから不動産を相続する予定の方は、ぜひ参考にしてください。
地元の専門家をさがす
相続登記の義務化とは?
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました。不動産を相続した相続人は、相続した事実を知った日から3年以内に相続登記することが義務付けられています。
相続登記の義務化に関する問題点を説明する前に、押さえておきたいポイントについて解説します。
相続登記義務化のポイント
相続人は、土地や建物などの不動産を相続によって取得した事実を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されました。正当な理由がある場合を除き、義務を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記が義務化になった目的は、全国各地に増えている所有者不明土地や建物を減らすことです。空き地や空き家による環境悪化だけでなく、土地開発の妨げにもなっており、社会全体の課題となっています。
所有者不明土地を減少させ、土地を有効活用するために相続登記の義務化がスタートしました。
相続登記は、3年以内に申請する必要がある
相続登記の申請期限は、不動産を相続で取得した事実を知った日から3年以内です。遺産分割協議を行う場合、遺産分割協議が成立した日から3年以内が期限となります。
遺産分割協議が長引いているなど、相続登記の申請をすぐに進められない正当な理由がない限り、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過去の相続にも遡って適用される
相続登記の義務化がスタートしたタイミングは令和6年4月1日ですが、それ以前に相続した不動産についても義務化されています。つまり、過去に相続した不動産の相続登記が済んでいない場合にも、対応しなければなりません。
正当な理由がないにもかかわらず相続登記を申請しない場合は、10万円以下の過料の対象となるため注意が必要です。
令和6年4月1日以前に不動産を相続で取得した事実を知った場合の相続登記の期限は、令和9年3月31日となっています。
遺産分割協議が遅れている場合は、相続人申告登記を利用できる
先述したように遺産分割協議が長引いている等の理由で相続登記の申請ができない場合、相続人申告登記を行うことで、相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。
なお、相続人申告登記を行っても、相続登記の義務が免除されるわけではありません。相続人申告登記は、あくまで相続登記の申請ができない場合の救済措置なので、特別な事情がない限り、相続登記の申請を行う必要があります。
「相続人申告登記」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

相続登記義務化に伴う問題点
相続登記義務化は施行から日が浅いため、さまざまな悩みや疑問が生じています。相続登記義務化に伴う問題点として、どのようなことが起きるのかを詳しく確認していきましょう。
期間内に登記しないと過料が発生する問題
相続登記の申請義務を履行しなければ、10万円以下の過料が発生する可能性があります。
相続登記の義務は令和6年4月1日にスタートし、3年以内の期限が設けられている新しい制度です。そのため、現在において相続登記の申請期限を迎えたケースはまだありません。
そのため、期限を守らなかった場合に一律で10万円の過料が科されるのか、あるいは悪質と判断された場合に過料が発生するのかなど、具体的な運用はまだ明らかになっていません。
ただ、法律で過料が定められている以上、相続登記を放置したまま期限を迎えてしまうと10万円以下の過料が発生する可能性は否定できないでしょう。
なぜ過料が科されるのか?
相続登記の義務化がスタートする前まで、相続登記は任意に行う手続きでした。しかし、過料という制裁的措置を設けることで、相続登記を義務として定めて履行させようとしています。その結果、所有者不明の不動産を減らし、社会課題の解決につなげたいという国の意図があります。
なお、過料を支払ったとしても、相続登記の義務は免除されません。過料を支払ったあとにも義務が課せられるため、早急に相続登記の申請手続きを済ませる必要があります。
手続きそのものが問題
相続登記を申請する意思があったとしても、手続きそのものに問題が発生しているケースがあります。相続登記をするには、登記申請書を作成し、必要書類を複数用意して法務局で申請しなければなりません。
更に法務局の取扱時間は平日9時から17時のみで、土曜日、日曜日、国民の祝日 等の休日、年末年始期間は取扱がありません。
慣れない手続きを限られた曜日と時間内で進めていくことは、かなりの労力と負担がかかります。
古い不動産で権利関係が不明
相続登記の義務化がスタートしたあと、新たに発生した相続であれば相続登記の手続きはそれほど難しくありません。しかし、古い不動産で権利関係が不明な場合は、何から手をつけてよいか分からなくなることもあります。
例えば、何世代にもわたって相続登記が行われていない場合、過去の相続登記も申請しなければなりません。過去の権利関係を明確にするだけでも大変で、提出する戸籍謄本などの書類の管理が難しくなることもあります。
このように、相続登記の義務を果たしたくても、相続人だけでは解決できない状況に陥ることも考えられます。
ほかの相続人に連絡を取ることが難しい問題
相続登記をしたくても、ほかの相続人と連絡が取れなくなっていると相続登記の申請ができません。なぜなら、相続登記の際には遺産分割を終わらせておく必要があるからです。
しかし、遺産分割協議を行うには相続人全員が参加する必要があります。相続登記の申請時には、合意の証として相続人全員が署名・捺印した遺産分割協議書が必要です。
なお、遺産を相続分通りに分ける場合や遺言書通りに分ける場合には遺産分割協議を行わずに相続登記の申請ができるため、負担が軽くなります。
相続人たちが全国に散在
他の相続人に連絡が取れない例として、相続人である兄弟姉妹が全国に散在しているケースが挙げられます。更には知らずに引っ越しなどをしてしまい、連絡すらつかないケースもあるようです。
このようなケースに陥ってしまうと遺産分割協議ができず、相続登記の申請もできないままになってしまうでしょう。
ほかの相続人に連絡を取りたくない問題
ほかの相続人との関係がよくない場合、連絡を取りたくないという問題もあります。関係が良くない相続人がいる場合、気持ちが優先してしまい連絡を取らずにそのまま放置してしまうケースも見受けられます。
しかし、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しなければ、相続登記の申請手続きを進められないため問題となるでしょう。
遺産分割協議が長引いている
相続人同士で意見が食い違い、遺産分割協議が長引くケースも挙げられます。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なので、結果として、相続登記の申請もできないという事態に陥ってしまいます。
相続・費用の問題
そもそも誰が相続するのか、誰が費用を負担するのかという問題も出てくるでしょう。
相続人が明確であれば手続きもスムーズに進められますが、誰が相続人か分からない場合もあります。相続人を確定しなければ、遺産分割ができず不動産を誰が相続するかが決まりません。
また、相続登記をする場合、不動産の評価額の0.4%を登録免許税として納付する必要があります。さらに、必要書類の取得費用や、専門家に依頼したときの報酬などが発生します。
誰が相続登記にかかる費用を負担するのかが決まらなければ、相続登記の手続きができないままでしょう。
誰が相続するのか?
民法では、相続人となることができる範囲と、その順位が定められており、法律上相続する権利を持つ人を「法定相続人」と呼びます。
例えば、亡くなった方に子どもがいれば、子ども全員が法定相続人です。子どもが亡くなっていれば、その子どもである孫が法定相続人となります。
亡くなった方に子どもがいない場合や、子どもが全員相続放棄をした場合は親が、親も亡くなっていれば兄弟姉妹が法定相続人となります。なお、配偶者は常に法定相続人です。
「法定相続人」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

誰が支払うのか?
相続登記にかかる費用を負担する人は、特段法律で定められていませんが、一般的には、相続する人が費用を負担することが一般的とされています。
しかし、どの相続人も相続したがらない不動産を仕方なく相続したなど、不本意な相続であった場合には他の相続人が費用を負担してもよいでしょう。状況に合わせて相続人同士が話し合って決める必要があります。
地元の専門家をさがす
相続登記の義務化に関わる問題点への解決アプローチ

相続登記の義務化に関わる問題点を解決する方法を解説します。ご自身の状況に合わせて、どの解決アプローチをすべきかチェックしましょう。
相続登記を司法書士に依頼する
相続登記を得意分野とする司法書士の力を借りましょう。
司法書士は相続に関するさまざまな業務に対応しており、なかでも不動産登記に関する業務は司法書士の独占業務です。そのため、手続きに関して困っている場合にも司法書士に必要書類の作成から法務局への申請までを一括して依頼できます。
「相続手続きを司法書士へ依頼するメリット」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

争族に発展しそうなら弁護士へ
遺産分割の段階で相続人同士が揉めている「争族」への発展が予測されるのであれば、弁護士を頼るとよいでしょう。
弁護士は相続手続きのサポートだけでなく、問題解決のための法律の専門家です。
法的観点から、双方の主張の落としどころを提案してくれるので、話し合いでは解決できない場合、調停や裁判においても代理人として裁判所へ出向いてもらえます。
「相続人同士の仲が悪い」「主張する遺産の取り分が異なる」など、相続人同士で対立しそうであれば、早い段階で弁護士に相談しましょう。
相続人申告登記を行う
すぐに相続登記できない理由がある場合は、相続人申告登記を申請しましょう。相続人申告登記とは、「不動産の相続人は自分である」と申告することです。相続人申告登記を行うと、申し出た相続人の氏名や住所などが登記されます。
相続人申告登記を行えば、相続登記の義務を果たしたとみなされます。何代にもわたって相続登記をしていない場合や、相続人と連絡が取れない場合など、遺産分割ができないときに活用できます。
ただし、相続人申告登記をすれば相続登記の義務がなくなるわけではありません。あくまで、すぐに相続登記ができない方への救済措置であり、最終的には相続登記を行う必要がある点に注意してください。
「相続人申告登記」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

相続放棄する
ほかの相続人と関わりたくないのであれば、相続放棄も選択肢の1つとして検討しましょう。
相続放棄とは、亡くなった方の遺産を一切相続しないための手続きです。借金や未払金などのマイナスの財産だけでなく、不動産や現金などのプラスの財産も一切引き継ぐことができません。
相続放棄をすると、もともと相続人ではなかったものとして扱われます。遺産分割協議に参加する必要がなくなるため、ほかの相続人と連絡を取る必要もなくなります。
相続放棄ができる期間は、自身に相続があることを知った日から3か月間です。この期間を熟慮期間と呼ばれ、熟慮期間中に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行わなければ、相続放棄できなくなくなります。
そして、相続放棄の手続きを完了させると、撤回することができません。そのため、本当に相続を放棄しても問題がないか、熟慮期間中に慎重に検討しましょう。
「相続放棄」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

相続土地国庫帰属制度を活用する
誰も相続できない・したくない土地があるのであれば、相続土地国庫帰属制度を活用してもよいでしょう。相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって引き継いだ土地を国に返す制度です。
相続したくない場合に相続土地国庫帰属制度を利用することで、所有者不明土地の発生を防ぎ、土地を有効活用することができます。
ただし、さまざまな細かな要件が設定されているため、該当する土地であるかどうかを確認しましょう。
「相続土地国庫帰属制度」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

相続登記に少しでも不安があれば専門家に相談しましょう
令和6年4月1日から始まった相続登記の義務化に伴う問題点はさまざまです。
まずは、相続した不動産の所有権や相続人の範囲を調べ、相続登記に向けて準備を始めましょう。自身で手続きを進めるのが難しい場合は、司法書士や弁護士に依頼することで、手続きがスムーズに進められます。
相続プラスでは、相続登記に強い司法書士を気軽に検索できます。相続登記に関する悩みがあれば、ご利用ください。
地元の専門家をさがす