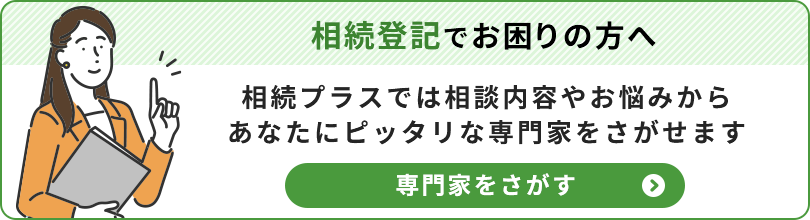不動産を相続する場合、法務局で相続登記手続きをする必要があります。法務局は「誰がどの不動産を所有しているのか」を管理しています。相続登記の手続きをしないままだと第三者に権利を主張できません。本記事では、法務局の役割や相続登記の申請手続きの流れについて解説します。どこの法務局で手続きすればよいかわからない場合にも役に立つ内容となっています。不動産を相続した方や相続する予定のある方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。
法務局とは?
法務局とは、国民の財産と権利を守るための事務を担当する機関です。法務省の地方支分部局の1つで、下記の事務処理を担っています。
- 登記
- 戸籍・国籍
- 供託
- 公証
- 司法書士・土地家屋調査士
- 人権擁護
- 法律支援
- 国の争訟
法務局の業務は下記のようになっており、財産の権利や身分に関連しているものが多く、法務局は国民に特に密接にかかわる業務を行っていることがわかります。
- 婚姻:戸籍事務
- マイホームの購入:不動産登記
- 会社の設立:商業・法人登記
- 子どもや障がい者に関する人権問題:人権擁護事務
- 遺言書の作成:遺言書保管
- 相続:不動産登記
法務局の組織は、全国を8つのブロックに分けて各ブロックに1つの法務局が設置されています。その下に都道府県単位に地方法務局が設置されています。
法務局でできることは?
法務局でできることは、国民の財産と権利を守るための事務処理です。事務処理が必要な事柄が出てきた場合に、国民は法務局で申請・手続きをしなければなりません。
具体的に、法務局でできることの一部をご紹介します。
- 不動産登記
- 自筆証書遺言書保管制度
- 筆界特定制度
- 商業・法人登記
- 戸籍事務
- 成年後見登記に関する事務
- 国籍事務
- 供託
- 訟務
- 説明会・相談会
詳しく見ていきましょう。
不動産登記
法務局と聞いて馴染みのある手続きは、不動産登記ではないでしょうか。不動産登記とは、不動産に関する情報が変わった場合に行う手続きです。
不動産登記と一口に言っても、下記のような登記の種類があります。
- 建物表題登記
- 所有権保存登記
- 所有権移転登記
- 抵当権設定登記
- 抵当権抹消登記
- 相続人申告登記
それぞれどのようなケースに必要な登記なのかを詳しく確認しましょう。
建物表題登記
建物表題登記とは、建物を新築した場合に行う「表題部」を新たに作成するための登記です。
不動産登記には大きく「表題部」と「権利部」の2つがあり、表題部には不動産の物理的状況が詳しく記録されます。記載される項目は、土地と建物とで異なります。
| 不動産の種類 | 記載される項目 |
|---|---|
| 土地 | ・所在 ・地目 ・土地面積建物 |
| 建物 | ・家屋番号 ・種類 ・建物の構造 |
建物表題登記は、建物の完成から1か月以内に行わなければなりません。
所有権保存登記
所有権保存登記とは、登記されていない不動産にはじめて所有者を設定するための登記です。建物を新築した場合に行うことが一般的です。
先述の通り、不動産登記には表題部と権利部の2つがあり、権利部には不動産の権利関係が詳しく記録されます。
権利部には「甲区」「乙区」の2つに分かれており、下記のように記載される内容が異なります。
- 甲区:所有者に関する権利
- 乙区:所有者以外に関する権利(抵当権や地上権など)
所有権保存登記では、甲区欄に最初の所有者を記載することになります。
甲区欄に記載される項目は、下記の通りです。
- 所有者の住所・氏名
- 不動産の取得日
- 取得の原因や経緯(売買・相続など)
所有権保存登記を行うことで、はじめて不動産の法的な所有権を第三者に主張できるようになります。
所有権移転登記
所有権移転登記とは、不動産の所有者が変わったときに新たな所有者を設定するための登記です。所有権移転登記は、下記のような場合に行います。
- 売買
- 贈与
- 相続
相続したときに行う不動産の名義変更を「相続登記」と呼びますが、実際に法務局で行う正式な手続きは、所有権移転登記になります。所有権保存登記で甲区欄に記載された所有者の氏名や住所が、新しい所有者のものに変更されます。
所有権移転登記を行わなければ、正式に不動産の所有権が旧所有者から新所有者へ移転しません。新所有者は、所有権移転登記の手続きを完了させたあとから、法的な所有権を第三者に主張できるようになります。
抵当権設定登記
抵当権設定登記とは、不動産に抵当権を設定するための登記です。抵当権については、権利部の「乙区」に記録されます。
抵当権とは、住宅ローンや事業資金の借入れをするときなどに、金融機関が不動産を担保として設定する権利です。債務者が返済できなくなったときに債権者はその不動産を売却して、売却代金を返済金に充てることができます。
抵当権抹消登記
抵当権抹消登記とは、設定された不動産の抵当権を抹消するための登記です。住宅ローンや事業資金の借入れを返済し終えたとしても、自動的に抵当権が抹消されるわけではありません。
抵当権抹消登記をしないと、下記のようなデメリットがあります。
- 抵当権のついた不動産は買い手が見つかりにくく、売却しづらい
- 相続時に抵当権がついたままだと手続きが煩雑になる
- 権利関係が複雑になり、将来トラブルを引き起こすリスクがある
なお、抵当権抹消登記をすると、権利部の「乙区」における抵当権についての記載が抹消されます。
相続人申告登記
相続人申告登記とは、不動産を相続するときに相続人が自分であることを申し出るための登記です。相続人申告登記をすると、申し出た相続人の氏名や住所が記載されます。
相続人申告登記は、令和6年4月1日よりスタートした相続登記の義務化とあわせて新しく設けられた制度です。相続登記は、原則不動産を相続した事実を知ってから3年以内に行わなければならず、義務を果たさなければ10万円以下の過料を科される可能性があります。
しかし、「遺産分割ができない」「相続人が把握できない」などの理由から、相続登記がすぐにできない相続人も少なくありません。そのような方々でも相続人申告登記をすれば、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
このように、相続人申告登記は相続人登記がすぐにできない方々のための救済措置として活用できます。
「相続人申告登記」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言書保管制度とは、自筆で作成した遺言書を法務局に保管できる制度です。自筆証書遺言書保管制度を活用するメリットは、下記の通りです。
- 遺言書の保管申請時に形式をチェックしてもらえる
- 原本と画像データが長期間適正に管理される
- 相続発生後の家庭裁判所による検認を割愛できる
自筆証書遺言書として効力を認められるには、民法で定められた形式を守らなければなりません。自筆であることはもちろん、訂正方法や封の仕方などにも細かなルールがあります。1つでもルールを守らない場合、遺言書としての効力が発揮されず、思い通りの遺産分割をしてもらえないでしょう。
自筆証書遺言書保管制度を活用すれば、民法で定められた形式に適合しているかを確認したうえで預かってもらえるため、無効となるリスクを軽減できます。
また、自宅に遺言書を保管していた場合、紛失や利害関係者による破棄・隠匿・改ざんなどのリスクがあります。しかし、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば原本は遺言者死亡後50年間、画像データは遺言者死亡後150年間保管されます。
通常、自筆証書遺言書を相続人に残した場合、本来開封する前に家庭裁判所において検認を行わなければなりません。検認をして、ようやく遺言書の内容の確認ができます。
しかし、法務局で保管すれば検認の必要がありません。そもそも、「遺言書をさがす」という作業の必要もないため、相続人はスムーズに遺産分割ができるでしょう。
なお、遺言書の内容を確実に残したいのであれば、公正証書遺言を作成するという選択肢もあります。どうしても自筆で遺言書を作成したいのであれば、ぜひ自筆証書遺言書保管制度を活用しましょう。
「自筆証書遺言書保管制度」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

筆界特定制度
筆界特定制度とは、土地が登記されたされたときに土地の範囲を区画するための線を現地で特定する制度です。区画するための線のことを「筆界」と呼びます。
土地の所有者が隣接する土地との筆界が不明確であったり、揉めたりしている場にも活用できる制度です。法務局に申請すれば筆界調査委員の意見を踏まえ、現地で筆界特定登記官が筆界の位置を特定できます。
裁判所を通さずに筆界が明確になるため、筆界をめぐるトラブル解決に活用できます。
商業・法人登記
商業・法人登記とは、会社を設立した際に取引上重要な事項を法務局に登録して、一般的に公開する制度です。具体的には、下記のような項目を登録します。
- 商号(会社の名称)
- 本店所在地
- 代表者の氏名・住所
- 資本金の額
- 事業目的
- 発行可能株式総数など
登記した内容は、誰でも閲覧が可能です。法務局で会社の登記情報から信用度が確認できるため、安心して取引をスタートさせられます。
戸籍事務
戸籍とは、人が出生して死亡するまでの親族関係を登録し、公に証明する制度です。父母の氏名や出生した年月日、婚姻した年月日などが記載されています。
出生届や婚姻届などは市区町村役場で事務手続きを行います。しかし、全国で統一された手続きと事務処理がされるよう、市区町村役場に対して助言・勧告・指示を行っている存在が法務局なのです。
成年後見登記に関する事務
成年後見制度とは、認知症や精神障がい、知的障がいなどによって十分な判断能力を持たない人を保護・支援するための制度です。
成年後見制度を利用するには、後見人を選任するために家庭裁判所で申立てを行います。法務局では、成年後見制度によって家庭裁判所で選任された後見人の法定後見人や契約による任意後見人を登録し、公にするための事務を担っています。
国籍事務
国籍とは、個人が特定の国家に属して、その一国民であるという身分や資格のことです。出生や帰化によって戸籍を取得できます。
日本の国籍を持っている日本人には、日本国憲法の規定により日本で生活して自由に職業を選び、自由に日本の入出国が認められます。さらに、参政権が認められ、公務の職務に就くことが可能です。
日本以外の外国国籍を持つ方が日本国籍を取得するには、法務局で帰化による法務大臣の許可申請や、日本国籍の取得の届出を行う必要があります。
供託
供託とは、国の機関である供託所に金銭や有価証券などを預け、地代などを支払ったことと同じ扱いを受ける制度です。
例えば、賃貸不動産の大家が行方不明になり、家賃が払えなくなったとします。しかし、放置して家賃を支払わないままでいると、賃貸借契約が解約される可能性があります。
そこで、供託所へ家賃に相当する金銭を預けて適切な対処をしてもらえば、債務者や債務を免れ、債務不履行の責任に問われません。
供託所は法務局に設置されており、申請手続きも法務局内で行います。
訟務
訟務とは、国の利害にかかわる訴訟や争訟があるときに、国の代表として裁判所へ主張・立証を行うことです。国に対して損害賠償を求めるような裁判が提起されると、法務局の職員が国の代理人として法定で訟務活動を行います。
説明会・相談会
法務局では、法律に関する説明会や相談会を随時開催しています。
説明会や相談会を開催する目的は、一般の方が法的な知識を深めて生活にいかしてもらうことです。登記制度や成年後見制度、相続手続きなどのテーマについて深く学べます。
また、担当窓口では法務局で行う手続きについての相談にものってもらえます。例えば、相続登記をしたい場合に必要な書類や申請書の作成方法などの確認が可能です。
説明会・相談会や個別相談に参加するには、事前予約が必要な場合があります。あらかじめ法務局に確認しておくと安心です。
説明会・相談会の注意点
説明会・相談会では、制度の説明や手続きの流れについて詳しく確認できます。しかし、個別の悩みに対応することや、手続き以外のことを解決できない点に注意しましょう。
例えば、相続登記をするにあたって「遺産分割で相続人と揉めている」「誰が不動産を相続すると節税になるのか」などは、個別の問題のため法務局では対応していません。
手続きはどこの法務局でもできる?

法務局ごとに管轄が決まっているため、どこでも手続きができるわけではありません。
一例として、相続登記をしたい場合、不動産の所在地によって手続きできる法務局が異なります。そのため、管轄の法務局をチェックしたうえで相続登記の申請を行わなければなりません。亡くなった方が、全国各地にある不動産を所有していたのであれば、それぞれの管轄を調べたうえで登記申請を行う必要があります。
一方、登記事項証明書や印鑑登録証明書などの証明書を発行したいときは、全国どこの法務局でも取得が可能です。
法務局、地方法務局及び支局の違い
法務局、地方法務局及び支局の違いは、組織の階層と管轄範囲です。
全国を8つのブロックに分け、ブロックごとに1つの法務局が設置されています。この法務局の下に、都道府県を単位とする地域を管轄する地方法務局が全国42か所設置されています。
8つの法務局は上位組織であり、その下部組織である各地方法務局を統括しているという組織イメージです。さらに、その出先機関として、一定の地域を管轄する支局と出張所があります。
法務局や地方法務局、支局では、登記・戸籍・国籍・供託・訟務・人権擁護の事務が、出張所では主に登記事務が行われています。
法務局で相続登記の手続きを行う流れ
ここからは、実際に法務局で相続登記の申請をするときの手続きの流れを解説します。相続登記の手続きの流れは、下記の通りです。
- 法務局へ行く前の準備をする
- 相続する不動産の確認や方針を決める
- 必要な書類の収集をする
- 登記申請書を記入する
- 法務局の窓口で申請する
5つの手順に沿って、詳しく確認しましょう。
法務局へ行く前の準備をする
相続登記の申請をする前に行わなければならない準備は、下記の2つです。
- 相続する不動産を確認する
- 相続する人を決める
相続開始後、まずは相続財産の洗い出しと相続人の範囲を確定させます。その後、どの財産を誰が相続するのかを決定します。
遺言書があれば遺言書通りに、遺言書がなければ遺産分割協議を行わなければなりません。なお、遺言書通りに遺産分割したくない場合、相続人全員の合意があれば遺産分割協議によって遺産分割の内容を決めることができます。
相続する不動産の確認や方針を決める
相続する人が決まったら、改めて不動産の確認や今後の方針を決めましょう。
相続登記をする際、不動産登記の際に必要な登録免許税が発生します。登録免許税の金額は固定資産税評価額に一定の割合を掛けて算出します。そのため、固定資産税評価額を調べておきましょう。固定資産税評価額は、下記のいずれかの方法で確認することができます。
- 市区町村役場から送付される固定資産税の納税通知書を確認する
- 市区町村役場で固定資産課税台帳を閲覧申請する
- 市区町村役場で固定資産評価証明書を入手する
また、相続した不動産の今後の方針についても決める必要があります。とくに、実家を相続する場合、相続人それぞれに考え方があるでしょう。引き継いだ人は「管理が難しくて売却したい」と思っていても、他の相続人は「思い入れがあるから残してほしい」と考えるかもしれません。
「賃貸不動産として貸し出す」「取り壊して駐車場経営をする」「更地にして国庫に帰属させる」など、選択肢は豊富にあります。できる限り、ほかの相続人にも納得してもらえるように話し合いを重ねましょう。
必要な書類の収集をする
相続登記をする際、申請書と一緒に下記の書類を提出する必要があります。
| 書類名 | 必要性 |
|---|---|
| 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本一式 | 必須 |
| 亡くなった方の住民票除票 | 必須 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 必須 |
| 不動産を相続する人の住民票 | 必須 |
| 遺言書 | 遺言書通りに相続する場合のみ |
| 遺産分割協議書+相続人全員の印鑑登録証明書 | 遺産分割協議によって遺産分割した場合のみ |
| 相続関係説明図 | 戸籍謄本の原本を返却してほしい場合のみ |
| 不動産の評価証明書(固定資産評価証明書) | 必須 |
上記のように、どのような経緯で遺産分割を行ったかによって必要な書類が異なります。
登記申請書を記入する
つづいて、登記申請書を作成しましょう。法務局のホームページに様式(フォーマット)が掲載されているため、ダウンロードして使用可能です。記載例も掲載されているため、確認しながら記入できます。
登記申請書は、遺産分割の方法によって選ぶ様式が異なるため注意しましょう。どの様式を選ぶべきかわからない場合や、記入方法がわからない場合は、法務局で相談できます。
法務局の窓口で申請する
登記申請書の作成と必要書類の収集ができたら、管轄法務局の窓口で登記申請をしましょう。管轄法務局は、法務局のホームページから確認できます。
管轄についてはお住まいの住所ではなく、登記申請する不動産の所在地をみて管轄法務局をチェックしてくださいね。
登記申請書や必要書類に不備がなければ、申請から1週間程度で登記完了証と登記識別情報通知書が交付されます。不備がある場合は、法務局からの指示に従って再度申請する必要があります。
郵送やオンラインでも申請できる
管轄法務局が遠くて窓口へ行けない方や、平日の日中に動けない方は、郵送やオンラインでの申請を活用しましょう。
郵送であれば、申請書と必要書類を封入し、管轄法務局へ送ります。登記完了後に書類の変装を希望する場合は、返信用封筒と切手を同封しましょう。
オンライン申請であれば、申請用総合ソフトを活用して申請書を作成します。申請時には電子署名の付与が必要ですが、不備がある場合にもオンライン上で補正できるため、便利に活用できます。
「相続登記のオンライン申請」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

相続登記は管轄法務局で申請しよう
法務局とは、国民の財産と権利を守るための事務を担当する機関です。相続によって不動産を引き継いだ場合、法務局で相続登記手続きをしてはじめて自身のものであると公的に認められます。
相続登記をするときは、不動産の所在地を管轄する法務局で申請しなければなりません。登記申請書と必要書類を準備して、管轄法務局で手続きをしましょう。自分で手続きをすると時間と労力がかかりますが、記入方法や必要書類について法務局で質問・相談することも可能です。