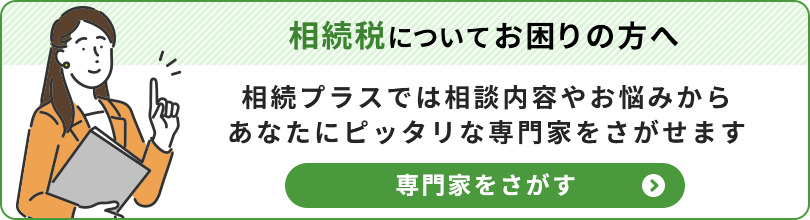住宅取得等資金贈与の非課税特例とは、父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受けた場合に最大1000万円まで贈与税が非課税となる制度です。しかし、特例を適用するには細かな要件を満たさなければなりません。本記事では、住宅取得等資金贈与の非課税特例の概要や適用要件、手続き方法について詳しく解説します。適用を受ける際の注意点も説明しているため、これから住宅取得等資金の贈与を行う方や贈与を受けた方は参考にしてください。
目次開く
住宅取得等資金贈与の非課税特例とは
住宅取得等資金贈与の非課税特例とは、一定の要件を満たすことで最大1000万円までの贈与で贈与税が非課税になる制度です。たとえば、親からマイホームを購入するための経済的援助を受ける場合、贈与税が非課税になる可能性があります。
住宅取得等資金贈与の非課税特例について、理解を深めるために下記のポイントを解説します。
- 要件を満たすと贈与税が一定額非課税になる特例
- 相続時精算課税制度や暦年贈与と併用できる
順番に見ていきましょう。
要件を満たすと贈与税が一定額非課税になる特例
住宅取得等資金贈与の非課税特例とは、父母・祖父母などの直系尊属からマイホームの新築や取得、増築等の資金を贈与された場合に最大1000万円まで贈与税を非課税にできる制度です。
通常の贈与では年間110万円の非課税枠があり、110万円を超える贈与がある場合に贈与税が発生します。しかし、住宅取得等資金の贈与の特例を活用すると、110万円を超える額の贈与を非課税で受けられます。
ただし、取得する住宅によって非課税枠が下記のように定められているため、よく確認しておきましょう。
| 取得する住宅 | 非課税枠 |
|---|---|
| 省エネ等住宅の場合 | 1000万円まで |
| 省エネ等住宅以外の住宅の場合 | 500万円まで |
省エネ等住宅とは、下記のいずれかに該当する住宅です。
- 断熱等性能等級4以上、または一次エネルギー消費量等級4以上であること※
- 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上、または免震建築物であること
- 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること
※新築もしくは建築後使用されたことのない住宅の場合は、断熱等性能等級5以上、かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること
ご自身で判断できない場合は、建築業者や不動産販売会社へ問い合わせるようにしましょう。
なお、住宅取得等資金の贈与の特例の適用期限は令和5年12月31日まででしたが、令和6年度の税制改正によって令和8年12月31日まで延長されています。
今後、さらに延長されるかどうかはわかりません。父母や祖父母からマイホームの支援を受ける予定があるなら、期限に間に合うよう考慮することをおすすめします。
相続時精算課税制度や暦年贈与と併用できる
住宅取得等資金贈与は、相続時精算課税制度や暦年贈与との併用が認められています。
それぞれの非課税枠は、下記の通りです。
| 課税方法 | 非課税枠 |
|---|---|
| 相続時精算課税制度 | 相続者1人あたり累計2500万円まで (別途、年間110万円の非課税枠あり) |
| 暦年贈与 | 年間110万円まで |
たとえば、暦年贈与と住宅取得等資金の贈与の特例を併用すれば、非課税枠は1110万円までとなります。
一方、相続時精算課税制度と住宅取得等資金の贈与の特例を併用した場合、年間110万円の非課税枠に加えて累計3610万円までの非課税枠が使えます。
贈与者が亡くなったときに、相続時精算課税制度を利用した贈与財産は相続税の課税対象となるため注意しましょう。

住宅取得等資金贈与の非課税特例の要件
住宅取得等資金贈与の非課税特例を適用させるには、細かな要件が定められています。下記の2つの要件を両方満たさなければ、適用できないため注意しましょう。
- 受贈者に関する要件
- 住宅用の家屋に関する要件
それぞれの詳しい要件について、解説します。
受贈者に関する要件
住宅取得等資金贈与の非課税特例を適用するためには、受贈者は下記の要件すべてを満たさなければなりません。
- 贈与を受けたときに、贈与者の直系卑属(子ども・孫など)であること
- 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳(令和4年3月31日以前は20歳)以上であること
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下(新築等をする住宅用家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1000万円以下)であること
- 平成21年分から令和5年分までの贈与税申告において「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けていないこと
- 配偶者や親族などの一定の特別な関係のある者から住宅用家屋を取得していないこと、またはこれらの人との請負契約等によって新築もしくは増改築等をしていないこと
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を使って住宅用家屋の新築等を行うこと
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住していること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
- 贈与を受けたときに日本国内に住所があり、日本国籍を持っていること
なお、贈与を受けたときに日本国内の住所を持っていなくても、一定の場合にはこの特例を受けることができます。
住宅用の家屋に関する要件
「住宅用の家屋の新築」および「住宅用の家屋の取得または増改築等」には、住宅用の家屋に必要な敷地用の土地の取得も含まれます。また、対象となる住宅用の家屋は、日本国内にあるものに限られます。
新築・取得・家屋ごとに定められた要件があるため、それぞれまとめました。
<住宅用の家屋を新築・取得した場合>
- 新築または取得した登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下であり、床面積の半分以上が受贈者の居住用であること
- 取得した住宅が、以下のいずれかに該当すること
- ①建築後使用されたことのない住宅用家屋である
- ②建築後使用されたことのある家屋で、昭和57年1月1日以降に建築された住宅用家屋である
- ③建築後使用されたことのある家屋で、地震に対する安全性にかかる基準に適合するものであることが書類によって証明されている住宅家屋である
- ④②③のいずれにも当てはまらない建築後使用されたことのある家屋で、その家屋の取得日までに同日以降その家屋の耐震改修を行い、一定の申請書等にもとづいて都道府県知事などに申請をして、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によって家屋が耐震基準を適合することになったことが書類によって証明されている住宅用家屋であること
<住宅用の家屋を増改築等(リフォーム)した場合>
- 増改築等後の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下であり、床面積の半分以上が受贈者の居住用であること
- 増改築等にかかる工事が自己所有で居住する家屋の増築であり、一定の工事※に該当することについて確認済証の写し、検査済証の写しまたは増改築等工事証明書などの書類によって証明されていること
- 増改築等にかかる工事費用が100万円以上であること(居住用部分の費用が総費用の半分以上)
※大規模増改築・耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修・給排水管または雨水の侵入を防ぐ工事など
このように、住宅用の家屋についても細かな要件が定められています。
住宅取得等資金の贈与の特例の手続き方法と必要書類

住宅取得等資金の贈与の特例の要件を満たす場合であっても、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告をしなければ適用を受けることができません。つまり、贈与税が0円であっても、贈与税の申告をする必要があります。
ここでは、下記の順番に、手続き方法について詳しく解説します。
- 共通する必要書類
- 住宅用の家屋によって異なる必要書類
順番にチェックしましょう。
共通する必要書類
大前提として、非課税特例を利用するためには贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告が必要です。
贈与税の申告時に必要な書類は、下記の通りです。
- 贈与税の申告書第一表
- 受贈者の氏名・生年月日と贈与者が受贈者の直系尊属であることが証明できる書類(戸籍謄本など)
- 合計所得金額を明らかにする書類(源泉徴収票・確定申告書など)
- 登記事項証明書(贈与税の申告書に不動産番号を記載すれば省略可能)
- 新築または増改築にかかる工事の請負契約書、または売買契約書の写し
贈与税の申告書第一表のフォーマットは国税庁のホームページからダウンロードできます。
ご自身で作成することに不安のある方は、贈与税に強い税理士に相談することも選択肢の1つとして覚えておきましょう。
住宅用の家屋によって異なる必要書類
住宅用の家屋の種類によって必要な書類が異なります。下記の順番に解説します。
- 住宅用家屋の新築・取得に関する必要書類
- 住宅用家屋の増改築に関する必要書類
スムーズに申告手続きを終えられるように、必要書類を集める準備をしましょう。
住宅用家屋の新築・取得に関する必要書類
住宅用家屋の新築・取得をした場合、住宅用家屋の種類によって必要書類が異なります。順番に確認しましょう。
<建築後使用されたことのある住宅用家屋で耐震基準に適合する場合>
耐震基準適合証明書や建設住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が1、2または3であるものに限る)、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の締結を証する書類の写し
<住宅用の家屋の耐震改修を行った場合>
申請書等の写し
- 建築物の耐震改修の計画の認定申請書
- 耐震基準適合証明申請書(仮申請書)
- 建設住宅性能評価申請書(仮申請書)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書
証明書等
- 耐震基準適合証明書
- 耐震基準適合証明書
- 建設住宅性能評価書の写し
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の締結を証する書類
<住宅用の家屋が省エネ住宅である場合>
下記いずれかの書類が必要
- 住宅性能証明書
- 建設住宅性能評価書の写し
- 住宅省エネルギー性能証明書
- 長期優良住宅建築等計画等の(変更)認定通知書の写し+住宅用家屋証明書(写し)または認定長期優良住宅建築証明書
- 低炭素建築物新築等計画の(変更)認定通知書の写し+住宅用家屋証明書(写し)または認定低炭素住宅建築証明書
ご自身の住宅家屋に対応する必要書類を揃えましょう。
住宅用家屋の増改築に関する必要書類
住宅用家屋の増改築をした場合、下記のいずれかの書類を提出する必要があります。
- 住宅性能証明書
- 建設住宅性能評価書の写し
- 増改築等工事証明書
取得しやすい書類を選び、申告書に添付しましょう。
住宅取得等資金の贈与の特例に関する注意点
最後に、住宅取得等資金の贈与の特例に関する注意点やデメリットについて解説します。
- 贈与税の納税は不要でも基礎控除超えの場合は申告が必要
- 住宅取得等資金の贈与は相続時に加算しなくて良い
- 贈与のタイミングは引き渡し日・棟上げから逆算する
- 贈与を受けた年の合計所得金額に注意する
- 住宅取得等資金贈与の非課税枠は夫婦別々に利用できる
特例を適用する前に、詳しく確認しましょう。
贈与税の納税は不要でも基礎控除超えの場合は申告が必要
住宅取得等資金の特例の非課税枠を活用して納税する贈与税が0円になったとしても、基礎控除を超える額の贈与を受けた場合には贈与税の申告をしなければなりません。
なぜなら、期限内に贈与税の申告をして、初めて住宅取得等資金贈与の非課税特例を適用させられるからです。贈与税の申告期限は、贈与を受けた翌年の3月15日です。なお、3月15日が土日祝日の場合、翌平日が期限となります。
期限までに申告書類の作成や必要書類の収集を行い、管轄の税務署へ提出しましょう。不安がある方は、税理士にすべて依頼することも可能です。
住宅取得等資金の贈与は相続時に加算しなくて良い
相続税には生前贈与加算の規定がありますが、非課税の適用を受けた住宅取得等資金の贈与は相続時に加算する必要はありません。生前贈与加算とは、相続発生から遡って3〜7年以内に生前贈与を受けた財産を含めて相続税を計算することです。
住宅取得等資金贈与の非課税の適用を受けていれば、住宅取得等資金を相続財産に含める必要がないため少額であっても適用を受けておくようにしましょう。

贈与のタイミングは引き渡し日・棟上げから逆算する
贈与するタイミングによっては特例が利用できない場合があるため注意しましょう。
1つ目のポイントは、受贈者の年齢です。贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上である必要があり、贈与時の年齢ではないため注意しなければなりません。
2つ目のポイントは、住宅を取得するタイミングです。
特に、分譲マンションや建売住宅を購入する場合、売買契約日から引き渡し日までに時差があり、贈与を受けた年の翌年3月15日までに引き渡されないリスクがあります。たとえば、新築物件の購入費用として贈与を受けたとしても、翌年の3月15日までに引き渡されなければ特例の利用はできません。
一方、注文住宅の場合、贈与を受けた年の翌年3月15日までに完成していなくても、屋根があり土地に定着した建造物として認められる状態であれば特例の利用が認められます。
このように、贈与のタイミングによっては特例適用の要件を満たさない場合があります。受贈者の年齢や引き渡し・棟上げに注意して贈与する日を決めましょう。
贈与を受けた年の合計所得金額に注意する
住宅取得資金贈与の特例を利用するためには、所得金額の要件も満たす必要があります。年間の合計所得金額が2000万円(家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1000万円)を超えると、特例の利用が認められません。
盲点なのが、今住んでいる家を売却して住み替えを行う場合です。今の家を売却することで譲渡所得が得られるため、年間所得金額2000万円を超える場合があります。
一時的な所得の増加であっても、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下でなければ特例を使えないため注意しましょう。
住宅取得等資金贈与の非課税枠は夫婦別々に利用できる
住宅取得等資金贈与の非課税枠は夫婦それぞれに設けられているため、2倍の非課税枠を活用できます。たとえば、夫婦がそれぞれの父母から1000万円ずつ贈与を受けた場合、最大2000万円までの非課税枠が使えるため、非課税で住宅取得等資金を受け取れます。
ただし、夫婦がそれぞれ利用したい場合、要件を満たすために住宅を共有名義にする必要があります。新築・取得した住宅が夫の名義にもかかわらず、妻が父母から1000万円の贈与を受けて住宅取得等資金に充てた場合、夫婦間で贈与があったとみなされて贈与税が課される可能性があるため注意しましょう。
住宅取得等資金贈与の非課税特例は節税に有効
住宅取得等資金贈与の非課税特例を適用できれば、最大1000万円まで非課税で贈与を受けられます。非課税枠を使った贈与財産は生前贈与加算の対象から外れるため、相続対策にも役立ちます。
ただし、適用には細かな要件を満たさなければなりません。将来的な税負担のシミュレーションや非課税枠の適用要件を確認するためにも、生前贈与や相続に詳しい税理士へ相談することをおすすめします。
住宅取得等資金贈与の非課税特例を活用して、賢く節税をしましょう。