土地を相続するからといって、必ずしも相続税が発生するとは限りません。本記事では、どのような場合に相続税が発生するかについて詳しく解説します。土地の評価方法や土地の相続時に活用できる特例・控除もご紹介しています。これから土地を相続する予定の方や、相続させる土地をお持ちの方は、相続税対策にこの記事を役立ててくださいね。
目次開く
土地の相続=“相続税が必ずかかる”訳ではない
土地を相続する場合、かならずしも相続税が発生するわけではありません。そもそも、相続税が発生するケースは、相続税の基礎控除額を遺産総額が超えた場合に限ります。
相続税が発生するかどうかを判断するために、遺産総額と基礎控除額について詳しく確認しましょう。
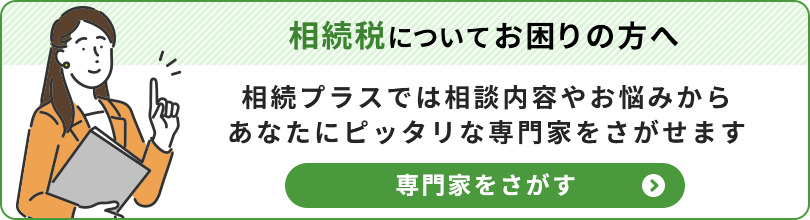
遺産総額とは
遺産総額と聞くと、被相続人が残した相続財産の合計のように感じるかもしれません。しかし、相続税を計算するうえでの遺産総額は、下記のように計算します。
遺産総額=相続財産の総額-相続税がかからない財産-(被相続人の負債+葬儀費用)+相続・遺贈によって財産を取得した人が相続開始前7年以内に受けた贈与財産の総額
それぞれの項目について、詳しく解説します。
相続財産の総額
相続財産の総額には、下記のような財産価値のあるものすべてが含まれます。
- 現金・預貯金
- 不動産(土地・建物)
- 有価証券
- 自動車・船舶
- 生命保険
- 貴金属
- 骨董品・美術品
被相続人が所有していた財産価値のあるすべての財産の合計金額を計算しましょう。
相続税がかからない財産
相続財産のなかには、相続税がかからない財産も含まれているため差し引く必要があります。
相続税がかからない財産の主なものは、下記の通りです。
- 墓地や墓石、仏壇、仏具などの日常礼拝をしているもの
- 宗教・学術などの交易を目的とする事業を行う個人が相続・遺贈によって取得した財産で、交易を目的とする事業に使われることが決まっているもの
- 地方公共団体の条例によって、精神・身体に障害のある方やその方を扶養する方が取得する心身障害者共済制度にもとづいて支給される給付金を受ける権利
- 被相続人の死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の数をかけた金額までの部分
- 被相続人の退職手当金のうち、500万円×法定相続人の数をかけた金額までの部分
- 個人経営している幼稚園事業で使われていた財産で、一定の要件を満たすもの
- 相続・遺贈によって取得した財産で、相続税申告期限までに国・地方教教団体・交易団体などに寄附したもの、あるいは特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
上記に当てはまる財産であっても、要件を満たさなければ相続税の課税対象とみなされる場合があるため注意しましょう。
被相続人の負債(債務)
被相続人に負債(債務)がある場合、相続財産の総額から差し引きます。具体的には、下記のようなものが該当します。
- 住宅ローン・自動車ローン
- クレジットカードの未払金
- 賃借料や水道光熱費、通信費、入院費などの未払金
- 事業にかかわる借入金
- 仕入れ時の買掛金
これらのマイナスの財産はすべて相続財産の総額から差し引けます。
葬儀費用
被相続人の葬儀にかかった一連の費用も、相続財産の総額から差し引きます。具体的には、下記のような費用が該当します。
- 通夜・告別式にかかる費用
- 葬儀に関する飲食代
- 火葬代・埋葬代
- 戒名料
- お布施・読経料
このように、葬儀にかかったすべての費用を相続財産の総額から差し引けます。
相続・遺贈によって財産を取得した人が相続開始前7年以内に受けた贈与財産の総額
相続・遺贈によって財産を取得した人が相続開始前7年以内(令和5年までは相続開始前3年以内)に受けた贈与財産の総額は、相続税の課税対象となるため注意しましょう。
たとえば令和6年1月20日に父親が亡くなった場合、平成29年1月20日以降に受け取った贈与財産が持ち戻しの対象となります。ただし、相続・遺贈によって財産を取得した人以外が受けた贈与財産は対象になりません。
基礎控除額とは
相続税の基礎控除とは、相続税の計算で誰もが無条件で活用できる非課税枠です。課税対象となる相続財産額から基礎控除額を差し引いたうえで、相続税を計算します。
基礎控除額の計算式は、下記の通りです。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が配偶者と長男・次男・長女の4人だったときの基礎控除額は、下記の通りです。
基礎控除額=3000万円+600万円×4人=5400万円
このとき、遺産総額が5400万円を超えていなければ相続税の申告・納税義務は発生しません。
「相続税の計算方法」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
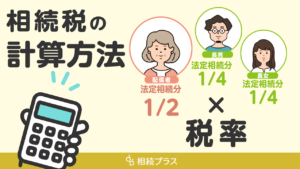
土地の相続税評価額を計算する方法
相続財産の総額を計算する際、不動産や有価証券、自動車などの財産価値のあるものはそれぞれ相続税評価額を計算しなければなりません。土地の相続税評価額を計算する方法は路線価方式と倍率方式の2つの方法があります。
それぞれの計算方法や土地の形状・状況によって変わる評価について詳しく確認しましょう。
路線価方式
路線価方式とは、土地に面している道路ごとに定められている1㎡あたりの価格を用いて相続税評価を計算する方法です。国税庁が発表している道路ごとの1㎡あたりの価格(路線価)に土地の面積を乗じて評価額を算出します。
たとえば、相続する土地350㎡に面している道路の路線価が20万円のとき、評価額の計算式は下記の通りです。
評価額=20万円×350㎡=7000万円
ただし、上記の計算では概算しか導き出せません。詳細な評価額を計算するには、土地の形や用途地域、接している道路の数などによって補正を行う必要があります。
倍率方式
土地によっては路線価が割り振られていない場合があります。路線価のないエリアの土地を相続するとき、評価額は倍率方式を用いて計算します。
倍率方式とは、固定資産税評価額に地域・用途ごとに決められた倍率を乗じて土地の評価額を産出する方法です。
固定資産税評価額は、自治体から送付される固定資産税の課税明細書に記載されています。評価倍率表は、路線価図と同様に国税庁が発表しているため確認できます。
土地の形や状況によって評価が下がる場合も
土地の形や状況によって評価額が下がる場合があります。
具体的には、下記のようなケースで評価額が下がる可能性があります。
| 評価額が下がるケース | 例 |
|---|---|
| 不整形地補正 | 三角・細長・L字など、土地の形がいびつだと減額されます。 |
| 地積規模が大きい宅地 | 三大都市圏(首都圏・中京圏・近畿圏)であれば500㎡以上の地積の宅地、それ以外のエリアであれば1000㎡以上の宅地は減額されます。 |
| 私道 | 原則、私道の評価は路線価で評価した金額の3割で評価することとなっています。 |
適正な評価額を算出するには、一定の専門知識が不可欠です。相続や土地評価に強い専門家に相談し、正しい評価額を計算してもらいましょう。
「相続した不動産評価額の計算方法」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

土地の相続時に利用できる特例・控除

土地を相続する場合、一定の要件を満たすことで下記のような特例・控除が受けられます。
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者の税額軽減の特例
- 未成年者控除
- 相次相続控除
- 障害者控除
それぞれどのような特例・控除なのか、詳細を確認しましょう。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人、または被相続人と生計を同じにしていた親族が居住用・事業用としていた土地を、被相続人の配偶者や同居していた子どもが相続したときに、土地の評価額を50%〜80%引き下げられる制度です。マンションの場合は敷地権が対象となります。
下記のように、土地の種類宅地の内容ごとに上限面積や減額割合が定められています。
<特定居住用宅地>
- 被相続人などが居住用にしていた宅地
- 上限面積:330㎡
- 限度割合:80%
<特定事業用>
- 被相続人などが事業用にしていた宅地※貸付事業をのぞく
- 上限面積:400㎡
- 限度割合:80%
<特定同族会社事業用宅地>
- 特定同族会社の事業用にしていた宅地※貸付事業をのぞく
- 上限面積:400㎡
- 限度割合:80%
<貸付事業用宅地>
- 被相続人などが貸付事業用(不動産貸付)にしていた宅地
- 上限面積:200㎡
- 限度割合:50%
特例を適用させるには、細かな要件が設けられています。また、更地や畑、別荘の土地には適用できないため注意しましょう。
配偶者の税額軽減の特例
配偶者の税額軽減の特例とは、下記のいずれか大きい方の金額までは配偶者に相続税がかからないという制度です。
- 1億6000万円まで
- 配偶者の法定相続分相当額(遺産総額の2分の1)まで
もちろん、土地の評価額も上記の金額のなかに含めて問題ありません。
たとえば、配偶者が相続した財産のうち、課税対象の財産総額が200億円だったと仮定しましょう。このとき、配偶者の法定相続分である100億円までであれば配偶者が相続しても相続税が発生しません。
未成年者控除
未成年者控除とは、法定相続人が18歳未満である場合に受けられる控除枠です。満18歳になるまでの年数1年あたり10万円を相続税から差し引けます。
たとえば、15歳の子どもが法定相続人となった場合、未成年者控除額を算出するための計算式は下記の通りです。
未成年者控除額=(18歳−15歳)×10万円=30万円
上記の場合、15歳の子どもが納めなければならない相続税から30万円分の控除を差し引くことができます。
相次相続控除
相次相続控除とは、被相続人が10年以内に相続を受けて相続税を納税している場合に受けられる控除枠です。10%×年数の割合で控除できます。相次相続控除は、同じ財産に対して相続税が何度もかからないようにするために考慮された制度です。
控除額は、1度目の相続税額や遺産総額、経過年数などによって算出されます。控除額を導き出す計算式はとても複雑なためここでは割愛しますが、10年以内に2度以上の相続が発生した場合に積極的に活用しましょう。

障害者控除
障害者控除とは、相続人が障害者である場合に受けられる控除枠です。満85歳になるまでの年数1年あたり10万円、もしくは20万円を相続税から差し引けます。
- 一般障害者が受けられる障害者控除額=満85歳になるまでの年齢×10万円
- 特別障害者が受けられる障害者控除額満85歳になるまでの年齢×20万円
たとえば、60歳の一般障害者が受けられる障害者控除額は、下記の通りに算出します。
障害者控除額=(85歳−60歳)×10万円=250万円
障害者控除が障害者本人が納めなければならない相続税額より多い場合、引ききれなかった金額を障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことが可能です。

土地の相続に関する注意点・知っておきたいこと
土地の相続に関してあらかじめ知っておくべき注意点は、下記の通りです。
- 相続税の申告・納税期限に気をつける
- 相続登記は義務化されている
- 相続税の申告書は煩雑で大変
- 専門家に頼ることで節税できた事例も多い
- 土地を分割して共有することは避ける
順番に確認しましょう。
相続税の申告・納税期限に気をつける
相続税の申告・納税の期限は、相続発生を知った日の翌日から10か月以内です。家族であれば、通常死亡日の翌日から10か月以内と覚えておきましょう。
遺産総額が基礎控除額を超えている場合、かならず相続税の申告が必要です。小規模宅地等の特例や配偶者控除などによって納める金額が0円であっても申告しなければなりません。
また、相続税には納税猶予が設けられていません。申告が遅れると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられるうえに、本来使えたはずの特例や控除が使えなくなる場合があります。
期限に遅れないよう、余裕を持って相続税の申告・納税の準備を進めましょう。
相続登記は義務化されている
令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されており、所有権取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。正当な理由なく義務を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となるため注意しましょう。
相続登記の期限は相続税の申告・納税の期限よりも遅くに設定されていますが、先に相続登記を済ませた方が相続税の申告・納税の際に揃える書類が少なく済みます。

相続税の申告書は煩雑で大変
相続税の申告書の作成は、税に関する知識を持っていなければ難しいと感じるでしょう。
たしかに申告書の書式には、計算方法や記入における注意点が記載されています。作成で悩むことがあれば、税務署で相談に乗ってもらうことも可能です。
しかし、財産の申告漏れや土地・建物の評価方法の間違い、計算ミスなどさまざまなリスクがあります。結果的に過少申告となれば税務調査が入ってしまい、ペナルティを受けることになりかねません。
また、適用できるはずの控除や特例を見逃したことで大幅に相続税額が上がる可能性もあります。
正しい相続税申告をするには、専門家の力を借りるようにしましょう。
専門家に頼ることで節税できた事例も多い
税に関する知識・相続に詳しい専門家に相談することで、相続税を大幅に節税できるケースは少なくありません。土地の評価1つとってみても、評価額を抑えるための補正ができるかどうかで相続税額は大きく変動します。
また、どのような遺産分割をすると相続税の負担を軽減できるかといったアドバイスもしてもらえます。遺産分割協議を行うまえから専門家に相談すれば、税負担を考慮した遺産分割が実現できるでしょう。
土地を分割して共有することは避ける
土地を相続する際、複数の相続人で共有分割することは避けるようにしましょう。共有分割とは、土地や建物など、物理的な分割が難しい相続財産を複数の相続人で共有名義にする遺産分割方法です。
一見、共有分割をすると公平な遺産分割を行っているように思えるかもしれません。しかし、共有すると以下のようなリスクが発生します。
- 土地活用の意思決定がしづらい
- 土地のすべてを売却するには共有している人全員の同意がいる
- 共有持分のみを買い取ってもらうことは難しい
- 相続を繰り返すと共有名義人がどんどん増えてしまう
共有分割以外の方法で土地を分割するには、土地を物理的に分ける現物分割や、1人の相続人が相続して代償金を他の相続人に支払う代償分割などの方法があります。
土地の分割方法で揉めそうな場合は、相続に詳しい専門家に相談して妥当な解決案を提案してもらいましょう。
土地を相続したらまず相続税評価額を計算しよう
土地を相続したからといって、必ずしも相続税が発生するとは限りません。
相続税が発生するかを判断するためには、土地や建物の相続税評価額を算出し、預貯金や現金などの遺産総額から負債などを差し引いて、遺産総額が基礎控除額を上回っているかを確認しましょう。
しかし、土地の評価額を求めるには専門知識が必要なため、土地や相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。また、相続税の負担をできるだけ軽減させたいのであれば、遺産分割協議の前から適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
相続プラスでは、相続や相続税に強い専門家をエリア別・悩み別に検索することが可能です。相談先に悩んでいる方は、ぜひ活用してください。


