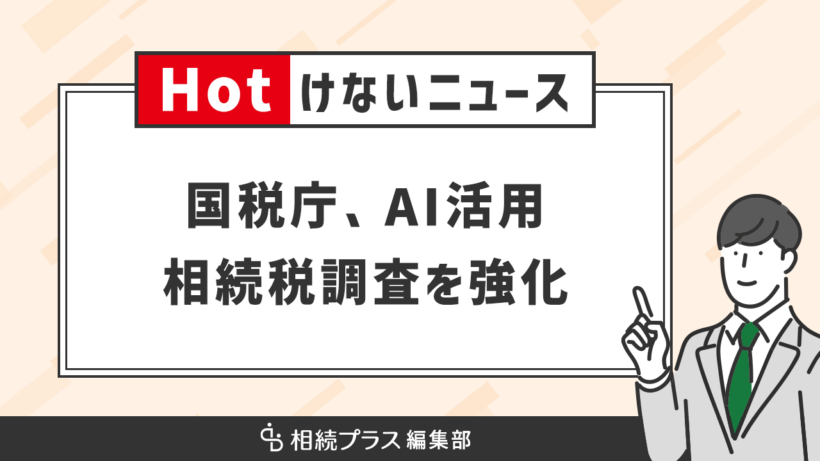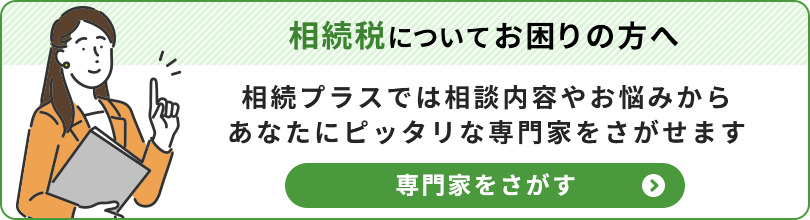国税庁は、相続税の申告漏れ対策として、令和7年夏からAI(人工知能)を本格的に活用することを決定しました。従来、経験豊富な調査官が行っていた調査対象の選定にAIを活用し、過去の申告ミスや不正事例を学習させることで、不正や誤りの傾向を分析するとしています。
国税庁、AI活用で相続税調査を本格化
国税庁によるとAIの活用方法は、申告書、財産債務調書、海外送金記録、保険金や金地金売却時の支払調書など、多岐にわたる資料をデータ化し、分析・スコアリングを行うこととしています。これにより、調査の効率化と精度向上が期待されています。
近年、高齢化の進展に伴い相続件数が増加しており、相続税の申告漏れも増加傾向にあります。国税庁は、名義預金や名義株の申告漏れ、亡くなる直前の定期預金解約による現金分配などにより、追徴税額が過去最高水準に達したと発表しています。
AIの導入により、これまで把握が難しかった海外資産や仮想通貨などのデジタル資産についても、申告漏れのリスクを高精度で検出できるようになると予想されます。
相続税は、相続財産の総額が基礎控除(3000万円+法定相続人1人当たり600万円)を超える場合に申告・納税義務が生じます。しかし、被相続人の資産全体を正確に把握できなかったり、現金なら見つからないといった安易な考えにより、申告漏れが発生するケースがあります。申告を怠った場合、重加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があり、負担の増加が予想されます。


相続税申告に迷ったら…専門家への相談がおすすめ
国税庁のAI活用は、課税をより厳しくするものではなく、公平に適正な課税を行うことを目的としています。AIの導入によって、これまで調査で見落とされていた部分が可視化され、申告の正確性が向上することでしょう。しかし、最初から適正な申告を行っていれば、不利益を被ることはありません。
そのため、AIの導入にかかわらず、被相続人が保有していた資産の範囲を正しく洗い出し、取引記録や口座情報を整理しておくことが大切です。不明点があれば専門家に相談することが、相続手続きの第一歩となります。
相続税の申告や生前対策について不安や疑問を感じた場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。