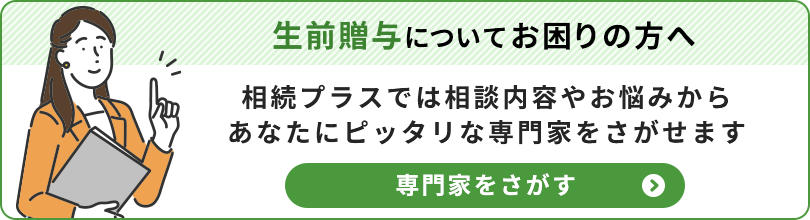土地の贈与を受けた場合、贈与された人は贈与税を支払う必要があります。しかし、贈与税は課税方法の選択や控除の特例適用で節税できる場合があります。また、相続か生前贈与かによっても税額は異なってくるものです。土地の贈与税を抑えるためには、贈与税の仕組みや特例について理解しておく必要があります。この記事では、土地の贈与税の課税方法や非課税になるケース・生前贈与のメリット・デメリットについてわかりやすく解説していきます。
目次開く
土地の贈与税の暦年課税制度と相続時精算課税制度とは?
土地の贈与を受けた場合、贈与税が発生します。
贈与税を計算する際、次の2つの課税方法から選択することになります。
- 暦年課税制度
- 相続時精算課税制度
それぞれの制度の基本や計算方法を詳しくみていきましょう。
暦年課税制度とは?土地の評価・計算方法
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)での贈与額合計に対して贈与税が課税される制度です。
暦年課税での贈与税の計算方法は次の通りです。
- 贈与税額=(年間の贈与額合計-110万円(基礎控除))×贈与税の税率
上記のように、暦年課税の贈与では年間110万円の基礎控除があります。そのため、年間の贈与額が110万円以下の場合は、贈与税が課税されません。
暦年贈与の場合、年間の贈与額合計である点に注意が必要です。1年間の間に土地以外にも贈与を受けている場合、それらを含めた贈与額が贈与税の対象となります。
贈与者単位ではなく贈与を受ける人単位で贈与額を計算するため、父・母から贈与を受けた場合はその合計額になる点にも注意しましょう。
また、贈与税の対象となる土地の贈与額は、時価ではなく評価額です。土地の評価額は、相続税評価額は固定資産税評価額となります。
土地の場合は、路線価に面積と補正率を乗じて算出する路線価方式か、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算出する倍率方式のどちらかで求めます。
「暦年課税制度」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。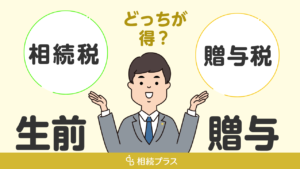
相続時精算課税制度とは?土地の評価・計算方法
相続時精算課税制度とは、贈与だけでなく相続時まで通じた課税方法です。この制度を適用することで、贈与額から2500万円を控除できます。
- 相続時精算課税制度の贈与税=(贈与額-2500万円)×20%(税率)
2500万円を超えた部分に20%の税率を乗じることで、贈与税額を算出できます。ただし、この制度を適用した場合、贈与を受けた財産は相続財産に加算される点に注意が必要です。相続時に贈与財産を加えた額で贈与税を算出し、すでに納めた贈与税を差し引いた額が相続税となります。
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫が贈与を受け取った場合のみ利用できます。相続時精算課税制度を一度適用すると、暦年課税は出来なくなるので、どちらを利用したほうがいいかはしっかりとシミュレーションしたうえで判断するようにしましょう。
また、相続時精算課税制度か暦年課税制度のどちらを適用するかは、贈与者ごとに選択できます。父からの贈与は暦年課税・母からの贈与は相続時清算課税制度かという選択もできるので、節税できる額を計算して選択するようにしましょう。
土地は相続がいい?生前贈与がいい?
土地を譲渡する場合、「相続」か「生前贈与」の選択肢があります。
相続:譲渡者が亡くなってから土地を譲渡する方法⇒相続税の対象
生前贈与:譲渡者が生きているうちに土地を譲渡する方法⇒贈与税の対象
それぞれ課税される税金が異なるため、税額も異なってくるので注意しましょう。相続と生前贈与のどちらが適しているかは、個別の事情によって異なります。
以下では、生前贈与した方がいいケース・相続した方がいいケースを解説します。
土地を生前贈与した方がいいケース
生前贈与した方がいいケースには、次のような例があります。
- 将来値上がりが見込まれる土地
- 収益を生む不動産
- 相続トラブルが発生する恐れがある場合
- 特定の人の土地を贈与したい場合
土地の贈与税・相続税を算出するための評価額は、譲渡時点での価値で算出されます。
将来的に値上がりが見込まれる土地であれば、値上がり前に贈与しておくことで相続税よりも税額を抑えられるでしょう。また、相続時に相続人間でトラブルが発生する恐れがある場合は、生前中に贈与しておくほうがトラブルを避けやすくなります。
生前贈与であれば、生きている間に贈与できるので贈与者の希望を確実に反映できます。相続の場合、遺言書を残していても確実に希望する人に渡る保証はありません。
特定の人に確実に土地を譲りたい場合は、生前贈与が適しているでしょう。
土地を相続した方がよいケース
相続した方が良いケースとしては、次のような例があります。
- 評価額が基礎控除に満たない
- 小規模宅地等の特例による節税効果を得たい場合
相続税には「3000万円+(法定相続人の人数×600万円)」という基礎控除があり、基礎控除内であれば相続税は掛かりません。土地の価格が基礎控除内に収まるのであれば、相続の方が節税になるでしょう。
小規模住宅等の特例とは、住んでいた土地や事業用の土地を相続した場合、要件を満たすことで土地の評価額を最大80%まで減額できる制度です。評価額を大きく下げられるので、税額の負担を減らせられます。
生前贈与と相続で支払う税金を具体事例で比較
具体的な計算例で生前贈与と相続の税金を比較してみましょう。
条件は次の通りです。
- 土地の固定資産税評価額:4000万円
- 父から子への譲渡
- 法定相続人:子ども1人
- 他の相続財産は考慮しない
なお、計算を簡単にするため特例は適用しないものとして計算します。
まずは、生前贈与の場合の贈与税を計算します。
父母・祖父母から18歳以上の子や孫への贈与の場合、特例贈与の税率で計算し、贈与額3000万円から4500万円までの税率は50%です。また、この場合は415万円の控除もできます。
そのため、暦年課税での贈与税は次の通りです。
- 暦年課税:(4000万円-110万円)×50%-415万円=1530万円
ちなみに、相続時清算課税制度を利用した場合は次のようになります。
- 相続時精算課税制度:(4000万円-2500万円)×20%=300万円
ただし、相続時精算課税制度の場合は、相続財産に4000万円をプラスして相続税を算出することになります。そこから算出した相続税から300万円を控除した額が、納税する相続税になるのです。
次に、相続の場合の相続税を見てみましょう。
法定相続人が子ども1人なので、基礎控除額は次のようになります。
- 基礎控除額=3000万円+(1人×600万円)=3600万円
- 相続財産=4000万円-3600万円=400万円
- 相続財産1000万円以下の場合の税率は10%で控除はありません。
そのため、相続税は次のようになります。
- 相続税=400万円×10%=40万円
ただし、土地を譲渡する場合、相続税・贈与税以外にも不動産取得税や登録免許税なども発生します。どちらがお得になるかは、総合的な税額で比較して検討するとよいでしょう。
贈与税が非課税になるケース

贈与税には、さまざまな非課税制度が設けられており、適用することで税額を大幅に抑えることが可能です。
贈与税が非課税になるケースとしては、次のような場合が挙げられます。
- 年間110万円以下(基礎控除内)の贈与
- 生活費や教育費の贈与
- 配偶者への贈与
- 結婚・子育て資金の贈与
- 教育費の一括贈与
- 住宅取得の資金のための贈与
- 障害者への贈与など
上記のような贈与の場合、一定額が非課税になるので大きく節税が可能です。
「生前贈与」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
土地を生前贈与するメリット・デメリット
土地の生前贈与にはメリットだけでなくデメリットもあるので、デメリットまで正しく理解しておくことが大切です。
ここでは、土地の生前贈与のメリット・デメリットを見ていきましょう。
メリット
生前贈与のメリットには、次のようなことが挙げられます。
- 節税効果が得られる
- 相続トラブルを避けられる
- 短期間で贈与が可能
- 贈与するタイミングや相手を自分で決められる
- 認知症対策になる
生前贈与は、生きているうちに贈与するので、贈与に自分の意志を反映できるというメリットがあります。また、不動産が相続財産に含まれると現金のように分割できないことからトラブルに発展するケースも珍しくありません。
生前贈与しておくことで相続時のトラブルを回避でき、相続人間の関係性を悪化させないことにもつながるでしょう。
デメリット
デメリットとしては、次のようなことがあります。
- 不動産取得税がかかる
- 贈与税がかかかる
不動産を生前贈与した場合、取得した人は不動産取得税を支払う必要があります。不動産取得税は、固定資産税評価額×4%です。
不動産の価値が高ければ、不動産取得税も高額になるので注意しましょう。また、生前贈与では贈与税がかかります。特例などを適用して節税することも可能ですが、場合によっては贈与税は相続税よりも高くなる恐れもあります。
税金ついて理解したうえで生前贈与しなければ、受け取った側に大きな負担となる可能性があるので、慎重に判断するようにしましょう。
土地の生前贈与手続きの流れ
土地を生前贈与する場合の大まかな流れは次の通りです。
- どんな目的で贈与するかを決める
- 贈与税の課税方法をきめる
- 受贈者の合意の元、贈与契約書の作成
- 贈与する財産を移す
- 不動産取得税を納付する
どんな目的で贈与するかを決める
まずは、贈与する相手と贈与する財産を決めます。
贈与税は、使用用途によって非課税枠があるので、使用用途を定めておくことも大切です。非課税額について要件などを確認したうえで、生前贈与を検討するとよいでしょう。
贈与税の課税方法を決める
贈与税の課税方法を「暦年課税」か「相続時精算課税制度」のどちらにするかを選びます。
それぞれ税額やメリット・デメリットが異なるので、贈与を受ける相手とよく話し合ってお互いにお得になる方法を選ぶようにしましょう。
受贈者の合意の元、贈与契約書の作成
贈与とは、贈る側と贈られる側の合意があって成立します。贈る側が一方的に渡したとしても贈与は成立しないのです。
贈与自体は契約書を作らず口頭での合意でも贈与と見なされます。しかし、非課税枠を利用する場合などでは贈与の合意があることを署名する必要があり、そのために贈与契約書を作成しておくことをおすすめします。
贈与契約書には決まった書式はなく、自分でも作成可能です。しかし、税金が絡んでくるため専門家に依頼して作成してもらうことも検討するとよいでしょう。
贈与する財産を移す
贈与の条件が決まったら、実際に財産を移す手続きに進みます。土地の生前贈与の場合、登記の変更が必要です。
贈る側・贈られる側での必要書類を揃えて、共同で登記申請しましょう。
贈与税の申告
贈与完了後は、受け取った人は贈与税の申告をする必要があります。贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年3月15日までです。
また、相続税精算課税制度を選択した場合で贈与税が発生しないケースでも申告が必要なので、税金が発生しなかったからと言って申告しないことが無いように注意しましょう。贈与税の申告は、管轄の税務署に申告書を提出することで申告できます。
不動産取得税を納付する
土地を生前贈与した場合、取得した側は不動産取得税を支払う必要があります。不動産取得税は、名義変更後3~6ヵ月後に納税通知書が送付されるので、通知書で納税します。
自治体によっては名義変更から1年後というケースもあるので、忘れずに税金の準備をしておくことが大切です。
土地の生前贈与で必要な書類と費用
土地の生前贈与ではさまざまな書類が必要になります。また、手続きによっては費用も掛かるので費用についても理解しておくことが大切です。
ここでは、生前贈与で必要な書類と費用をそれぞれ見ていきましょう。
土地の生前贈与に必要な書類
生前贈与に必要な書類は、課税方法によっても異なります。暦年課税と相続時精算課税での必要省類を一覧で確認しましょう。
| 暦年課税 | ・本人確認書類 ・贈与税申告書 ・土地の評価明細書 ・特例を受ける場合は贈与者との関係が分かる戸籍謄本や対象不動産を照明する登記事項証明書 |
|---|---|
| 相続時精算課税 | ・本人確認書類 ・相続時精算課税制度選択届出書 ・贈与を受ける人の戸籍謄本や戸籍附票の写し ・贈与した人の戸籍附票の写しや住民票の写し |
また、登記する際にも必要な書類があります。
「登記に必要な書類」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
土地の生前贈与に必要な費用
生前贈与で必要な費用には、次のような項目が挙げられます。
- 土地の不動産取得税:不動産の評価額×4%(原則)
- 登録免許税:不動産の評価額×2%
- 贈与税
- 専門家に依頼する場合は依頼料
生前贈与では、贈与税以外にも不動産取得税や登録免許税が発生します。また、登記や契約書の作成などを司法書士・税金の相談を税理士にした場合は依頼料も発生します。
依頼料は依頼内容や依頼先によっても異なりますが、5~10万円程が目安となるでしょう。
まとめ
贈与税の計算方法や生前贈与のメリット・デメリットなどをお伝えしました。
生前贈与の場合、「暦年課税」と「相続時精算課税制度」のどちらかを選ぶ必要があり、それぞれ税額が異なります。また、土地を譲渡する場合、生前贈与か相続かという選択もあるので、税額やメリット・デメリットを比較して慎重に贈与方法を選択することが大切です。