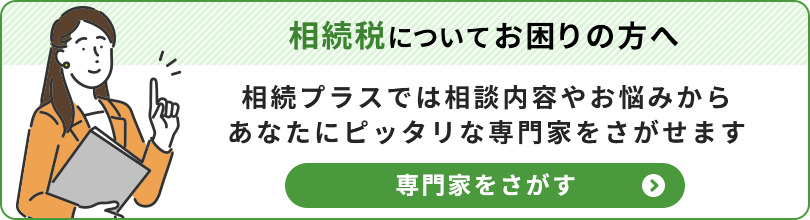「土地の相続税がいくらになるかわからない」と悩んでいませんか。土地の相続税はその土地の評価額によって決まり、相続税はあらゆる財産を含めた額で計算します。つまり、相続税の計算方法と土地の評価額の算出方法の両方を把握しておかないといけません。今回は、相続税の計算方法と土地の評価額の算出方法をわかりやすく解説します。
相続税とは?

相続税とは、被相続人(亡くなった人)の財産を引き継いだときに課される税金のことです。相続した財産の合計が基礎控除の額を越えると相続税の対象になります。
基礎控除とは、すべての納税者を対象に一定の額を所得から差し引くことです。故人が残した相続財産の合計額が基礎控除内に収まる金額の場合、相続税はかかりません。
基礎控除額は以下の計算式で算出できます。
- 基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
土地を含めた財産の総額から基礎控除額を引いた額に課税されます。つまり、どのくらい相続税がかかるかの判断は、土地だけでなくあらゆる財産を含めた額で考えなければなりません。
相続税の計算ステップ
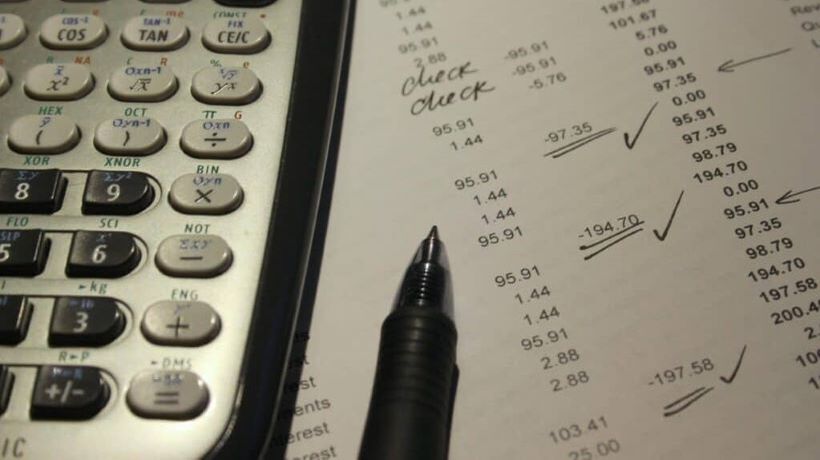
相続税を計算する方法を6つのステップで確認しましょう。
ステップ1:相続財産の総額を計算する
正味の遺産額を計算しましょう。正味の遺産額とは、遺産総額に相続開始前3年以内の暦年課税される贈与財産の金額を加算し、そこから非課税財産・葬式費用・債務を控除したものです。土地や建物を相続する場合、相続税算出のための評価額を算出します。
正味の遺産額は、以下のように計算しましょう。
正味の遺産額=遺産総額+課税対象の生前贈与分‐(非課税財産+葬式費用+債務)
非課税財産とは、以下に当てはまるものです。
- 墓所、仏壇、祭具など
- 行政や公益法人に寄附した財産
- 生命保険金(500万円×法定相続人分)
- 死亡退職金(500万円×法定相続人分)
課税されない費用を差し引いた額が、正味の遺産額です。
ステップ2:基礎控除額を計算する
以下の計算式で基礎控除額を計算しましょう。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、被相続人の妻と子ども2人がいるケースだと以下の通りです。
- 3000万+600万×3(妻+子ども2人)=4800万円
この場合、正味の遺産額が4800万円を超過したときに相続税が課せられます。
正味の遺産額が基礎控除を超過した分を課税遺産総額といいます。
ステップ3:相続財産を法定相続分で分けたときの計算をする
課税遺産総額に法定相続分の割合を当てはめて仮の相続税額を算出します。
この時点では仮の納税額を算出するため、実際に法定相続の割合通りに分けていなくても以下の表に照らして計算します。
<法定相続分>
| 相続人 | 相続分 | 参考 |
|---|---|---|
| 配偶者と直系卑属 (子ども) | 配偶者:2分の1 | 養子・胎児を含む子ども同士は均等に分割 |
| 子ども:2分の1 | ||
| 配偶者と直系尊属 (両親) | 配偶者:3分の2 | 直系卑属同士は均等に分割 |
| 直系尊属:3分の1 | ||
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:4分の3 | 血のつながった兄弟姉妹は均等に分割 |
| 兄弟姉妹:4分の1 |
配偶者は必ず法定相続人の資格を得ます。具体例を見ていきましょう。
正味の遺産が4億円、妻と子ども2人の場合は以下の通りです。
課税遺産総額を計算する
4億‐4800万(上記で算出した基礎控除額)=3億5200万円(課税遺産総額)
課税遺産総額からそれぞれの法定相続人が取得する遺産額を算出する
- 妻…3億5200万×1/2=1億7600万円
- 子ども…3億5200万×1/2×1/2(人数分)=8800万円
ステップ4:相続人ごとの税額を算出して総額を計算する
相続人ごとに速算表から相続税を算出し、合算させます。
各相続人の相続税は、以下の速算表に記載された税率をかけて控除額を差し引いた額です。
<相続税の速算表>
| 法定相続分の金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1000万円以下 | 10% | – |
| 1000~3000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3000~5000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5000~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億~2億円以下 | 40% | 1700万円 |
| 2億~3億円以下 | 45% | 2700万円 |
| 3億~6億円以下 | 50% | 4200万円 |
| 6億円以上 | 55% | 7200万円 |
正味の遺産が4億円、妻と子ども2人のケースだと、それぞれの税額は以下の通りです。
- 妻…1億7600×40%(税率)‐1700万(控除額)=5340万円
- 子ども1人あたり…8800万×30%‐700万=1940万円
それぞれの法定相続人の相続税額を合算して、相続税の総額を算出します。
- 5340万+11940万×2(子どもの数)=9220万円
ステップ5:相続税の総額を実際の相続割合で分ける
合算した相続税を各相続人の相続割合に当てはめましょう。
妻が遺産の1/2、残りの1/2を長男が1/5、次男が4/5で分配したケースで考えてみましょう。
- 妻…9220万×1/2=4610万円
- 長男…9220万×1/2×1/5=922万円
- 次男…9220万×1/2×4/5=3688万円
ステップ6:相続税から控除を行う
使える控除があれば適用します。以下の控除や特例が代表的です。
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者控除
- 未成年者控除
配偶者が相続する場合、必ず配偶者控除を活用できるか確認しましょう。
以下の2つのうち、どちらか高い方の金額が控除されます。
- 実際に取得した正味の遺産額が1億6000万円まで
- 法定相続分相当額まで
相続税の計算例

いくつかの遺産額のパターンごとに計算してみましょう。
どのケースも家族構成は妻と子ども2人、法定相続割合通りに相続しています。
例1:遺産4000万円の相続税の計算方法
まず基礎控除額を計算します。
- 3000万円+600万円×3(妻と子ども2人分)=4800万円(基礎控除額)
この場合、遺産額が基礎控除額を超えないため、相続税はかかりません。
例2:遺産8000万円の相続税の計算方法
基礎控除額は以下の通りです。
- 3000万円+600万円×3=4800万円(基礎控除額)
正味の遺産額8000万から基礎控除額を引いて、課税遺産総額を算出します。
- 8000万‐4800万=3200万円(課税遺産総額)
課税遺産総額を法定相続分どおりに分配します。
- 妻…3200万×1/2(法定相続割合)=1600万
- 子ども1人当たり…3200万×1/2(法定相続割合)×1/2(人数)=800万
それぞれに速算表の税率と控除額を適用し、それぞれの法定相続人別に税額を計算します。
- 妻…1600万×15%‐50万=190万円
- 子ども1人当たり…800万×10%=80万円
上記の税額を合算して相続税の総額を算出しましょう。
- 190万+80万×2(人数)=350万円(相続税の総額)
相続税の総額に実際に得た遺産額の割合をかけて計算します。
- 妻…350万×1/2=175万
- 子ども1人当たり…350万×1/2×1/2(人数分)=87.5万円
配偶者控除が適用されるため実際に納める税金は以下の通りです。
- 妻…0円
- 子ども1人当たり…87.5万円
例3:遺産10億円の相続税の計算方法
基礎控除額は以下の通りです。
3000万円+600万円×3=4800万円(基礎控除額)
正味の遺産額10億から基礎控除額を引いて、課税遺産総額を算出します。
- 10億‐4800万=9億5200万円(課税遺産総額)
課税遺産総額を法定相続分どおりに分配します。
- 妻…9億5200万×1/2=4億7600万円
- 子ども1人当たり…9億5200万×1/2×1/2=2億3800万円
それぞれに速算表の税率と控除額を適用し、各法定相続人別に税額を計算します。
- 妻…4億7600万×50%‐4200万=1億9600万円
- 子ども1人当たり…2億3800万×45%‐2700万円=8010万円
上記の税額を合算して相続税の総額を算出しましょう。
- 1億9600万+8010万×2=3億5620万円(相続税の総額)
相続税の総額に実際に得た遺産額の割合をかけて計算します。
- 妻…3億5620万×1/2=1億7818万
- 子ども1人当たり…3億5620万×1/2×1/2=8905万円
法定相続割合通りに遺産を分けたことにより配偶者控除が適用されるため、実際に納める税金は以下の通りです。
- 妻…0円
- 子ども1人当たり…8905万円
相続における土地の評価額について

相続における土地の評価額の計算方法について見ていきましょう。
相続税評価額とは
相続税評価額とは、財産ごとに決められた評価方法にのっとって計算した財産価格のことです。自宅や土地、美術品などの相続する財産を一通り評価し、貨幣換算して財産価格を算出します。
評価方法は財産ごとに定められており、その方法に従って計算します。相続税評価額の基本的な考え方は、原則「時価」で計算することです。不動産の場合、固定資産税や路線価が基準の価格になります。
また、一口に土地といっても、更地や建物が建っている場合で計算方法が変わってきます。それぞれの場合にどのような計算をするのか詳しく見ていきましょう。
更地の評価額計算法
更地(土地)の評価額の計算方法は以下の2種類です。
- 路線価方式
- 倍率方式
路線価とは、路線(道路)に面する土地1㎡あたりの評価額のことです。路線価方式による相続税評価額は以下の計算式で算出します。
路線価×各種補正率×土地面積
補正率とは、「使いづらい土地の形」や「間口が道に面していない」といった各土地ごとの事情を考慮した数値です。土地のマイナス要素を計算式に組み込むことで、正確な評価額を算出できます。
たとえば、以下の土地があったとします。
- 路線価…20万円
- 各種補正率…0.8
- 土地面積…100㎡
この場合の相続税評価額は、20万×0.8×100㎡=1600万円です。
各種補正率を算出するのは難しいので、大まかな金額を見積もりたい場合は、路線価と土地面積で計算しましょう。路線価は国税庁ホームページの路線価図・評価倍率表で確認できます。
倍率方式とは、路線価が定められていない地域の土地評価方式です。
倍率方式の計算式は以下の通りです。
固定資産税評価額×倍率
固定資産税評価額とは、市区町村から毎年送られてくる納税通知書に記載されている、土地の価格のことです。
倍率とは、国税庁ホームページの路線価図・評価倍率表に掲載されている数値のことです。
例を挙げて確認しましょう。
- 固定資産税評価額2000万円の土地
- 評価倍率1.1
この場合の相続税評価額は、2000万×1.1倍=2200万円です。
どちらの場合でも相続税評価額は、取引される価格よりも低いことが一般的です。
自宅のある土地の評価額計算法
建物がある土地の場合だと、小規模住宅地等の特例により更地よりも評価額を下げられる可能性があります。小規模住宅地等の特例は、被相続人等の居住の用に使われていた敷地は330㎡を限度に80%減額できる制度です。
以下のケースで小規模住宅棟の特例の計算方法を確認しましょう。
- 相続税評価額…1億円
- 面積…150㎡
この場合の小規模宅地等の特例適用額は、1億×80%=8000万円です。評価額は1億-8000万(減額分)=2000万円と計算できます。
特定居住用宅地等の対象となるのは、被相続人または被相続人と同じ生計の親族が住んでいた土地です。また、配偶者以外の人が相続した場合、取得した土地を相続税の申告まで所有し続けたり、居住し続けたりしなくてはなりません。
アパート・マンションのある土地の評価額計算法
アパートが建っている土地は貸家建付地(かしやたてつけち)として扱われ、その土地にかかる評価額を下げることができます。
貸家建付地の計算式は以下の通りです。
貸家建付地の評価額= 自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合30%)
借地権割合とは、土地の権利の中で借地の割合を示す数字のことです。割合は土地によって異なりますが、だいたい60〜70%です。借家権割合とは、建物の価値に占める借家権の割合のことで、割合は全国一律で30%と決められています。
貸家建付地であれば更地の8割程度の評価に抑えられることが多い傾向にあります。さらに、貸家建付地で小規模住宅地等の特例を使えば、200㎡の限度で50%減額が可能です。
ここまで見てきたことをまとめると、以下の通りです。
- 路線価方式、倍率方式いずれも取引価格よりも低めに算出される
- 更地よりも建物が建っている方が評価額を下げられる
- 小規模住宅地等の特例を活用すれば評価額を下げられる
土地の評価はひとつひとつ異なるため、正確な費用が知りたい場合は税理士に相談しましょう。
納税金額を抑える控除一覧

納税金額を抑えられる控除を一通り確認しましょう。
基礎控除
被相続人が遺した財産のうち、一定の金額まで相続税を課さない制度のことです。遺産総額が基礎控除額を超過した分に相続税がかけられます。遺産が基礎控除内に収まれば、申告や納税する必要はありません。
配偶者控除
配偶者控除とは、配偶者に一定の額まで課税しない制度のことです。この場合の配偶者とは、婚姻に基づく配偶者のことで内縁の妻や夫は対象になりません。配偶者控除は、以下の2つのうち金額の高い方で控除されます。
- 相続した遺産のうち課税対象額が1億6000万円まで
- 配偶者の法定相続分
1億6000万円を超える相続でも、法定相続の割合に沿った相続なら課税されません。配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。
未成年者控除
未成年者控除とは、教育費や養育費が必要な未成年であることを考慮した控除のことです。相続人が20歳未満の場合、20歳に達するまでの年数分×10万円が控除されます。
計算式は以下の通りです。
未成年者控除額=(20‐相続した年齢)×10万
たとえば、15歳で相続した場合、未成年者控除額は50万円です。
障害者控除
障害者控除とは、障害者であることを考慮した控除のことです。相続人が85歳に達するまでの年数×10万円を控除できます。特別障害者の場合は20万円です。
計算式は以下の通りです。
障害者控除額=(85‐相続した年齢)×10万もしくは20万円
たとえば、特別障害者が40歳で相続した場合、900万円が控除されます。

相次相続控除
相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)とは、相続が発生してから10年以内に次の相続が発生したときに、一定の金額を控除できる制度のことです。最初の相続から2回目の相続までの期間が短いほど控除額は大きくなります。

小規模宅地等の特例
小規模住宅地等の特例とは、一定の要件に当てはまる土地を相続したときに、相続税の計算をする際の評価額を50%または80%減額にできる制度のことです。
小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた自宅だけでなく、保有している賃貸アパートや賃貸駐車場にも適用できます。
相続税申告のあれこれ〜期限や土地の活用方法など〜

相続税を申告するときに把握しておきたいポイントを確認しましょう。
相続することが決まったら必ず相続登記をしよう
相続することが決まったら必ず相続登記を行いましょう。相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに名義を相続人に変更する手続きのことです。
これまでは義務ではありませんでしたが、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
※引用:不動産登記法|第76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請)
また、不動産を売るときに正しく登記が行われていないと売買できません。土地を相続したら忘れずに相続登記を行いましょう。
相続税の申告・納税期限は10か月以内
相続税の申告・納税期間は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限が土、日、祝日に当たる場合、これらの日の翌日が期限日となります。
期限までに申告をしなかったり実際の額より少ない値で申告をしたりすると、本来の税金だけでなく加算税や延滞税も課される場合があるので注意しましょう。
ただし、相続が基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません。
相続した土地の活用方法
相続した土地の活用方法を見ていきましょう。代表的な活用方法は、以下の4つです。
| 活用方法 | 特徴 |
|---|---|
| 賃貸 |
|
| 売却 |
|
| 等価交換 |
|
| 商業に活用 (トランクルーム・駐車場など) |
|
等価交換とは、土地を建築会社や不動産会社に売却して、土地の価格に応じた建物の区分所有権を取得することです。
どの方法もメリット・デメリットを吟味して選択することが大切です。
まとめ

土地の相続税を計算するときは土地の評価額がカギになります。
所有している土地の評価額の概算は簡単に計算できますが、土地によって当てはめる数字が変化するため正確な数字を出すのは困難です。正確な土地の評価額が知りたい場合は税理士に相談しましょう。
相続税は土地だけでなくあらゆる相続財産を含めた額で計算します。基礎控除額を明らかに超過する場合は、今のうちから税金対策のために手を打つことが大切です。
相続税が算出される流れと土地の計算方法を把握して、税金を抑える小規模住宅地等の特例や控除を上手に利用しましょう。