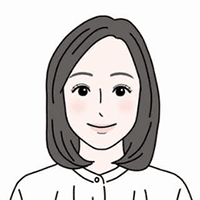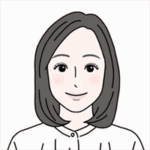連れ子を伴った相手と結婚をしても、連れ子と自身の間には親子関係がないため相続する権利はありません。しかし、連れ子に遺産を譲る方法は複数あります。本記事では、連れ子に相続させる5つの方法や注意点について詳しく解説します。家庭の状況や遺産内容によって最適な方法が異なるため、連れ子に財産を譲りたい方はぜひ参考にしてください。
地元の専門家をさがす
連れ子に再婚相手の相続権はない
以前の配偶者との子どもを伴った方と結婚した場合、自分が死亡したときに連れ子に相続権はありません。再婚しただけでは再婚相手と連れ子との間には親子関係がなく、相続人になれないからです。
一方で、両親が離婚したとしても、両親と子どもの間にある親子関係には無関係です。離婚したあと母親が子どもを連れて再婚したとしても、その子と実父との法律上における親子関係は続き、実父の相続権も求められます。
ただし、再婚したあとに生まれた子どもには血縁関係があり法律上の親子関係が認められるため、相続権が発生します。実子と同じように連れ子を養っていたとしても、手続きをしなければ連れ子は再婚相手の相続人になれません。
遺産を連れ子に相続させる方法
遺産を連れ子に相続させたい場合、以下の5つの方法があります。
- 遺言書に遺贈する旨を記載する
- 連れ子と養子縁組をする
- 連れ子に生前贈与をする
- 実子の場合は認知届を提出する
- 相続発生後に連れ子が特別寄与料を請求する
「相続」という方法だけでなく、「遺贈」や「贈与」という選択肢も含めて財産を連れ子に譲る方法をご紹介します。
遺言書に遺贈する旨を記載する
遺言書に遺贈する旨を記載し、遺言内容を実行してもらいましょう。この場合、連れ子は相続ではなく「遺贈」という形で財産を引き継ぐこととなります。
妻が前夫との間にできた子どもを連れて再婚相手と結婚したとき、連れ子と夫の間には法律上の親子関係が認められません。しかし、夫の実子と同じように連れ子に接してきたのであれば、実子と同様に遺産を譲りたいと考えるのではないでしょうか。
このような場合、以下のような内容の遺言書を作成できます。
「嫁Aに50%、連れ子Bに25%、実子Cに25%の財産を与える」
本来連れ子には相続権がないため、法定相続分は嫁と実子に50%ずつです。しかし、兄弟同然に育ててきた連れ子と実子の取り分に差をつけたくないと考えるのであれば、上記のように本当の親子・兄弟と同じ法定相続分で財産を分け合って欲しいと遺言を残しましょう。
もちろん、連れ子と実子で取り分を変えても問題ありません。
遺言書の内容を確実に遺族に残し、実行してもらいたいと考えるのであれば、公正証書遺言を選びましょう。公正証書遺言であれば、不備によって無効になる心配がありません。
また、あらかじめ遺言執行者を指名しておくと、スムーズに遺言内容を実現してもらえるでしょう。
「遺言書」や「遺贈」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
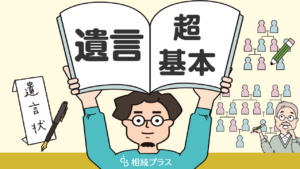


連れ子と養子縁組をする
再婚相手と連れ子が養子縁組すると、連れ子に相続権が認められます。なぜなら、養子縁組を行った両者の間に法律上の親子関係が生まれるからです。養子縁組をすれば、実子と同等の相続分が法律で認められます。
たとえば、夫が前妻との間にできた子どもを連れて再婚相手と結婚したとしましょう。このとき、再婚相手である妻と連れ子が養子縁組をすれば妻が亡くなったときに相続人になれます。
夫、または妻の連れ子と養子縁組をするには、市区町村役場にて手続きを行いましょう。ただし、未成年者と養子縁組をするときは、原則、市区町村役場での手続きの前に家庭裁判所での手続きが必要ですが、連れ子を養子縁組する場合は不要となります。届出を出した日から法律上の親子関係が認められます。ちなみに、普通養子縁組をしても実親との親子関係は継続されるため、実親の相続人にもなれます。
「養子縁組における相続トラブル」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

連れ子に生前贈与をする
亡くなる前に、連れ子に対して生前贈与をすることで財産を取得させる方法もあります。贈与は誰にでもできる行為のため、連れ子に対しても贈与ができます。
贈与額に応じて受けとった側の連れ子に贈与税が発生しますが、年間110万円以内の贈与であれば贈与税は発生しません。計画的に財産を移転させれば、贈与税・相続税の節税につながります。
ただし、贈与は双方の合意があって初めて成立します。連れ子の通帳を勝手に作って振り込んだり、不動産の名義変更をしたりしないように注意しましょう。
「生前贈与」や「生前贈与のやり方」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。


実子の場合は認知届を提出する
事実婚の相手や内縁の妻(夫)など婚姻関係のない実親同士が結婚した場合、連れ子は結婚相手の実子です。しかし、何も手続きをしないままだと結婚相手と連れ子の間には法律上の親子関係はないままです。
そこで、事実婚の相手や内縁の妻(夫)の子どもを実子として認知すれば、法律上の親子関係が認められ相続する権利を与えることができます。
親同士に婚姻関係がないときに生まれた子どもは、結婚しないままの関係でも認知をすれば相続権を与えられます。市区町村役場で認知届を提出すれば、ただし、成年の子を認知するときは、その子の承諾がなければできません。

相続発生後に連れ子が特別寄与料を請求する
相続発生後、連れ子から相続人らに対して特別寄与料を請求できる可能性があります。特別の寄与とは、被相続人の生前に介護や療養看護などを無償で尽くした寄与度に応じて金銭を請求できる制度です。
たとえば、被相続人に介護が必要となったときに同居していた連れ子が無償で介護を行い、相続人の遺産が目減りすることを防いだときに請求できます。有償で行った場合や請求に値するほどの貢献がなかった場合には、特別寄与料の請求はできません。
特別寄与料を請求するには、連れ子が相続人に対して直接交渉する必要があります。もし交渉してもらえない場合や、交渉が決裂してしまった場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てることが可能です。
また、特別寄与料を請求できる期限は、相続開始および相続人をしったときから6か月以内と定められています。
連れ子に相続させたいときに注意すべきポイント

連れ子に相続させたいとき、あらかじめ理解しておきたい注意点は以下の通りです。
- 実子やほかの相続人との揉めごとに発展しやすい
- 相続税が2割加算の対象になる場合がある
- 数次相続が発生すると養子縁組なしでも相続権が与えられる
- 連れ子の親と離婚しても子どもとの養子縁組は解消されない
4つのポイントを理解しておき、トラブルや揉めごとを未然に防ぎましょう。
実子やほかの相続人との揉めごとに発展しやすい
連れ子に財産を譲る場合、結婚相手や連れ子をよく思っていない親族から反発される恐れがあります。とくに実子や相続人にとっては、連れ子に財産を譲ることで自分の取り分が少なくなり不満を抱くかもしれません。
このようなトラブルを防ぐためには、遺言書を作成して被相続人の意思を伝えるようにしましょう。連れ子に対する思いや他の親族たちにも理解して欲しい旨を伝えることで、受け入れてもらえる可能性が高まります。もちろん、生前から親族たちに連れ子を受け入れてもらう努力をすることも大切です。
また、遺留分には十分注意が必要です。遺留分とは、法律上相続人に定められた最低限の遺産の取り分です。相続人の遺留分を侵害する遺言書を残すと、実質的に遺言内容とは違う結果を招くだけでなく訴訟トラブルにつながりかねません。
万が一、他の相続人の遺留分を侵害してまで連れ子に財産を引き継がせたいのであれば、生前に「妻の面倒をすべて連れ子に任せたい」「事業を連れ子にすべて引き継ぎたい」などの理由を話し、家族へ理解してもらう努力をしましょう。
相続税が2割加算の対象になる場合がある
連れ子と養子縁組をせずに遺産を引き継がせると、相続税に2割加算が適用されます。相続税が発生するとき、法定相続人ではない第三者に課される相続税は法定相続人の1.2倍です。
もちろん、遺産総額が基礎控除額を超えていなければ相続税は発生しません。金銭だけであれば遺産のなかから相続税を支払えますが、価値の高い不動産を引き継がせると連れ子の自己資金から相続税を支払う必要があります。
財産状況を理解したうえで、連れ子に譲る遺産の内容を決定しなければ相続税による経済的負担が大きくなってしまうでしょう。
数次相続が発生すると養子縁組なしでも相続権が発生する
数次相続が発生した場合、養子縁組をしていなくても相続権を取得することがあります。数次相続とは、相続の手続き中に相続人が亡くなって次の相続が発生することです。
たとえば、妻が連れ子と一緒に夫と再婚し、妻と夫の間に実子が生まれたと仮定します。夫が亡くなった場合、夫と連れ子は養子縁組をしていないため相続人にはなれません。夫が死亡したときの相続人は、妻と実子のみです。
しかし、相続の手続きをしている間に妻も亡くなると、本来夫の遺産を受け取るはずだった妻(連れ子の実親)が亡くなったことで、妻の相続権が実子と連れ子へ移ります。
<夫が亡くなったときの相続分>
- 妻:2分の1
- 実子:2分の1
- 連れ子:0
<相続手続き中に妻が亡くなったとき、妻から相続する夫の遺産の相続分>
- 実子:4分の1
- 連れ子:4分の1
妻が相続した遺産の2分の1を実子と連れ子で分け合うため、夫の遺産の4分の1ずつを妻から相続することとなります。結果的に夫の遺産の相続分は、それぞれ実子は4分の3、連れ子は4分の1です。
このような特殊なケースでは、養子縁組をしていなくても連れ子が相続権を持って遺産を相続します。
連れ子の親と離婚しても子どもとの養子縁組は解消されない
結婚のタイミングで相手の連れ子と養子縁組をしても、離婚に至るケースもあるでしょう。離婚をすると連れ子との親子関係がなくなると考えている方もいますが、実際には離婚によって親子関係が解消されることはありません。
そのため、何も手続きをしないままだと、相手の連れ子が相続人となってしまいます。もちろん、長年実子のように育ててきた連れ子に相続権を与えたいと考えているのであれば、問題ありません。
しかし、親子関係を解消したいと考えるのであれば離縁手続きをする必要があります。離縁手続きをすれば、親子関係による扶養義務や相続権はなくなります。
万が一、離婚に至った場合は、養子縁組を続けるか離縁手続きをするかよく検討しましょう。

連れ子の相続に関するよくある質問
最後に、連れ子の相続に関するよくある質問に回答していきます。
よくある質問は、以下の通りです。
- 連れ子を養子にしたときの相続分はどれくらいですか?
- 連れ子に財産を渡さないことは可能ですか?
- 離婚した元配偶者との子どもにも相続させなければなりませんか?
- 相続税を軽くしたい場合の対策方法はありますか?
順番に確認し、疑問や不安を解消しましょう。
連れ子を養子にしたときの相続分はどれくらいですか?
連れ子を養子にしたときの相続分は、実子と同じです。
被相続人の子どもが相続人の場合、民法では以下のような相続分が定められています。
| 相続人の内容 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者+子ども | 配偶者:2分の1 子ども:2分の1を子どもの数で均等に分ける ※子どもが2人だった場合、子ども1人あたりの相続分は4分の1 |
| 子どもだけ | 子どもの数で均等に分ける ※子どもが2人だった場合、子ども1人あたりの相続分は2分の1 |
連れ子も実子も関係なく、「被相続人の子ども」として同等の相続分が認められています。
連れ子に財産を渡さないことは可能ですか?
そもそも連れ子には相続権がないため、養子縁組や生前贈与、遺言における遺贈をしなければ財産を渡すことになりません。
すでに養子縁組をしている連れ子に遺産を相続させたくないのであれば、離縁手続きが必要です。しかし、両者で合意が取れなければ調停・訴訟に発展する恐れがあります。調停・訴訟の末、結果的に離縁が認められない場合もあるでしょう。
もし、離縁手続きができない場合は、遺言書に最低限の取り分である遺留分のみを相続させる旨を記載することが有効です。遺留分は民法で定められた相続分であるため、まったく相続させないことはできません。
離婚した元配偶者との子どもにも相続させなければなりませんか?
離婚した元配偶者との子どもとの親子関係は解消されないため、子どもに相続する権利があります。法定相続人として認められるため、遺留分を侵害することはできません。
ただし、離婚した元配偶者に相続する権利はありません。
相続税を軽くしたい場合の対策方法はありますか?
相続税を軽くしたい場合、連れ子との養子縁組を検討しましょう。相続税は、法定相続人が多いほど基礎控除額が高くなって相続税の負担が軽減されるからです。
相続税の基礎控除額は、以下のように計算します。
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
つまり、法定相続人が1人増えるごとに600万円の基礎控除額が増えます。連れ子に遺産を譲りたいと考えているのであれば、法定相続人にさせるために養子縁組をしたほうが遺族の負担も軽減されます。
ただし、法定相続人の数にカウントできる養子の数は、原則として被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までと定められているため注意しましょう。
連れ子に相続させる方法は家庭の状況に合わせて選ぼう
連れ子であっても実子同然に可愛がっている子どもに、自分の財産を少しでも譲りたいと思うことは自然な親心です。連れ子に相続させたい場合、養子縁組や生前贈与、遺言書による遺贈などのさまざまな方法があります。
しかし、安易に養子縁組をするとあとあと後悔したり、生前贈与や遺言書の内容によっては相続人とトラブルに発展したりする可能性も否定できません。そのため、司法書士や弁護士などの専門家に相談し、家庭状況や遺産状況を踏まえたアドバイスをもらいましょう。
できる限りのリスクを軽減するためにできる対策をしっかり教えてもらえます。無料相談を受け付けている専門家事務所も多数あるため、気軽にお問い合わせくださいね。
地元の専門家をさがす