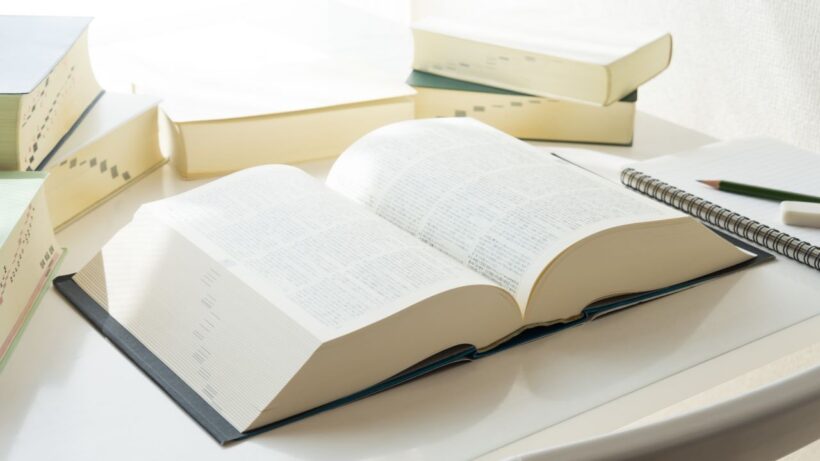「相続人でない人に遺産をとられた」「相続人の自分をのけ者にして他の相続人だけで遺産を分割している」そんな時に主張できるのが、相続回復請求権です。相続回復請求権を主張することで、本来の遺産を取り戻せる可能性があります。この記事では、相続回復請求権が何なのか、その要件や時効・行使方法について詳しく解説します。
地元の専門家をさがす
相続回復請求権とは?
相続回復請求権とは、自身の相続権が侵害されている際に、侵害を排除して相続財産を回復する権利のことです。
次のようなケースでの行使が、相続権回復請求に該当します。
- 相続人ではない人が「自分が相続した」と称して相続人の権利を侵害している
- 他の相続人が自身の相続分以上の遺産を占有している
相続人でない人が相続を称するとは、たとえば、相続欠格事由に該当した相続人や相続廃除された相続人が、相続財産を勝手に管理しているケースです。なお、相続権を侵害された本来の相続人を「真正な相続人」、行使する相手方(侵害している人)を「表見相続人」と呼びます。
また、相続人が相続する場合でも、その人の相続分を超えて他の相続人の権利を侵害しているなら、侵害された相続人は相続回復請求権を行使できます。たとえば、相続人である子ども2人のうち1人が勝手にすべての遺産を管理している場合や、相続人の自分が知らないところで他の相続人が遺産分割を進めているようなケースです。
このように、相続人でない人や相続分を超えている相続人に対して、自分の権利を回復するために行使するのが相続回復請求権となります。
遺留分侵害額請求権との違い
遺留分侵害額請求権とは、他の相続人の相続分が、自分の遺留分を侵害している場合に請求できる権利です。
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して、最低限保証された遺産取得分のことをいいます。遺言や遺贈などで偏った相続になった場合、遺留分を持つ相続人は侵害された遺留分の請求が可能です。たとえば、遺留分が500万円のときに自身が300万円しか相続できなかった場合、侵害された200万円を侵害した相続人に請求できます。
侵害された権利を回復する救済措置という点では、相続回復請求権も遺留分侵害額請求も同じです。しかし、両者は以下のような点が異なります。
| 行使できるとき | 行使した場合 | |
|---|---|---|
| 相続回復請求権 | 相続人でない人による相続権の侵害のとき | 相続財産の返還 |
| 遺留分侵害額請求 | 他の相続人への遺贈・贈与で遺留分が侵害されたとき | 遺留分に相当する金銭での清算 |
相続回復請求権は、相続人でない人が自身の相続権を侵害した際に請求できる権利です。権利を行使することで、侵害された相続財産自体の返還を請求できます。
一方、遺留分侵害額請求は、他の相続人に対する遺贈などによって遺留分が侵害されたときに請求できる権利です。この場合、侵害があっても他の相続人に対する相続や遺贈自体は有効です。また、権利を請求した場合でも財産自体の返還ではなく、相当する額の金銭での清算となります。
仮に、侵害された相続財産が土地である場合、相続回復請求なら土地を返還をしてもらえるのに対し、遺留分侵害額請求では土地は返還されず、土地の価値分の金銭が支払われるのです。
相続回復請求権を行使するための要件
相続回復請求権を行使するためには、「請求者」「相手方」「時効」の3つの要件を満たさなければなりません。
具体的には以下の通りです。
- 請求人が真正の相続人である
- 相続権を侵害しているのが表見相続人や共同相続人
- 相続回復請求権の時効が成立していない
それぞれ詳しくみていきましょう。
①請求人が真正の相続人である
真正の相続人とは、相続権を有している相続人のことです。配偶者や子どもといった法定相続分を持っている親族や、遺言書で指定された相続人が該当します。
また、以下のような人も相続回復請求の行使が認められています。
- 真正な相続人から相続した人
- 相続分の譲受人
- 包括受遺者
- 相続財産清算人
- 遺言執行者
なお、相続人との売買取引などで相続財産の譲渡を受けた「特定継承人」は、相続回復請求権が認められないので注意しましょう。
②相続権を侵害しているのが表見相続人や共同相続人
相続回復請求権を行使できるのは、自己の相続権を侵害されている場合です。また、請求する相手方(侵害している人)は、「表見相続人」と「共同相続人」のいずれかになります。
表見相続人
表見相続人とは、表向きは相続人に見えるような人ですが実際には相続人ではなく、かつ相続財産を占有している人です。具体的には、以下のような人が相続権を主張したり、相続財産を勝手に占有している場合が該当します。
- 相続欠格事由に該当して相続権を失った人
- 相続廃除された人
- 偽りので出生届・認知届を出された人(本当は被相続人の子ではない)
- 無効の婚姻で配偶者となった人
- 無効の養子縁組で養子となった人
なお、最高裁の判例では表見相続人にあたるかどうかについて、以下のような判例があります。
自ら相続人でないことを知りながら相続人であると称し、又はその者に相続権があると信ぜられるべき合理的自由があるわけでもないにもかかわらず相続人であると称し相続財産を占有管理することによりこれを侵害しているものは、本来、相続回復請求制度が対象として考えている者にはあたらない※引用:最高裁判判例 昭和53年12月20日|裁判所
つまり、そもそも自分に相続権がないことを知っている人は、表見相続人には当たらないということになります。相続権がないことを知っていながら遺産を占有する人は、不法占有者として所有権に基づく返還請求を行うことになります。
また、表見相続人から財産を譲渡された人は相続回復請求権の対象とはならない点も注意しましょう。
共同相続人
共同相続人とは、相続開始後で遺産が共有状態の時に一緒に相続している人のことを言います。遺言書のない相続の場合、遺産をどのように分割するかは遺産分割協議で決めます。遺産分割協議が決まるまでは、いったん遺産は相続人全員の共有状態となり、その場合相続人を共同相続人と呼ぶのです。
遺産分割が行われていない状態で、他の相続人を無視して遺産を自分のものにしている場合は相続回復請求権を行使できます。また、以下のようなケースも該当します。
- 特定の相続人を除いた相続人だけで遺産分割協議を行う
- 特定の相続人に本当の遺産額を伝えずに遺産分割協議を行い、本来得られる相続分を侵害している
このように本来の相続人であっても、他の相続人の相続権を侵害しているケースでは相続回復請求権の対象となるのです。
③相続回復請求権の時効が成立していない
相続回復請求権には、以下のように時効が定められています。
- 相続権を侵害された事実を知った時から5年
- 相続開始から20年
5年または、20年が経過すると相続回復請求権を行使できなくなるので注意しましょう。
時効については、以下で詳しく解説します。
相続回復請求権の時効について・時効を止める方法

相続回復請求権は、いつでも行使できるわけではありません。時効を超えてしまうと行使できなくなるので、時効について詳しく押さえておくことが重要です。
相続回復請求権には消滅時効がある(5年・20年)
民法では、相続回復請求権を以下のように規定しています。
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。※引用:民法|第884条(相続回復請求権)
侵害されたことを知った時から5年を経過すると、権利を行使できなくなります。さらに、侵害されたことを知らない場合でも相続開始から20年を経過すると行使できません。
消滅時効を援用できるのは善意・無過失の表見相続人のみ
時効が適用されるのは、侵害する相手が「善意・無過失」である場合のみです。
善意・無過失とは、まったく落ち度がなく事実を知らなかったという意味となり、侵害する相手が善意・無過失というのは、自分が相続人である、または相続分が正しいと信じるに足る合理的な理由があり占有がそれに基づいているということになります。
つまり、自分が相続人でないことを知っている、他の相続人の持分を侵害していると認識しているといったケースは、善意・無過失に該当しないのです。
そのため、他の相続人がいることを知りながら遺産を独り占めしているようなケースは、5年・20年の時効は適用されず、それ以上経過している場合でも遺産を取り戻せる可能性があります。
ただし、相手方が善意・無過失であると、相続回復請求権の時効だけでなく取得時効を援用されて遺産が相手の物になるケースもあります。
取得時効とは、善意無過失で所有の意志を持って10年専有した場合、相手が所有権を取得できるという制度です。
相続人でない人に遺言で相続させたケースで、10年後に遺言書が見つかった場合、最高裁では以下のような判例が出ています。
相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができる。※引用:最高裁判所判例集 令和6年3月19日|裁判所
このケースでは、被相続人の唯一の相続人である子のAさんが不動産を所有し10年経過した時点で、本来相続人ではない甥のBさんに相続させるという旨の遺言書が見つかっています。遺言書が見つかってから(侵害があったことを知ってから)5年以内にBさんは相続回復請求権で不動産の返還を請求しています。しかし、この判例では所有時効でAさんが不動産を所有することを認め、Bさんは相続回復請求権での不動産の取得ができなかったのです。
稀なケースではありますが、時効前に相続回復請求権を行使しても必ずしも遺産が取り戻せるわけではないことは覚えておきましょう。相続回復請求権の行使を検討している場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
地元の専門家をさがす
時効を止める方法
以下のような手続きが行われると時効がとまります。
- 訴訟や調停手続き
- 権利行使の意思表示
相続権の侵害を知ってから5年以内に訴訟などを起こすことで、時効が一時的にとまる「完成猶予」となります。その後、判決が出ると時効はリセット(時効の更新)され10年延長となるのです。また、訴訟の相手方が返還を認めた場合は、時効がリセットされて5年延長となります。
相続回復請求権を行使する方法
相続回復請求権は、以下のような方法で行使できます。
- 相手方との話し合い
- 訴訟
まずは、相手方との話し合いで返還を請求します。時効を止める方法でも解説したように、権利行使を意思表示することでも時効をとめることが可能です。しかし、口頭での主張は言った・言わないに発展するため、内容証明郵便で請求することをおすすめします。話し合いで解決できた場合、内容を公正証書で作成しておくことも大切です。
話し合いで解決できない場合は、法的な手続きに進むことになります。訴訟を起こす場合、相手方の住所の管轄の裁判所で手続きする点には注意しましょう。
訴訟により相続回復請求権が認められれば、裁判所から遺産の返還命令がでて遺産を取り戻すことができます。なお、相手が返還に応じない場合でも強制執行による返還が可能です。
ただし、遺産分割調停や審判では、相続回復請求の行使や時効の停止ができない点は注意しましょう。遺産分割協議中や調停・審判中であっても、相続回復請求権は別途訴訟しなければなりません。
権利の行使を検討している場合は、早い段階で弁護士に相談して訴訟の手続きを進めるようにしましょう。
相続回復請求権の相談は弁護士に
表見相続人や共同相続人に自分の相続権が侵害されている場合、相続回復請求権を行使することで侵害された遺産を取り戻せる可能性があります。
しかし、相続回復請求権は相手方などの要件が限定的で時効もあるので、自身で行使するのは難しくトラブルになる恐れもあります。相続回復請求権の行使を検討しているなら、弁護士に相談することが大切です。弁護士であれば、相続回復請求権の手続きがスムーズに行えるだけでなく、他の最適な解決方法の選択肢を提案してもらうことも可能です。
自分の相続権が侵害されているなら、まずはどのような方法で取り戻せるか弁護士に相談してみることから始めるとよいでしょう。
地元の専門家をさがす