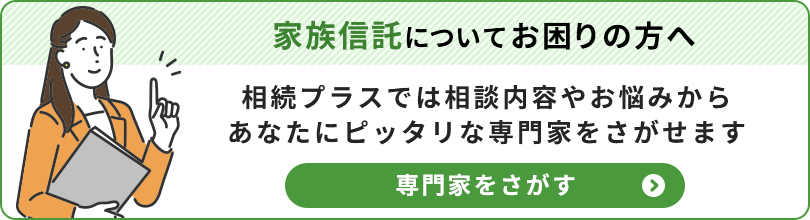「家族信託の契約書は公正証書で作らないといけないのか」と疑問に思われていませんか。結論からいうと、公正証書を作成しなくても契約は成立しますが、公正証書で作成することをおすすめします。本記事では、家族信託契約書を公正証書で作成すべき理由やメリット・デメリットを解説します。作成方法や費用、注意点についても解説しているため、これから家族信託をする方はぜひ参考にしてください。
目次開く
家族信託の契約書を作成する2つの方法
認知症を発症したときの備えとして注目されている家族信託の契約書は、公正証書で作成することが推奨されています。
そもそも、家族信託とは、財産の所有者が委託者となって信頼できる家族などの受託者に財産管理を任せる制度です。家族信託をするには信託契約書を作成し、契約書に記載された内容に従って財産管理をしてもらいます。
家族信託のポイントは、下記の通りです。
- 委託者が受託者に財産の管理を委託する
- 受託者は委託者や指定された者(受益者)のために財産を管理・運用する
- 受益者は財産から生じた利益を受け取る
家族信託は、主に認知症発症後の財産凍結や管理・処分のしづらさを解消することを目的として契約が交わされます。家族信託を契約しておくと、委託者が認知症を発症しても受託者によって適切な財産管理をしてもらえます。
ただし、家族信託は、委託者に意思能力があるうちに契約を交わさなければなりません。なぜなら、委託者の意思通りの財産管理・運用を約束するための契約だからです。
また、より法的効力を高めるために、私文書ではなく公正証書で契約書を作成することを推奨します。公正証書は公証人が作成する公的な文書であるため、法的効力が強まって契約内容を第三者に証明しやすくなるからです。
ここでは、家族信託の契約書を作成する2つの方法について解説します。
- 公正証書で作成する方法
- 私文書で作成する方法
具体的に確認し、2つの違いを理解しましょう。
公正証書で作成する方法
公正証書で契約書を作成する場合、公証人と契約内容についての面談を行って公証人が契約書を作成します。専門家のチェックを受けることが可能なため、内容の信頼性が高いと考えられます。
作成した公正証書の原本は公証役場に保管されるため、紛失や偽造のリスクが低いです。万が一、自宅などで保管していた契約書を紛失したとしても再発行できます。
また、公証人が面談を行ったうえで作成するため、本人の意思による契約であることを証明しやすいことも特徴です。
私文書で作成する方法
私文書で契約書を作成する場合、自宅のパソコンなどを使って契約書を作成し、委託者・受託者が署名・押印するだけで契約できます。
公証役場での認証は不要で手軽に作成できるものの、法的効力が弱いことがデメリットです。親族や第三者から無効であると主張されたときに訴訟に発展したり、訴訟の結果無効となることも考えられます。また、自宅に保管する場合、紛失や改ざんのリスクがあります。
たしかに私文書で家族信託の契約書を作成することはかかる時間や費用をカットできるものの、法的保証や管理方法に課題が残ることを認識しなければなりません。

なぜ家族信託契約書は公正証書が推奨されるのか?
家族信託契約書を私文書で作成したとしても、問題はありません。家族関係や預ける財産の内容によって、公正証書か私文書かの選択肢が変わってくるでしょう。
ここでは、家族信託契約書を公正証書で作成することが推奨される理由をより理解するために下記のポイントについて順番に解説します。
- 公正証書作成が推奨される具体的なケース
- 公正証書のメリット
- 公正証書のデメリット
詳しく見ていきましょう。
公正証書作成が推奨される具体的なケース
公正証書作成が推奨される具体的なケースは、主に3つあります。
- 家族・親族から訴訟されるなどトラブルの可能性があるケース
- 金融機関での取引に公正証書の提示が必要なケース
- 委託者の判断能力の低下が見られるケース
順番に確認しましょう。
家族・親族から訴訟されるなどトラブルの可能性があるケース
家族や親族などとの関係性が悪く、当事者だけで契約を交わしたことに納得してもらえない可能性があるのであれば、公正証書で契約書を作成することをおすすめします。
なぜなら、第三者が不在の状態で契約書を作成して署名・押印した場合、本当に委託者本人の意思が反映されているのか疑問を持たれる可能性があるからです。
公正証書で契約書を作成する場合、第三者である公証人が委託者・受託者の双方の意思確認を行うため、トラブル回避につながるでしょう。
金融機関での取引に公正証書の提示が必要なケース
信託する内容に金融機関が関わる場合、公正証書による契約書の提示を求められるケースが多いです。たとえば、下記のケースにおいて公正証書の契約書の提出を求められる可能性が高いです。
- 銀行・証券会社で信託口口座を開設するとき
- 銀行で信託内借入を受けるとき
預金を信託する場合、受託者の個人財産と信託財産を明確に分けて管理するために金融機関で信託口口座を開設する必要があります。その際、公正証書で作成された信託契約書を求められる場合があります。
また、信託内借入とは、家族信託に関連した借入のことです。賃貸アパートの経営などのために金融機関から融資を受けたい場合に活用できます。信託内借入を受ける際にも、公正証書で作成された信託契約書を求められるケースが多いです。
委託者の判断能力の低下が見られるケース
委託者が高齢で判断能力の低下が感じられる場合は、公正証書で信託契約書を交わすことをおすすめします。
重度の認知症と診断されてしまうと、法律行為は行えなくなり、預金の入出金もできなくなります。重症化すると、本人の意思ではないと判断される信託契約も交わせません。
公正証書で契約書を作成する場合、公証人は契約内容を当事者に説明し、内容を理解していると判断したうえで契約書を作成します。たとえ委託者に認知症などがあったとしても、意思能力が十分であると判断されれば効力のある信託契約を交わせます。

公正証書のメリット
公正証書で信託契約書を作成するメリットは、下記の通りです。
- 公証人による意思確認のうえ作成するため、法的効力が高くて無効になるリスクが低い
- 金融機関や不動産登記などでの手続きがスムーズに進められる
- 公証役場に原本が保管されるため、紛失・盗難・改ざんのリスクがない
将来に備えるために、公正証書で契約書を作成することをおすすめします。
公正証書のデメリット
公正証書で信託契約書を作成するメリットは大きいものの、デメリットもあるため理解しておきましょう。
- 作成のために費用や手間、時間がかかる
- ひな型どおりの契約内容になってしまう可能性がある
公正証書で作成する場合、当事者の細かな要望が契約内容に反映されない可能性があります。なぜなら、公証人が内容を聞き取って契約書を作成するため、一般的な書式で作成される傾向にあるためです。
このように、費用面・時間面や内容が制約される面においてデメリットがあります。メリットとデメリットを比較し、資産状況や家族関係などを踏まえたうえで公正証書と私文書のどちらで契約書を作成すべきかを検討しましょう。
判断に迷う場合は、家族信託に詳しい専門家からアドバイスを受けることをおすすめします。
家族信託契約書を公正証書で作成する手順

家族信託契約書を公正証書で作成するときの手順は、下記の通りです。
- 事前準備(信託内容の決定)
- 公証役場での手続き
- 公正証書の作成・署名
3つのステップごとに詳しく確認しましょう。
①事前準備(信託内容の決定)
まずは、事前準備からスタートしましょう。
家族や資産の状況、何を心配しているのかを専門家に相談し、家族信託の目的を定めます。専門家に相談せずに信託内容を決めることも可能ですが、できるだけ無料相談などを活用してアドバイスをもらうことをおすすめします。
家族信託の目的はケースバイケースですが、多くの場合は下記のいずれかに当てはまるでしょう。
- 認知症対策をしたい
- 高齢になったときの財産管理や資産運用を家族に任せたい
- 所有している不動産管理を任せたい
目的が定まれば、目的に従ってどの財産を信託するのかを決定していきます。信託財産には、預貯金や不動産、株式などが挙げられます。
また、下記のような内容も決めていかなければなりません。
- 受託者・受益者
- 信託期間や制限
- 信託修了後の財産の継承先(残余財産受取人)
委託者を受益者とするケースが一般的です。第三者を受益者とする場合、贈与税の課税対象となる場合があるため注意しましょう。
受託者には、信託財産を管理する権限が与えられます。そのため、何をどこまで任せるのかは慎重に判断しましょう。
さらに、ほかの家族への説明や配慮をすることで、あとのトラブルに備えられます。
②公証役場での手続き
信託内容が決定したら、公証役場での手続きに移ります。
いきなり公証役場へ行っても対応してもらえないため、公証人との打ち合わせ日時を事前予約しましょう。最寄りの公証役場へ電話をかけると予約できます。
打ち合わせ日時までに、下記のような必要書類を揃えておきましょう。
- 信託契約書案
- 本人確認書類
- 不動産登記事項証明書(不動産を信託する場合)
予約した公証人との打ち合わせ日時に公証役場へ出向き、内容確認と修正を行います。打ち合わせの日までに、信託内容を書き出しておくとスムーズに公証人に伝わるでしょう。
また、このときに公正証書の作成に必要な書類や費用についても確認しておくと安心です。
③公正証書の作成・署名
準備が整ったら公証役場で契約書を作成しましょう。当日は、公証人が本人確認を行い、契約内容の読み上げをします。当事者が契約内容を理解していることを確認できれば、契約当事者が署名・押印を行います。
必要書類の提出と作成費用の支払いができたら公証人の認証を受け、正式に公正証書として成立し手続きは完了です。
作成された契約書の原本は公証役場で保管され、副本を関係者が各自保管することになります。
なお、専門家に依頼して公正証書の契約書を作成する場合、公証役場への連絡や公証人の打ち合わせは専門家に任せられます。ただし、公正証書を作成する当日は、原則当事者本人も公証役場に出向く必要があるため注意しましょう。
家族信託契約書の公正証書作成にかかる費用
家族信託契約書の公正証書作成にかかる費用は、大きく下記の2つに分類できます。
- 公証人手数料
- 専門家ヘの依頼費用
具体的な金額も見ていきましょう。
公証人手数料
公正証書を作成する場合、信託財産の価格に応じた手数料を公証人へ支払う必要があります。
財産額に応じた公証役場の手数料を下記の表にまとめました。
| 信託財産の価格 | 公証人手数料の額 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円超え500万円以下 | 1万1000円 |
| 500万円超え1000万円以下 | 1万7000円 |
| 1000万円超え3000万円以下 | 2万3000円 |
| 3000万円超え5000万円以下 | 2万9000円 |
| 5000万円超え1億円以下 | 4万3000円 |
| 1億円超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
| 3億円超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
| 10億円超え | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
また、契約書の正本・謄本の交付に1通あたり250円、必要書類の取得に数千円程度の費用がかかります。
専門家ヘの依頼費用
家族信託の設計を専門家に依頼する場合、相場は10〜30万円程度です。目安として、信託財産の1%前後の費用が発生すると考えておきましょう。
家族信託は法律行為であるため、司法書士や弁護士へ依頼することが一般的です。
専門家へ依頼すると費用がかかりますが、下記のようなメリットがあります。
- 契約内容のアドバイスをしてもらえる
- 書類作成のサポートが受けられる
- 必要書類の取得を一任できる
- 公証役場とのやり取りを任せられる
一方、手続きが専門家主導になり、柔軟な対応がしづらくなる点はデメリットといえるでしょう。
デメリットはあるものの、家族信託の設計は専門家と一緒に行うことをおすすめします。なぜなら、家族信託は平成28年頃から普及し始めた比較的新しい制度であり、過去の事例が少ないからです。
家族信託で任せたいことを実現させるためにも、家族信託の経験が豊富な専門家へ相談することを推奨します。
家族信託契約書を公正証書で作成する際の注意点
家族信託契約書を公正証書で作成する際に知っておきたい注意点を4つご紹介します。
- 原則として本人が公証役場に出向いて作成する必要がある
- 公正証書作成時に利害関係者は立ち会えない
- 必要書類の不備に注意する
- 受託者の選定が重要
公正証書で契約書を作成する前にしっかり確認しておきましょう。
原則として本人が公証役場に出向いて作成する必要がある
原則、契約をする当事者本人が公証役場へ出向いて契約書を作成する必要があります。専門家に依頼していたとしても、代理で作成する場に出向いてもらうことはできません。
ただし、本人が高齢者や身体障がい者などの理由で公証役場へ行けない場合は、公証人の出張で対応してもらうことが可能です。出張費が別途かかりますが、どうしても難しい場合には検討しましょう。
出張を依頼する場合、管轄によって出張できる範囲が異なるため、公証役場の管轄を事前にチェックしておく必要があります。公証役場の管轄については、日本公証人連合会から確認が可能です。
事前に確認し、スムーズに手続きを進めましょう。
公正証書作成時に利害関係者は立ち会えない
公正証書作成の現場には、利害関係者が立ち会うことはできません。
利害関係者が公正証書作成に立ち会うことで契約当事者が圧迫を感じ、本意とは異なる内容を契約してしまう恐れがあるからです。また後日、立ち会いをした利害関係者が自分に有利な契約内容に変更するよう迫ったり、信託財産以外の財産についての贈与を要求するケースも考えられます。
このような理由から、公正証書作成は公証人と本人のみで行います。
必要書類の不備に注意する
公証役場に提出しなければならない書類の不備に注意しましょう。
家族信託の契約書を公正証書で作成する場合に必要な書類は、下記の通りです。
- 本人確認書類
- 実印と印鑑登録証明書
- 戸籍謄本・住民票
- 不動産関係書類(不動産登記事項証明書など)
また、不動産登記を伴う信託の場合、登記事項証明書や固定資産税納税通知書、委任状などの追加の書類が必要です。
これらの書類は、原則、公正証書を作成するタイミングに揃えておかなければなりません。必要書類は信託の内容や公証役場ごとに異なる場合があるため、事前に公証役場で確認しておくと安心です。
受託者の選定が重要
家族信託を行う場合、受託者の選定も非常に重要です。受託者には信託財産の管理責任があり、自分のためではなく受益者のために管理・運用しなければなりません。
しかし、残念ながら勝手な判断で不動産を売却したり自分のために預金を使ってしまったりと、財産の管理権限を悪用する受託者がいることも事実です。
金融機関によっては、特定の受託者(法人・個人)を制限する場合があるため、事前に確認しておくことを忘れないようにしましょう。
受託者に信頼できる人を選ぶことはもちろん、信託監督人や受益者代理人を設定しておくこともおすすめです。信託監督人と受益者代理人は、受託者が適切な財産管理・運用をしているか確認してくれるため、トラブル対策に適しています。
また、受託者が辞任・交代する場合のルールも明確にしておくと、財産を放置される心配が軽減されます。安心できるルールを契約内容に盛り込んでおきましょう。
家族信託の契約書は公正証書で作成しよう
家族信託契約書を公正証書で作成すると費用はかかるものの、法的効力や安全性を考えると大きなメリットが得られます。内容によっては相続税や贈与税に影響が出る可能性があるため、信託内容を十分に検討したうえで契約書を作成しましょう。
また、公正証書の手続きは準備に時間がかかります。家族信託を考えているのであれば、早めに準備を始めることをおすすめします。
信託内容や公正証書の手続きに不安がある場合は、司法書士や弁護士へ相談しましょう。相続プラスなら、悩み別・エリア別に相続や生前対策に詳しい専門家を手軽に検索できます。積極的に専門家の力を借りて、将来を守るための家族信託契約書を作成してくださいね。