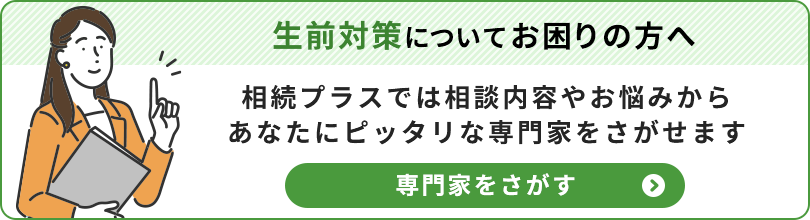相続税対策として「生前贈与が節税につながる」と知っていても、「具体的にどうすればいいのか、そもそも生前贈与はどのような仕組みか」を理解している人は少ないかもしれません。本記事では「生前贈与とは?」という基本だけでなく、節税対策になる生前贈与の方法も徹底的に解説していきます。令和5年度税制改正で贈与税のルールが変更予定です。「変更点を知らなくて節税に失敗した」と後悔しないためにも、生前贈与についてしっかり理解しておきましょう。
目次開く
生前贈与の概要
生前贈与とは何か、どのような課税方法があるのかといった仕組み、生前贈与のメリット・デメリットについて順番に解説します。
生前贈与とは、亡くなる前に財産を無償で渡すこと

「贈与」とは、自分の財産を他人にあげること。「生前贈与」はそうした贈与行為の一種で、個人から個人へ財産を生前に無償で渡す行為を指します。
財産を贈る側が「あげる」、贈られた側が「もらう」と双方が意思表示する、つまり合意することで贈与は成立します。お互いの意思が合致していないと成立しません。
財産をあげる人は「贈与者」、財産をもらう人は「受贈者」と呼ばれます。その行為にかかる税金が「贈与税」であり、受贈者が課税対象者になります。
相続との違いについては課税対象、相手によって以下の通り分けられます。
| 贈与 | 相続 | |
|---|---|---|
| 課税対象 | 贈与された財産のみ | 死亡した人が所有する財産すべて |
| 相手の合意 | あり | なし |
| 受け取る相手 | 自由に選択可能 (法定相続人以外でもOK) | 法定相続人に取得する 権利が発生する |
生前贈与は「いつでも・誰にでも・何回でも」贈与できます。一般的に相続税対策として生前贈与が行われます。生前贈与することで、相続税の対象となる財産を減らし、相続税負担の軽減ができるのです。
生前贈与する際には、贈与税の課税方法について理解しておく必要があります。生前贈与では、贈与税の課税方法を次の2つから選べます。
「暦年課税」と「相続時精算課税制度」とは?
生前贈与における贈与税の課税制度は2種類あります。
1つが、1月1日から12月31日の1年間(暦年)に贈与された財産に対して課税される「暦年(れきねん)課税制度」、もう1つが贈与税・相続税を一体化した課税が行われる「相続時精算課税制度」です。
暦年課税の贈与税の計算方法は次の通りです。
贈与税=(贈与財産-110万円(基礎控除))×税率-控除額
暦年課税は110万円の基礎控除があるため、年額110万円以下の贈与であれば贈与税は課せられません。そのため、毎年110万円以下で贈与者から受贈者に贈与することで課税されずに、相続財産を減らすことが可能です。なお、非課税枠を超えると、課税対象額に比例して税率も上昇する超過累進課税が適用されます。
さらに、「暦年課税制度」は贈与者と受贈者の関係、受贈者の年齢などによって贈与財産が「一般贈与財産」「特例贈与財産」に区分されます。
<特例贈与財産>(特例税率)
- 贈与者:祖父母や父母などの受贈者の直系尊属
- 受贈者:養子を含む子ども、孫、ひ孫などの直系卑属
- 受贈者の年齢:18歳※1以上
<一般贈与財産>(一般税率)
上記の特例贈与財産に該当しないもの
<一例>
- 夫婦間(配偶者同士)・兄弟間など
- 受贈者の年齢が18歳※1未満の子どもや孫など
相続時精算課税制度は、2500万円までの贈与を非課税にできる制度です。2500万円を超えた分については一律で20%の贈与税が課されます。
相続時精算課税制度の贈与税の計算方法は次の通りです。
贈与税額=(贈与額-2500万円(特別控除額))×20%
相続時精算課税制度は、相続発生時(贈与者が亡くなったとき)に生前贈与された財産を、相続財産に足し戻して相続税を算出します。そこから、すでに支払った贈与税額を差し引きます。
相続時精算課税制度では、贈与者と受贈者に条件があります。贈与者は60歳以上の直系尊属(父母または祖父母)、受贈者は贈与者の直系卑属(子ども、孫またはひ孫)で、かつ18歳※1以上。
暦年課税制度と相続時精算課税制度を項目ごとに比較した一覧表は、以下の通りです。
| 暦年課税 | 相続時精算課税制度 | |
|---|---|---|
| 贈与者 (財産をあげる人) | 誰でも可能 | 60歳以上の直系尊属 (父母または祖父母など) |
| 受贈者 (財産をもらう人) | 誰でも可能 | 18歳以上の直系卑属 (子どもや孫など) |
| 非課税枠 | 年間110万円 | 一組につき2500万円 |
| 申告する条件 | 110万円を超えたら | 2500万円以下でも 制度の適用を受けたら |
相続時精算課税制度を選択する際の注意点は、一度こちらの制度を選択すると、その後暦年課税を使えなくなってしまうこと。ただし、一組(贈与者と受贈者)ごとに制度を選択することは可能なため、祖父からの財産は相続時精算課税制度、祖母からは暦年課税とすることはできます。
申告・納税期間については、暦年課税制度・相続時精算課税制度ともに翌年2月1日から3月15日です。暦年課税制度は基礎控除額以下であれば申告する必要はありませんが、相続時精算課税制度は基礎控除額以下でも申告する必要があります。
参照:No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁
※1その年の1月1日時点での年齢。令和4年3月31日以前は20歳。
「贈与税の税率と控除額」についてさらに詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

生前贈与の3つのメリット
生前贈与するメリットは、次のようなことが挙げられます。
- 相続税の軽減効果が期待できる
- 財産を相手に確実に渡せる
- 渡す時期を自由に選べる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
<メリット1:相続税の軽減効果が期待できる>
相続財産が多いと、相続税額が高額になると予想されます。生前贈与では年間110万円が非課税枠なので、それ以下であれば贈与税が課税されません。さらに、課税対象となる相続財産を減らせ、相続人が相続税の負担に苦しむことを回避できるでしょう。
<メリット2:財産を相手に確実に渡せる>
生前贈与は、財産を贈る人(贈与者)が生きている間に贈与する行為なので、自分が選んだ相手(受贈者)に確実に財産を渡せます。相続だと遺言書を遺しても、必ずしも被相続人の指定した通りに遺産が継承されるわけではありません。
法定相続人が遺留分を主張したり、相続人同士で遺産分割協議したりすると、遺言とは異なる財産分与が行われる可能性があります。
生前贈与であれば、自分の希望する相手に希望通りに財産を渡し、受け取ったところまで確認できるというメリットがあります。相続トラブルが予測される場合も、あらかじめ生前贈与しておくことでトラブルを回避することが可能です。
<メリット3:渡す時期を自由に選べる>
生きていればいつでも実行できるため自分の好きなタイミング、もしくは相手が必要としている時期に財産を渡せるのも生前贈与のメリット。孫の入学に合わせて学費を渡したい、子どもの結婚資金に渡したい、マイホームを購入したいといった財産を渡したい相手のライフステージの変化に合わせて贈与者は贈与できます。
こうした人生の節目にあわせて結婚資金などの贈与をしたいのであれば、次の特例を活用すればさらなる節税対策が期待できます。非課税枠とあわせて確認しておきましょう。
- 結婚・子育て資金の一括贈与の特例:300万円まで
- 教育資金の一括贈与の特例:500万円まで
- 住宅取得資金贈与の特例:1000万円まで
相続で財産を渡そうとすると、被相続人が死亡するタイミングを予測できないため、相手にいつ財産を渡せるのかも当然わかりません。生前贈与することで、希望するタイミングで財産を渡せるのは受贈者にとっても大きなメリットとなるでしょう。
参照:No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁/No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁/No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
生前贈与の3つのデメリット
生前贈与にはデメリットもあるため、理解したうえで生前贈与しなければ、想定よりも税金を余計に支払ってしまう可能性があります。
次のようなデメリットがあるので、注意しましょう。
- 贈与税の方が割高になってしまう
- 贈与税以外の税金が発生してしまう
- 死亡前3年以内だと相続税扱いになってしまう
<デメリット1:贈与税の方が割高になってしまう>
贈与税と相続税では、非課税枠・金額区分ごとの税率が異なります。上手に活用しなければ相続税よりも高額な贈与税が課税され、受贈者がその負担に苦しむことになりますので、相続財産の金額がいくらかを把握しておきましょう。
<デメリット2:贈与税以外の税金が発生してしまう>
たとえば、不動産を生前贈与する場合、贈与税を節税できても、贈与税以外の税金が発生しています。不動産の所有権を登記するための「登録免許税」、土地や家屋の購入や贈与などで不動産を取得した際に発生する「不動産取得税」が発生してしまいます。「登録免許税」は相続でも発生しますが、税率が異なります。「登録免許税」は贈与税だと2.0%、相続税だと0.4%です。つまり、納税額に5倍の差が生じるということです。
このように登録免許税・不動産取得税以外にもさまざまな費用が掛かり、不動産価格の1割ほどが諸経費として必要になることも、あらかじめ認識しておきましょう。
<デメリット3:死亡する3年以内だと相続税扱いになってしまう>
受贈者への生前贈与が完了していても、贈与者が死亡して3年以内※2の贈与であれば相続財産の扱いとなります。結果的に、生前贈与した金額分が相続税の課税対象になってしまうため、せっかくの節税対策が台無しになってしまうことも。
ただし、「贈与税の特例」を受けているなどの場合、生前贈与は3年以内であっても原則として相続財産に加算されません。
- 教育資金の一括贈与の特例
- 結婚・子育て資金の一括贈与の特例
- 住宅取得資金などの贈与の特例
- 夫婦間贈与の特例
- 相続人以外への生前贈与
- 相続時精算課税にかかる贈与者からの財産
※2令和5年度の税制改正により、加算期間が3年から「7年」に変更になる予定です。
参照:令和5年度税制改正大綱|自民党
贈与税の節税対策について:相続税との比較・注目すべき最新情報
生前贈与は贈与税に区分されるため、贈与税に関連する法律や、節税効果が高くなる金額などについて解説していきます。
贈与税と相続税の違いとは?
自分の所有する財産を相手に取得させる主な手段は、贈与と相続の2種類。同じ財産価額であっても、贈与と相続のどちらを選ぶかで負担する税金額は変わります。
そのため、贈与税と相続税の税率を比較すると、支払う税金にどのくらい差が生じるのかがわかります。
「相続税と贈与税の税率の違い」について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

生前贈与の節税対策が一番高くなる金額は?
贈与税の特例を適用せず、暦年課税を選択している場合、非課税枠となる基礎控除額は1年間で110万円。贈与財産価額を110万円以下に抑えて生前贈与する方が、相続税対策に有効だと考える人がいるかもしれません。
しかし、場合によっては110万円超の生前贈与をした方が、一番の相続税対策になることもあります。大切なのは、相続税と贈与税の合計金額を最も低く抑えること。110万円を超える生前贈与に対して贈与税を払っても、結果的に支払った納税額が最低になれば問題ないので、そのために最適な贈与税額を見極めましょう。
たとえば、両親から、子ども1人への贈与(特例贈与財産)の場合では、最大510万円が年間贈与額のボーダーライン。
相続税は最低でも10%の税率が発生します。したがって、贈与税で税率から控除額を差し引いたあとの実際に負担する税率が10%未満であれば、お得であるといえるのです。
贈与額が510万円だと、実際に負担する税率は「9.8%」です。計算方法は次の通りです。
- 贈与税額:50万円=(510万円-110万円)×15%-10万円
- 実際に負担する贈与税率:9.8%=50万円÷510万円
ただし、誰から誰に贈与するか、相続する人数や相続させたい財産価額によってボーダーラインは変わります。詳しくは専門家に相談した方がより確実に最適な贈与額を導き出せると思います。
生前贈与の加算期間が3年から7年へ。65年ぶりの税制改正
令和5年度税制改正大綱にて、贈与税・相続税に関するルールの見直し案が発表されました。
被相続人から生前に贈与された財産と、死亡した後に相続した財産を合算する対象期間を3年から7年に延長するという内容です。
要するに、こちらの目的は「早い段階で高齢世代から若年層への財産移転を図る」ということ。いずれにしても、生前贈与を活用した相続税対策に大幅な制限が掛けられる見通しです。相続税・贈与税をめぐるルールがどのように変化するのか確認したうえで、生前贈与を行う必要があります。
生前贈与以外の相続税の節税対策
生前贈与は相続財産を減らす一般的な方法として知られていますが、生前贈与以外にも相続財産を減らす方法があります。
不動産・住居に関する特例やさまざまな控除などが、あなたの相続税対策の心強い味方になってくれるかもしれません。
「さまざまな相続税対策」について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

生前贈与に生命保険を上手に活用する方法
生命保険を活用して生前贈与すれば、将来の相続財産を減らせるので相続税節税につながります。どのような方法で生命保険を生前贈与として活用するのか、生命保険を活用するメリット・デメリット、注意点について解説していきます。
生前贈与に適した生命保険に加入
まずは、生前贈与に適した生命保険の種類と加入プランを確認しましょう。生命保険の対象となる被保険者が死亡したら死亡保険金が支払われますが、解約や満期などで被保険者が生存し、一定の条件を満たしても保険金を受け取れます。
被保険者が生存していても受け取れる保険金は「満期保険金・解約返戻金・生存給付金」などで、これらが生前贈与の対象となる贈与財産です。次に挙げる保険が生前贈与に適しています。
- 終身保険
- 養老保険
- 長期平準定期保険
次に、生命保険を活用して生前贈与を行う場合は、契約形態、つまり「保険契約者(保険料負担者)・被保険者・保険金受取人」の関係に注意する必要があります。
とくに注意したいのが「誰が保険料を支払い、誰が受け取るか」について。組み合わせを間違えてしまうと、課税される税金の区分が変わり生前贈与は成立しません。
被保険者が生存している状態で、満期保険金などを受け取る際に課せられる税金が、契約者と受取人の関係でどのように変わるのかを確認してみましょう。
| 契約者 (保険料の負担者) | 受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|
| 母親 | 子ども | 贈与税 |
| 母親 | 母親 | 所得税 |
生前贈与として成立させるためには、「贈与税」に区分されるように各人の契約形態を組みます。生前贈与は自分から他人に財産を贈与する行為ですので、契約者と受取人が異なるように組み合わせます。贈与者を契約者に、受取人を受贈者にそれぞれ設定しましょう。契約者と受取人が同じだと所得税に区分され、贈与行為になりません。
満期保険金から暦年課税の基礎控除額110万円を差し引き、契約者と受取人(贈与者と受贈者)の関係に応じて、一般贈与財産もしくは特別贈与財産に区分し、贈与税を算出します。
参照:No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき|国税庁
生命保険を生前贈与に活用するメリット
生命保険を生前贈与に活用する4つのメリットを解説します。
- 相続税などへの節税対策になること
- 計画的な贈与とみなされるリスクが低いこと
- 運用益を受け取れる可能性があること
- 相続放棄をしても保険金は受け取れること
1つ目が、相続税などへの節税対策になること。生前贈与すれば、相続税の課税対象となる財産を減らすことにつながります。また、生命保険で支払っている保険料は、年末調整や確定申告で「生命保険控除」の対象であるため、所得税や住民税の節税にも役立ちます。
2つ目が、計画的な贈与とみなされる可能性が低いこと。生前贈与は、計画性があると税務署に判断された場合、「定期贈与」に分類されて1年間の贈与額が基礎控除額110万円以下でも課税対象になってしまうことがあります。
しかし、生命保険金は受贈者と贈与者の間に保険会社が入ります。さらに、定期贈与とみなされない理由は次の通りです。
・生存給付金受取人は、生存給付金の支払事由が発生するまでは生存給付金を受取る権利がない。(契約者の判断で生存給付金の受取人を変更できます。)
・契約者(被保険者)が死亡した場合、契約は消滅し、死亡保険金受取人に死亡保険金が支払われる。
こうした理由から定期贈与とみなされず、贈与税の課税対象になるリスクは低いといえます。
3つ目が、運用益が期待できること。生命保険は、銀行への預貯金よりも高い利回りが期待できます。契約者から集めた保険料を株式などの資産運用に充て、利益が出ると毎年の配当として支払われたり、解約返戻金や満期保険金に上乗せされたりすることがあるからです。このように支払った金額以上の返戻金を期待できるのが、生命保険を生前贈与として活用するメリットだといえます。
4つ目が、相続放棄をしても保険金は受け取れること。死亡時に相続財産を放棄しても、生命保険金は、そのまま受け取れます。このメリットが活用できるケースは、被相続人が多額の借金を抱える経営者であるとき。相続人に借金までも相続させたくない場合は、相続人が相続放棄をすれば借金を相続せずに済み、生命保険金だけをそのまま受け取れます。
生命保険を生前贈与に活用するデメリット
生命保険を生前贈与に活用する3つのデメリットを解説します。
- 長期加入が必須になること
- 元本割れのリスクがあること
- インフレによる貨幣価値が低下すること
1つ目が、長期加入が必須であること。生命保険は満期まで年数がかかることが多いです。そのため、生前贈与のために生命保険を活用しようと計画しても、受け取るまでに不測の事態が起きてしまうと、必ずしも計画通りにはならない恐れがあります。
2つ目が、元本割れのリスクがあること。短い加入期間で、生命保険を解約すると元本割れする可能性が高いです。急にお金が必要になったなどの事情で解約せざるを得ない場合は、元本割れのリスクがあることも覚えておきましょう。
3つ目が、インフレにより貨幣価値が低下すること。生命保険は満期まで長期間加入する必要があります。満期時までに物価が上昇してしまうと、加入時に想定されていた保険金の貨幣価値が低下してしまいます。生命保険のデメリットとして、インフレリスクがあることを認識しておきましょう。
生命保険を生前贈与に活用する際の注意点
生命保険を生前贈与に活用する際の注意点を解説します。
生命保険による生前贈与が、税務署に定期贈与ではないと判断してもらうことが大切です。次の2つが挙げられます。
- 贈与契約書を作成しておくこと
- 受贈者がお金の管理すること
1つ目が、贈与契約書を作成しておくこと。暦年課税が適用されるために、「いつ誰に、いくら贈与したか」を証拠として残しておく必要があります。「贈与契約書」は、贈与者と受贈者の間で「毎年の贈与ではなく、1回限りの贈与として交わされた契約」であると立証するための有効な手段になります。
生前贈与したという証拠として、贈与契約書は大変有効です。毎年贈与をする度に、日時・贈与額・贈与者・受贈者などに関する必要事項が記載された贈与契約書を作成し、証拠として保管しておきましょう。
「100万円を10年間に分けて、総額1000万円贈与する」といった計画性のある贈与は税務署に「定期贈与」とみなされる可能性があります。そうすると総額1000万円に贈与税が発生してしまうので、毎年贈与契約書を作成し定期贈与ではないことを証明しておくことで安心につながります。
2つ目が、受贈者が自分でお金の管理をすること。生命保険金の贈与後に、受贈者が自由に使用できる状態であるかどうかもポイントです。受贈者名義の口座に贈与者が加入していた生命保険金などが振り込まれていれば、贈与の証拠にもなります。
生前贈与した方がお得になる5つのパターン
「相続」ではなく「生前贈与」に向いている人は、どのような場合が当てはまるのでしょうか?
向いているかのどうかの判断材料となるのは、「財産をあげる人(贈与者)、財産をもらう人(受遺者)、所有している財産」です。それぞれの状態を把握して、生前贈与が適しているのかを確認していきましょう。
パターン1:所有財産が相続税の基礎控除額よりも多い
相続税には非課税枠となる基礎控除額があります。相続税の基礎控除額に収まらない財産がある場合、贈与税の非課税枠を活用した「生前贈与」が有効です。財産をあらかじめ渡して、所有財産を減らしておくことで節税対策につながります。
「相続税の基礎控除」について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
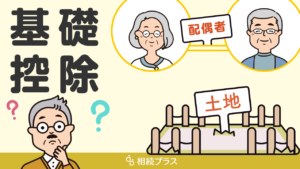
パターン2:値上がりが期待される不動産を所有している
相続発生時の不動産評価額が、贈与時よりも上昇していれば、生前贈与をした方が節税対策につながる可能性があります。
ただし、「相続」ではなく「贈与」で不動産を取得すると、贈与税に加えて不動産取得税、さらに相続税よりも高い登録免許税が発生してしまいます。贈与と相続で発生する税金をいくらなのか把握し、両者を比較した上で、所有している不動産を生前贈与すべきかを考えるべきでしょう。
パターン3:安定した家賃収入を得ている
安定した家賃収入のあるアパートなどの不動産を所有している場合、相続よりも「生前贈与」した方が節税につながります。
アパートなどの不動産から得られる収益は財産として蓄積され、将来相続税の課税対象になります。所有する財産を自分が渡したい相手(受贈者)に生前贈与をしておけば、贈与した後に発生する収益は受贈者の財産となるので、原則相続税に関係しません。
パターン4:贈与者の年齢が若い
財産をあげる人(贈与者)がまだ若い場合は、暦年贈与で多くの年月を掛けて贈与ができるため、生前贈与が向いています。
暦年贈与の基礎控除(非課税枠)は1年間で110万円。非課税額が大きくないため、多額の財産を贈与するには長い年月がかかります。さらに、贈与者が途中で死亡してしまった場合、死亡した3年以内の贈与財産は相続税の対象となってしまいます。
したがって、高齢の贈与者よりも若い人の方が「生前贈与」のメリットがより得られるといえます。若くて健康的な贈与者の方が、長期的な暦年贈与が可能であるため、暦年贈与の非課税枠を最大限活用できる可能性が高いです。
パターン5:受贈者が複数いる
財産をあげる人(贈与者)は贈与税の対象外であるため、贈与をもらう人(受贈者)が複数いれば、非課税枠は1年間の基礎控除額110万円に受贈者の人数を掛けた分の金額です。仮に子ども4人に贈与するとしたら、1年間に贈与できる非課税枠額は最大440万円となるため、自分の所有する財産を一気に減らすことが期待できます。
このように贈与税の非課税枠を最大限活用する方法は、贈与する年数だけでなく財産を受け取る人数にも影響されます。財産をもらう人が複数いる場合、非課税枠を広げるために有効的な手段といえるでしょう。
生前贈与と認められない注意が必要な5つのケース
節税効果を生み、財産所有者の意思も反映しやすいメリットを持つ生前贈与。しかし、場合によっては税務署に「生前贈与」を認められない可能性があります。ときには、追徴課税などのペナルティが発生したり、相続税の対象とされたりしてしまうことも。
生前贈与する際に確認しておきたい5つの注意点をご紹介します。
ケース1:名義預金とみなされる
名義預金とは、「実際にお金を所有・管理する人とは異なる人の名義が使用されている預金口座」です。相続や贈与のケースでは、「名義こそ死亡した人(被相続人)の子どもや孫であるが、実際は被相続人の所有する口座」を指します。名義預金は被相続人の相続財産に含まれるため、相続税の課税対象です。
子どもの名義の銀行口座を作り、子どものためにお金を積み立てたとしても、税務署に「名義預金」とみなされると「生前贈与」が成立しません。
生前贈与と認めてもらうためには、子どもや孫が自分名義の預金口座の通帳や印鑑を管理し、いつでも自由に使える状態にしておくなどが有効です。
ケース2:現金の手渡しを行う
現金の手渡しは法的に認められた行為なので、「生前贈与」を現金の手渡しで行えば、通帳の記録にも残らないため「贈与税の対象から外れる」と考える方がいるかもしれません。
しかし、税務署には故人の通帳を調査する権限があり、使途がわからない多額の出金が発覚すれば、税務署から追及されてしまいます。
現金の手渡しだと「お金が誰から誰に渡った」という記録が残らないため、生前贈与の証拠とならず、相続財産として相続税が課されます。銀行で受贈者の銀行口座に振り込み、入出金の記録を残すと生前贈与の証拠と認めてもらえる可能性が高いです。
ケース3:受贈者が生前贈与を知らない
「贈与」は、財産をあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)双方の合意のもとで成立します。そのため、財産をもらう側の承諾も必要です。親が子ども名義の口座を作り、お金を積み立てても、子ども自身が子ども名義の預金口座の存在を認識していないと、生前贈与の成立が難しいでしょう。
したがって、生前贈与が成立するポイントを挙げると、贈与者からの財産が振り込まれている口座を受贈者は認識し、その口座を管理・運用していることだといえます。
ケース4:定期贈与とみなされる
生前贈与が税務署から「定期贈与」とみなされてしまうと贈与税が発生してしまいます。
定期贈与とは、「一定のまとまった金額を何年かにわたって計画的に贈与する約束(契約)を交わすこと」です。たとえば、1000万円を一括ではなく毎年100万円ずつ10年間贈与する行為が当てはまり、この場合では1000万円が贈与税の課税対象になってしまいます。
税務署から定期贈与ではなく暦年贈与であると認めてもらうために、「贈与契約書」の作成が有効です。贈与者と受贈者の間で「毎年の贈与ではなく、1回限りの贈与として交わされた契約である」と立証する手段になります。
贈与した日時、毎年異なる贈与金額を契約書に記載し、銀行口座への振り込みで記録を残して対策しておきましょう。
ケース5:死亡3年(7年)以内の生前贈与
生前贈与をしても、財産のあげる人(贈与者)の死亡する3年※3以内に贈与された財産は相続税の対象になります。この規定を「生前贈与加算」と呼びます。
そのため、慌てて親から子どもへ生前贈与を開始しても、贈与したい目標金額が多い場合は受け渡に年月を要するため、節税対策になりにくいといえます。節税対策で生前贈与をするのであれば、早くから生前贈与を開始し、相続税の対象とならないように気を付けましょう。
※2令和5年度の税制改正により、加算期間が3年から「7年」に変更になる予定です。
参照:令和5年度税制改正大綱|自民党
生前贈与のトラブルになりやすい原因
相続人が複数いると、相続人の間でさまざまなトラブルが起きてしまうことも。トラブルの原因となりそうな3つのケースを解説します。
トラブル1:生前贈与が特別受益になる場合
生前贈与は相続時に「特別受益」の対象となり、相続人の間でトラブルを生む原因になってしまうことがあります。
特別受益とは、死亡した人(被相続人)から遺贈されたり、生活に必要な資金などを生前贈与されて得た利益。配偶者や子どもといった法定相続人の中で、特別受益を得た人のことを「特別受益者」と呼びます。
遺産の相続時に特別受益者がいる場合、生前贈与された分(特別受益)が遺産にカウントされる「特別受益の持ち戻し」が発生します。これは相続人の間で不公平な遺産分割が発生しないように、相続人同士で公平な遺産分割をするために定められた規定です。
たとえば、配偶者のいない母親から住宅購入や事業開始などの資金援助を受けた弟と、母親から資金援助を一度も受けたことのない兄が相続人だったとします。この場合、相続時の相続財産だけで2人に遺産分割をするのは不公平ですよね。相続時だけでなく、死亡するまでの長い期間で母親から子どもへ総額でどのくらい動いたのかを判断します。
このように生前贈与したからといって、生前贈与した財産分が相続時の遺産分割に無関係になるというわけではありません。「特別受益分」を考慮して遺産分割の計算をやり直す必要が出るため、相続人同士でトラブルになる可能性があるので注意しましょう。
トラブル2:生前贈与が遺留分を侵害していた場合
遺留分とは、法定相続人が最低限受け取れる遺産の割合。生前贈与された「特別受益」が、相続人に保障されている遺産の割合を侵害していた場合、侵害された相続人は遺留分を主張することで侵害された分を取り戻せます。
たとえば、配偶者のいない母親が死亡し、兄と弟が相続人になったとします。死亡する前に母親から住宅購入や事業開始などの資金援助を弟が受けていた場合、その資金援助が「特別受益」です。
弟が受けとった「特別受益分」が、相続人である兄が最低限受け取れる金額を侵害しているとき、兄は遺留分侵害額請求を行使することで侵害された分の財産を取り戻せることがあります。
このように生前贈与を行っても遺留分が侵害されている場合は、遺産分割をめぐって相続人同士のトラブルを生むきっかけになってしまいます。
生前贈与した財産分を含めて、相続人が平等に相続できているか贈与者は考慮しましょう。
「遺留分」について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

トラブル3:税務署に生前贈与を否認された場合
贈与者が生前贈与できたと思っていても、税務署が生前贈与と認めないケースがあります。その一例として「名義預金」が挙げられます。
仮に、親が子どものために子どもの名義で預金口座を作り、お金を積み立てて贈与したとします。親が死亡したとき、子ども名義の預金口座が「名義預金」とみなされ、相続財産の1つとして相続税の対象となる主なケースは次の通りです。
- 子どもが口座の存在を知らない
- 子どもが印鑑・通帳を管理していない
- 子どもが口座を自由に使えない(運用できていない)
相続税とみなされない対策として有効なのが贈与の事実を残すこと。贈与契約書を作成したり、贈与税を少額でも納税したりすることで、税務署に生前贈与があったという証拠を主張できます。
まとめ:生前贈与されたら、どうしたらいいの?
財産をもらう側である受贈者は生前贈与をされたらどうすべき?
贈与税の申告納税が必要かどうか、非課税枠を確認。
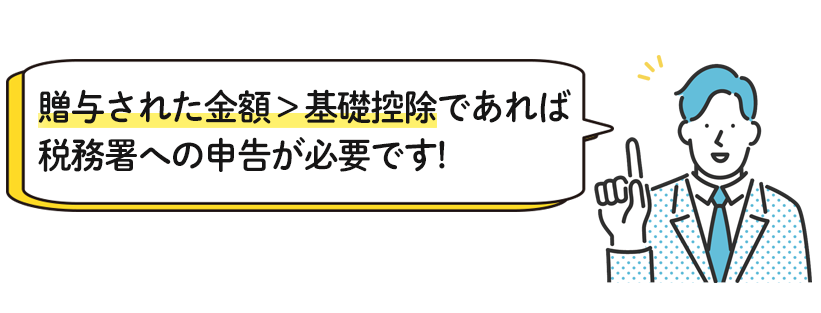
生前贈与で財産をもらったときにしなければいけないことは2種類あります。
- 贈与税の申告・納税するかの確認
- 特例の要件を満たすかの確認
生前贈与で非課税枠となるのは基礎控除額が年間110万円。贈与財産をもらったら、贈与された金額が基礎控除未満か、どうかを確認しましょう。
もし、基礎控除額を上回ったら、贈与税を申告納税する必要があります。暦年贈与であれば、贈与の対象期間が1月1日から12月31日までの1年間であり、申告納税期間は翌年2月1日から3月15日までの約1か月半の期間です。
なお、贈与税の申告漏れなどによる追徴課税は増加傾向にあります。令和元事務年度において、実地調査1件当たりの追徴税額(231万円)が対前事務年度比128.2%と、実に3割近くも増加。定められた期間内に贈与税を申告・納税することを忘れないようにしましょう。
さらに、生前贈与には基礎控除以外の非課税枠が存在し、要件を満たしていれば活用できます。代表的な特例は次の通りです。
- 住宅取得等資金の贈与
- 教育資金の一括贈与
- 結婚・子育て資金の一括贈与
- 配偶者控除(おしどり控除)
もし、「結婚資金の贈与」「住宅取得資金の贈与」などの特例を利用して納税額が0円になった場合、納税は不要ですが申告は必要になります。要件を満たすかどうか確認したうえで、特例を申請するようにしましょう。
参照:【贈与税の申告等】|国税庁/令和元事務年度における相続税の調査等の状況|国税庁
生前贈与をする際の注意点
ここまでお伝えしてきた生前贈与の注意点をまとめると次の通りです。
- 贈与者が若いうちに計画的に行う
- 相続時の所有財産の価額を想定する
- 生命保険の活用も検討する
- 遺留分や特別受益に配慮する
- 贈与した証拠を銀行振り込みや契約書などで残す
- 名義預金ならないようにする
- 贈与者の死亡による生前贈与加算期間に注意する
まず意識したい項目が、生前贈与の成立させるための証拠を残す、関連する制度を理解すること。その上で、非課税枠を最大に活かす方法を計画しましょう。
最後に:生前贈与は計画的に実行しよう
生前贈与のメリット・デメリットやお得になる方法などを中心に、生前贈与について解説してきました。
自分に必要な財産を確保してから贈与することは前提ですが、財産をうけとる相手の状況や、生前贈与に関する制度や特例を理解したうえで、生前贈与を計画的に行うことが望ましいといえます。