親族とは血縁や婚姻などでつながっている間柄であり、話し言葉としては「身内」や「親戚」と近い意味の言葉として用いられます。一方で、法律用語としての「親族」は、どの範囲の人々を指すのか明確に決まっています。ここでは、法律用語としての親族の定義と権利義務・制度の関係から、結婚式や葬儀といったライフイベントでの関わり方までわかりやすく解説します。
地元の専門家をさがす
親族とは?
親族とは、親子や兄弟・姉妹、さらに配偶者を通じてつながりのある法律上の関係性のことを指します。日常生活でも「身内」や「親戚」などと近しい意味をとして親族と呼ぶことがありますが、法的な関係を示すときは「親族」は厳密に範囲が決まっている点に注意しましょう。
親族とは?主に法的なテーマで用いる用語です
人間の生活関係について定める民法では、一定の範囲にある家族の関係を指して「親族」と呼び、親族の間におけるさまざまな権利義務について定めています。定められている内容には、誰が誰と生活を助け合う義務(扶養義務)や、成年後見制度の申立てなどにおける家庭裁判所での手続きは誰ができるのかなどといったものがあります。
親族とされる範囲
身近な家族や親戚を通じてつながりのある人は無限に存在しますが、法律上の「親族」は範囲が限定されます。法律用語として用いられる「親族」も、下記のいずれかに当てはまる人を指し(第725条)、それ以外は親族に含まないと考えます。
- 六親等内の血族
- 配偶者
- 三親等内の姻族
以下では、まず配偶者の定義(上記2)について解説したうえで、血族や姻族・親等の意味などから「六親等以内の血族」と「三親等以内の姻族」(上記1と3)に誰が当てはまるのか紹介します。
配偶者は原則として「法律婚の相手」と解釈する
親族に含まれる「配偶者」とは、婚姻届を提出することで戸籍上に夫婦として記載されるようになる「法律婚」の相手を指します。婚姻届を出さずに夫婦同然の生活を送る「事実婚」や「内縁関係」のパートナーは、原則としてここに含まれません。
現在の社会情勢では会社の福利厚生や社会保険の手続きなどで、事実婚のパートナーも配偶者とみなす動きが広がっています。ですが、相続や扶養、そのほかの家庭裁判所での手続きなどでは、依然として法律婚の相手のみが「配偶者」として扱われます。
親等の意味・数え方
親等とは、親族関係の近さ遠さを表すための単位です。本人を起点として親または子どもへと辿った距離が「一親等」です。同じように、本人から子・孫の順で辿ったときと、本人から親・祖父母の順で辿ったときは「二親等」と考えます。
六親等内の血族とは
血族とは、血のつながりがある、または法律上血のつながりがあるとみなされる親族のことです。具体的には、親子や兄弟姉妹の関係を通じてつながる人々を指します。
民法で親族の範囲に含まれる「六親等内の血族」は、下の世代は玄孫の孫、上の世代は高祖父の祖父母まで及びます。一親等から六親等の範囲の血族を示すと次の表の通りです。
| 親等 | 本人との関係 |
|---|---|
| 一親等 | 子ども、父母 |
| 二親等 | 孫、祖父母、兄弟姉妹 |
| 三親等 | 曽孫(ひまご)、曾祖父母、叔父・叔母、甥・姪 |
| 四親等 | 玄孫(やしゃご)、高祖父母、いとこ(従兄弟姉妹)、兄弟姉妹の孫、祖父母の兄弟姉妹 |
| 五親等 | 玄孫の子ども、高祖父母の父母、いとこの子ども、甥・姪の孫など |
| 六親等 | 玄孫の孫、高祖父母の祖父母、はとこ(再従兄弟姉妹)、いとこの孫など |
三親等以内の姻族とは
姻族(いんぞく)とは「配偶者の血族」と「自分の血族の配偶者」のことです。いわゆる義理の家族がこれにあたります。
民法では、配偶者の血族のうち「三親等内の姻族」の者が親族と定められています。最も近い一親等の姻族は「配偶者の父母(義父母)」や「子どもの配偶者」です。最も遠い三親等の姻族には「配偶者の叔父・叔母」や「配偶者の甥・姪」などが含まれます。
| 親等 | 本人の配偶者の血族 | 本人の血族が婚姻した相手 |
|---|---|---|
| 一親等 | 配偶者の子ども、配偶者の父母 | 子どもの配偶者 |
| 二親等 | 配偶者の孫、配偶者の祖父母 | 孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者 |
| 三親等 | 配偶者の曾孫、配偶者の曾祖父母 | 曾孫の配偶者、叔父・叔母の配偶者 |
親族と親戚の違いとは?
「親族」と「親戚」の違いは、主に法的な文脈で使用する堅い言葉か、それとも日常会話で用いる言葉かです。つながりのある人のうち法的な関係が生じる相手のみを「親族」とするのに対し、電話・対面などの交流や感情的な交わりがある人は広く「親戚」とするのが一般的です。なお「親戚」という言葉には法律的な意味合いはありません。
上記のような違いから、親族=親戚とは限りません。疎遠であるため親戚とは呼べない「親族」もいれば、交流が定期的にあっても手続き上は「親族」ではない人もいます。
間違えやすい間柄
親族かどうかの判断は、婚姻歴が複雑になっているなどの兼ね合いで難しいことがあります。ここで解説するのは、本人の子どもや兄弟・姉妹の扱いです。
異母兄弟・異父兄弟
父親または母親のどちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹は「二親等以内の傍系血族」であり、親族の範囲に含まれます。一般には異母兄弟、異父兄弟と呼ばれるこれらの関係は、法的には半血兄弟姉妹(はんけつけいていしまい)と呼ばれます。
なお、相続権の割合(法定相続分)は、子どもたちのなかで半血兄弟姉妹だけ少なくなります。半血兄弟姉妹の法定相続分は、父母ともに共通の全血兄弟姉妹の2分の1です(民法第900条4号但し書き)
認知された非嫡出子
婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを「非嫡出子」といいます。父親がその子どもを自分の子であると法的に認める「認知」をすれば、法的な親子関係が成立します。認知された子どもは、父親との関係で「一親等の直系血族」となり、親族として扱われます。
非嫡出子の法定相続分は、婚姻関係にある男女の子どもである嫡出子と同じです。かつては非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされていましたが、法改正により同等に扱われるようになりました。
両親が離婚した子ども
両親が離婚しても、法的な親子関係が消えることはありません。親権のない親と子どもの関係は、親権のある親との関係と同じく「一親等の直系血族」であり続けます。
上記の扱いにおいて、離婚した夫婦の子どもは、親権のない親についても相続権を持ちます。例外的に相続権を失うのは、特別養子縁組を養親と行ったときです。
養子縁組した子ども
養子縁組は、血のつながりがなくても法的な親子関係(法定血族関係)を生じさせる制度です。養子となった子どもは、養親との間で「一親等の直系血族」となり、実の子どもと全く同じ権利義務を負います。
なお、実親との関係については、養子縁組の種類によって異なります。普通養子縁組は実親と養親両方の親族として取り扱いますが、特別養子縁組は実親との親族としての関係を絶つものです。
配偶者の連れ子(継子)
再婚相手が前の結婚でもうけた子、いわゆる「連れ子」(民法上では継子という)は、そのままでは法的な自分の子どもにはなりません。法律上、連れ子と親の再婚相手との間には親子関係は発生せず、関係性は「一親等の姻族」となります。
配偶者の連れ子と親族関係を持ち、相続権などの権利義務を発生させるための条件は、婚姻後改めて養子縁組の手続きをすることです。婚姻した相手の連れ子が養子となったあとは、本人の連れ子や配偶者ともうけた実子と分け隔てなく権利義務が生じます。
直系と傍系とは?
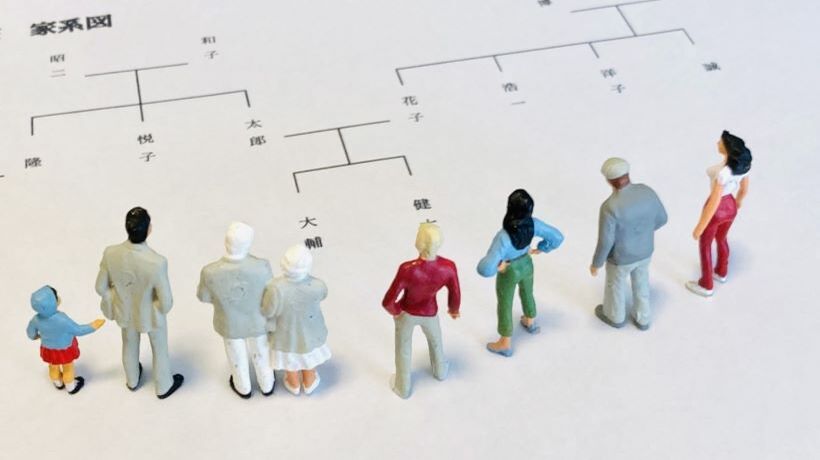
親族とされる人々は、親子関係で結ばれているか否かで直系(ちょっけい)と傍系(ぼうけい)に分かれます。特に強い関係で結ばれるのは「直系親族」です。
直系親族とは?
直系とは、親子で連なる親族関係です。具体的には、本人の父母、祖父母、曾祖父母といった自分より前の世代や、子ども、孫、ひ孫といった自分より後の世代が直系親族にあたります。
なお、自分より前の世代の親族を直系尊属(ちょっけいそんぞく)、自分より後の世代の親族を直系卑属(ちょっけいひぞく)と呼びます。相続では、直系卑属、直系尊属のうち最も親等が近い人、兄弟姉妹の順で優先的に法定相続人となります。
上記以外にも、直系親族に関する法的な制限や税制については、次のようなものがあります。
- 婚姻の制限(直系血族・民法第734条)
- 絶対的扶養義務(直系血族及び兄弟姉妹・民法第877条)
- 相続時精算課税制度(直系尊属から直系卑属への贈与・相続税法第21条の9)
- 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置(同上・租税特別措置法第70条の2)
傍系親族とは?
傍系とは、同一の親や祖先から生まれた子ども同士で連なる親族関係です。兄弟姉妹は、親を共通の祖先とする最も身近な傍系親族です。そのほか、祖父母を共通の祖先とする「叔父・叔母」や「いとこ」、または兄弟姉妹の子どもである「甥・姪」なども傍系親族にあたります。
相続における傍系親族は兄弟姉妹のみが相続人となり、直系尊属や直系卑属よりも順位が低くなります。
傍系親族に関する法的なルールには、三親等以内の傍系血族の婚姻の制限(民法第734条)があります。いとこ同士(四親等以内の傍系血族)は婚姻できますが、叔父叔母と甥・姪は婚姻できません。
尊属と卑属とは?
親族を本人を基準として世代の上下で分けると、尊属(そんぞく)と卑属(ひぞく)となります。法的には、尊属から卑属への財産の移転を支えるルールが複数あります。
尊属親族とは?
尊属(そんぞく)とは、本人を基準としたときに親以上の世代となる人々です。尊属親族には、父母・祖父母・曾祖父母などの直系と、叔父叔母など傍系が存在します。
相続では、尊属は卑属よりも相続順位が低くなります。税制では「相続時精算課税制度の選択」や「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置」など、直系尊属からの贈与を支える優遇制度が複数あります。
卑属親族とは?
卑属(ひぞく)とは、本人を基準としたときに子ども以下の世代となる人です。卑属親族には、子ども・孫・曾孫といった直系と、甥・姪以下の傍系がいます。
直系の卑属親族は、相続権で最も順位が高く、生前贈与を受ける側となったときもさまざまな税制上のメリットがあります。傍系の卑属は、兄弟姉妹が死亡などの理由で相続権を失っている場合に甥・姪までが相続権を得ることになります。これを代襲相続といいます。
地元の専門家をさがす
親族が集まるイベントの例

家族行事などのイベントでは親族=親戚となることが一般的ですが、私たちの生活のなかでは法律用語としての「親族」を意識する場面がたびたびあります。ここでは、親族との関係を身近なシーンで考え、集まって顔を合わせるイベントと、そこで知っておきたい知識について解説します。
お正月・お盆・年末年始などの帰省
お正月やお盆は、多くの人々が故郷へ帰り、家族や親族と過ごす伝統的な習慣です。これらは単なる長期休暇ではなく、先祖を敬い、家族の絆を再確認する意味合いを持つ大切な年中行事といえます。
上記のようなシーズンでは、祖父母、親、兄弟姉妹、叔父叔母、いとこなど、二親等から三親等程度の比較的近い親族が集まることが多いでしょう。子どもたちへ渡すお年玉やお盆玉の金額は、相手の年齢や関係性によって異なりますが、親族間で事前に相談して金額を揃えるケースも見られます。
祝儀(お祝いごと)への参加
祝儀とは主に結婚式のことであり、親族が集合するイベントの代表です。新郎新婦との関係性によりますが、一般的には三親等内の親族(叔父叔母、甥姪、いとこなど)までを招待することが多いようです。ほかには出産・新築・子どもの入学・卒業などがありますが、これらのイベントで集まるのは二親等以内の親族(祖父母など)となるのが一般的でしょう。
祝儀でお祝いを贈るときは、親族とはいえ紅白の水引がついたのし紙を使うのがマナーです。結婚式のご祝儀の金額は、新郎新婦との関係性や自身の年齢、社会的立場によって変わります。一般的な相場は以下の通りです。
| 関係性 | 20代 | 30代以降 |
|---|---|---|
| 兄弟・姉妹 | 5万円 | 5~10万円 |
| いとこ | 3万円 | 3~5万円 |
| 甥・姪 | 3~5万円 | 5~10万円 |
| そのほかの親族 | 3万円 | 3~5万円 |
不祝儀(不幸なこと)への参加
不祝儀とは、親族が亡くなったときの葬儀・告別式や、一周忌などの法事を指します。これらの行事には、三親等内の親族までは参列するのが一般的です。喪主は故人の配偶者や子どもが務めるのが通例ですが、法律上の決まりはなく、血縁関係の深い人や故人と縁の深かった人が務めます。
葬儀や告別式における香典の金額は、故人との関係性や自身の年齢によって異なります。香典袋は、宗教や金額に合わせて選び、表書きは薄墨で書くのがマナーです。通夜または葬儀・告別式の受付で渡します。
| 関係性 | 20代 | 30代 | 40代以降 |
|---|---|---|---|
| 祖父母 | 1万円 | 1~3万円 | 3~5万円 |
| 親 | 3~10万円 | 5~10万円 | 10万円以上 |
| 兄弟・姉妹 | 3~5万円 | 5万円 | 5万円以上 |
| 叔父・叔母 | 1万円 | 1~2万円 | 2万円以上 |
| そのほかの親族 | 3000~1万円 | 1万円 | 1万円以上 |
不祝儀は、悲しい出来事であると同時に、相続について考えるきっかけにもなります。誰が法定相続人になるのか、遺産にはどのようなものがあるのか、といった基本的な知識は、いざというときに役に立ちます。
親族が健在なうちに財産のことや将来のことを話し合っておくことは、後の円満な相続につながります。親族が集まる場では、その場にいる人の心情に配慮しつつ、折を見て相続に関する話題に触れてみるとよいでしょう。
円満な将来のため親族の意味・範囲の理解を
日常会話で使用されることもある「親族」は、法律用語としての側面も持ちます。親族を構成するのは、六親等以内の血族、配偶者、三親等以内の姻族です。親族の関係には直系・傍系と尊属・卑属があり、直系尊属と直系卑属の関係が相続では重要です。
親族の意味やその範囲から「誰と法的な関係があるのか」を正しく把握することは、相続などを円満に迎えるため必要です。親族らが集まる機会があれば、お互いの関係や将来について少しずつ話し合ってみるとよいでしょう。
地元の専門家をさがす


