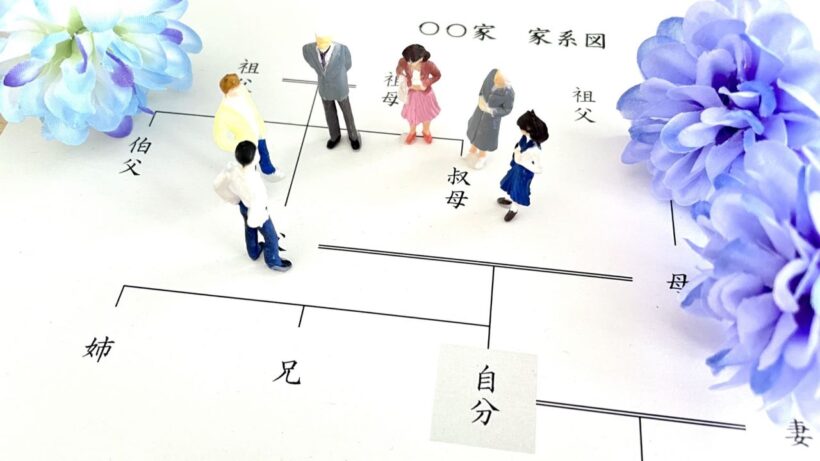1994年(平成6年)の制度改正以前の戸籍のうち、改製によって作成された戸籍を原戸籍といいます。正式には「改製原戸籍」といいます。一方、戸籍謄本とは1994年の制度改正から現在まで使用されている戸籍を指します。相続登記や口座の名義変更などの相続手続きにおいて、原戸籍と戸籍謄本が必要です。本記事では、改製原戸籍と戸籍謄本の違いや相続手続きで必要となる書類、改製原戸籍の取得方法などをまとめて解説します。これから相続手続きを進める方は、ぜひ参考にしてください。
地元の専門家をさがす
原戸籍(改製原戸籍)とは
原戸籍(げんこせき・はらこせき)とは、制度改正前の戸籍のことです。1994年のコンピューター上で保管される様式にするための制度改正されたものが現在の戸籍で、制度改正以前につくられた昔の戸籍の正式な名称を「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」といいます。
現在の戸籍とは違って改製以前に除籍した人や認知した子ども、養子縁組、離婚などに関する項目も記載されており、被相続人が1995年(平成7年)より前に出生している場合の相続手続きに必要となる書類です。
原戸籍と戸籍謄本の違いを理解するには、日本における戸籍の歴史を知る必要があります。ここでは、戸籍の歴史を遡りながら下記の順番で詳しく解説します。
- 平成原戸籍(改製原戸籍)とは
- 昭和原戸籍(改製原戸籍)とは
- 昭和原戸籍(改製原戸籍)以前の戸籍
順番に見ていきましょう。
平成原戸籍(改製原戸籍)とは
平成原戸籍(改製原戸籍)とは、1994年の制度改正以前の戸籍のことです。制度改正で戸籍がコンピューター化されましたが、それ以前の戸籍はすべて紙で管理されていました。
制度改正では戸籍をコンピューターで記録・管理できるようになり、書式や記載形式が変更されました。書式もB4サイズの縦書きからA4サイズの横書きに変わり、記載形式は文章から項目化に変更されています。
現在における「改製原戸籍」では、この平成原戸籍を指すことが一般的です。平成原戸籍より前の改製原戸籍は「昭和改製原戸籍」などと呼ばれます。
昭和原戸籍(改製原戸籍)とは
昭和原戸籍(改製原戸籍)とは、1947年(昭和22年)の制度改正によって改製された戸籍です。
制度改正における大きな変更点は、戸籍の基本単位が「家」から「夫婦」になったこと、「戸主」が「筆頭者」へと記載が変わったことです。
昭和原戸籍(改製原戸籍)以前の戸籍
昭和原戸籍(改製原戸籍)以前にも何度か制度改正が行われ、制度や書式が下記のように変容してきました。
| 制度改正の年 | 戸籍の特徴 |
|---|---|
| 1886年(明治19年) | 地番や除籍制度が採用されている戸籍 |
| 1898年(明治31年) | 家制度に変更された戸籍 |
| 1915年(大正4年) | 戸主となった原因・日付の記載が廃止された戸籍 |
| 1947年(昭和22年) | 家制度から現在の家族制度に変更され、戸主が筆頭者に変更された戸籍 |
このように、時代の移り変わりとともに、戸籍の管理方法や記載内容も変更されてきた歴史があります。
戸籍謄本・除籍謄本と原戸籍の違い
原戸籍に似た言葉に、戸籍謄本や戸籍抄本、除籍謄本といった言葉があります。
相続手続きにおいて、このような似た名前の書類が必要書類として羅列されていると、何のために取得しなければならないのかが理解しづらいでしょう。ここでは、下記のポイントごとに戸籍謄本・除籍謄本と原戸籍の違いについて詳しく解説します。
- 戸籍謄本(抄本)とは
- 除籍謄本(抄本)とは
- 原戸籍と戸籍謄本に記載される内容の違い
順番に確認しましょう。
戸籍謄本(抄本)とは
戸籍謄本とは、1994年の制度改正から現在まで使用されている戸籍のことです。現在戸籍とも呼ばれ、1組の夫婦(筆頭者とその配偶者)とその子ども(未婚に限る)について、下記の項目が記録されています。
- 本籍
- 氏名
- 生年月日
- 続柄
- 出生
- 婚姻
- 離婚
- 養子縁組
なお、現在の戸籍謄本の正式名称は「戸籍全部事項証明書」です。市区町村役場によっては「戸籍全部事項証明書」と表記されている場合があるため、気をつけましょう。
また、戸籍を証明する書類には戸籍抄本と呼ばれるものもあります。戸籍抄本の正式名称は、「戸籍個人事項証明書」です。
戸籍謄本は戸籍に記載されている全員について証明する書類である一方、戸籍抄本は戸籍に記載されている一部の人について証明する書類であるという違いがあります。
親族関係を証明する必要のある相続手続きでは戸籍謄本の提出が求められ、年金の請求や国家資格の受験などは個人の身分証明として戸籍抄本が使えると覚えておきましょう。
除籍謄本(抄本)とは
除籍謄本とは、1994年の制度改正から現在まで使用されている除籍簿のことです。1つの戸籍に記載された全員が結婚や死亡、転籍などによって戸籍から除かれ、空になった状態を除籍簿といいます。
除籍を証明する書類には、除籍謄本と除籍抄本があります。除籍謄本の正式名称は「除籍全部事項証明書」といい、除籍簿に記載されている全員について証明する書類です。
一方、除籍抄本の正式名称は「除籍個人事項証明書」といい、除籍簿に記載されている一部の人について証明する書類です。
相続手続きでは親族関係を証明するために、除籍謄本の提出を求められる場合があります。一方、死亡の事実を証明するだけであれば除籍抄本でも問題なく証明できます。
原戸籍と戸籍謄本に記載される内容の違い
改製原戸籍と戸籍謄本の違いは、記載されている情報の量です。現在の戸籍謄本には、一世帯分の最新情報しか記載されていません。
1994年の制度改正によって戸籍謄本には、下記の項目が記載されなくなりました。
- 改製前の除籍
- 改製前の離婚
- 改製前の子どもの認知
- 改製前の養子縁組
制度改正によって戸籍が切り替わるときに、過去の情報が引き継がれませんでした。そのため、上記の情報を調べるためには改製原戸籍が必要です。
相続の手続きで必要になる戸籍情報
ここからは、相続の手続きで必要になる戸籍情報について、下記のポイントごとに解説します。
- 原戸籍・戸籍謄本・除籍謄本は原則相続の手続きで必要になる
- 住民票もしくは戸籍の附票(原戸籍の附票)も必要になる
どのような場合に、どの書類が必要となるのかを確認しましょう。
原戸籍・戸籍謄本・除籍謄本は原則相続の手続きで必要になる
預貯金口座の名義変更における金融機関での手続きや、不動産の名義を変更する相続登記の手続きなど、ほとんどの相続手続きにおいて被相続人の出生から死亡までが辿れる戸籍の提出が求められることになります。
原則すべての相続手続きにおいて被相続人の出生から死亡までが辿れる戸籍の提出が求められる場合があります。
そのため、下記の書類が必要です。
- 原戸籍(被相続人が1995年以降に生まれている場合には不要)
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
財産を引き継ぐための手続きだけでなく、法定相続人の調査や相続税の申告にも上記書類の提出が必要です。
ただし、被相続人が1994年以降の生まれなら原戸籍がないため、原戸籍を取得する必要はありません。
住民票もしくは戸籍の附票(原戸籍の附票)も必要になる
不動産の相続登記や、自動車の名義変更・廃車手続きをするとき、住民票もしくは戸籍の附票(原戸籍の附票)も必要となる場合があります。
不動産の相続登記では、登記されている住所から現住所までの変遷を証明する必要があり、戸籍の附票や原戸籍の附票が必要になる場合があります。一方、自動車の手続きでは、車検証に記載された住所に住んでいた事実を証明するために戸籍の附票が必要です。
戸籍の附票と住民票は、どちらも住所を証明するための書類です。しかし、記載内容が異なります。戸籍の附票には戸籍が作成されてから現在、もしくは除籍されるまでの住所の履歴が書かれています。引っ越しによって市区町村の転出・転入があったとしても辿ることが可能です。
一方、住民票は現住所の市区町村で管理されており、現住所と前住所しか記載されていません。また、同一市区町村内での住所しか辿れず、転出すると除票となります。なお、除票の保管期間は5年間となっています。
どちらもマイナンバーカードのコンビニ交付に対応しています。ただし、窓口で取得したい場合には、戸籍の附票は本籍地の役場でしか取得できない一方で、住民票は現在の住所地(もしくは最期の住所地)の市区町村役場でしか取得できない点に注意しましょう。
原戸籍(改製原戸籍)の取得方法

相続手続きにおいて原戸籍(改製原戸籍)を取得するときに備えて、下記のポイントをおさえておきましょう。
- 原戸籍(改製原戸籍)を取得できる人
- 原戸籍(改製原戸籍)を取得するための必要書類
- 原戸籍(改製原戸籍)を取得できる場所
詳しく解説します。
原戸籍(改製原戸籍)を取得できる人
原戸籍(改製原戸籍)を取得できる人は、原則下記に当てはまる方に限られます。
- 本人
- 同一戸籍の人(配偶者)
- 直系尊属(両親・祖父母など)
- 直系卑属(子ども・孫など)
ただし、正当な事由がある場合、委任状を提出すれば上記以外の方でも原戸籍を取得できます。たとえば、相続手続きのために原戸籍を取得したい場合、司法書士や弁護士など士業は職権で取得することが可能です。
原戸籍(改製原戸籍)を取得するための必要書類
原戸籍(改製原戸籍)を取得する際に提出する必要書類は、下記の通りです。
- 交付申請書(申請窓口で取得可能)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 手数料(1通あたり750円)
- 委任状(代理人の場合)
取得日に向けて、あらかじめ準備しておきましょう。
原戸籍(改製原戸籍)を取得できる場所
原戸籍(改製原戸籍)を取得できる場所は、市区町村役場の窓口です。自治体によっては、地域センターや市民サービスコーナーなどでも発行している場合があります。窓口によって取り扱い時間が異なるため、あらかじめ受付時間を調べておきましょう。
以前は、被相続人の本籍地の市区町村役場でしか取得できませんでした。しかし、令和6年3月1日より戸籍証明書等の広域交付が開始され、最寄りの市区町村役場でも原戸籍を取得できるようになりました。
ただし、本籍地以外で取得する場合、取得する人自身が窓口へ出向かなければなりません。また、本籍地以外で取得できる人は、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属のみです。
つまり、司法書士や弁護士などに委任状を預けて代理人として取得してもらったり、兄弟姉妹や叔父叔母の原戸籍を取得したりするには、本籍地の市区町村役場で手続きしなければなりません。
本籍地の市区町村役場へ出向くことが難しい場合は、郵送で取り寄せることも可能です。郵送で取り寄せる際に必要な手続きは下記の通りです。
- 交付請求書を作成する
- 本人確認書類の写しと交付手数料分の定額小為替、返信用封筒を準備する
- 代理人が郵送で取り寄せる場合は委任状を準備する
- 必要書類を揃えて本籍地の市区町村役場へ郵送する
返信用封筒には、住所と宛名を記載し、必要分の切手を貼りましょう。
なお、原戸籍はコンビニで取得することができないため、注意してください。
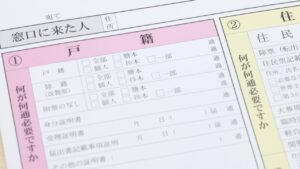
原戸籍(改製原戸籍)の注意点
最後に、原戸籍(改製原戸籍)の3つの注意点をご紹介します。
- 原戸籍の保存期間は150年
- 原戸籍の附票は保存期間が5年のものもある
- 原戸籍と戸籍謄本には有効期限がない
詳しく確認しましょう。
原戸籍の保存期間は150年
かつて下記のように原戸籍の保管が定められていました。ですが、現在の原戸籍の保存期間は、2010年(平成22年)の制度改正によって150年と定められています。
| 作成された原戸籍の期間 | 保存期限 |
|---|---|
| 明治19年式・明治31年式で原戸籍になったもの | 80年 |
| 大正4年式で原戸籍になったもの | 50年 |
| 昭和22年式で原戸籍になったもの | 100年 |
2010年の制度改正以前に作成された戸籍を請求する場合、改正前の保存期限が過ぎてしまっていると廃棄されている可能性があります。その場合、廃棄証明を交付してもらうことが可能です。
また、先述の通り制度改正以前の戸籍は紙で管理されていました。そのため、戦争や災害で消失している可能性もあります。この場合は、消失証明を発行してもらうことが可能です。
いずれにしても古い原戸籍を取得したいのなら、はやめに市区町村役場へ交付請求をしましょう。
原戸籍の附票は保存期間が5年のものもある
2010年制度改正前、原戸籍の附票の保存期間は5年でした。現在は150年に延長されていますが、古い原戸籍の附票を取得したくても保存期間を過ぎている場合、廃棄されている可能性があります。
戸籍の附票が廃棄されている場合、上申書を作成して相続登記することが可能です。しかし、手続きの内容が複雑になるため、相続登記に強い司法書士に相談することをおすすめします。
原戸籍と戸籍謄本には有効期限がない
原戸籍と戸籍謄本には有効期限が定められておらず、法的にはいつ取得したとしても戸籍の証明にできます。
しかし、金融機関や証券会社で相続手続きをするときには、発行から6か月以内のものを指定される場合があります。スムーズに相続手続きを終えるためにも、手続きに有効となる期限をあらかじめ確認したうえで提出するようにしましょう。
相続手続きには改製原戸籍や戸籍謄本が必要
相続手続きを進めていくなかで、改製原戸籍や戸籍謄本、除籍謄本などが必要になってきます。
1994年の制度改正までの戸籍は改製原戸籍、それ以降の制度改正以降の戸籍は戸籍謄本と覚えておきましょう。制度改正によって戸籍に記載される項目が変わり、情報が引き継がれていないため、相続手続きでは改製原戸籍が必要となる場合があります。
相続の手続きは、ほとんどの場合に被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍の提出を求められます。収集が難しい場合は専門家に相談すると、他の必要書類もまとめて取得してくれます。
相続プラスでは、相続に強い司法書士や弁護士を気軽に検索することができます。悩み別・エリア別に検索できるため、あなたの困りごとを解決してくれる専門家に出会えるでしょう。
専門家の協力やアドバイスを受け、スムーズに相続手続きを済ませましょう。
地元の専門家をさがす