家族が亡くなったとき、いつから遺品整理を始めるべきか悩んでいませんか。この記事では、遺品整理を始めるタイミングを決める材料や一般的な開始時期、注意点について解説しています。家族が亡くなると多くの手続きをしなければいけません。各種手続きの期限もご紹介しているため、いつ頃から遺品整理を始めるかの参考にしてください。
目次開く
地元の専門家をさがす
遺品整理はやらないといけないの?
まず、遺品整理には法律で決められた期限はありません。そのため、いつから始めるかは家族の心境や状況で異なります。多くの場合、家族の心が落ち着き、時間や気持ちに余裕ができた節目(タイミング)をきっかけに、遺品整理を始める人が多いようです。
特に、四十九日を一つの節目(タイミング)とするケースがよく見られます。
四十九日の法要が終わった頃から遺品整理を始める場合や、親族が集まる四十九日までに整理が終えられるよう、葬儀が一段落したらすぐに始める場合などです。
しかし、法律で定められた期限が無いからといって、いつまでも遺品整理をしないままでいると、相続に関するさまざまな手続きが進まなくなることもあります。
なので、遺品整理の期限はありませんが、いずれは行う必要のあることと言えます。
次の章では、遺品整理のタイミングをどのように決めるのかについて詳しく解説していきます。
遺品整理のタイミングを決める材料
先述の通り、遺品整理に明確な期限はないため、相続人などの家族・親族が開始するタイミングを決めて行うことになります。
気持ちの整理がつかず、なかなか遺品整理を始められない場合もありますが、賃貸物件に住んでいた場合には、引き渡しや退去の手続きを早めに始めないと、家賃やその他の費用の支払いが継続してしまいます。
遺品整理のタイミングを決める材料は、下記の通りです。
- 遺品の量や価値、場所
- 相続の状況
- 賃貸などの費用が発生している
- 手続き期限や費用が発生する時期
順番に確認しましょう。
遺品の量や価値、場所
遺品整理にかかる日数は、被相続人の遺品の量や価値、場所によって大きく変わります。
遺品の量が少なければすぐ終わりますが、遺品の量が多かったり、古美術品などの価値が高そうなものが多かったりすると、当然整理にかかる時間が長くなってしまいます。
また、片付けをする方が亡くなった人の住まいから離れた場所に住んでいた場合では、何度も足を運んで遺品整理を進めていく必要があり、どうしても時間がかかってしまいます。
そのため、遺品整理の際には、遺品の量や価値、場所などをきちんと把握することが重要だと言えます。
相続の状況
相続放棄や限定承認の手続きの期限は、相続発生を知った日から3か月以内です。期限日から逆算して早めに相続財産の把握を急ぐ必要があります。ただし、遺品の整理や処分をすると放棄できなくなる恐れがあるため注意しましょう。
また、下記のケースに当てはまる場合、遺産分割協議が長引く可能性があります。早めに相続財産の内容を把握するほうがよいでしょう。
- 相続人が多い
- 相続人同士の仲が悪い
- 遺産分割で揉めそう(実家がほしい人が多いなど)
- 価値の高い遺産が多い
あくまでも、相続放棄や限定承認を考えている場合は遺品の整理や処分を行わず、遺品の把握に留めましょう。
賃貸などの費用が発生している
亡くなった人が賃貸物件などに住んでいた場合、当然家賃が発生し続けます。なのでいつまでも先延ばしにしておくと資産が減ってケースでは、特に早めに対応した方が良いでしょう。
ほかにも、レンタルやリースをしている介護用品など、継続的に費用が発生しているものがあれば早めに解約手続きをする必要があります。
ただし、相続放棄を検討している場合は単純承認とみなされないように、専門家に相談してから手続きを始めることが推奨されます。
地元の専門家をさがす
手続き期限や費用が発生する時期
遺品整理をいつまでも先延ばしにしていると、手続き期限や費用が発生する時期を迎えてしまう場合があります。そのため、下記の手続き期限から逆算して遺品整理を始めましょう。
| 手続き内容 | 期限 |
|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 相続発生を知った日から3か月以内 |
| 相続税の申告・納税 | 相続発生を知った日の翌日から10か月以内 |
相続財産の内容を把握しなければ、これらの手続きを進められません。遺品整理とは少し異なりますが、相続財産1つ1つの価値を正確に把握する必要があります。
また、賃貸物件であれば賃料が発生し、持ち家の場合は固定資産税が発生するため、相続人が支払わなければなりません。賃料は毎月発生するうえに、更新時期を迎えると更新料の支払いも必要です。
固定資産税は毎年1月1日時点の土地所有者に請求され、所有者が亡くなっている場合には相続人が納税義務者となります。万が一、持ち家が特定空き家に指定されてしまうと、固定資産税は最大で6倍となり、相続人の負担が大きくなってしまいます。
無駄な出費を防ぐためには、早めに遺品整理を完了させて住居の解約・売却をするようにしましょう。
誰が遺品整理をする?

遺品整理は家族や親族で行うことが可能ですが、業者に依頼する手段もあります。それぞれどのようなメリット・デメリットがあるのか確認しましょう。
自分で遺品整理をするとき
自分で遺品整理をするメリットとデメリットは、下記の通りです。
<メリット>
- あまり費用がかからない
- 遺品1つ1つと向き合える
- 自分のペースで進められる
<デメリット>
- 手間と労力がかかる
- 遺品と向き合う精神的な辛さがある
遺品と向き合いながら自分のペースで遺品整理を進められるため、心の整理をしながら丁寧に片付けることができます。思い出の詰まった遺品を誤って捨ててしまうことも少なくなります。
ただし、自分で遺品を廃棄したり片付けたりするには、時間や労力がかかります。また遺品を手に取ることで、精神的な負担を感じることもあるでしょう。
自分で遺品整理しても負担にならないケースは、下記の通りです。
- 時間的・精神的・体力的に余裕のある場合
- 大人数で家具・家電の運び出しがスムーズにできる場合
上記に当てはまる方であれば、いつまでに遺品整理を終えるかを明確にしたうえで、自分で進めてもよいでしょう。
業者に依頼するとき
業者に遺品整理を依頼する時のメリットとデメリットは、下記の通りです。
<メリット>
- 短時間で遺品整理が終えられる
- 手間・労力がかからない
<デメリット>
- 費用がかかる
- 必要なものを捨てられてしまう場合がある
家具や家電など、遺品が多くても業者に頼めば短時間で処分してもらえます。家族にかかる負担は大幅に軽減されるでしょう。
しかし、当然業者に依頼すると報酬を支払わなければなりません。業者に依頼する場合は、複数社に見積もりを依頼してサービス内容や費用を比較して選定しましょう。
また、業者には思い出の詰まったものや必要なものの判断がつきません。残してほしいものを明確にしておき、別の場所に移動したり目印をつけたりしておく必要があります。
遺品整理を業者に依頼したほうがよいケースは、下記の通りです。
- 手続きの期限が迫っている
- 片付ける範囲が広い
上記に当てはまる方は、業者に依頼した方が負担なく遺品整理を終えられるでしょう。
遺品整理をするタイミング・時期の目安
遺品整理をするタイミング・時期の目安として、下記を参考にしてください。
- 葬儀の後(亡くなってから数日後~)
- 年金や健康保険などの手続きの後(1週間後~)
- 四十九日法要の後(49日後~)
- 相続税申告までに(~10か月以内)
- 相続税申告期限の後・気持ちが落ち着き次第(10か月後~)
一般的なタイミングについて詳しく確認しましょう。
葬儀の後(亡くなってから数日後~)
葬儀・告別式は、一般的に亡くなってから数日以内に行います。
葬儀・告別式のあとは相続人や親戚などが集まっているときや連絡を取り合っているときのため、遺品整理をしながら形見分けがしやすいといった利点があります。また、人が集まりやすいタイミングのため、スムーズに遺品の処分も進めることができるでしょう。
とくに、被相続人が賃貸物件に住んでいた場合や孤独死などで特殊清掃をしなければならない場合など、時間が経つにつれ費用負担が大きくなる場合には、葬儀の直後から動き出すことをおすすめします。
年金や健康保険などの手続きの後(1週間後~)
年金や健康保険などの手続きが完了し、精神的にひと段落できるタイミングで遺品整理を始めてもよいでしょう。
人が亡くなった直後に行わなければならない手続きの期限は、下記の通りです。
<死亡届の提出>
- 期限:死亡後7日以内
- 手続きできる場所:市区町村役場
<埋火葬許可証の交付申請>
- 期限:死亡後7日以内
- 手続きできる場所:市区町村役場
<健康保険の資格喪失・資格取得>
- 期限:死亡後すみやかに
- 手続きできる場所:市区町村役場、または被相続人の勤務先
<厚生年金の手続き>
- 期限:死亡後すみやかに
- 手続きできる場所:年金事務所
<国民年金加入状況変更の手続き、健康保険の変更・加入※配偶者が被相続人の扶養になっていた場合>
- 期限:死亡後すみやかに
- 手続きできる場所:市区町村役場
<免許証の返納>
- 期限:死亡後すみやかに
- 手続きできる場所:警察署、または運転免許センター
<公共料金・賃貸契約・携帯電話などの解約>
- 期限:死亡後すみやかに
- 手続きできる場所:各サービス事業主
<年金受給権者死亡届(報告書)の提出>
- 期限:死亡後10日以内(国民年金受給者は14日以内)
- 手続きできる場所:年金事務所
<世帯主の変更>
- 期限:死亡後14日以内
- 手続きできる場所:市区町村役場
<介護保険料過誤納還付金の請求>
- 期限:死亡後14日以内
- 手続きできる場所:市区町村役場
<雇用保険受給資格者証の返還>
- 期限:死亡後1か月以内
- 手続きできる場所:ハローワーク
<遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求>
- 期限:死亡後5年以内
- 手続きできる場所:年金事務所、または市区町村役場
このように、人が亡くなったあとは行わなければならない手続きが多く、しかも葬儀が終わってから1週間程度で済ませなければならないものも多いため、すべての手続きが終わると時間的な余裕も生まれます。
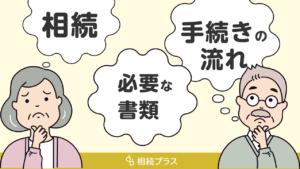
四十九日法要の後(49日後~)
四十九日法要は、被相続人が亡くなってから7週間後(49日後)に行われる法要です。仏教では四十九日の法要をもって忌明けとなり、喪に服す期間が終了します。
四十九日法要には諸手続きが完了しており、相続人や親族が一同に集まるため、遺品整理を開始しやすいタイミングです。遺品整理をしながら形見分けをしたり、遺産分割協議の段取りを決めたりできます。
また、相続放棄や遺産分割を急ぐ場合は、四十九日法要を遺品整理開始のタイミングと考えておきましょう。とくに、相続放棄の期限は相続発生から3か月以内のため、急いで相続財産の内容を確認しましょう。
相続税申告までに(~10か月以内)
相続税の申告義務が発生している場合、相続発生を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税をしなければなりません。
申告の際には相続財産1つ1つの価値評価や遺産分割を終わらせておく必要があります。そのため、被相続人が亡くなってから7〜8か月が経過する頃を目処に遺品整理も済ませておきましょう。
相続税の申告・納税に遅延すると、ペナルティとして余分な税金が発生する場合があります。正しく期限内に申告・納税するためには、相続に詳しい税理士に依頼することをおすすめします。

相続税申告期限の後・気持ちが落ち着き次第(10か月後~)
大切な家族を亡くしたときの悲しみは計り知れません。遺品整理をしたくても、被相続人との思い出がよみがえり、なかなか遺品を処分できないこともあります。
そのため、気持ちが落ち着いてから遺品整理を行うのも一つの選択肢です。
ただし、時間が立ちすぎてしまうと遺品整理への意欲が薄れてしまう可能性があります。すぐに遺品と向き合う気になれない場合は、「半年経過したら始めよう」などと自分なりの期限を設けると良いでしょう。
なお、相続税の申告義務がある場合は、期限までに一度概算で多めの額を申告・納税しておくことをおすすめします。その後、遺品整理を行って財産内容が確定した際に更正の請求を行えば、余分に納めていた分の還付を受けることができます。
更正の請求の期限は、相続税申告期限から5年以内です。時間的な猶予はあるため、焦る必要はありません。
そのため、更正の請求を考えている場合には、「更正の請求までには必ず終わらせる」ことを目標にしておくとよいでしょう。
また、概算で相続税の申告・納税をし、そのあと更正の請求を行いたい場合は、相続に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

遺品整理についての注意点・知っておきたいこと
遺品整理についての注意点・知っておきたいことは、下記の通りです。
- 事前に計画を立ててから実施する
- 相続人や家族などの了承を得る
- 遺言書やエンディングノートも確認する
- 相続放棄をする場合は単純承認とみられないようにする
- 空き家の放置はリスクがある
5つのポイントについて、詳しく確認しましょう。
事前に計画を立ててから実施する
まず、遺品整理の計画を立てておきましょう。計画を立てる際のポイントは、下記の通りです。
- いつまでに終わらせるか
- 誰が遺品整理を行うか
- どの順番で遺品整理を行うか(台所・寝室など)
- 家具家電などの処分をどうするか
いつまでに遺品整理を終えるかを決めれば、逆算してスケジュールを立てやすくなります。
また、家具家電などの大きい遺品を業者に処分してもらう場合は、早めに日にちを決めて手配しておきましょう。
相続人や家族などの了承を得る
相続人や家族などの了承を得たうえで遺品整理を進めましょう。なぜなら、遺産分割が決定するまでの間、遺品は相続人全員の共有財産だからです。
合意を得ておくべきポイントは、下記の通りです。
- 処分にかかる費用の負担をどうするか
- 価値が高いものの処分方法・形見分けをどうするか
遺品整理を行う本人にとっては大切でないものでも、他の家族や親戚にとっては思い出深い品である場合もあります。誤って処分してしまうと、トラブルの原因になることもあります。
そのため、遺品整理を進める前に「残してほしいものはあるか」「処分前に住居を見にこなくてよいか」などと確認しておくことをおすすめします。また、処分に迷うことがあれば、都度相続人や家族に確認・相談するようにしましょう。
遺言書やエンディングノートも確認する
遺品の処分を始める前に、被相続人が遺言書やエンディングノートを残していないかチェックしましょう。遺品の処分方法や譲り先などを指定している場合があるからです。
また、遺言書がある場合は、遺産分割の話し合いや相続手続きの負担や手間が大幅に軽減されます。そのため、金庫や大切なものを保管していそうな引き出しなどに遺言書が残されていないか探してみるとよいでしょう。
ただし、自宅から遺言書が見つかった場合、勝手に開封することはできません。家庭裁判所での検認を受け、相続人立ち会いのもと開封する必要があるため注意しましょう。
相続放棄をする場合の遺品整理には注意する
遺品整理を行った際に経済的な価値のある遺品を処分したり持ち出したりすると、遺産を相続する意思があるとみなされ、相続放棄ができなくなる恐れがあります。
形見分けとして、アルバムや身の回りのものなど経済的価値のないものであれば、相続放棄に影響しない可能性は高いです。しかし、高価なジュエリーや着物、美術品などは相続財産の一部とみなされるため、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
また、携帯電話や賃貸物件の解約も単純承認の意思があるとみなされる場合があるため、慎重に手続きを進める必要があります。
遺品整理をした場合に相続放棄が認められるかどうかは、弁護士によっても見解が分かれるほど非常に曖昧です。安易に遺品整理を進めず、相続に詳しい弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

空き家の放置はリスクがある
被相続人が死亡したことによって住宅が空き家になっている場合、放置していると下記のようなさまざまなリスクが生じます。
- 火災
- 倒壊
- 犯罪
また、空き家のまま放置していると固定資産税がかかり続け、相続人に納税義務が発生します。
特定空き家や管理不全空き家などに指定されると固定資産税の優遇措置を適用されなくなり、最大約6倍もの税金を支払う義務が生じることになります。
相続人や家族が空き家となる住居に住まない場合には、早めに家の中の遺品整理を済ませて、不動産の売却や土地活用の検討を進めましょう。
早めに遺品整理を始めて相続手続きを期限内に終わらせよう
いつから遺品整理を始めようかと考えている方は、できるだけ早く始めることをおすすめします。
事情や状況によって遺品整理を始めるタイミングはさまざまですが、葬儀後や四十九日法要後を一つの目安として遺品整理を始める方が多いです。
また、相続税の申告義務がある場合は、申告期限の2〜3か月前までに終わるよう逆算して計画を立てることをおすすめします。
ただし、遺品の処分や形見分けを行うと相続放棄が認められない場合があるため、注意が必要です。相続放棄をする場合の遺品整理の進め方については、相続を専門とする弁護士などの専門家に相談しましょう。
地元の専門家をさがす


