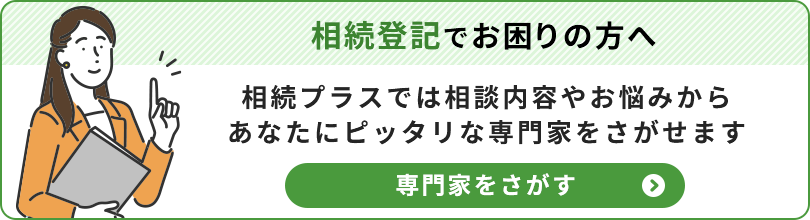相続登記(不動産の名義変更)の難しさや、令和6年4月以降の相続登記の義務化により、司法書士への相談が増えつつあります。一方で、今まさに相続手続きを迎えようとする人は、遺産分割や相続税などのさまざまな分野が交わることから「司法書士への相談でよいのか」と迷うのではないでしょうか。ここでは、司法書士の役割・立ち位置から、相続について相談した方がよいケース、信頼できる相談先の選び方まで解説します。
目次開く
相続における司法書士の立ち位置
司法書士は「登記の専門家」と呼ばれ、会社(法人)について必要となる商業登記や、土地・建物の権利変更について必要となる不動産登記を主な業務とします。
実際には「法律相談や手続き支援を幅広く扱う専門家」であり、相続や相続準備に関する相談・依頼では下の表のような役割を担っています。
| 登記全般 | 相続の際に必要となる登記申請の支援・代理を行う 例:相続登記(相続した不動産の名義変更) |
|---|---|
| 相続手続きの支援 | 相続の状況に合わせた提案やアドバイス、手続きの代理を行う 例:遺産分割の方法に関する相談対応、実行 |
| 必要書類の作成 | 相続手続きのため提出する必要のある書類を代理で作成する 例:遺言書・遺産分割協議書、登記申請書 |
| 添付書類の収集 | 相続手続きのため申請書などに添付する書類を代理で収集する 例:戸籍謄本、固定資産評価証明書 |
登記全般の支援・代理
司法書士は各種登記の申請代理を業務として独占的に行える資格です。登記が必要になる場合として、贈与・売買のほかに相続によって不動産の所有者が変わったとき(不動産登記)や、会社の設立・経営者交代(商業登記)などが挙げられます。
登記の手続きは法務局で行われ、必要な法的書類の作成・内容チェックも司法書士が担います。申請内容に不備があった場合の補正(=申請内容の修正)の対応や、そのほかの法務局とのやり取りも、司法書士が行っています。
相続手続きの支援
司法書士法や司法書士法施行規則では、登記に関する法律相談も司法書士の業務です。ほかにも、判断能力が不十分だとされる人を保護する「成年後見人」としての活動や、長期間にわたり居所がわからない「不在者」の財産を管理する業務も担っています。
こうした専門性は、元気なうちに行う認知症対策・相続対策から、相続が開始された後の手続きに関する提案・アドバイスまで、さまざまな状況で活用されています。相続や遺産分割協議書の内容検討や作成に関することなら、手続きに関する相談対応から代理まで、全般的なサポートができるのです。
必要書類の作成
司法書士が行う業務には、裁判所に提出する書類の作成も含まれています。依頼があれば、銀行そのほかの民間の窓口が求める書類についても、依頼人の代わりに作成・提出する業務も担っています。
具体的には、相続する権利の放棄(相続放棄)や、遺産分割のため特別代理人の選任などの際、そのために家庭裁判所に提出する申述書・申立書などを司法書士が作成しています。こうした手続きが必要ない場合でも、関係各所で随時求められる「相続関係説明図」などの書類の多くは司法書士が作成しています。
添付書類の収集
司法書士は、依頼された内容や範囲により、市区町村役場そのほかの関係各所への書類請求を代理で行うことができます。相続手続きでは、戸籍謄本や固定資産評価証明書などの交付請求を委任できます。
上記の書類は、登記に関わる手続きで申請書・申立書などに添付します。手続きの代理では、これらの添付書類を集めるのも司法書士の業務です。
相続を司法書士に依頼した方がよいケース
司法書士が専門とする不動産登記は、スムーズかつ確実に実施したい手続きです。財産を受け継ぐための遺言書・遺産分割協議書の作成や、その内容の実現、やむなく相続する権利を手放すための相続放棄も、適切に行う必要があるといえます。
ここで解説するように、相続手続きに対応するための時間的なゆとり・知識などに不安があるときは、司法書士に依頼した方がよいでしょう。
相続登記
土地・建物の所有者が亡くなったときに行う相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)は「提出書類の数が多い」などの理由で複雑です。自分たちで行うことも不可能ではないものの、相続登記に関連する手続きは司法書士に代理してもらうのが確実だといえます。
司法書士に相続登記を依頼した方がいい場合として、下記のような状況が挙げられます。
- 登記の知識がまったくない
- 書類収集・作成のための時間がない
- 相続人の数が多く、多数の戸籍謄本が必要になる
- 複数の土地・建物があり、同時申請の件数が多い
- そもそも不動産の所有状況がわからない
- そもそも相続人の数や状況がわからない
- 売却そのほかの利活用を急いでいる
不動産の相続登記は、土地・建物をもらい受けるべき人が決まりしだい、なるべく早く完了させるべきでしょう。登記の完了によって法務局での所有者情報(登記名義人)が書き換わった後にならないと、利活用したくても、買主・不動産会社・入居者などの第三者との取引できないためです。
なお、令和6年4月1日以降は3年以内の相続登記が義務付けられ、違反した場合は10万円以下の過料が科される点に要注意です。それ以前に、相続税の申告期限である10か月以内には登記を完了させ、いくら課税されるのかを計算できるようにしなければなりません。

抵当権抹消登記
土地や建物を相続するとき、たとえ団体信用生命保険などによって住宅ローンの支払いが終わっていても、銀行(金融機関)が設定した「抵当権」が残ったままになっていることがあります。この場合、金融機関から受け取った書類で「抵当権抹消登記」を申請しなければなりません。
抵当権抹消登記も、迅速かつ確実な実施を求めるのであれば、司法書士に依頼すべきだと言えます。具体的には、下記のような状況が挙げられます。
- 抵当権抹消の手続きに慣れていない
- 銀行発行の書類の内容がわからない
- 相続登記と同時に抵当権抹消も行いたい
- 登記用の書類の有効期限が迫っている
- 銀行との連絡調整が面倒だと感じる
- 不動産の売却を急いでいる
抹消登記の多くは、売却あるいは不動産を担保として融資を受ける際に、相手方と取引するための条件として、取引の直前に行います。
遺言書の作成・検認、遺言執行
遺言書は、作成者が亡くなった後に財産をどう分割するか判断し、その内容に法的な効力を持たせるための大切な書面です。遺言の内容を実現する手続き(遺言執行)では、預貯金の払戻し・証券の移管・不動産登記といった資産ごとの対応が必要です。
こうした複雑な状況を最後まできちんと行うため、下記のようなときは司法書士に依頼するとよいでしょう。
- 確実に有効な遺言書を作成したい
- 公正証書遺言の作成で証人が必要になった
- トラブルにならないよう遺言の内容について検討したい
- 遺言執行者に指定されたが何をすればよいかわからない
- 遺言内容に不動産の名義変更が含まれている
遺言書には複数の形式(遺言方式)があります。作成の手軽さの面では「自筆証書遺言」が選ばれがちですが、作成するときの方式が厳格に定められているため方式違背により無効になるリスクが高い点や、執行前に「検認」が必要となる点が問題です。公証役場で作成する「公正証書遺言」は、有効性に信頼がおけるものの、作成時に証人の用意が欠かせません。
以上のように、遺言書とその内容の実現では「生前」も「相続開始後の対応」でも慎重な対応が求められます。
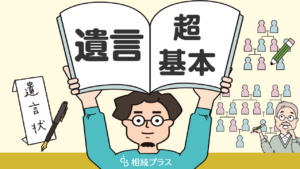
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、相続人全員で合意した内容を正確に記載し、実務的には遺産の名義変更の際に必要となるものです。登記申請する人向けに法務局でひな型の公開がされていますが、合意する内容も文面も状況次第です。
こうした財産の法的な帰属先に関わる文書の作成は、司法書士に任せるのが望ましいです。とくに下記のような状況のときは、専門家による作成が必要です。
- 不動産の分割方法がわからない
- 法的に有効な文書の作成経験が浅い
- 相続人同士の意見調整に第三者の助言が欲しい
- 相続人の数が多く、全員の合意を取りまとめるのが困難
- 実印、印鑑登録証明書、印鑑登録証明書の準備・管理が大変
上記の中で特に難しいのは、不動産の分割方法がわからないにおける「土地・建物の取り分の決め方」についてです。この場合、共有や単独での取得や、単独で取得する人がほかの相続人に代償金を払うなどの方法がありますが、現在の用途と将来の利活用を考えて適切に判断しなければなりません。こうした判断は、登記を通じて不動産の知識を有する司法書士の得意分野でもあります。
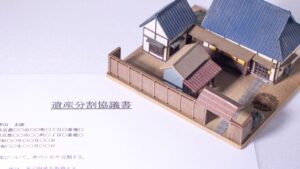
相続放棄
負債などを理由に行う「相続放棄」は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。時間的制約が厳しく、申述書の記載内容や添付書類に不備があると受理されないため、確実な対応が必要です。
確実に相続放棄を実行できるよう、とくに下記のようなケースでは、司法書士に手続きを代理してもらうようにしましょう。
- 相続放棄の期限が迫っている
- 申述書の書き方がわからない
- 必要な戸籍謄本などの収集が難しい
- 借金の額や相続財産の全体像が把握できない
- ほかの相続人も同時に放棄したいと考えている
- 放棄後の財産管理について不安がある
相続放棄は一度行うと撤回できないため、慎重な判断が必要です。司法書士に相談することで、相続放棄が最適な選択かどうかを含めて適切なアドバイスを受けることができます。

司法書士が対応できないケース
司法書士は相続手続きにおいて幅広い業務を担うことができますが、法律で定められた業務範囲があるため、すべての相続問題に対応できるわけではありません。
ここで紹介する状況に当てはまるときは、その分野に詳しい別の士業に相談するか、相談先の司法書士から連携してもらう必要があります。
相続人同士に争いがある場合は対応できない
相続人同士でもめ事になっている状況は、司法書士だと対応できません。司法書士は当事者のあいだでスムーズに合意できるときの手続きを専門としており、相続人同士の対立を調整したり、代理人として交渉を行う権限は持っていないためです。
訴訟代理権(協議・調停・訴訟での代理権)を持っているのは弁護士です。同じ相続手続きの依頼であっても、下記のような場合は、司法書士ではなく弁護士に相談しましょう。
- 遺産分割の割合でもめている
- 遺言書が無効になるかもしれない
- 遺贈(遺言による贈与)が多すぎる
- 遺留分(最低限保障される取り分)を請求したい・請求されている
相続税申告についての相談には対応できない
相続が開始すると10か月以内に相続税の申告・納付が必要となりますが、税に関する相談は税理士の専門です。相続登記した不動産について課税がある場合は、司法書士から税理士に連携をとってもらうことになるでしょう。
なお、次のようなケースでは、基本的に税理士が相談先となります。
- 相続財産の評価額・課税額を計算したい
- 相続税の申告書作成・提出を任せたい
- 準確定申告(最終年度の所得税申告について相談したい)
- 生前のうちに対策し、相続税の課税額を小さくしたい
- 税務調査への対応を任せたい
資産によっては名義変更に対応できない(自動車など)
司法書士は不動産のほかに預貯金、証券(株式や債権など)の名義変更に対応していますが、資産によっては別の士業に任せる必要があります。亡くなった人の財産に下記のような資産が含まれるときは、それぞれの専門家に相談しましょう。
- 自動車(行政書士)
- 個人事業主の許認可(行政書士)
- 特許・商標などの知的財産権、産業財産権(弁理士または行政書士)
- 保険金請求権など(保険会社と直接やりとりする必要あり)
信頼できる司法書士の探し方

相続手続きを司法書士に依頼するときは、相続分野での経験や実績、対応するための体制やコミュニケーション能力などをチェックしましょう。信頼できる人物の特徴として、次のようなことがいえます。
- 相続関係業務の経験が豊富である
- 異分野の士業と連携している
- 事務所に通いやすい・相談方法や時間帯が利用しやすい
- コミュニケーションがとりやすい
相続関係業務の経験が豊富である
司法書士の業務は実にさまざまで、得意とする分野は人によってさまざまです。依頼先を選ぶときは、過去の実績を確認し、相続に関係する業務の取扱い経験が十分か確認しましょう。実績数だけでなく、相談したいこと・依頼したいことに内容が近い経験があるかどうかも要確認です。
異分野の士業と連携している
相続手続きには複数の分野の内容が含まれており、司法書士だけでは解決できないことも多々あります。相談の手間や情報共有のスムーズさを考えて、弁護士・税理士・行政書士などのほかの士業との連携が取れている人物を選びましょう。異分野との連携があることで、難しい悩みや依頼でもワンストップで解決できます。
事務所に通いやすい・相談方法や時間帯が利用しやすい
相続手続きは数か月から1年以上かかることがあり、そのあいだに何度も司法書士との協議や面談があります。事務所の立地やアクセスの良さ、利用しやすい相談方法や時間帯も大切な要素といえるでしょう。とくに、オンラインでの対応があれば、移動時間ゼロでコンタクトできるため便利です。
コミュニケーションがとりやすい
相続は多くの法律知識を必要とする分野であり、状況や手続きの内容についてわかりにくいと感じることが多々あります。司法書士とのやりとりでは、わからないことを明確にできるよう、親切で説明が上手く、コミュニケーションのスタイルが合う人物を選びたいところです。初回相談を活用し、複数の司法書士のなかから相性がよい相手を選ぶとよいでしょう。
司法書士への費用の相場
司法書士に相続手続きを依頼する際の費用は平均すると7万5000円ですが、業務内容や案件の複雑さによって大きく変わります。ここでは、不動産登記の相場と、その費用の考え方について整理してみましょう。
相続登記の司法書士報酬の相場は5万から15万円程度
相続登記を司法書士に依頼したときの報酬相場は5万円から15万円程度です。必要な報酬額は、不動産の評価額や件数によって変動します。一般的には、評価額が高い不動産や複数の不動産がある場合は、報酬額が上がる傾向にあります。
令和6年に実施された司法書士報酬に関するアンケート調査では、司法書士1,109人を対象に報酬の調査が行われています。この調査では、土地1筆・建物1棟の合計で固定資産評価額の合計が1000万円となる不動産を3人で相続(うち1人が単独で取得)したケースで、報酬について次のような回答がありました。
| 司法書士報酬 | 回答数(有効回答数に対する割合) |
|---|---|
| 5万円台 | 203(18.3%) |
| 6万円台 | 188(16.9%) |
| 7万円台 | 168(15.1%) |
| 8万円台 | 161(14.5%) |
| 9万円台 | 68(6.1%) |
| 10万円台 | 72(6.4%) |
| 4万円台以下の合計 | 151(13.6%) |
| 11万円台以上の合計 | 98(8.8%) |
| 平均 | 7万4888円 |
司法書士報酬以外にも費用がかかる
相続登記では司法書士報酬以外にもさまざまな費用が発生します。最も大きな費用は登録免許税で、不動産の固定資産税評価額の0.4%を法務局に納める必要があります。
仮に実勢価格(売買するときの価格)が2000万円の不動産を相続し、固定資産税評価額は実勢価格の8割になるものとして、登録免許税を計算してみましょう。
- 実勢価格:2000万円
- 固定資産税評価額:2000万円×0.8=1600万円
- 相続登記の登録免許税:6万4000円
なお、固定資産税評価額は市区町村が3年おきに定めており、かならずしも実勢価格に対する一定の割合になるとは限りません。
上記以外にかかるものとしては、戸籍謄本や除籍謄本、住民票、印鑑登録証明書などの各種証明書の取得費用があります。これらの書類の交付を受けるときは、交付手数料として数千円から1万円程度かかります。ほかに、登記事項証明書や固定資産評価証明書の取得費用なども必要です。
相続登記の司法書士報酬が高くなるケースもある
基本的な相続登記であれば上記の相場内で納まることが多いものの、難易度の高い依頼は報酬額が高くなる場合があります。具体的には、次のような場合です。
- 相続人が多数いる場合
- 登記を要する不動産の数が多い場合
- 相続関係が複雑で戸籍調査に時間がかかる場合
- 農地相続など、相続登記だけでなく別途届出などの手続きが必要になる場合
- 2人以上で1つの土地・建物を共有しており、共有持分の整理が必要になる場合
また、事務所によっては、初回相談料や調査費用がかかる場合もあります。依頼するときは、あらかじめ費用の内訳を詳しく説明してもらうことが大切です。
相続登記に限らず、遺産に関する手続きの相談は司法書士へ
司法書士は「登記の専門家」として、相続でも重要な役割を果たしています。得意とするのは不動産の名義変更(相続登記)ですが、遺産分割協議書の作成、相続放棄など、多くの手続きで頼りになります。
信頼できる司法書士を選ぶときは、相続業務の経験や他士業との連携体制、コミュニケーションの取りやすさなどを総合的に判断しましょう。初回相談では「そもそも司法書士で対応できる内容か」「費用総額と内訳はどのくらいになるのか」も忘れずチェックすることが大切です。