「亡くなった親が賃貸アパート暮らしだったけど借りていた部屋はどうする?」被相続人が賃貸物件に暮らしていた場合、賃借権も相続の対象となります。賃借権を相続した場合、住むか解約するかの選択が必要です。この記事では、賃借権の相続について相続後の対処法や注意点などをわかりやすく解説します。
賃借権は相続される
賃借権とは、賃料を支払うことで借りたものを利用する権利です。賃貸借契約に基づいて発生し、賃借人(借主・居住者)は住むために建物を使用する権利を得る一方で、賃料を支払う義務を負います。
被相続人が生前賃貸アパートやマンションで暮らしていた場合、被相続人と家主との賃貸借契約に基づいて賃借権が発生しています。そして、この賃借権は相続の対象です。相続財産は現預金や不動産などの目に見える財産だけでなく、不動産上の権利や著作権といった被相続人が有していた権利も含まれます。賃借権も相続財産に含まれるため、相続発生後は建物に住む権利と賃料を支払う義務が相続人に相続されるのです。
賃借権の相続が発生する場合、相続人全員で賃借権を共有する準共有状態となります。相続人が複数人いる場合は、それぞれが法定相続分に応じて借りている部屋を使う権利と賃料を支払う義務を負うことになるのです。
とはいえ、賃借権を相続人全員で共有するのは現実的ではないため、実際は遺産分割協議や遺言により特定の相続人が引き継ぐことになります。相続人が決まるまでは準共有状態が続くので、賃料の支払いなどでトラブルになりやすい点は注意しましょう。
なお、被相続人が賃貸暮らしでも終身建物賃貸借契約の場合は、賃借権の相続は発生しません。終身建物賃貸借契約では借りた人が亡くなった時点で契約が終了するため、賃借権が相続財産にならないのです。被相続人が賃貸暮らしだった場合は、まず賃貸借契約の内容を確認するようにしましょう。

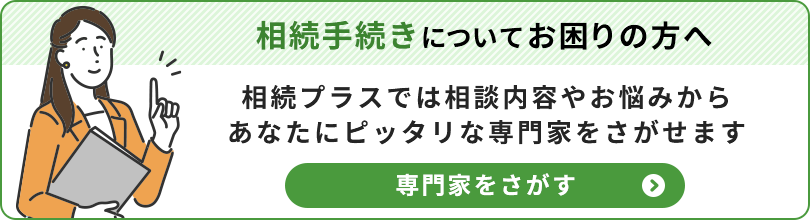
賃借権を相続した場合の対処方法
賃借権に相続が発生する場合、以下のような対処方法を検討できます。
- 相続した人が住み続ける
- 賃貸借契約を解除する
- 相続放棄をする
相続した人が住み続ける
賃借権は相続財産であるため、遺産分割協議で相続する人を決められます。相続人で話し合い誰が相続するか決まったら、その相続人は単独で住むことが可能です。家主に新しい賃借人を伝える必要はありますが、相続人が新たに住むことに対して家主の同意や承諾料、新たな契約手続きなどは必要ありません。
ただし、新たな賃借人と家主でトラブルになりやすいため、相続で賃借権を引き継ぎ合意を得た旨など書面にしておくことをおすすめします。また、相続人を明確に提示できるように遺産分割協議書を作成しておくことも大切です。
なお、相続が決まるまでの間も賃料は発生します。この場合は、相続人全員で法定相続割合に応じて賃料を負担することになります。相続人の誰か1人が代表として支払った場合は、別の相続人に賃料分を請求することが可能です。相続人の確定以降は、賃借権を引き継いだ相続人で負担することになります。
賃貸借契約を解除する
相続人の誰も住まない場合は、賃貸借契約の解除が可能です。契約を解除するまで賃料は発生し続けるので、早めに解除の手続きを進めましょう。
複数人の相続人が賃借権を共有している状況の場合、契約解除するには全員の同意が必要です。一方、遺産分割協議で特定の相続人が賃借権を引き継いだ後なら、その相続人単独で契約を解除できます。
また、解除手続きは賃貸借契約の規定に従って行う必要があります。一般的には「解約の1か月前に申し出る」などの中途解約の規約が定められているので、契約内容にあわせて手続きを行っていきましょう。
なお、相続人は敷金返還を請求する権利も引き継ぐため、契約解除にともない敷金返金を請求することが可能です。複数相続人がいる場合は、法定相続分に応じた敷金を請求することになります。遺産分割協議で特定の誰かが敷金を受け取ると決めるケースが多いでしょう。解約を視野に入れて遺産分割協議を行う場合は、返金される敷金についても考慮することが大切です。
相続放棄をする
相続放棄することで賃借権を相続することはなくなり、賃料の支払いや契約の解除も必要なくなります。しかし、相続放棄の時点で現に不動産を占有していた場合、次の相続人もしくは相続財産清算人が決まるまでは、建物の管理義務が残る場合がある点には注意が必要です。
管理義務がある状態で管理を放置し、周囲に迷惑をかけると損害賠償請求される恐れがあります。相続放棄する場合は、次の相続人への連絡や相続財産清算人選定手続きなども考慮することが大切です。
また、相続放棄すると賃借権以外の相続財産も取得できなくなります。賃借権はいらないけど現預金や他の不動産は相続したいといった場合は、相続放棄は適切ではないので別の手段を検討したほうがよいでしょう。賃借権を相続放棄したほうがよいか悩む場合は、相続放棄の手続きとあわせて専門家への相談をおすすめします。
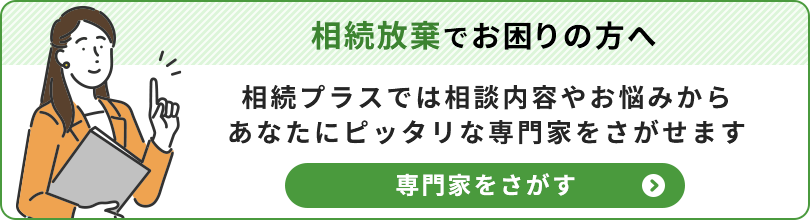
賃借権の相続に関する注意点

賃借権の相続では賃料の支払いなどを巡ってトラブルになる恐れもあります。以下の注意点を理解し対処方法を検討することが大切です。
大家側から立ち退きや承諾料を請求することはできない
賃借権は相続財産であるため、被相続人が死亡したからといって大家側から簡単には立ち退き請求できない可能性があります。また、相続人が新たな賃借人になる場合でも、名義書き換えなどの名目での承諾料は不要です。仮に、請求された場合でも応じる必要はありません。
賃料を滞納すると契約を解除される可能性がある
相続後契約を解除するまでは賃料が発生し続け、相続人は賃料を支払う義務を負います。相続したからといって立ち退きを請求されることはありませんが、賃料を滞納すると契約解除される恐れがあるので注意が必要です。
1か月程度の滞納で解約されることはないでしょうが、3か月程度滞納すると解約される可能性が高くなるでしょう。
賃借権の相続人が確定するまでの間は、相続人全員で賃料を負担するため、賃料の支払いが滞りやすくなります。相続後に賃貸に住みたい場合は、賃料の延滞が起きないように注意しましょう。
契約内容によっては賃借権を相続できないこともある
前述のとおり、終身建物賃貸借契約は被相続人の死亡によって契約が終了するため、賃借権は相続されません。また、期間付死亡終了建物賃貸借契約も相続はできないので注意が必要です。
期間付死亡終了建物賃貸借契約は、定期借家契約と終身建物賃貸契約を合わせた契約内容になります。契約時に一定の契約期間を設けており、契約終了か契約者の死亡どちらか早い方で終了となる契約です。この場合も、死亡により契約が終了するため、賃借権は相続できません。
賃借権が相続できるかは契約内容によって異なるため、事前に契約内容を確認することがとても大切です。
内縁の配偶者であっても賃借権の建物に住み続けることはできる
内縁の配偶者は、戸籍上配偶者ではないため相続権はありません。しかし、内縁の配偶者であっても以下のケースでは賃借権を引き継いで住み続けられます。
- 被相続人に相続人がいない
- 相続人がいる場合は賃借権の援用ができる
被相続人に相続人がいない場合、内縁の配偶者は賃借権の引き継ぎが可能です。賃借人の内縁の配偶者を保護するよう法律で定められており、賃借人が亡くなったからといって内縁の配偶者が追い出されることはありません。
また、相続人がいる場合は基本的に相続人が賃借権を引き継ぐので、内縁の配偶者は賃借権の引き継ぎができません。ただし、この場合でも相続人の持つ賃借権の援用という形で賃借権が主張でき、追い出されないのが一般的です。
ただし、内縁の配偶者が住むためには賃料の支払いが必要です。賃料を延滞すると追い出される可能性があるため、相続人がいるケースでも相続人に代わって賃料を支払うなど契約解除されないように注意しましょう。

公営住宅の賃借権は相続で引き継がれない
公営住宅とは、低所得者などの住宅の確保が難しい人を対象として、廉価の家賃で提供される住宅です。主に自治体が運営しており、県営住宅や市営住宅とも呼ばれます。
公営住宅はそもそも低所得者などに住宅を確保する目的で運営されており、相続人が収入などの条件を満たしていないのに入居するのは目的と反しています。その存在意義から最高裁判所の判例でも公営住宅の賃借権は相続により当然に引き継がれないと判断されているのです。
ただし、低所得など入居基準を満たす相続人であれば、入居の継続を認めてもらえる可能性はあります。この場合、使用権の相続が認められたというわけではなく、自治体の判断で入居が継続されただけという点は覚えておきましょう。
賃借権の相続は専門家に相談を
賃借権は相続の対象となり、相続人は住み続けるか契約解除・相続放棄の判断が必要です。しかし、相続後の対応は一度選択すると容易に戻すことはできません。また、対処法を誤ってしまうと大家とトラブルになる恐れもあるので、相続後の対応は慎重に行う必要があります。
賃借権の相続をどうするか不安がある場合は、相続トラブルに強い弁護士に相談してみるとよいでしょう。


