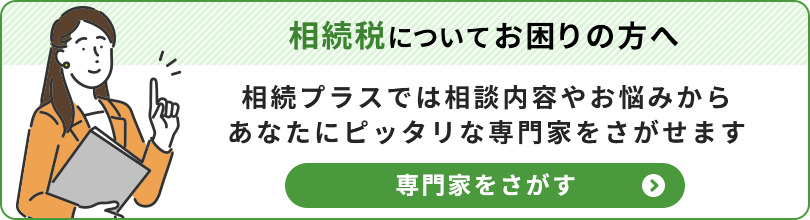令和6年4月より相続登記の義務化がスタートし、相続について専門家へ問い合わせをする方が増えています。なかには専門家の1つである税理士に依頼すべきかどうか悩む方もいるでしょう。本記事では、税理士の役割や税理士に依頼した方がよいケースについて詳しく解説します。税理士のさがし方や報酬目安についても解説しているため、ぜひ参考にしてください。
目次開く
税理士の立ち位置
相続が発生したからといって、必ずしも税理士への依頼が必要とは限りません。税理士の役割は税務に関するサポートのため、相続税や贈与税などの税金が発生しない相続では必要性が感じにくいかもしれません。
ですが、税理士は相続税や贈与税の専門家であり、相続税や贈与税などの発生の有無を確認するという立ち位置は重要であると言えます。
そして税理士の主な業務内容は、下記のようになります。
- 税務代理
- 税務書類の作成
- 税務相談
上記の3つは、税理士法によって税理士だけに認められている独占業務です。税理士以外の士業がおこなうことはできません。3つの業務内容について、詳しく確認しましょう。
税務代理
納税者の代理人として税務署への申告・申請などを行う税務代理は、税理士にとっての基本業務です。相続の場合、相続税や贈与税などの申告を相続人などに代わって行います。同様に、所得税や消費税などの確定申告も税理士による代行が可能です。
万が一、不備や税務調査がある場合には、代理で申告・申請した税理士に対して税務署から問い合わせがあります。あわせて、税務署への対応も税理士に任せられます。
税務書類の作成
税務署に対する提出・申告にかかる税務書類の作成も税理士が担う業務です。税理士が専門知識を用いて、相続税や贈与税などの申告書類を代行して作成します。
相続税の申告書は第1表から第15表まであり、控除・特例の利用にあわせて必要な作成書類を把握しなければなりません。相続税の申告の際には膨大な量の申告書類を記入する必要がありますが、税理士に依頼すればすべて作成を任せられます。
税務相談
税金に関する相談も税理士が担う業務の1つです。生前にできる相続税対策から相続発生後の特例・控除の活用、発生する税金の計算まで幅広い税務相談に乗ってもらえます。
相続における税金対策はさまざまありますが、資産状況や家族・親族の人数、関係性などによって活用できる控除や特例が異なります。適切な節税対策をするために税理士へ税務相談はもちろん、そもそも相続税の申告義務があるかどうかの判断を相談することも可能です。
相続を税理士にも依頼した方がよいケース
相続が発生した際、税理士に依頼すべきかどうかの大きな判断基準として、「相続財産の総額が基礎控除額を超えているか」は大きなポイントです。
そもそも、相続が発生したとしても相続税の申告が必要であるとは限りません。相続財産の総額が基礎控除額を超えている場合に、相続税の申告義務が発生します。
もちろん、自分で相続税の申告を行うことも可能です。相続について税理士に依頼すべきかどうか悩む場合、下記に当てはまるケースのであれば税理士へ依頼することを検討しましょう。
- 評価の難しい財産がある場合
- 遺産総額が多額の場合
- 相続人が複数人いる場合
- 相続税申告をすべて任せたい場合
- 相続税の控除や特例の対象となるのか判断が難しい場合
- 準確定申告をする必要がある場合
- 税務調査リスクをできるだけ軽減したい場合
ただし、税理士によるサポートの範囲は、あくまでも税務関連に限られます。遺産分割や相続手続きについて相談したい場合は、司法書士や弁護士に相談するとスムーズです。
それでは相続を税理士にも依頼した方がよいケースについて、詳しく解説します。
評価の難しい財産がある場合
相続財産のなかに評価の難しい財産が含まれている場合、税理士に依頼することをおすすめします。なぜなら、評価額の算定によって相続税が発生するかどうかが変わるからです。
相続税の申告で複雑で難しいといわれている作業の1つが財産評価です。金融機関の預金や現金はそのままの金額ですが、不動産や証券、美術品などは相続税計算のために評価額を算定する必要があります。
財産評価は、単純に市場価格や購入時の価格ではなく、相続税法や財産評価基本通達にもとづいて行わなければなりません。
評価の難しい財産がある場合は、税理士に依頼して正しく評価してもらうことを推奨します。
遺産総額が多額の場合
遺産総額が多額となる場合、税計算が複雑になるため税理士への依頼が望ましいです。
具体的には、遺産総額が基礎控除額を上回っているときと考えておきましょう。基礎控除額の算出方法は、下記の通りです。
- 相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
相続財産の総額が基礎控除額を超えなければ相続税の申告・納税は不要です。
一方、相続財産の総額が基礎控除を超える場合、相続税が発生しなかったとしても申告義務が発生します。なお、相続税の申告において税理士が関与している割合は令和5年度で86.3%となっており、多くのケースで税理士を頼っていることがわかります。
相続税の申告書類を作成するには専門知識が必要となるため、税理士に依頼することが一般的です。
相続人が複数人いる場合
相続人が複数人いる場合、申告書類の作成や相続税の計算が複雑化するため税理士への依頼を検討しましょう。
2人以上の相続人がいる場合、共同で申告書を提出するか、個別に申告書を提出するかを選ぶことになります。しかし、個別で申告書を作成すると整合性が取れずにトラブルへ発展する恐れがあります。
そのため、共同申告が望ましいとされており、相続人全員で1人の税理士に依頼するとスムーズに手続きを終えられるでしょう。
また相続税は、単純に相続した財産の額に課税されるのではなく、一度法定相続分通りに遺産分割したと仮定して、相続税の総額を計算しなければなりません。さらに、実際の相続割合に応じて按分する必要があり、税額の算出は複雑です。
このように、相続人が複数人いる場合の相続税の計算や申告は難しいため、税理士の力を借りることをおすすめします。
相続税申告をすべて任せたい場合
相続税申告に割く時間のない方や、知識に自信がない方は、相続税の申告をすべてお任せしたいと考えるのではないでしょうか。税理士であれば、相続税の計算から申告書の作成、添付書類の取得までを丸投げできます。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。日常生活を送りながら期限内に相続税申告を行う自信のない場合は、税理士に丸投げすることを選択肢の1つとして検討しましょう。
相続税の控除や特例の対象となるのか判断が難しい場合
相続税の控除や特例を活用したくても、控除や特例の適用対象となるのか判断できない場合や控除・特例を適用させたときの税計算が難しい場合は、税理士の力を借りましょう。
相続で多いケースとしては、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の活用が検討されます。しかし、それぞれに細かな適用要件が定められており、対象となるかどうかの判断がしづらい場合もあるでしょう。
また、控除・特例を適用させた税計算はとても煩雑です。条件や相続発生のタイミングによっても計算方法が異なるなど、気をつけるべきポイントがたくさんあります。
なお、相続税の控除や特例の制度を活用して納める相続税額が0円になったとしても、申告書の提出が必要となるため注意しましょう。
準確定申告をする必要がある場合
年の途中で亡くなった方の所得について、1月1日から亡くなった日までの所得や税額を確定させて申告することを準確定申告と呼びます。準確定申告は、相続人が行わなければなりません。
準確定申告の必要性は、前年に亡くなった方が確定申告をしていたかどうかを1つの判断基準にするとよいでしょう。下記のようなケースでは、準確定申告が不要となる可能性があります。
- 亡くなった方が会社員・パートなどの給与所得者かつほかの所得はなかった
- 亡くなった方が年金受給者(受給額400万円以下・他所得が20万円以下)だった
ただし、準確定申告が不要だったとしても、下記のようなケースでは還付金が受け取れるかもしれません。
- 年末調整を勤め先で行っておらず、源泉徴収によって税金を納めすぎていた場合
- 生前の医療費や介護費が高額で、医療控除を受けられる場合
- 配偶者控除や扶養控除、特定寄付などの控除を受けられる場合
なお、準確定申告と納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。正しく期限内に準確定申告をするためには、相続発生後すぐに準備を始める必要があります。
準確定申告に時間を割けられない方や知識に不安がある方は、税理士に依頼することを検討しましょう。
「準確定申告」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
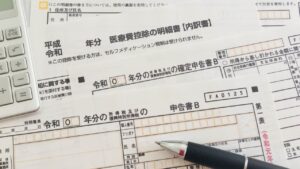
税務調査リスクをできるだけ軽減したい場合
税務調査リスクを可能な限り減らしたい場合にも、税理士に依頼することをおすすめします。
所得税や法人税など、さまざまな税金に関しての税務調査が行われていますが、相続税は比較的高額な税収が見込まれるため、税務調査が入りやすいといわれています。
令和5年においては、相続税申告15万5740件のうち、相続税の実地調査件数は8,556件と5.4%の割合で税務調査が行われました。さらに、税務調査が行われたうちの84.2%が申告漏れの指摘を受けています。つまり、税務調査が実施されると高い確率で追徴課税となってしまいます。
はじめから税理士に相続税の申告をサポート・代理してもらっていれば、税務調査の対応もお任せできます。税務調査の連絡がきてから税理士をさがしても、なかなか依頼を受けてもらえないこともあるため注意しましょう。
税理士に依頼しなくてもよいかもしれないケース
相続発生にあたって、税理士の力を借りなくてもよい可能性のあるケース例をご紹介します。
- 相続税の申告義務がない場合
- 評価の難しい財産がない場合
- 相続登記の手続きがメインの場合
- 遺産分割で揉める可能性が高い場合や相続放棄を検討している場合
上記のような悩みがメインなら、税理士以外の専門家に依頼するとスムーズに手続きを済ませたり、トラブルを解決したりできるでしょう。ケースごとに相談先候補もご紹介しているため、ぜひ参考にしてください。
相続税の申告義務がない場合
相続税の申告義務がない場合、あまり税理士との関わりは少なくなるでしょう。そもそも、相続税の申告は相続財産の総額が基礎控除額を超えていなければ、相続税の申告義務はありません。もちろん、場合によっては税務観点からのアドバイスが必要となる場合もあります。
ただし、控除や特例などを適用させて相続税が0円になる場合には、相続税の申告義務はなくなりません。申告をもって控除や特例を適用させられるため、注意しましょう。
相談先候補
相続税の申告義務がない場合、相続の相談は司法書士や弁護士、行政書士に依頼することをおすすめします。相続手続きのサポートであれば司法書士や行政書士、相続トラブルのリスクがある場合は弁護士と考えておくと、スムーズに悩みを解決できます。
評価の難しい財産がない場合
不動産や証券、美術品などの評価しづらい財産が遺産に含まれていない場合、税理士に依頼しなくても税知識を持ち合わせていれば遺産総額を自分たちで計算しやすいでしょう。
例として、亡くなった方が持ち家以外に住んでいて、相続財産の内容が現金や預貯金に限られている場合が挙げられます。相続財産の総額が把握しやすいため、相続税の申告義務があるかどうかの判断も難しくありません。
相談先候補
評価の難しい財産がない場合、司法書士や行政書士に相続手続きのサポートを依頼するとよいでしょう。法定相続分通りの遺産分割がしやすく、相続トラブルに発展しづらいためです。
ただし、遺言書の内容に納得がいかない場合や法定相続分以上の取り分を主張する相続人がいる場合などは相続トラブルを引き起こす可能性があります。トラブルが予測される場合は弁護士に相談することをおすすめします。
相続登記の手続きがメインの場合
相続財産のほとんどが不動産で、相続手続きの多くが相続登記を占める場合、税理士の出番がないかもしれません。なぜなら、相続登記の手続きの代理を税理士に依頼できず、任せられることが少ないからです。
不動産の相続登記をする際に、不動産の固定資産税評価額を知ることが可能です。相続税の評価額とは異なる数値ではあるものの、おおよその評価額がわかるため相続税の申告義務があるかどうかの判断もしやすいでしょう。
ただし、税理士以外の専門家には、原則不動産の相続税の評価額計算を依頼できません。不動産の評価額によっては相続税申告の義務が発生する点に注意しましょう。
相談先候補
相続登記の手続きがメインとなる場合、司法書士に依頼するとスムーズに手続きを終えられます。相続した不動産の名義を変更する相続登記を代行できる専門家は、司法書士のみです。
なお、令和6年4月から相続登記が義務化されました。令和5年4月以降に発生した相続について、正当な理由なく相続発生から3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料が科される場合があるため、早めに相談することを推奨します。
「相続と司法書士」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

遺産分割で揉める可能性が高い場合や相続放棄を検討している場合
遺産分割で揉める可能性がある場合や相続放棄を検討している場合、税理士の力で解決を図ることは難しいと考えておきましょう。
例えば、下記のようなケースでは遺産分割で揉める可能性があります。
- 相続人全員が納得できない内容の遺言書が見つかった
- 亡くなった方に婚外子や前妻の子どもがいると発覚した
- 不動産や美術品など物理的に分割できない遺産があった
- 相続財産のなかに負債が含まれていた
また、相続人同士の仲が悪い場合や相続財産のなかに負債が含まれている場合、相続放棄を検討する方もいるでしょう。相続放棄に関する手続きの代行は税理士の業務外となるため、相談したとしても簡単なアドバイスにとどまると予想されます。
相談先候補
遺産分割についてトラブルに発展するリスクがある場合や、相続放棄を検討している場合は弁護士に相談しましょう。
弁護士は、トラブルの防止や解決に向けて頼りになる法律の専門家です。遺産分割の話合いの場に立ち会ってもらえれば、法的なアドバイスを受けながら冷静な話合いが実現できるでしょう。万が一、調停や控訴、裁判に発展した際にも代理人として裁判所へ出向いてもらえます。
また、相続放棄を検討している場合にも、弁護士にすべてお任せできます。相続放棄が認められる期間は相続の開始があったことを知った日から3か月と短く、素早い判断が必要です。
相続放棄をするかどうかの判断はもちろん、必要な書類作成や家庭裁判所での手続きも弁護士に依頼できます。
「相続と弁護士」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

信頼できる税理士をさがすポイント

税理士に依頼したいことがあっても、どのように税理士をさがすべきか悩む方も多いでしょう。
ここでは、信頼できる税理士をさがすポイントを5つご紹介します。
- 相続関係業務の経験が豊富である
- ほかの士業と連携している
- 税理士事務所へ通いやすい
- スムーズにやりとりできる
- 適正な料金設定がされている
詳しく確認していきましょう。
相続関係業務の経験が豊富である
まず、相続税や準確定申告などの相続関連業務の経験が豊富な税理士を選びましょう。
税理士と一口にいっても、法人の決算業務から個人事業主の確定申告業務など得意な分野がそれぞれにあります。会社でお世話になっている税理士は法人税関連には強くても、相続に関するノウハウがほとんどないというケースは珍しくありません。
相続税を申告する際には控除・特例の適用や財産の評価額計算などを正しく行う必要があります。
相続関係業務に強い税理士事務所であれば、ホームページに相続税申告の年間実績件数が掲載されています。問い合わせ前に確認するようにしましょう。
ほかの士業と連携している
次に、司法書士や弁護士などのほかの士業と連携する体制が整っているかを確認しましょう。なぜなら、相続に関連する手続きを税理士だけで完結することは難しいからです。
例えば、税理士には相続税申告を、司法書士には不動産の相続登記を、弁護士には遺産・相続人調査や遺産分割を依頼することで円滑に相続手続きを進められます。そのため、それぞれの専門知識を持つ士業との連携は欠かせません。
ワンストップで相続に関する手続きを進められるよう、ほかの士業との協力体制が整っている税理士に依頼しましょう。
税理士事務所へ通いやすい
税理士事務所が通いやすい位置にあるかどうかも、税理士を選ぶうえで重要なポイントです。自宅や職場から近い距離にある税理士事務所であれば、提出する書類を届けたり対面での相談をしたりする負担が軽減されます。
相続税申告の依頼をする場合、1度の訪問ですべて完結するケースはほとんどありません。もちろん、電話やメールのやり取りで済む場合もありますが、書類を手元で確認しながら対面で話す方が伝わりやすい内容も当然あります。
円滑に相続税申告を終えるためにも、自宅や職場の周辺で相続税に強い税理士事務所をさがしましょう。
スムーズにやりとりできる
スムーズにやりとりできる税理士かどうかもチェックしておきたいポイントです。
税理士に相続税や確定申告について依頼をしたとしても、書類収集や財産・相続人の洗い出しについては依頼者である相続人が行います。税理士に相談しなければ解決できない疑問点も出てくるでしょう。
そのため、誠実な対応をしてくれるか、スピーディーに返答がもらえるかなどもチェックしておくと安心して依頼できます。
平日の日中仕事をしている方であれば、土日や夜遅い時間にも連絡がつきやすい税理士を選ぶ必要があります。また、対面や電話以外のオンライン相談にも対応していれば、よりスムーズにコミュニケーションが取れるはずです。
依頼者に寄り添った対応をしてくれるかどうかはもちろん、事務所の体制やシステムについても確認しておくことをおすすめします。
適正な料金設定がされている
適正な料金設定がされているかどうかも選ぶポイントの1つです。
報酬が相場と比較して高すぎると、相続した財産のほとんどが手に残らないかもしれません。一方、相場よりも安すぎる料金が設定されている場合にも、依頼した内容を十分に遂行してもらえない可能性があるため注意しましょう。
多くの税理士事務所では、ホームページに料金設定についての記載があります。問い合わせ前に掲載されている料金設定が適正かどうかを確認することはもちろん、あとから追加料金が発生し高額な報酬を請求されないように相談時に見積もりを出してもらいましょう。
税理士報酬の目安については、次の章で解説するためぜひ参考にしてください。
相続税について税理士に依頼したときの報酬目安
相続税に関して税理士に依頼する場合、いくらの料金が必要なのか不安になる方もいるでしょう。ここでは、依頼内容別の報酬目安について解説します。
- 相続税申告を税理士に依頼した場合の報酬目安
- 生前対策を税理士に依頼した場合の報酬目安
税理士に依頼しようかどうか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
相続税申告を税理士に依頼した場合の報酬目安
相続税申告を税理士にすべて依頼するときの報酬目安は、遺産総額の0.5~1%です。例えば、相続財産1億円の場合に税理士へ支払う報酬は50〜100万円と考えておきましょう。
また、下記のようなケースでは、難易度が高まるため追加料金発生の可能性があります。
- 評価額計算を必要とする財産が多い場合
- 相続人の数が多い場合
- 相続税の申告期限が迫っている場合
正式に依頼をする前に相続財産の内容や相続人の数を具体的に伝え、見積もりを出してもらうと安心です。
生前対策を税理士に依頼した場合の報酬目安
相続税について生前対策を税理士に依頼する場合、報酬の相場はないと思っておきましょう。なぜなら、財産状況や家族・親族の関係性などによって提案にかかる労力が大きく変わるからです。
なお、税理士に相談するときの費用相場は30分あたり3,000〜5,000円程度です。つまり、複雑になればなるほど時間を要するため、報酬も高額になります。さらに生前対策プランの提案については、資産総額にあわせて料金設定をしている税理士事務所が多いです。
初回の30分〜1時間程度の相談を無料で受け付けている税理士事務所はたくさんあります。積極的に無料相談を活用し、生前対策プランの見積もりを出してもらうとよいでしょう。
税理士費用は誰が支払う?払えないときはどうする?
相続人が複数人いる場合、税理士費用を誰が支払うべきか悩むかもしれません。誰が税理士費用を支払っても問題なく、相続人同士で話し合って負担割合を決めることが一般的です。
ただし、節税を意識するのであれば、亡くなった方の配偶者が税理士費用を全額負担するとよいでしょう。
配偶者による税理士費用の全額負担に節税効果があるといわれる理由は、下記の通り2つです。
- 配偶者控除による負担軽減
- 二次相続時の負担軽減
順番に見ていきましょう。
配偶者控除による負担軽減
配偶者控除を活用すれば、税負担が軽減されます。配偶者控除とは、亡くなった方の配偶者が相続する額がいずれか大きい額までであれば非課税になる制度です。
- 1億6000万円まで
- 配偶者の法定相続分相当額
相続人が亡くなった方の配偶者と子どもだった場合、配偶者の相続分に税理士費用を上乗せして遺産を分けることで節税につながります。
例えば、配偶者の法定相続分に税理士費用を上乗せしても1億6000円におさまるのであれば、配偶者に相続税は発生しません。もし、1億6000万円を超える法定相続分だったとしても、税理士費用分にのみ相続税が課税されるため、税負担は少ないといえるでしょう。
二次相続時の負担軽減
亡くなった方の配偶者が税理士費用を負担すると、二次相続時における子どもの税負担が軽減できます。二次相続とは、両親のうち1人が亡くなって相続が発生したあとに、その配偶者が亡くなって次の相続が発生することです。
二次相続では1回目の相続よりも相続人の人数が減り、基礎控除の額が下がってしまいます。つまり、相続税申告・納税の可能性が1回目の相続よりも高まります。
そこで、1回目の相続で配偶者が税理士費用を負担しておくと、配偶者の将来的な相続財産を抑えることが可能です。もちろん、財産状況や相続人の数などによって誰が支払うと最適かは異なりますが、原則的に亡くなった方の配偶者が支払うと将来的な税負担を軽減できることを覚えておきましょう。
「税理士費用」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

相続税・準確定申告で困ったら税理士へ相談しよう
相続財産の総額が基礎控除額を上回る場合、相続税申告の義務が発生します。相続税申告の必要がある場合はもちろん、申告義務があるかどうかの判断がつかない場合にも税理士に相談することをおすすめします。
もちろん、自分で相続税の申告をすることは可能です。しかし、相続税の計算は複雑で不備や抜け漏れが多く税務調査の対象になりやすいことも事実です。過少申告をしてしまった場合、ペナルティを課される恐れがあります。
相続について税理士に依頼する場合、相続税に強く、司法書士・弁護士との連携体制がしっかりしている事務所を選ぶことが重要です。相性のよい税理士事務所を見つけ、スムーズに相続手続きを終わらせましょう。