「財産を譲ると口約束したけど有効だろうか?」生前、相続について口約束するケースは少なくありません。しかし、口頭での遺言は法的に無効です。口頭の遺言に近い形で遺産分割できる可能性はありますが、確実ではなく実現できない恐れがあります。この記事では、口頭での遺言の効果や口頭での遺言を実現する方法を解説します。
地元の専門家をさがす
口頭・口約束での遺言は原則無効
口頭・口約束での遺言は、法律的に無効です。仮に、録音や動画などデータとして残している場合でも、遺言としては認められません。また、後述しますが遺言書としての形式を満たす必要があるため、メールやLINEなどで残っている場合でも無効です。
遺言は、「要式行為」に該当し、法的に認められるためには一定の要式を満たす必要があります。要式を満たしていない・違反があるといった場合では、法的効果は不成立・無効となってしまうのです。
第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。※引用:民法|第960条(遺言の方式)
民法で定められた遺言の方式は2つ
遺言が成立する「法律に定める方式」とは、以下の2つです。
- 普通方式:一般的に利用される遺言書の作成形式
- 特別方式:特別な状況下で利用される遺言形式
普通方式の遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、いずれも形式を満たした書面での作成が必要です。
一方、普通方式での遺言が間に合わないというような特別な状況下で認められるのが、特別方式の遺言になります。疾病などで命に危機が迫っている、伝染病で一般社会から隔絶されている、船舶の遭難といった状況下で認められており、状況に応じて必要な要式も異なります。
「遺言」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
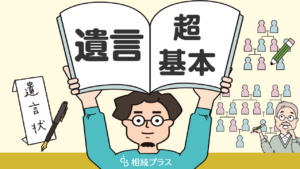
公正証書遺言と危急時遺言は口述によって遺言書を作成することが認められている
普通方式のうち、自筆証書遺言・秘密証書遺言は自分で遺言書を作成し署名捺印が必要となるため、字が書けることが前提となります。しかし、疾病などで字が書けない状況もあるでしょう。字が書けない状況でも、公正証書遺言書と危急時遺言であれば口頭での作成が可能です。
公正証書遺言とは、普通方式の1つで公正役場で公証人に作成してもらう遺言書です。遺言者が口頭で伝えた内容をもとに公証人が遺言書を作成し、遺言者と証人がその内容を確認し署名捺印して作成します。
遺言者が署名できない場合でも、公証人がその旨を記載し代筆できるため字が書けなくても作成することが可能です。また、公証人は病院などに出向くこともできるので、病気で動けない状況でも作成できます。
もう1つの方法である、危急時遺言とは特別方式の遺言の1種です。生命の危険が迫って自分では書けない状況で作成する遺言で、一般危急時遺言と難船危急時遺言の2つがあります。危急時遺言では、遺言内容を口頭で伝え証人が遺言書を作成、内容を確認して証人が署名捺印して作成します。
ただし、証人や家庭裁判所への提出が必要など細かい条件もあるので注意しましょう。危急時遺言については、後ほど解説するので参考にしてください。
上記2つの方法であれば署名できない状況でも作成可能です。また、手話などで伝えても有効となるため、口頭ができない状況でも作成できます。
ただし、どちらも口頭で伝えた後に、形式を満たした書面で作成しなければ認められません。口約束のみで書面にしていない・書面にしても遺言書としての形式が満たせていないといった場合では、法的に無効となるので注意しましょう。
口頭・口約束での遺言を実現させる方法

口頭での遺言は法的に無効ですが、口頭のすべてが無駄になるわけではありません。以下のような方法で口頭での遺言内容を実現できる可能性があります。
- 遺産分割協議で合意する
- 死因贈与を成立させる
- 生前贈与をする
- 要件を満たした遺言書を作成してもらう
遺産分割協議で合意する
遺言書のない相続では、遺産分割協議で遺産の分割方法を決めます。口頭で遺言を聞いていた相続人がその旨を伝えて、他の相続人全員が合意すれば口頭どおりの相続を実現できるでしょう。
ただし、遺産分割協議に参加できるのは相続人となるため、口頭で聞いた人が相続人でなければ遺言の実現が難しくなります。また、相続に全員の合意が必要となるため、口頭での遺言では不利になる相続人がいると合意を得にくい点にも注意しましょう。
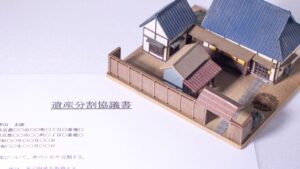
死因贈与を成立させる
死因贈与とは、贈与する人の死亡を原因として成立する贈与です。「自分が亡くなったら財産を渡す」といった死後に発生する贈与になります。死因贈与は、贈与する人(贈与者)と贈与される人(受贈者)の合意で成立し、贈与される人は相続人であるかは問われません。
ちなみに、相続は相続させる人(被相続人)の一方的な意思表示で成立するのに対し、死因贈与は贈与者・受贈者双方の合意で成立するという違いがあります。
死因贈与は口約束でも成立します。そのため、被相続人の口約束を死因贈与と認めてもらうことで、口頭での遺言を実現することが可能です。
ただし、死後に死因贈与を履行することを他の相続人が拒む可能性もあります。他の相続人の承諾を得られない場合は裁判で争うことになります。口頭のみでは他の相続人の同意を得たり贈与の内容を裁判で立証したりすることは難しく、基本的には贈与契約書などの書面が必要になる点には注意しましょう。

生前贈与をする
死亡をきっかけに贈与する死因贈与に対して、生前中に行う贈与が生前贈与です。生前贈与も贈与者と受贈者の合意で成立し、口約束でも有効となります。被相続人の「財産をあげる」という口約束を生前贈与が成立していたと認めてもらう方法も検討できます。
しかし、生前贈与は口頭の場合、贈与の実行前には当事者のどちらかが一方的に契約を解除することが可能とされています。口頭の場合は解除しやすくトラブルにつながりやすい点には注意が必要です。
なお、死因贈与・生前贈与は口頭でも成立するため、録音や動画のデータがあれば立証できる可能性があります。とはいえ、トラブルは起きやすいため贈与契約書などの書面の作成をおすすめします。

要件を満たした遺言書を作成してもらう
被相続人の生前中に口頭で遺言について聞いていたなら、その旨を遺言書に作成してもらうことをすすめましょう。遺言書があれば、口頭の内容をより確実に実現できます。被相続人に口頭では有効にならないことを伝えれば、遺言書の作成を前向きに検討してくれる可能性があります。
ただし、作成する遺言書は要式を満たしていることが重要です。要式を満たさないとせっかく作成しても無効となるので、注意しましょう。また、遺言書作成時には相続トラブルが起きないように考慮することも大切なので、弁護士など専門家にアドバイスをもらうことをおすすめします。

生命の危機が迫った状態で作成するなら危急時遺言
危急時遺言とは、危篤など生命の危険が迫った状況で緊急的に作成する遺言です。書式で残す余裕もない状況であることから、口頭で遺言しても有効となります。ただし、一定の要件を満たす必要はあるので、内容を理解しておくことが大切です。
危急時遺言の種類・要件
危急時遺言には、以下の2種類があります。
- 一般危急時遺言:疾病などで生命の危機が迫っている人に認められる遺言
- 難船危急時遺言:乗船した船の遭難により生命の危機が迫っている人に認められる遺言
また、いずれも口頭で伝えるだけで認められるわけではなく、一定の要件を満たす必要がある点には注意しましょう。種類によって要件は異なりますが、一般危急時遺言では以下の要件を満たす必要があります。
- 遺言者が生命の危急に迫られている
- 証人3人以上の立ち会いがある
- 証人の1人に遺言者が口頭で遺言を伝える
- 口頭を受けた人が内容を書面化する
- 書面にした内容を遺言者と他の証人に読み聞かせまたは閲覧させる
- 証人全員が署名押印すること
なお、一般危急時遺言・難船危急時遺言ともに、危急の状況を脱して普通方式の遺言を作成できるようになった時から6か月生存していると、危急時遺言の効力はなくなります。この場合は、新たに普通方式の遺言を作成しなければなりません。
危急時遺言を行う流れ
ここでは、一般危急時遺言を行う流れを見ていきましょう。大まかな流れは、以下のとおりです。
- 証人3人以上が立ち会う
- 証人の1人に遺言者が口頭で遺言を伝える
- 口頭を受けた人が内容を書面化する
- 書面にした内容を遺言者と他の証人に読み聞かせまたは閲覧させる
- 証人全員が署名押印する
- 家庭裁判所に遺言確認を申し立てる
- (相続開始時)家庭裁判所の検認
証人になれるのは、未成年者および利害関係者以外の人です。具体的には、下記以外の人となります。
- 推定相続人・受遺者、それらの配偶者と直系血族
- 公証人の配偶者・4親等以内の親族、書記および使用人
- 未成年者
上記以外であれば特別な資格は必要ありません。弁護士や司法書士などの専門家にも依頼できるので検討するとよいでしょう。
立会人が揃ったら遺言者が口頭で証人の1人に遺言を伝え、その人が書面を作成します。書面は自筆だけではなくパソコンでの作成でも問題ありません。書面化したら、遺言内容を遺言者と他の証人で確認し、内容が正しければ証人全員が署名捺印します。
また、遺言書は作成しただけでは効力が発生しない点には注意しましょう。作成後20日以内に家庭裁判所に遺言確認を申し立て承認してもらって、ようやく効力が生じます。
なお、遺言確認手続き中に遺言者が死亡したとしても、手続きは有効です。この場合、家庭裁判所に遺言が認められれば、遺言作成時点にさかのぼって効力は発生します。
家庭裁判所に遺言を認めてもらってはいますが、相続開始時にそのまま遺言の執行はできません。相続開始時には、遺言書の検認手続きが必要になる点は覚えておきましょう。
相続をより確実に実現させたいなら公正証書遺言
危急時遺言なら口頭でも作成できますが、生命の危険が迫っている状況のうえ一定の要件を満たす必要があるため、容易にとれる方法ではありません。仮に作成できたとしても状況が状況だけに、焦って希望とは異なる遺言になる・相続トラブルを考慮できていないなども恐れもあるでしょう。
より確実に相続の希望を実現させるには、心身に問題のない時期からしっかり準備し遺言書を作成することをおすすめします。ただし、遺言書は形式を満たせないと無効になる恐れがある点には注意が必要です。
また、自筆証書遺言を自宅で保管していると、相続開始時に見つけてもらえないリスクがある点にも気を付けましょう。リスクを軽減するためにも、公正証書遺言を作成することをおすすめします。
口頭で遺言について聞いている場合も、できるだけ生前中に公正証書遺言を作成してもらうようにすすめるとよいでしょう。
遺言の悩みは専門家に相談を
口頭での遺言は法的に無効となりますが、遺産分割協議や死因贈与などの方法で実現できる可能性はあります。実現できる可能性はゼロではないとはいえ、実現のハードルは高く、さらに相続トラブルに発展する恐れもあるので専門家への相談をおすすめします。
より確実に相続を実現させるには、形式を満たした遺言書を作成することが大切です。ただし、遺言書作成時には形式や遺留分など考慮しなければならない点も多くあります。弁護士などの専門家にアドバイスをもらいながら、納得いく相続を目指しましょう。
地元の専門家をさがす



