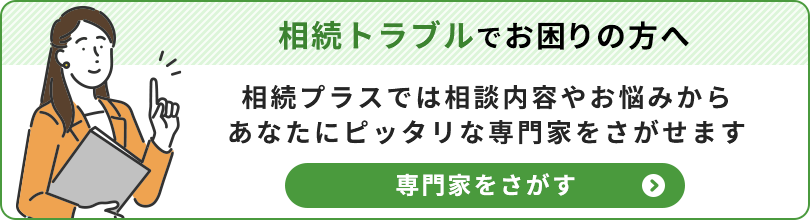令和6年4月より相続登記が義務化されたことで、相続に関する専門家への相談のニーズは高まっています。しかし、相続手続きには弁護士だけでなく司法書士や税理士など複数の専門家が関わるため、相談先に迷うことがあるでしょう。本記事では、弁護士の役割や他の専門家との違いなどについて、詳しく解説します。
弁護士の役割
相続において、弁護士がどのような役割を果たすかについて解説します。司法書士や税理士、行政書士といった他士業には法律上業務範囲の制限がありますが、弁護士は基本的にすべての法律業務に対応可能です。
ただし、登記手続きにおいては司法書士、相続税については税理士など、各士業にはそれぞれの専門分野があるため、相談内容に応じて使い分けることが重要です。
以下、相続における弁護士の具体的な役割について詳しく解説します。
法律相談を受けられる
相続では法的な判断を要する問題が生じますが、これらの問題に対する法律相談が行えるのは弁護士のみです。例えば、「認知症の人が書いた遺言書は有効なのか」「相続放棄は可能なのか」といった問題に対して、弁護士は法的な観点から適切なアドバイスができます。
なお、これらの問題に対して弁護士以外が法律相談を行うことは「非弁行為」に該当するため、法律上禁止されています。非弁行為とは、弁護士以外の者が報酬を得る目的で法律事件について相談に応じたり、代理人として対応したりすることです。
そのため、弁護士以外の専門家に相談できるのは、相続に関する問題の中でも法律相談以外のことに限られます。例えば、登記申請書の作成方法に関する相談であれば、司法書士への相談も可能です。
また、相続税に関する相談であれば税理士の専門分野であるため、税理士の方が弁護士よりも適切な回答が期待できます。
このように、弁護士であれば基本的に相続に関するすべての相談に対応できますが、他士業の専門分野に関しては司法書士・税理士といった専門家への相談が適する場合もあります。
参考:司法書士法3条第1項第4号、同5号│e-Gov法令検索
交渉や訴訟の代理人となれる
相手方との交渉や訴訟の代理などの法律事務も、弁護士以外の者が行うと非弁行為に該当します。相続においては協議・調停・裁判と段階的に手続きが展開されますが、これらの各段階において弁護士は交渉や訴訟の代理人となれます。
まず、遺産分割協議の段階では、相続人同士の利害調整や法定相続分とは異なる分割案の提案などについて、弁護士が依頼者の代理人として交渉できます。
次に、協議がまとまらない場合は家庭裁判所での調停・審判に移行しますが、弁護士は依頼者の代理人として調停に出席できます。そして、依頼者に代わって調停委員との交渉や主張の展開、法的主張などを行います。
さらに、紛争が複雑化した場合は訴訟によって解決を図る場合がありますが、弁護士は訴訟においても依頼者の代理人を務められます。
このように、弁護士は相続の各段階における交渉・訴訟の代理を一貫して引き受けることが可能です。
家庭裁判所での手続きを代理できる
相続放棄申述書などの書類作成や、手続きの流れに関する事務的な説明であれば、司法書士にも行うことが可能ですが、相続放棄申述の代理、限定承認の申述代理、遺言書検認の申立て代理など、家庭裁判所における手続きは弁護士以外の者が依頼者に代わって行うことはできません。なぜなら、相続放棄すべきかどうかの法的判断や、家庭裁判所での代理人としての活動などは非弁行為にあたるため、司法書士には対応できません。
したがって、相続放棄申述書などの書類作成のみであれば司法書士へ相談し、それ以外の法律相談を含む場合には弁護士に相談するというように、内容に合わせて相談先を選ぶことで効率よく家庭裁判所の手続きが進められます。
相続を弁護士に依頼した方がよいケース

前章で弁護士の役割について解説しましたが、では具体的にどのような場面で弁護士に依頼すべきなのでしょうか。相続手続きは複雑で専門的な知識を要する場面が多く、思わぬ不利益を被るリスクがあります。
以下では、具体的にどのような場面で弁護士に依頼すべきかを詳しく解説します。
相続人調査・財産調査が必要なとき
遺産分割協議を行う上で、相続人と財産の把握は必須です。しかし、相続が何代にもわたっていたり遺産が高額であったりする場合、相続人や財産を把握しきれないことがあるため、専門的な調査が必要となります。
相続人調査では、被相続人の戸籍謄本などを出生から死亡まですべて取得する必要があります。そのため、戸籍を読むことに慣れていないと調査に時間がかかる上に、誤りが生じるリスクもあります。
一方、財産調査においては、プラスの財産だけでなくマイナスの財産もすべて正確に把握する必要があります。相続放棄を判断する上でも財産調査は非常に重要であり、債務超過の状況を正確に把握できなければ、相続放棄の判断を誤る可能性があります。
弁護士に依頼すれば、これらの複雑な調査を誤りなく正確に実施できるため、後のトラブルを未然に防ぐことができます。
相続人の間で意見が分かれトラブルになっているとき
相続においては人間関係や利害の対立などにより、相続人同士の間で意見が分かれることも少なくありません。特に仲の悪い親族間や遠縁の親族、腹違いの兄弟間などにおいては感情的なトラブルに発展することもあり、協議が難航する傾向にあります。
こういったとき、弁護士が間に入れば冷静な話合いができ、協議が円滑に進みやすくなります。弁護士であれば第三者の客観的な観点から利害を調整し、各相続人が納得できる解決策を提案することが可能です。
さらに、法的根拠に基づいた提案により、各相続人が「なぜその解決策が妥当なのか」を理解しやすくなり、合意形成が促進されます。
そして、すでにトラブルが深刻化し、任意の協議では解決しない場合でも、調停や訴訟まですべて対応を任せられます。
遺言書に問題があるとき
自筆で作成して自宅に保管される自筆証書遺言の場合、形式や内容に誤りがあり、遺言の法的有効性が争われることがあります。遺言の成立要件は法律によって厳格に定められているため、このような法的判断については弁護士に相談するのがおすすめです。
遺言書の有効性が問題となる場合、まずは任意の交渉によって解決を図るのが一般的です。しかし、形式的な不備程度であれば交渉で解決できることもありますが、認知症などの影響で遺言能力が問題となる場合、交渉では解決できないことも少なくありません。
交渉で解決できない場合、遺言無効確認訴訟で有効性を争うことになりますが、弁護士であれば訴訟の対応まで一貫してサポートできます。
相続放棄・限定承認など専門的判断が必要なとき
相続放棄や限定承認、遺留分侵害額請求など、法的に専門的な判断を要するときは弁護士への相談が最適です。
相続放棄とは相続の権利を放棄して相続財産を受け取らない制度であり、限定承認とはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ制度です。遺産の中に借金がある場合、どちらを選択してどのように手続きを進めるべきかについて、弁護士から法的に適切なアドバイスを受けられます。
また、遺留分侵害額請求においては複雑な財産調査や遺留分の計算が必要となり、法的知識がないと適切な対応が困難です。
そして、これらの手続きには厳格な期限があり、一度選択すると原則として撤回できません。そのため、弁護士に依頼して依頼者の状況に最適な選択をすることが重要です。
弁護士に依頼しなくてもよいかもしれないケース
相続問題のすべてが弁護士への依頼を必要とするわけではありません。相続の状況によっては、他の専門家への相談が適しているケースや、自分で手続きできるケースもあります。
ただし、一見シンプルに見える相続でも、思わぬ落とし穴が潜んでいることがあるため、以下を参考にして適切に判断しましょう。
争いの要素がないとき
争いが起こりにくいケースとは、相続人が配偶者のみ、または子どもひとりのみといったように単純な構成の場合が多いです。なおかつ相続財産も預貯金や自宅のみなど限定的な場合です。このようなケースでは、事前に関係者間で話合いが済んでいれば遺産分割協議もスムーズに進み、弁護士への依頼は不要かもしれません。
しかし、一見平穏に見える相続でも注意が必要です。例えば、配偶者と子どもだけの相続においても、子どもが複数いる場合には実家の処分方法で意見が分かれることがあります。
また、一部の相続人が生前贈与を受けていた場合などは、生前贈与を受けられなかった相続人との争いに発展する可能性もあります。
そのため、「争いはない」と思っていても、不安なことや気になることがあれば、一度弁護士に相談してみることも重要です。
書類の作成など事務的な手続きのみを依頼するとき
相続において法的な争いや複雑な判断が不要であり、単純な書類作成のみが必要な場合などは、他の専門家でも対応可能な場合があります。
例えば、遺産分割協議書の作成や遺言書の起案であれば、行政書士にも依頼できます。また、不動産の相続登記申請書の作成については司法書士が専門分野として対応できます。
費用面においても、一般的には司法書士や行政書士の方が弁護士より安い傾向にあります。
ただし、書類作成の過程で法的な問題が発見されたり相続人同士の間で意見の相違が生じたりした場合、最終的に弁護士への相談が必要になる可能性があることも念頭に置いておきましょう。

相続税に関する疑問があるとき
弁護士は法律の専門家である一方、税務の専門家は税理士です。そのため、相続税の申告や節税対策については税理士に相談するのが適切といえます。財務省の調査によれば、相続税の申告に税理士が関与する割合は約86%とされており、多くのケースで税理士に依頼されていることがわかります。
これは、申告漏れによる追徴課税のリスクや、財産評価の誤りによる相続税の過払いなどの問題があるためです。不動産や有価証券の適切な評価には知識が必要であり、適切な評価ができないと本来より多く税金を支払ってしまう可能性があるのです。
また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった控除制度も活用できるので、適切な申告を行うためには税理士への相談が望ましいといえます。

依頼する弁護士の選び方
相続案件を扱う弁護士は多数いますが、経験や専門性、対応方針に大きな違いがあります。弁護士選びを間違えると期待した結果が得られないだけでなく、費用や時間の無駄にもつながりかねません。
適切な弁護士を選ぶためにはいくつかの重要なポイントがあるので、以下を参考にして信頼できる弁護士を見つけましょう。
相続案件の実績が豊富である
弁護士にはそれぞれ専門分野があり、すべての弁護士が相続案件に精通しているわけではありません。そのため、弁護士を選ぶ際は、法律事務所のウェブサイトで相続案件の取扱実績を確認し、実績豊富な弁護士を選びましょう。
相続分野での経験が豊富な弁護士ほど複雑な案件に対応でき、よりよい解決策を提案できます。「相続専門」という表記をしている法律事務所や、相続案件を多数手がけている弁護士であれば、相続分野に長けていると考えられます。
司法書士や税理士など他の専門家と協力体制を築いている
相続手続きでは、弁護士以外の専門家の協力が必要になることが頻繁にあります。例えば、不動産の相続登記であれば司法書士、相続税の申告には税理士がそれぞれ専門としています。そのため、相続分野に精通した弁護士は、依頼者の利便性を考慮して他の専門家との連携体制を整備しています。
そういった相続問題全体をワンストップで解決できる法律事務所を選べば、複数の専門家を個別にさがす手間が省けて手続きもスムーズに進行します。
やりとりのしやすさ
実績や経験も大切ですが、弁護士選びではコミュニケーションの取りやすさも重要な要素です。説明がわかりやすく、質問しやすい雰囲気があるか、親身になって対応してくれるかなどを確認しましょう。どれほど知識が豊富でも、やりとりがしにくい弁護士では依頼後にストレスを感じることになります。
また、よい弁護士は依頼者にとって不利な点も率直に伝えてくれます。法的に実現困難な要望については丁寧に説明し、代替案を示した上で可能な限り希望に沿った提案をしてくれる弁護士であれば、依頼後の満足度は高くなりやすいでしょう。
インターネット上の弁護士ランキングや口コミ情報は多く存在しますが、それらは参考程度に留め、実際に面談して自分で判断することが重要です。
柔軟な対応体制
事務所への通いやすさ、営業時間、オンラインでの対応など、事務所の対応体制も弁護士選びの重要なポイントです。
まず、事務所が自宅や職場からアクセスしやすい場所にある方が、相談や打ち合わせの負担を軽減できます。遺産分割調停などで家庭裁判所での手続きが必要な場合は、管轄裁判所の所在地も考慮するとよいでしょう。
また、仕事をしている方にとって、平日日中の相談は困難な場合が多いため、夕方以降や土日祝日の相談に対応してくれる事務所を選ぶと便利です。オンライン相談システムを導入している事務所であれば移動時間を節約できるため、長期間にわたる遺産分割協議でも相談しやすいというメリットが得られます。
これらを考慮して弁護士を選ぶことで、自分に合った体制を整えている弁護士への依頼ができます。
相続に関わる弁護士費用の相場
相続に関わる弁護士費用をまとめると、以下の通りです。
- 遺言書の作成:約20~30万円
- 遺言の執行:最低でも30万円~
- 相続放棄:約5~10万円/人
- 遺産分割協議:最低着手金約20~30万円
- 遺留分侵害額請求:約3~5万円程度
- 成年後見人:20万円前後+実費約6万円/報酬・月額2~6万円
以前は日本弁護士連合会による報酬基準が定められており、遺言書作成や遺言執行などの費用が明確に規定されていました。
しかし、現在この基準は撤廃されており、今でもこの旧基準に準じて料金設定している弁護士もいれば、独自の料金体系を採用している弁護士もいます。
そのため、弁護士によって費用に差が生じるので、詳しい費用の内訳や追加費用については相談時に見積もりを取ることをおすすめします。
相続トラブルや遺言書に問題があれば弁護士へ相談を
弁護士は法律相談、交渉・訴訟の代理、家庭裁判所での手続き代理など、他の専門家では対応できない業務を担うことができます。単純な手続きや相続税の問題であれば他の専門家でも対応可能ですが、法的な争いや複雑な判断が必要な場面では弁護士の専門性が不可欠となります。
弁護士を選ぶ際は、相続案件の実績、他の専門家との連携体制、コミュニケーションの取りやすさ、事務所の対応体制などを総合的に判断することが重要です。費用については弁護士によって差があるため、事前に見積もりを取って比較検討しましょう。適切な専門家選びにより、相続問題をスムーズに解決へと導けます。