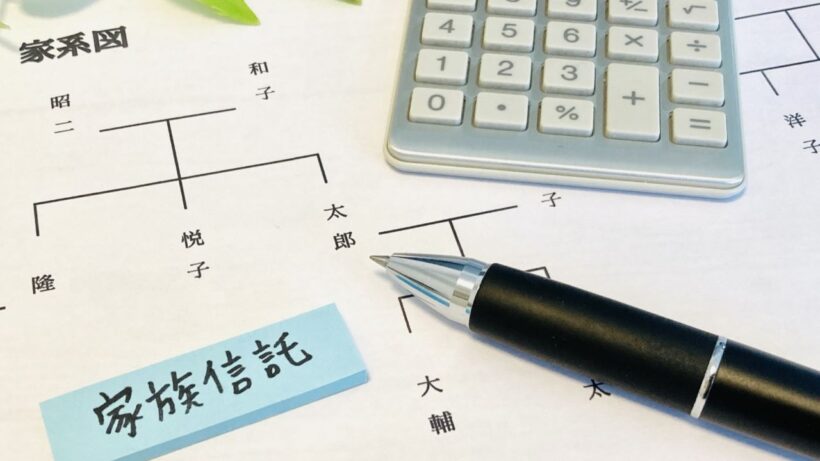家族信託の検討を進めているなかで、どのような税金がかかるのか気になっていませんか。家族信託を設定する際、受益者を誰にするかによって課税される税金が異なります。また、税金を支払うタイミングもさまざまです。本記事では、家族信託の税務上の取り扱いや発生する税金の種類について詳しく解説します。最後に注意点も説明しているため、家族信託を検討している方はぜひ参考にしてください。
地元の専門家をさがす
家族信託とは
家族信託とは、家族に対して自分の意思通りになるよう財産の運用・管理を任せる制度です。生活費・介護費の支払いや不動産収入の管理などを信頼できる家族に任せることができます。
平成18年度に行われた信託法改正によって新設された制度で、まだまだ歴史が浅い制度でもあります。認知症対策として活用されるケースが増え、近年知名度が上がってきました。成年後見制度とは異なり、家族が柔軟に財産管理を行える点がメリットですが、どちらの制度にもそれぞれの特性があります。
そのため、親の財産を子どもに託す家族信託の設定が一般的です。このとき親を委託者、子どもを受託者と呼びます。さらに、信託財産が生み出す利益を受け取る受益者を設定します。
一見、財産を管理する権限が家族に移ることから財産の移転のように見えますが、あくまでも利益を受け取れるのは受益者です。そのため、家族信託をしていたとしても、税務上は財産の管理方法を変更しただけだとみなされます。
そのため、親が子どもに対して家族信託を設定したとしても、原則、贈与税や不動産取得税は課税されません。たしかに信託財産の名義人は受託者となりますが、形式的な名義人に過ぎず、受益者に実質的な財産権があるからです。受益者を委託者本人にする自益信託を設定する場合は、原則新たな税金は発生しないと考えてよいでしょう。
ただし、受益者は委託者にしなければならないというルールはありません。受益者を誰に設定するかによってさまざまな税金が発生する場合があります。次の章から、家族信託をするとどのような税金が発生する可能性があるのかについて詳しく解説していきます。

家族信託で発生する主な税金の種類
家族信託によって課税される税金の種類は、自益信託か他益信託かによって異なります。
自益信託とは、委託者本人を受益者として設定することです。一方、他益信託は委託者本人以外の子どもや配偶者を受益者として設定することです。
税法には、受益者課税の原則という考え方があります。受益者課税の原則とは、受益者に対して課税されるといった基本ルールです。
家族信託契約を交わすと財産の所有権は受託者へ移るものの、信託財産によって生み出された利益を受け取れません。利益を享受できるのは受益者です。
そのため、税法では、実際に利益を受け取る受益者に対して課税することとなっています。
ここでは、下記の2つのケースにおける税金の考え方について詳しく解説します。
- 自益信託は不動産の移転に伴う税金が発生しない
- 他益信託は利益の移転に伴う税金が発生する
順番に確認しましょう。
自益信託は不動産の移転に伴う税金が発生しない
委託者本人を受益者に設定する自益信託の場合、不動産移転に伴う税金は原則発生しません。
財産権の移動があるときに課税される贈与税や、実質的な所有権移動時に課税される不動産取得税は、課税されません。また、受益者が死亡したことで家族信託が終了して受益権を引き継いだときに相続税が課税されます。
受託者は登録免許税や固定資産税の納税義務者となりますが、受託者自身の財産から支払うのではなく、信託財産のなかから支払うことが一般的です。
信託財産が利益を生み出す場合は、所得税が受益者である委託者に対して課されます。
他益信託は利益の移転に伴う税金が発生する
委託者本人以外を受益者として設定する他益信託の場合、財産権の移転があったとみなされるため、受益者に対してさまざまな税金が課税される場合があります。
- 贈与税:財産の移動があるため受益者に課税
- 相続税:受益者が死亡し、受益者としての権利を引き継いだ人に課税
- 登録免許税・固定資産税:財産の所有権移動があるため受託者に課税
- 所得税:信託財産が利益を生み出す場合、利益を受け取る受託者に課税
また、信託終了時には、贈与税あるいは相続税が新たな受益者に課税されます。
ただし、信託開始時の受託者への不動産移転は、形式的な移転とみなされるため不動産取得税は非課税です。
家族信託にかかる税金の具体例

家族信託にかかる税金について、時期ごとに具体的にご紹介します。
- 家族信託の開始時に発生する税金
- 家族信託の期間中に発生する税金
- 受益者の生存中に信託契約が終了した場合に発生する税金
- 受益者が死亡して信託契約が終了した場合に発生する税金
- 家族信託で発生する主な税金一覧
家族信託契約を交わす前にしっかりと確認しておきましょう。
家族信託の開始時に発生する税金
家族信託の開始時にかかる税金について、下記の2つに分けて解説します。
- 受益者に課税されるもの
- 受託者に課税されるもの
それぞれ確認しましょう。
受益者に課税されるもの
家族信託の開始時、受益者に課税される税金は贈与税です。贈与税は、他益信託の場合にのみ課税されます。自益信託の場合は、実質的に財産が移動していないため贈与税は課税されません。
受託者に課税されるもの
家族信託契約を交わすとき、信託財産の所有者を委託者から受託者へ名義変更します。不動産が信託財産に含まれる場合に、以下の税金が発生します。
- 登録免許税
- 固定資産税
登録免許税は不動産信託登記の際に納付し、固定資産税はその年の1月1日時点の所有者に対して納付義務が発生します。
ただし、登録免許税も固定資産税も受託者本人が負担するのではなく、信託財産のなかから支払うことが一般的です。
家族信託の期間中に発生する税金
家族信託を契約したあと、期間中にかかる税金について下記の2つに分けて解説します。
- 受益者に課税されるもの
- 受託者に課税されるもの
それぞれ確認しましょう。
受益者に課税されるもの
家族信託の契約期間中、受益者に課税される税金は下記の通りです。
- 所得税・住民税(信託財産から所得を得ている場合)
- 譲渡所得税(信託財産や受益権を売却した場合)
上記の税金は、信託財産から納付することが可能です。
また、受益権の譲渡があった場合、新たな受益者に対して贈与税が課されます。
受託者に課税されるもの
家族信託の契約期間中、受託者に課税される税金は固定資産税です。信託財産に不動産が含まれる場合に課税されます。
ただし、信託財産のなかから支払うことが一般的なため、実質的な受託者の負担はほとんどありません。
受益者の生存中に信託契約が終了した場合に発生する税金
受益者の生存中に信託契約を終了する場合にかかる税金について、下記の2つに分けて解説します。
- 受益者に課税されるもの
- 帰属権利者に課税されるもの
詳しく確認しましょう。
受益者に課税されるもの
自益信託で、受益者と帰属権利者が同じ場合に課される税金はありません。帰属権利者とは、家族信託終了のタイミングで信託財産を取得する人のことです。
家族信託が終了したとしても実質的な財産移転がないため、贈与税や不動産取得税、登録免許税などの税金は課税されません。
帰属権利者に課税されるもの
受益者以外の第三者が信託財産を取得する場合、帰属権利者に対して下記のような税金が課税されます。
- 贈与税
- 不動産取得税
- 登録免許税(所有権移転・抹消登記の登録免許税)
受益者から第三者へ信託財産が移転するため、上記の税金が課せられる可能性があります。
受益者が死亡して信託契約が終了した場合に発生する税金
受益者の死亡が原因で信託契約が終了した場合、帰属権利者に課税される税金に限られます。詳しく確認しましょう。
帰属権利者に課税されるもの
受益者が死亡して信託契約が終了した場合、帰属権利者に対して下記の税金が課されます。
- 相続税
- 登録免許税(抹消登記の登録免許税も発生)
家族信託の中には、受益者連続型信託となっている場合もあるでしょう。受益者連続型信託の場合、受益者が死亡しても家族信託は終了せずに次順位の受益者が定められています。このときも、受益権を新たに引き継いだ人に相続税が課されます。
また、信託財産に不動産が含まれている場合、相続による名義変更となるため、登録免許税の軽減措置が適用されることがあります。さらに、相続による移転であるため不動産取得税は発生しません。
家族信託で発生する主な税金一覧
家族信託で課税される主な税金の課税のタイミングや課税対象者、税率について、下記の表にまとめました。
| 税金の種類 | 課税されるタイミング | 課税対象者 | 税率 |
|---|---|---|---|
| 登録免許税 | 信託開始時・終了時 | 受託者 | 信託開始時:不動産評価額に対して0.3~0.4% 信託終了時:抹消登記1000円+所有権移転登記(不動産評価額に対して2%) |
| 固定資産税 | 信託期間中 | 受託者 | 不動産評価額に対して1.4%※1 |
| 所得税 | 信託期間中 | 受託者 | 信託財産の収入に対して5%〜45% |
| 住民税 | 信託期間中 | 受託者 | 信託財産の収入に対して10% |
| 贈与税 | 他益信託の設定時 (受益者が変わるとき) | 受益者 (次の受益者) | 信託財産の評価額に対して課税※2 |
| 相続税 | 受益者死亡時 | 次の受益者 | 信託財産を含めた遺産総額に対して10〜55%※3 |
※1減額・減免の特例措置あり
※2暦年課税か相続時精算課税によって税率が異なる
※3遺産総額が基礎控除額を超える場合のみ
上記のような税金がかかるかどうかは、信託の設計内容によって異なります。いつ・誰に・どのような税金が課税されるのかについて、詳しくは専門家に相談することをおすすめします。
地元の専門家をさがす
家族信託の税金に関する注意点
家族信託契約を交わす際、税金に関して知っておきたい注意点は、下記の通りです。
- 家族信託そのものに節税効果はない
- 家族信託は税金の他にも費用がかかる
- 家族信託の損益通算禁止に注意
詳しく確認し、後悔しないよう家族信託を設計しましょう。
家族信託そのものに節税効果はない
あくまでも家族信託そのものに節税効果はありません。
家族信託では、財産の引き継ぎ方について柔軟に設計することが可能です。しかし、原則受益者には課税されるため節税対策にはつながらないと考えておきましょう。
家族信託のメリットは、認知症で財産を管理できなくなった場合に家族に任せられることや、生きているうちに財産の引き継ぎ先を指定できることにあります。
財産の引き継ぎ方次第ではなにも相続対策しなかったときと比べて節税できる可能性はあるものの、家族信託をすること自体には節税効果がないことを理解しておきましょう。
家族信託は税金の他にも費用がかかる
家族信託には、税金以外にも一定の費用がかかります。家族信託の開始時と開始後にかかる費用をそれぞれ表にまとめました。
<家族信託の開始時にかかる費用>
| 項目 | 費用目安 |
|---|---|
| 信託設定費(専門家への報酬) | 30万円〜 ※信託財産の評価額によって変動 |
| 司法書士への登記依頼費用 | 8〜12万円 |
| 公正証書の作成費用 | 3〜10万円 |
| 公正証書作成の代行費用 | 10〜15万円 |
<家族信託の開始後にかかる費用>
| 項目 | 費用目安 |
|---|---|
| 受託者への信託報酬 | 月額2~6万円 |
| 信託監督人・受益者代理人への報酬 | 月額3~20万円 |
設定内容によっては、開始後にかかる費用を0円に抑えることも可能です。実際、受託者への信託報酬を支払わないケースや信託監督人・受益者代理人を設置しないケースもあります。
家族信託の損益通算禁止に注意
信託財産に収入不動産が含まれている場合に注意すべきポイントが、損益通算禁止です。
家族信託の有無にかかわらず、個人に所得が発生した際には確定申告をしなければなりません。不動産所得に加えて、事業所得や給与所得、雑所得などを計算して確定申告を行います。
たとえば、運送業で事業所得を得ている人が不動産の賃貸でも収入を得ている場合、同年における赤字の所得を他の黒字の所得から差し引くことが可能です。これを損益通算といいます。
仮に、運送業で600万円の所得があるものの、賃貸不動産のリフォームにより赤字が200万円となった場合、事業所得600万円から不動産所得の赤字200万円を差し引いた400万円が課税対象となります。
しかし、家族信託における受託者名義の信託不動産は損益通算できません。つまり、信託不動産で出た赤字は不動産所得の計算上なかったものとされます。そのため、税負担が増えてしまう場合がある点に注意しなければなりません。
万が一、信託不動産の大規模修繕が計画されているなどで赤字が見込まれる場合には、家族信託の設計段階で専門家へ相談することをおすすめします。
家族信託で発生する税金は設計内容によってさまざま
家族信託によって発生する税金は、誰を受益者にするかによって大きく異なります。発生するタイミングや種類がさまざまなため、設計段階で明確にしておくことが重要です。
また、家族信託そのものには節税効果はありません。むしろ、相続で財産を引き継いだ方が軽減措置が受けられて、税金が抑えられるケースもあります。相続に向けて節税対策を考えているのであれば、家族信託以外の選択肢もたくさんあります。
家族信託契約によって発生する税金は設計内容によってさまざまなため、間違った認識でいると納税通知書が届いて驚くことになりかねません。家族信託契約を交わすべきかどうかもふくめ、早い段階で専門家の支援を受けましょう。
相続プラスでは、家族信託や相続に強い弁護士や司法書士を気軽に検索できます。悩み別・エリア別に専門家を検索できるため、ぜひ一度活用してください。専門家に相談しながら、財産を引き継ぐためのベストな方法を見つけましょう。
地元の専門家をさがす