父母や孫などは馴染みがあり、読みやすい名称ですが、「玄孫(やしゃご)」や「曾祖父(そうそふ)」など、読みづらい漢字表記も多く存在します。
血族や姻族、親等とはどのようなものかといった基礎知識についても解説していますので、あわせて参考にしてください。
地元の専門家をさがす
親族とは
親族とは、民法第725条において、親族を「六親等内の血族」「配偶者」「三親等内の姻族」と定めています。
ただ、これだけ見ると「六親等ってどこまで?」「姻族って誰のこと?」とわからないことが多いと思いますので、ここからは「親等」や「血族」「姻族」などの意味と一緒に、親族の概念や範囲について詳しく解説します。
親族の概念
親族とは、血縁関係または婚姻関係によって結ばれた人たちのことを指します。民法で明確に定義されている法律用語で、「六親等内の血族」「配偶者」「三親等内の姻族」と定められています。
親等・血族・配偶者・姻族の言葉の意味について、下記の表にまとめました。
| 親等 | 親族間の関係の近さを表す概念です。 親子のように一世代離れるごとに「一親等」ずつ遠くなります。 |
|---|---|
| 血族 | 血族とは、血のつながりがある人々のことを指します。 これは、生物学的な血縁関係だけでなく、養子縁組などによる法的な血縁関係も含まれます。 |
| 配偶者 | 配偶者とは、戸籍上で夫または妻として記載されている人のことです。 |
| 姻族 | 姻族とは、配偶者の血族や親族のことを指します。 |
なお、似た言葉に「親戚」がありますが、親戚に法的な定義はありませんが、日常的には親族関係にある人や、近しい血縁・姻戚関係の人々などをまとめて指す言葉として用いられます。
親族の範囲
親族の範囲は、民法によって「六親等内の血族」「配偶者」「三親等内の姻族」と定められています。
まず、六親等内の血族について見てみましょう。親等ごとに自身からみた六親等内の血族は下記のような間柄の人々となります。
| 一親等 | 父母・子ども |
|---|---|
| 二親等 | 祖父母・孫・兄弟姉妹 |
| 三親等 | 曾祖父母(祖父母の親)・曾孫(孫の子ども)・伯叔父母(親の兄弟姉妹)・甥姪 |
| 四親等 | 高祖父母(曾祖父母の親)・玄孫(孫の孫)・従兄弟姉妹・大甥姪(甥姪の子ども)・伯叔祖父母(祖父母の兄弟) |
| 五親等 | 五世の祖(高祖父母の親)・来孫(玄孫の子ども)・従甥姪(従兄弟姉妹の子ども)・曾姪甥(大甥姪の子ども)・従伯叔父母(伯叔祖父母の子ども)・曾祖伯叔父母(曾祖父母の兄弟姉妹) |
| 六親等 | 六世の祖(高祖父母の祖父母)・昆孫(来孫の子ども)・玄姪孫(曾姪甥の子ども)・従姪孫(従甥姪の子ども)・再従兄弟姉妹(従伯叔父母の子ども)・従伯叔祖父母(曾祖伯叔父母の子ども) |
養子縁組によって生物学上の血のつながりがなくても、法的な親子関係が認められる場合は、その関係も親族に含まれます。また、父母の一方だけが共通している異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹についても、法律上は兄弟姉妹として親族にあたります。
つづいて、三親等内の姻族について見てみましょう。親等ごとに自分からみた三親等内の姻族を表にまとめました。
- 一親等:義父義母
- 二親等:義祖父義祖母・義兄弟姉妹
- 三親等:義曾祖父義曾祖母・義甥義姪
配偶者は血族にも姻族にも分類されず、親族の範囲には含まれますが、独自の立場となっています。
ここまでの説明に挙げられている人は親族であり、記載されていない人は基本的に親族ではないと考えてください。
例えば、自分の従兄弟は血のつながりがある四親等のため親族ですが、配偶者の従兄弟は姻族であっても三親等を超えるため親族には含まれません。
また、配偶者の兄弟姉妹の配偶者も親族の範囲には入りません。
直系親族の呼び方
ここからは親族の呼び方について詳しく解説します。
まず、直系親族の呼び方について説明します。直系親族とは、親子の関係で上下に直接つながる親族を指します。ここでは、次に挙げる直系親族について詳しく解説します。
- 父
- 母
- 祖父
- 祖母
- 曾祖父
- 曾祖母
- 高祖父
- 高祖母
- 子
- 息子
- 娘
- 孫
- 曾孫
- 玄孫
- 来孫
- 昆孫
それぞれの呼び方のよみがなや、一般的な呼称、また自分から見た場合の親等も確認していきましょう。
父
父(ちち)とは、父親のことで一親等にあたります。
生物学的・遺伝子的な意味での父はもちろん、養子縁組によって親子関係が成立している場合も、男親を「父」と呼びます。また、両親が離婚しても、親等に影響はしません。
また、母と未婚の男性との間に生まれた子の場合でも、生物学上の父がその子を認知すれば、その男性は親族となります。
親族関係においては、父は尊属親族に含まれます。
母
母(はは)とは、母親のことで、一親等にあたります。
父と同様に、生物学的・遺伝子的な意味での母はもちろん、養子縁組によって親子関係が成立している場合も、女親を「母」と呼びます。また、両親が離婚しても親等に影響はありません。
親族関係においては、母は尊属親族に含まれます。
祖父
祖父(そふ)とは、父親または母親の父親のことで、二親等にあたります。一般的には、「父方の祖父」「母方の祖父」といったように、どちらの系統の祖父かを区別して呼ぶことが多いです。
親族関係においては、祖父は尊属親族に含まれます。
祖母
祖母(そぼ)とは、父親または母親の母親のことで、二親等にあたります。呼称については、祖父の場合と同様に、父方の祖母・母方の祖母と区別して呼ばれることが多いです。
親族関係においては、祖母は尊属親族に含まれます。
曾祖父
曾祖父(そうそふ)は、祖父母の父親を指し、三親等にあたります。日常会話では「ひいおじいさん」と呼ばれることが多いです。
親族関係においては、曾祖父は尊属親族に含まれます。
曾祖母
曾祖母(そうそぼ)は、祖父母の母親を指し、三親等にあたります。日常会話では「ひいおばあちゃん」と呼ばれることが多いです。
親族関係においては、曾祖母は尊属親族に含まれます。
高祖父
高祖父(こうそふ)とは、曽祖父母の父親のことで、四親等にあたります。日常会話では「ひいひいおじいさん」と呼ばれます。
親族関係においては、高祖父は尊属親族に含まれます。
高祖母
高祖母(こうそぼ)とは、曽祖父母の母親のことで、四親等にあたります。日常会話では「ひいひいおじいさん」と呼ばれます。
親族関係においては、高祖母は尊属親族に含まれます。
子
子(こ)とは、自分の子供、つまり息子や娘のことを指します。子は一親等にあたり、親族関係では「卑属親族」に分類されます。
両親が離婚した場合であっても父と子、母と子の関係は変わりません。離婚前と変わらず、一親等のため親族です。親権の有無は関係ありません。
また、未婚の男女の間に生まれた、いわゆる非嫡出子の場合、母と子は法律上親子関係があり親族とされます。
一方、父と子どもの関係は、父親がその子を法律的に認知しているかどうかで異なります。父が認知していれば親族となりますが、認知していなければ法律上の親族関係は生じません。
さらに、血縁関係のない子どもであっても、養子縁組をすると法的に親子関係が成立し、一親等の親族と見なされます。
つまり、結婚相手の連れ子は、養子縁組をしなければ「姻族」(法律上の配偶者の親族)となりますが、養子縁組をすれば「血族」(法律上、親子の血縁関係があるとみなされる親族)となります。
息子
息子(むすこ)とは、自身の子供のうち、男の子のことで、一親等に当たります。息子と娘は、子という概念の中にある男女における違いであるため、親等に差異はありません。
親族関係において、息子は卑属親族に含まれます。
娘
娘(むすめ)とは、自身の子供のうち、女の子のことで、一親等に当たります。先述の通り、息子と娘には親等の差異はありません。
親族関係において、娘は卑属親族に含まれます。
孫
孫(まご)とは、自身の子供の子供のことを指し、二親等にあたります。日常会話では、男の孫を男孫(だんそん)、女の孫を女孫(じょそん)と呼ぶほか、息子の子供を内孫、娘の子供を外孫と呼ぶ場合もあります。
親族関係において、孫は卑属親族に含まれます。
曾孫
曾孫(ひまご/そうそん)とは、自分の孫の子どものことで、三親等にあたります。日常的には「曾孫」という漢字はあまり使わず、読みやすさのために「ひ孫」と平仮名で表記するのが一般的です。
親族関係において、曾孫は卑属親族に含まれます。
玄孫
玄孫(やしゃご/げんそん)とは、自身の孫のそのまた孫のことで、四親等にあたります。ここまでくると、日常会話で「玄孫」という言葉が登場することはほとんどありません。ただし、「げんそん」と読むよりも「やしゃご」と言ったほうが、相手に伝わりやすい場合が多いでしょう。
親族関係において、玄孫は卑属親族に含まれます。
来孫
来孫(らいそん)とは、玄孫の子どものことです。つまり、自分から見て、子、孫、ひ孫、玄孫、その次の世代であり、五親等にあたります。
親族関係において、来孫は卑属親族に含まれます。
昆孫
昆孫(こんそん)とは、来孫の子どものことです。つまり、自分から見て、子、孫、ひ孫、玄孫、来孫、その次の世代であり、六親等にあたります。自分を0世代と数えた場合、六世代後となるため六親等となります。
親族関係において、昆孫は卑属親族に含まれます。
昆孫より後の世代には、仍孫(じょうそん)や雲孫(うんそん/つるのこ)などがありますが、これらは日常会話ではほとんど使われないため、ここでは割愛します。
来孫・昆孫はあまり使われない
来孫や昆孫という言葉は、日常的にはあまり使われていません。これは、多くの人が自分の来孫や昆孫と実際に会う機会がほとんどないためです。
令和5年における第一子出生児の母の平均年齢は31歳です。本人、子ども、孫、玄孫の全員が31歳のときに出産したと仮定すると、玄孫が生まれる時に本人の年齢は93歳、来孫が生まれる時には124歳になります。
長寿大国の日本とはいえ、120歳以上の長寿となるのは稀です。そのため、来孫や昆孫と実際に会う機会は極めて少なく、親族関係図に登場しないことが多いのです。
同様に、自分が生まれたときに、尊属親族である五親等の「五世の祖」や六親等の「六世の祖」が存命している可能性も非常に低いです。そのため、これらの言葉も日常的にはあまり使われません。
参照:結果の概要|厚生労働省
地元の専門家をさがす
傍系親族の呼び方
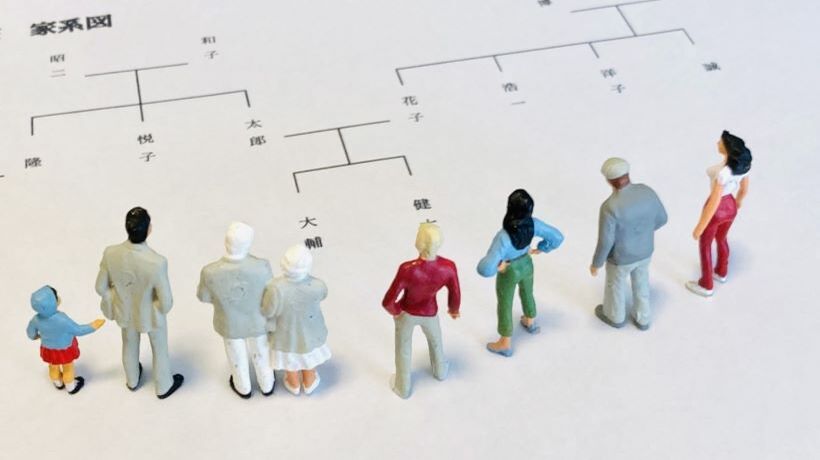
つづいて、傍系親族の呼び方について詳しく見ていきましょう。
傍系親族とは、直系と違い、兄弟姉妹によって枝分かれした系統の親族のことです。ここでは、下記の傍系親族について詳しく解説します。
- 兄
- 姉
- 弟
- 妹
- 従兄
- 従弟
- 従姉
- 従妹
よみがなや一般的な呼び方、自分から見た親等を見ていきましょう。
兄
兄(あに)とは、自分より先に生まれた男の子で、二親等にあたります。
多くの場合は同じ父母から生まれた男の子を指しますが、親が養子をとった場合や、親の再婚相手の連れ子も「兄」と呼ばれることがあります。
そのため区別が必要な場合は、「義理の」とつけることが多いでしょう。
なお、連れ子同士は親族になりません。養子縁組をすれば連れ子同士は法定血族となり、その場合は、二親等の関係となります。
姉
姉(あね)とは、自分より先に生まれた女の子で、二親等にあたります。先述の兄と親等的な差異はありません。
弟
弟(おとうと)とは、自分よりあとに生まれた男の子で、二親等にあたります。後述の妹とともに、親等としてみた場合には、兄姉と大きな差異はありません。
妹
妹(いもうと)とは、自分よりあとに生まれた女の子で、二親等にあたります。弟と同様、親等としてみた場合には、兄姉と大きな差異はありません。
従兄
従兄(じゅうけい)とは、自分より年上の男の子のいとこのことで、四親等にあたります。日常的には後述の従弟とともに「いとこ」と一括りに呼ばれることが多く、従兄や従弟と言われることはあまりありません。
従弟
従弟(じゅうてい)とは、自分より年下の男の子のいとこのことで、四親等にあたります。
従姉
従姉(じゅうし)とは、自分より年上の女の子のいとこのことで、四親等にあたります。従兄や従弟などと同様に、従姉と従妹もまとめて「いとこ」と呼ばれることが多いため、「従姉」や「従妹」という呼び方は日常ではあまり使われていません。
従妹
従弟(じゅうてい)とは、自分より年下の女の子のいとこのことで、四親等にあたります。
尊属親族の呼び方
尊属親族とは、「そんぞくしんぞく」と読み、自分よりも前の世代に属する血族を指します。
尊属親族に該当する親族の例は、下記の通りです。
- 父
- 母
- 祖父
- 祖母
- 叔父
- 叔母
- 曾祖父
- 曾祖母
- 高祖父
- 高祖母
尊属親族は、「直系尊属」と「傍系尊属」に分けられます。父母や祖父母のような直系親族は、直系尊属と呼ばれます。
ただし、一般的な法律の定義では、尊属は直系の親族(父母、祖父母など)を指し、叔父や叔母は通常含まれません。また、叔父や叔母は直系親族ではないため直系尊属にも該当しません。叔父や叔母は傍系親族にあたるため、傍系尊属と位置付けられます。
なお、配偶者の父母、つまり義父や義母は血族ではないため、尊属親族には含まれません。
卑属親族の読み方
卑属親族とは「ひぞくしんぞく」と読み、自分よりもあとの世代に属する血族を指します。
卑属親族に該当する親族の例は、下記の通りです。
- 子
- 孫
- 甥姪
- 姪孫
- 従甥姪
- 曾孫
- 玄孫
- 来孫
- 昆孫
卑属親族は、直系卑属と傍系卑属に分けられます。たとえば、子どもや孫は直系親族にあたるため、直系卑属と呼ばれます。
一方で、甥や姪、または従甥や従姪の場合は直系親族に当てはまらないため、直系卑属には含まれません。これらは傍系親族にあたるので、傍系卑属と呼ばれます。
なお、兄弟姉妹や従兄弟姉妹は自分と同じ世代であるため、卑属親族にも尊属親族にも含まれません。
親族の範囲は法律で定められている
親族の範囲は、民法によって「六親等以内の血族」「配偶者」「三親等以内の姻族」と定められています。六親等の血族ともなると人数が多くなり、知らない呼び方や読み方も多かったのではないでしょうか。
相続権や後見人の選任・解任を求める権利、扶養義務などは、親族だけに認められている権利や義務です。今回の記事が、誰が自分の親族にあたるのかを明確にするうえで、参考になれば幸いです。
地元の専門家をさがす


