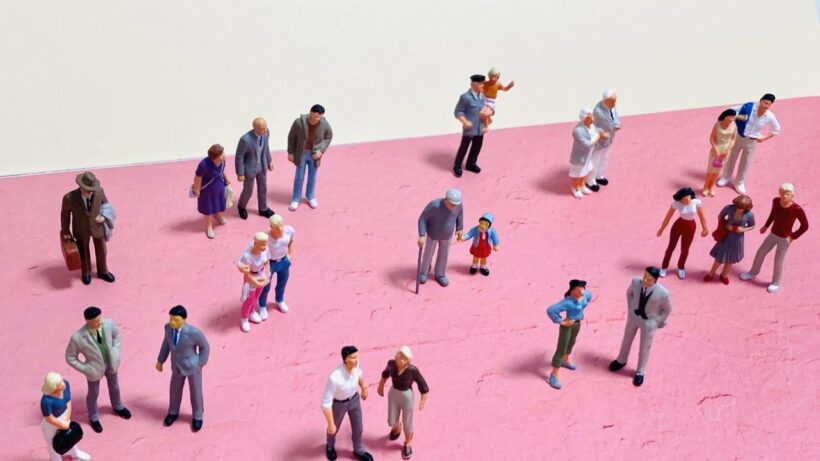家族関係を表す言葉としては、親戚、親族、血族、姻族などがあります。法的な関係を明確にする場面では「親族」と呼ばれ、遺伝や婚姻によってつながっている関係性を一般的に「親戚」と呼びます。
そして相続などの法的な手続きの際には、「どのような関係で、どの範囲の親戚(親等)なのか」によって重要な判断が分かれることがあります。そこでは血縁関係がある人を「血族」、婚姻によって親族となった人を「姻族」も深く関わってきます。
まとめると、親戚や親族をはじめとするこれらの意味は非常に複雑です。本書では、「親族」「親戚」「親等」「血族」「姻族」という5つの言葉の意味について、わかりやすく解説します。
地元の専門家をさがす
親族とは?
親族とは、主に法的なつながりがある人々を指す言葉です。親族と呼べる範囲は法律で定められており、共通の祖先を基準として「直系」と「傍系」に分かれるほか、世代でも「尊属(そんぞく)」と「卑属(ひぞく)」に分かれます。これらの関係は、相続権や扶養義務、そのほかの親族としてのつながりを要件とする契約・給付などの基準です。
親族の概念
法律の基礎となる「民法」には、親族法と呼ばれるさまざまな規定があります。親族法にあるように、法的に何らかの権利や義務が発生するときは「親族」と呼ぶのが一般的です。具体例として、財産の権利は誰にあるのか、誰が誰を生活面で助ける必要があるのかなどの判断が挙げられます。
親族の範囲
親族と呼ばれる範囲は、民法第725条で「六親等以内の血族」と「配偶者」のほかに「三親等以内の姻族」を指します。血族、姻族などの考え方はこのあと説明しますが、簡単に補足すると次のようになります。
- 六親等内の血族:子どもは養子の関係も含む
- 配偶者:現時点で法律婚をしている相手
- 三親等内の姻族:配偶者の血族の一部
直系と傍系とは?
つながりのある人々につき共通の祖先を基準とすると、親族の範囲は「直系」と「傍系」の2つに分かれます。
直系とは、本人と親子でつながれた「縦のつながり」の関係です。祖先であれば父母・祖父母など、子孫であれば子ども・孫などが「直系」にあたります。
一方の傍系とは、共通の祖先が複数の子どもをもうけたことで分かたれた「横のつながり」の関係です。上の世代であればおじ・おば、同世代であれば兄弟姉妹やいとこ、次世代であれば甥・姪などが「傍系」にあたります。
尊属と卑属とは?
特定の人を基準として世代で区別すると、親族の範囲は「尊属」もしくは「卑属」に分かれます。これらの単語を用いるときは、直系・傍系と組み合わせることでさらに範囲を絞り込むことが可能です。
尊属とは、本人より前の世代の人々のことです。父母や祖父母などは「直系尊属」として、おじ・おばなどは「傍系尊属」と呼びます。
一方の卑属とは、本人より後の世代の人々のことです。子どもや孫は「直系卑属」として、甥や姪は「傍系卑属」と呼びます。
親族の言葉の使われ方・使われるシーン
つながりのある人々を親族と呼ぶのは、主に何らかの手続きを行うときです。具体的には、福祉を受ける前に生活について頼る必要があるとき、本人に代わって家庭裁判所で手続きする必要があるとき、税申告が必要なときなどが挙げられます。
「親族」という言葉を使うケースについて、ここでいくつかを挙げてみましょう。
- 互いに助け合う義務があるとき(同居親族・民法第730条)
- 死亡届の提出義務が課されるとき(同居親族・戸籍法第87条)
- 本人のため成年後見制度の申立てができるか確認するとき
- 市区町村役場での手続きを代理できるか確認するとき
- 贈与の当事者の関係に基づいて税制上の優遇を受けるとき
- 勤め先の各種休暇・手当をもらえるか確認するとき
- 生命保険契約の受取人指定ができる範囲を調べるとき
会話のなかでは、つながりがある人をあいまいに指し示すときは「親戚」と呼び、何らかの手続きで条件・制約として指定された関係を示すときは「親族」と呼びます。
親戚であっても、会話のテーマである手続きの対象にはならないなどの理由で「親族」にはあたらないかもしれません。反対に「親族」でありながら、関係が離れすぎている・ほとんど交流がないなどの理由で、安易に親戚として扱うわけにはいかない場合もあるでしょう。
親戚とは?
親戚とは、家族との血縁を通じてつながりがある人々を広く指す言葉です。親戚と呼んでもいい範囲に決まりはなく、時勢や個人の価値観や、家族・地域で共有する価値観に合わせて柔軟に判断されます。
親戚の概念
親戚とは、血縁関係や結婚などによってつながりのある人々を指す言葉です。法律用語としてではなく、日常会話で使われるのが特徴です。個人の感覚や時勢、慣習などに基づき、広く捉えられるのが「親戚」という言葉の概念といえます。
なお、親戚とほぼ同じ意味で使われる言葉として、親類(しんるい)や、親戚縁者(しんせきえんじゃ)などがあります。
親戚の範囲
親戚の範囲にこれといった決まりはなく、柔軟に判断されるのはすでに述べたとおりです。個人の感覚、時期、地域によってとらえ方は異なります。交流がある人を広く「親戚」の範囲に含める場合があれば、交流がない人も含めてつながりを示す意味で「親戚」とする場合もあります。
親戚の言葉の使われ方・使われるシーン
日常会話では「親戚の集まり」や「親戚付き合い」などのように高い頻度で登場します。親戚という言葉が特に使われるのは、冠婚葬祭や定期的な交流、そのほかの付き合いの相手方を指すときです。よくあるのは「親戚を結婚式に呼んだ」や「親戚から旅行のお土産をもらった」などの使い方です。
なお、親戚のなかでも、特に交流する機会・回数が多い人を示したいときは「身内」と呼ぶことがあります。親戚が客観的な関係性を示すのに対し、身内はより強い一体感や家族としての意識を伴う言葉といえるでしょう。
親等とは?
親等とは、血族の関係や範囲を表すときに用いられる言葉です。血縁の距離を示す「ものさし」であり、法的な関係があることを示すときに血族のどの範囲か特定するため用いられます。
親等の概念
「血族と何親等離れているか」という考え方は、法的な権利義務が発生するかどうかを見極めるうえで重要です。
親等の数が小さいほど血縁関係が近く、法的関係も発生しやすくなります。反対に、親等の数が大きいほど血縁関係が遠く、法的関係が発生しにくいと判断できます。
親等の範囲
親等の最も狭い範囲は、親から子ども(もしくは子どもから親)へと辿ったときの「一親等」です。本人と父または母、本人と子どもとの距離は一親等となります。このように辿ると「二親等」の範囲は、本人と祖父または祖母や、本人と兄弟や姉妹となります。
ここで、法律で定める「親族」の範囲が特定できるよう、六親等以内の血族を挙げてみましょう。
| 血族との距離 | 直系(本人との関係) | 傍系(本人との関係) |
|---|---|---|
| 一親等 | 子ども、父母 | – |
| ニ親等 | 孫、祖父母 | 兄弟・姉妹 |
| 三親等 | 曾孫、曾祖父母 | 甥・姪、おじ・おば |
| 四親等 | 玄孫、高祖父母 | 甥・姪の子ども、いとこ、大おじ・大おば |
| 五親等 | 玄孫の子ども、高祖父母の父母 | 甥・姪の孫、いとこの子どもなど |
| 六親等 | 玄孫の孫、高祖父母の祖父母 | 甥・姪の曾孫、いとこの孫など |
親等の使われ方・使われるシーン
親等は、法的な権利義務の関係を示すときに広く利用されています。勤務先の就業規則などの私生活でも、親族・血族に関係するルールを指定するときに用いられることがあります。
- 一親等の血族でも配偶者でもない人(相続税の2割加算・相続税法第18条)
- 三親等以内の親族(相対的扶養義務・民法第877条)
- 三親等以内の血族(証言拒絶権・刑事訴訟法第147条)
- 三親等以内の傍系血族(婚姻の制限・民法第734条)
- 四親等以内の親族(成年後見の申立権者・民法第7条)
- 六親等以内の血族(法律上の親族、同居中は相互扶助や死亡届提出が義務)
血族とは?
血族(けつぞく)とは、本人と親子または兄弟・姉妹の関係を通じてつながりがある人々です。親族(法的なつながりのある人々)のなかでも、戸籍簿の情報を基準にしたとき「遺伝的な関係がある」と考えられる人が血族にあたります。
血族の概念
親子や兄弟・姉妹を通じてつながる血族は2種類に分かれます。遺伝的なつながりがあると考えられる「自然血族」と、遺伝的なつながりはなくとも法的手続きでつながりが生じる「法定血族」です。
自然血族には、父母や祖父母、子どもや孫、父母いずれかもしくは両方を同じくする兄弟や姉妹などの関係があります。一方の法定血族は、養子縁組などをした関係で成立します。
ただし、戸籍上の婚姻をしていない夫婦の子どもについては、父親が認知しない限り血族としての関係は生じません。
血族の範囲
血族の範囲は、戸籍の記録で「親」と「共通の親を持つ人々」として記載されている人々のつながりを限界まで辿ったとき、その調査した範囲に含まれる人々の全体に及びます。親子関係については「出生」あるいは「養子縁組」もしくは「認知」として戸籍に記載されます。
上記のように広い範囲を示すことから、血族のなかでも特定の範囲に入っている人を指定したいときは、下記の表のように、直系・傍系などの言葉を用います。
| 血族の範囲 | 具体例 | 直系血族 |
|---|---|---|
| 直系血族 | 親子関係でつながっている血族 | 父母、祖父母など |
| 傍系血族 | 同一の祖先でつながっている血族 | 兄弟・姉妹、いとこ、甥・姪など |
なお、特定できる血族のなかでもっとも遠い祖先にあたるのは、行政文書として閲覧可能なもので最も古い戸籍に当たる明治19年式戸籍に記載された人です。なお、戸籍の保管期限は150年と定められているため、行政文書に該当するとしても古い戸籍は閲覧できない可能性があります。
血族の使われ方・使われるシーン
血族という言葉は日常的には使用されません。血族が使用される主なシーンは、親族(法的なつながりがある人々)につき、相続・扶養義務・婚姻の制限などの説明にあたって範囲を絞りたいときです。
また、単に血族と言ってもその範囲は広く、言葉が用いられるときは「何親等以内の血族」や「直系血族・傍系血族」のように範囲をさらに絞る場合が多々あります。
- 直系血族(婚姻の制限・民法第734条)
- 直系血族及び兄弟姉妹(絶対的扶養義務・民法第877条)
- 2親等内または3親等内の血族(死亡保険金の受取人に指定できる一般的な範囲)
姻族とは?
姻族(いんぞく)とは、婚姻によって生じる親族を指す言葉です。一般的には「義理の家族」と呼ばれる人たちがこれにあたります。血のつながりはありませんが、法律上は親族として扱われます。
姻族の概念
姻族という言葉は、法律婚をしている夫婦につき「夫側の血族」と「妻側の血族」の関係を示しています。この関係は離婚などによって婚姻関係を解消するまでとなり、夫婦としての関係が終了したときには、双方の血族がつながりをもたない状態となります。
姻族の範囲
一般的な用語として姻族と呼ぶ場合、その範囲は「本人の配偶者の血族」と「本人の血族が婚姻した相手」に分かれます。
本人の配偶者の血族とは、本人から見て「義理の父母」(姑・舅)や「義理の兄弟や姉妹」などです。本人の血族が婚姻した相手とは、本人から見て「姉の夫」や「父の後妻」など当てはまります。
なお、法律で定める「親族」に当てはまる姻族は、下の表にある人々に限定されます。
| 親等 | 本人の配偶者の血族 | 本人の血族が婚姻した相手 |
|---|---|---|
| 一親等 | 配偶者の子ども、配偶者の父母 | 子どもの配偶者 |
| 二親等 | 配偶者の孫、配偶者の祖父母 | 孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者 |
| 三親等 | 配偶者の曾孫、配偶者の曾祖父母 | 曾孫の配偶者、おじ・おばの配偶者 |
姻族の使われ方・使われるシーン
姻族とされる人々について指し示すとき、普段の生活では「姑」や「義理の兄」とのように身近な人を特定するのが一般的です。あえて「姻族」とするのは、法的な関係や手続きを説明したいときです。
- 過去に一度でも直系姻族であった人(婚姻の制限・民法第735条)
- 二親等内の姻族(証言拒絶権・刑事訴訟法第147条)
- 三親等以内の姻族(犯人隠避罪や証拠隠滅罪の免除の可能性・刑法第105条)
- 三親等以内の姻族(法律上の親族、同居中は相互扶助や死亡届提出が義務)
地元の専門家をさがす
相続における扱い

つながりのある人の誰かが亡くなって相続が発生した場合、親戚を表す言葉によって手続きに関する判断が変わります。下記の通り、違いを理解することが重要です。
親族の扱い
法的な「親族」でも、直接相続に関われるのはごく一部の人です。法定相続人となるのは、亡くなった人(被相続人)の配偶者に加え、血族相続人である直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹のうち最も相続順位が高い人だけです。
もっとも、親族のなかでも生前の被相続人について療養看護など特別の貢献(寄与)があった人については、特別寄与料を請求できる可能性があります(民法第1050条)
親戚の扱い
いかに親密な「親戚」としての付き合いがあったとしても、それ自体が法的な相続権に結びつくことはありません。例えば、大変お世話になった遠い親戚に財産を残したいときは、生前のうちに遺言による贈与(遺贈)を検討しなければなりません。
親等の扱い
相続における「親等」は、相続税申告のときに重要です。すでに紹介した通り、血族のうち一親等の範囲に収まらない人(父母でも子どもでもない人)が相続する場合には、相続税の2割加算があります。
一親等の範囲でも、養子の取り扱いには注意を要します。自然血族である孫と養子縁組して法定血族になった場合、その養子と本人との距離は「二親等」であるため、相続税の2割加算の対象です。
血族の扱い
亡くなった人の「血族」は、血族のうちの相続権を持つ人との意味で「血族相続人」として登場します。血族相続人の判断では、血族の状況と関係性に加え、法定相続人の考え方をしっかりと理解しなければなりません。
ほかにも、血族相続人のあいだに存在する権利の違いや、相続放棄する場合の取り扱いに注意を要します。具体的には次の通りです。
血族相続人の相続順位・相続権の扱い
民法第887条及び第889条では、配偶者のほかに一定範囲の血族について下記の相続順位があるとされ、遺産をもらい受ける権利は相続順位が最も高い人が得ます。
- 子ども(直系卑属):第一順位
- 直系尊属のうち最も親等が近い人:第二順位
- 兄弟姉妹:第三順位
代襲相続が発生する場合がある
本来相続人であるはずの血族が死亡などの理由で権利を失っている場合、その権利は代襲相続として子どもに受け継がれます。つまり本人より先に亡くなった子どもの代わりに、孫が遺産を相続するようなケースです。
本来の相続人が直系尊属であるとき、次は孫へ、孫も死亡している場合は曾孫へ…とのように代襲相続は何代でも起きる可能性があります。これに対し、兄弟姉妹が相続人であるケースでは、甥・姪の代までしか代襲相続は起きません。
兄弟姉妹には遺留分はない
どのように遺産を分けるか遺言で自由に取り決める場合でも、最低限確保しなければならないとする「遺留分」という制度があります。
遺留分が認められるのは、配偶者のほか、血族相続人のうち直系卑属と直系尊属だけです。兄弟姉妹については遺留分はありません(民法第1042条)
相続放棄すると次順位の人が相続人になる
血族相続人が相続放棄した場合、繰り上がりで次順位の人が相続人となる点に注意しましょう。例えば、子ども(第一順位)が相続放棄すると、次は父母や祖父母のうち存命で親等の近い人(第二順位)が法定相続人となります。
姻族の扱い
亡くなった人の姻族に相続権はなく、遺贈などがない限り配偶者の血族が相続に関わることはありません。
なお、相続における配偶者の扱いには、次の2つのポイントがあります。
配偶者がいる場合の法定相続のルール
亡くなった時点で法律上の婚姻をしていた場合、その配偶者は法定相続人となります。なお、配偶者がもらい受けることのできる権利の割合(法定相続分)は、血族相続人の相続順位によって下記のように判断されます。
- 第一順位(直系卑属)と一緒に相続する場合:2分の1
- 第二順位(直系尊属)と一緒に相続する場合:3分の2
- 第三順位(兄弟姉妹や甥・姪)と一緒に相続する場合:4分の3
最大1億6000万円まで課税されない(配偶者の税額の控除)
配偶者がもらい受けた財産は、法定相続分もしくは1億6000万円のいずれか大きい方まで相続税の課税はありません。これを「配偶者の税額の控除」と言い、遺言や遺産分割協議での合意で取り分を決めるときの重要な判断基準となります。
相続などの場面では「親戚」を表すさまざまな言葉がある
日常会話で「親戚」などと呼ぶ人は、法的な手続きだと「親族」として範囲を絞ります。相続手続きでは、配偶者以外の法定相続人を指して「血族相続人」と呼ぶ、税に関して「一親等以内か」を重要視するなどの場面があります。相続以外の手続きでも「姻族」と呼び、配偶者側のつながりに限定して示す場合があるでしょう。
親族・親戚・親等・血族・姻族の範囲や言葉の意味するところを理解しておくと、相続だけでなくさまざまな手続きや親族・親戚の関係理解がスムーズになります。
地元の専門家をさがす