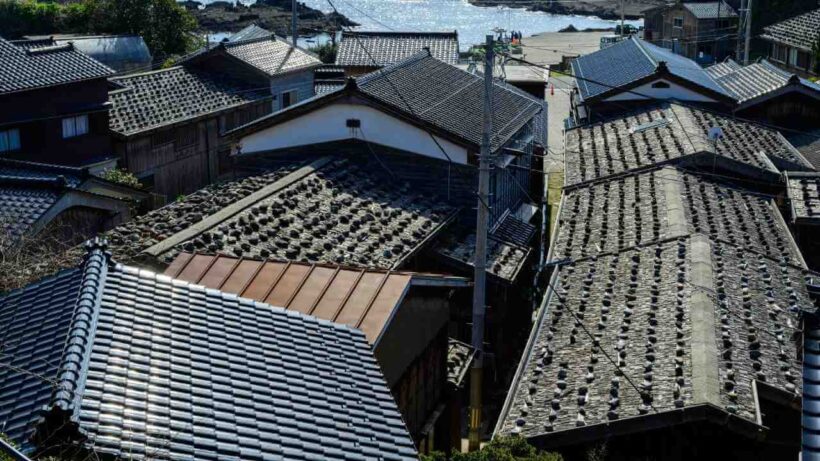「相続する物件が既存不適格建築物といわれたけれど、相続すると法律違反になるの?」古い物件や増改築した物件では既存不適格建築物や違反建築物というケースがあります。両者は法的な扱いが異なりますが、それぞれリスクがあるため、違いや注意点を押さえておくことが大切です。この記事では、既存不適格建築物・違反建築物の概要と違い・相続時の対処法を詳しく解説します。
地元の専門家をさがす
既存不適格建築物とは
既存不適格建築物とは、建築当初は法律に適合していたものの法改正に伴い適合しなくなった建物です。建物を建てるためには、建築基準法や都市計画法などの法律の基準をクリアする必要があります。
しかし、それらの基準はいつまでも同じではなく、建築技術の進歩や状況に応じて適宜改正されます。そのため、建築当時の基準で建築されたとしても、後に法改正され現行の基準に適合しなくなるケースがあるのです。
既存不適格建築物とみなされやすい原因
既存不適格建築物になりやすい原因としては以下が挙げられます。
耐震基準を満たしていない
耐震基準とは建物が備えておくべき最低限の耐震性の基準です。耐震基準は大きな地震があるたびに見直され適宜改正を繰り返しています。
なかでも大きな改正となったのが、昭和53年の宮城県沖地震を受けて行われた昭和56年6月1日からの耐震基準です。これにより昭和56年6月1日以降の耐震基準は新耐震基準、それ以前の基準を旧耐震基準として分けられています。
旧耐震基準の時代に建築された建物は現行の耐震基準を満たしていない場合があります。
建築物の高さが制限を超えている
建物には建てられる高さにもさまざまな制限があります。主な高さを制限する規制は以下のとおりです。
- 道路斜線制限
- 隣地斜線制限
- 北側斜線制限
- 日陰制限
- 絶対高さ制限
たとえば、絶対高さ制限では用途地域が第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域の場合、10mまたは12mのいずれかで定められている高さを超えられません。もともとは絶対高さ制限の規制がなかったエリアであったのにも関わらず、用途地域の変更などを理由に絶対高さ制限のあるエリアになってしまった場合、既存不適格建築物になってしまう可能性があります。
また、建物の高さは別途自治体の条例で定められているケースもあり、その場合も条例が改正されることで現行の基準を超えてしまう場合があります。
建ぺい率・容積率をオーバーしている
建ぺい率・容積率は建物の大きさに関する基準です。
- 建ぺい率:敷地面積に対する建築面積(真上から見た建物の面積)の割合
- 容積率:敷地面積に対する延床面積(各階の床面積の合計)の割合
たとえば、敷地面積120㎡で建ぺい率80%・容積率200%なら建築面積96㎡・延床面積240㎡までの家しか建てられないのです。建ぺい率・容積率は用途地域ごとに上限が定められています。そのため、都市計画の変更などで用途地域が変わるとオーバーしてしまう場合があります。
既存不適格建築物の活用方法
相続する家が既存不適格建築物だからといって直ちに取り壊す必要はありません。
住み続けられるが増改築は制限される
既存不適格建築物は、現行の基準には適合していないとはいえ、以前の基準で合法的に建てられているので法律違反にはなりません。そのため、基本的にはそのままの状態で住むことが認められます。
ただし、一定規模を超える増改築の際には、不適格な状況を解消し現行の基準への適合が必要です。建て替えしようとすると、建て替えが認められないケースや以前と同じ規模の建物が建築できない恐れがあるので注意しましょう。
危険性・有害性があるとみなされると是正命令がおりる
既存不適格建築物であっても、建て替えや増改築しないのであればそのままの状態で住み続けられますが、状態によっては特定行政庁(自治体)から撤去などの是正命令が下される可能性があります。是正命令が下されるのは、保安上危険・衛生上有害とみなされる場合です。
具体的には以下のようなケースで該当する可能性があります。
- 倒壊する危険性が高い
- 倒壊すると周囲に被害が及ぶ可能性が高い
- 建築物や設備の破損で被害が出る可能性が高い
たとえば、基礎が傾いているなど劣化が著しく倒壊のリスクが高いと保安上危険とみなされる可能性があります。また、アスベストが使用されており破損による飛散で周囲に健康被害を及ぼす可能性があると衛生上有害とみなされ改修や撤去などの是正命令が下される恐れがあるのです。
保安上危険・衛生上有害とみなされるかの基準は国土交通省のガイドラインがひとつの目安となります。
参考:既存不適格建築物に係る指導・助言・勧告・是正命令制度について|国土交通省
違反建築物とは
違反建築物とは、建築基準法などの法律に違反して建てられている建物です。建築時点から法律に適合していない建築物や適合しない増改築を行った建築物などが違反建築物となります。
違反建築物となる主な要因
違反建築物になる主な原因には、以下が挙げられます。
増築による違法
建築当初は建ぺい率・容積率を満たしていた物件でも、無断で増改築すると基準をオーバーし違反建築物になるケースは珍しくありません。建ぺい率・容積率では面積に含める部分の判断が難しい箇所も多くあります。たとえば、車庫や物置は一定の条件を満たすと延床面積に含めますが、そのことを失念し設置するケースで基準オーバーになってしまう恐れがあるのです。
一定規模の修繕や増改築時には建築確認申請が必要となりますが、防火地域や準防火地域で床面積10㎡以下の増改築などでは建築確認申請が必要ありません。建築確認申請を通さずに増改築した場合で、基準をオーバーする恐れがあるので注意しましょう。
用途の変更による違法
用途の変更とは、建築物の使用用途を変更する手続きです。以下のケースでは用途変更時に確認申請が必要になります。
- 特殊建築物への用途変更
- 変更する部分の面積が200㎡を超える
特殊建築物とは飲食店や共同住宅・物販品の販売店などが挙げられ、たとえば、新築時は居住用だった物件を飲食店に変える場合は確認申請が必要です。この確認申請の手続きを行わずに用途変更を行うと違反建築物になります。
建築申請と異なる工事による違法
建物を建築する際には自治体に建築確認申請し、確認済証の交付が必要です。また、着工後は中間検査や完了検査で計画通りに建築されているかがチェックされます。
しかし、建築確認申請は受けていても完成後の完了検査を受けない物件は少なくないのです。計画では法律に適合していても、完了検査を受けていなければ実際に法律に適合して建築されているかはわかりません。そのため、建築申請とは異なる建築が行われ違反建築物となるケースがあるのです。
違反建築物には是正命令がおりる
違反建築物に対して特定行政庁は建築物の撤去や移転・使用禁止などの是正命令を下すことが可能です。また、法律に適合しないとわかりながら確認申請を怠ると施工業者だけでなく建築主も行政処分を受ける恐れがあります。
違法建築物への罰則は平成19年6月20日の建築基準法の改正にともない強化されています。たとえば、建築確認・検査に関する罰金は30万円から100万円への引き上げなど、よりペナルティが重くなっているので注意しましょう。
既存不適格建築物と違反建築物の違い

既存不適格建築物は、法改正という所有者の意図に関係なく不適合になってしまった物件です。一方、違反建築物は新築や増改築時に法律に違反し建てられています。どちらも現行の法律に適合していない点は同じです。
しかし、既存不適格建築物は建築時点では合法的に建築されているのに対し、違反建築物はそもそも法律に違反している点が異なります。そのため、既存不適格建築物と違反建築物では以下のような違いが生じます。
違反建築物はローンを活用できない
違反建築物は、基本的に金融機関で住宅ローンを利用できません。住宅ローンを組む際、金融機関は不動産を担保にし、担保価値に基づいて住宅ローンの借入額を算出します。しかし、違反建築物は法律に違反していることから正確な担保価値の算出が難しいため、住宅ローンが利用できないケースが多いのです。
違反建築物でも売却はできます。とはいえ、住宅ローンを利用できないと買主は現金一括での購入となるので、買い手を探すのは困難になるでしょう。
一方、既存不適格建築物は法律に違反しているわけではありませんので、既存不適格建築物であることだけを理由に、住宅ローンの利用を断られるケースは多くありません。
ただし、既存不適格建築物も住宅ローンは不利になりがちです。たとえば、旧耐震基準で建てられた家は対象外という金融機関もあるので、事前に利用できる物件かどうかは確認するようにしましょう。
違反建築物は是正命令があれば従わなければならない
既存不適格建築物・違反建築物はどちらもそのまま住み続けることは可能ですが、現行の法律に適合させるタイミングが異なる点に注意が必要です。違反建築物は特定行政庁から是正命令があれば、直ちに現行の法律に適合されなければなりません。是正命令に従わなければ罰金などのペナルティが科せられる恐れがあります。
一方、既存不適格建築物でも保安上危険・衛生上有害とみなされれば是正命令が下されるリスクがありますが、基本的には増改築・用途変更時に法律に適合させれば問題ないケースがほとんどです。
既存不適格建築物や違反建築物を相続する時の対処法
既存不適格建築物や違反建築物を相続した、またはこれから相続の予定がある場合は、建築物の状況を考慮した対策が必要です。ここでは、相続する際の3つの対処法を解説します。
- 相続して活用する
- 相続放棄する
- 売却する
それぞれ見ていきましょう。
相続して活用する
建物に住むなどの予定があるなら相続して活用することが検討できます。既存不適格建築物なら増改築の予定がなく、保安上や衛生上の問題がなければ、活用にそれほど大きなデメリットは生じません。しかし、違反建築物は是正命令が下されるリスクがある点には注意しましょう。
相続放棄する
不動産を相続してしまうと、やっぱり使わないとなっても容易に手放せなくなります。活用する予定がなく相続すると負担が大きいというのであれば、相続放棄することで所有を避けられます。
ただし、相続放棄では以下のようなデメリットがある点には注意が必要です。
- 他の財産が相続できない
- 相続放棄には期限がある
- 自分が相続放棄すると次の相続人が相続することになる
相続放棄はすべての相続財産を放棄することになります。不動産は放棄するけど現預金は相続したいという選択はできないため、他の相続財産も含めて検討することが大切です。
また、相続放棄できるのは相続開始があったことを知った日から3か月以内という期限があります。期限を超えると相続放棄が難しくなるため早めに判断し手続きを進めるようにしましょう。
自分1人だけが法定相続人であるケースを除き、自分が相続放棄するとその代わりに別の相続人に既存不適格建築物・違反建築物の相続権が移ります。相続放棄は他の相続人の合意は必要ありませんが、他の相続人に影響が出てトラブルになるケースもあるので事前に説明しておくことをおすすめします。
相続放棄を検討する際には、相続放棄が妥当なのかから慎重に判断し早めに手続きすることが大切です。相続放棄の判断に悩む・手続きをサポートしてもらいたい場合は、専門家に相談するとよいでしょう。

売却する
既存不適格建築物・違反建築物はどちらも売却が可能です。しかし、どちらも買い手は購入後に制限が生じるリスクもあるため、相場よりも低い価格での売却になるかそもそも買い手が見つからない可能性があります。既存不適格建築物・違反建築物を売却するなら、訳あり不動産を専門的に取り扱う業者への売却が現実的です。専門業者の買取であれば短期間でスムーズな売却を目指しやすくなるでしょう。
なお、相続した不動産であれば売却前に被相続人から相続人に名義を変更する相続登記が必要です。また、相続登記は義務化されているため、売却に関わらず相続後は速やかに登記手続きを行いましょう。

地元の専門家をさがす
既存不適格建築や違反建築の相続は、専門家に相談しよう
既存不適格建築物は、住み続けることはできますが増改築時に現行の法律に適合させる必要があります。また、違反建築物は特定行政庁から是正命令が下されれば、直ちに法律に適合させなければなりません。
既存不適格建築物・違反建築物を相続する可能性があるなら、その物件がどの程度不適合・違反しているかを確認するようにしましょう。そのうえで、相続放棄や売却などの最適な対策を講じることが大切です。
相続放棄なら弁護士や司法書士、売却なら不動産会社は訳あり不動産の買い取り業者といった専門家に相談して適切に対処するようにしましょう。