「底地を相続してしまったけれどどうすればいい?」底地とは人に貸している土地であるため、相続しても所有者は自由に活用できないなどのリスクが生じます。とはいえ、底地は処分も容易ではないので、処分方法を理解したうえで相続するかの判断が必要です。この記事では、底地の基本やメリット・デメリット、処分方法について詳しく解説します。
底地とは
底地とは建物の所有を目的とした賃借権が設定されている土地です。簡単に言えば、家を建てたい第三者に貸している土地を指します。
「借地契約を結び第三者に貸している土地」を底地または貸地と呼び、貸している人は底地権者や地主・底地権設定者などと呼ばれます。ちなみに、底地は貸す側から見た土地の呼び方であり、借りる側から見た場合は、借地です。底地も借地も同じ土地を指しますが、貸す側・借りる側のいずれから見るかによって呼び方が異なる点は覚えておきましょう。
また、底地では、貸し出す代わりに土地の所有者は地代(賃料)を受け取れます。この地代を受け取る権利を底地権、借りた側の賃料を支払って底地を利用する権利を借地権と呼びます。
なお、底地は建物の所有を目的として土地を貸し出す場合で使われる言葉です。土地を貸す場合でも、駐車場や看板・資材置き場など建物所有が目的でない場合は、底地には当てはまりません。
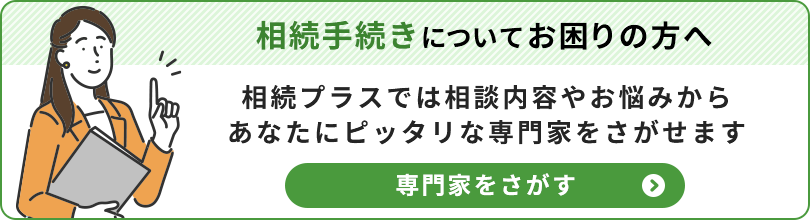
底地を相続するメリット
底地を相続することにはメリットもあります。ここでは、底地を相続するメリットについてみていきましょう。
賃料収入を得られる
底地は賃借契約を結んでいる土地のため、借主から賃料を受け取れます。底地の場合、家を建てることが目的なので借主が短期間で出ていくことは稀です。また、地代は経年によって値下がりすることは基本的にないため、長期間安定した収入を得られるというメリットがあります。
建物の維持管理費用は建物を建てた借主が負担するため、貸主は地代を受け取るだけで固定資産税以外の維持費はかかりません。アパートやマンションといった土地活用にくらべ、費用や手間の負担が少ない収入源というのも大きな魅力でしょう。
さらに、底地では以下のような費用を受け取ることも可能です。
- 更新料
- 建て替えや増改築時の承諾料
- 売却時の名義書換料
借地契約の契約期間が終了し、更新する場合には更新料を受け取ることができます。
また、建物の建て替えや増改築・売却時には貸主の合意が必要になります。この際、建て替えや増改築の際には承諾料を、売却の際には名義書換料を受け取るケースが一般的であり、貸主の臨時収入となるでしょう。
小規模宅地等の特例を適用できる
小規模宅地等の特例とは、相続する土地の評価額を減額できる特例です。被相続人が所有する土地が一定の要件を満たす場合、最大20%まで評価額を下げられます。
住宅用や事業用など土地の種類によって減額割合は異なりますが、底地の場合、貸付事業用地と見なされれば面積200㎡までの部分の評価額が50%に減額されます。ただし、底地で適用できるかは状況によって異なるので、税理士などに確認するとよいでしょう。
なお、底地はもともと自分で利用する土地(自用地)に比べて評価額が低くなるようになっています。底地の評価額の低さと小規模宅地等の特例を合わせることで、より評価額が小さくなり相続税の節税につながるでしょう。
底地を相続するデメリット
底地を相続するかはデメリットまで踏まえて慎重に検討する必要があります。ここでは、底地を相続するデメリットをみていきましょう。
相続しても活用できない可能性がある
底地は自分の土地とはいえ、第三者に貸し出しているため相続しても自由に活用できない可能性があります。活用するためには、借主に立ち退いてもらう必要がありますが立ち退き要求は難しいことが多いです。
借地借家法においては、借主の方が守られる傾向が強く、立ち退きを要求するには更新時に正当な理由や立退料が必要となります。また、借地権は契約期間が長期に渡り、さらに契約方法によっては更新が認められます。特に旧借地法においては、契約が自動更新されるなど、半永久的に土地を貸したままになり自由に使えない恐れがあるのです。
収益性が低い
地代の収入があるとはいえ、自分で土地活用するよりも収益性は低くなります。
一般的に地代は土地の価格や固定資産税・都市計画税を考慮して決められ、年間の地代は土地の価格の1〜3%、固定資産税の3〜4倍ほどが目安です。土地の価格や固定資産税は大きく変動しないため、地代が下がりにくいというメリットがある反面、地代を上げるのも難しくなります。
運用の手間やコストはかからないとはいえ収益性も低いため、収益目的の運用としては適していません。収益性を求めるなら自分で活用したほうが利益を大きくできる可能性は高いでしょう。
借地人とトラブルになるリスクがある
借地人との関係性もデメリットの1つです。底地では以下のような借地人とのトラブルに発展するケースは珍しくありません。
- 賃料の滞納
- 借地人がリフォームや売却を希望した場合の協議が難航する
- 借地人に相続が発生し権利関係が複雑になる
底地の場合、アパートやマンション経営のように管理会社や保証会社が関わっていないケースが一般的なため、賃料トラブルは自分で対応する必要があります。また、借地権は相続の対象となるため、借地権の相続がスムーズに進んでいないと賃料の請求先が分からないなどの恐れもあるのです。
賃料が滞った場合でも、固定資産税は待ってくれません。自己資金で納税に対応する必要が出てくると、金銭的な負担につながりやすいので注意しましょう。
処分をするのが難しい
底地は底地として売却することが可能です。ただし、土地自体を自由に売れるわけではありません。土地として売却するには借地人の合意が必要となり、合意のない場合は底地の権利のみを売却することになります。
しかし、底地の権利の売却先を見つけるのは容易ではないでしょう。底地は借地人の権利が強く購入しても土地を自由には使えないため、買主にメリットはあまりありません。収益性が高いなど特別な魅力があるなら別ですが、一般的な底地では権利のみの売却は難しくなります。
相続税の課税対象になる
自由に活用できない土地ですが、財産であり相続税の対象です。底地の評価額は相続財産に含まれるため、財産額によっては相続税が発生します。
ただし、前述のとおり底地の評価額は、自分のための土地よりも低くなるように考慮されています。具体的な評価額の計算方法は以下のとおりです。
底地の相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合)
借地権割合とは、土地の評価額に対する借地権の割合を指し、国税庁によって10~90%の間で地域ごとに設定されています。地域によっても異なりますが、宅地の場合は50~70%が目安です。
たとえば、自用地としての価格が4000万円、借地割合が60%の土地を貸し出した場合の評価額は以下のようになります。
上記のように、底地は借地権割合の分、自用地よりも評価額が低くなるのです。そのため、自用地として相続するよりも評価額が抑えられ相続税の節税につながります。
とはいえ、所有すると相続税だけでなく固定資産税なども発生します。所有すべきか売却すべきか税負担も考慮して決めたいという場合は、専門家に相談して決めるとよいでしょう。
底地を相続することになったときの対処法

底地を相続すると活用しにくいなどデメリットもあるため、相続するかは慎重に判断する必要があります。相続前であれば相続放棄、相続後なら売却も視野に入れることが大切です。
ここでは、底地を相続することになったときの対処法を解説します。
底地権の承継に関する契約を確認する
底地の相続では、土地の所有権と底地権の2つを分けて考える必要があります。土地の所有権は相続により相続人に継承されます。一方、底地権は賃貸借契約の内容によって相続されるかが異なってきます。一般的には、貸主の死亡により契約は終了しないため、相続人が底地権を相続します。
ただし、契約により貸主の死亡で契約が終了する場合は、底地権は継承されません。まずは、底地権の継承について契約内容を確認しましょう。そのうえで、底地権の相続が発生する場合は、以下のような対処を検討する必要があります。
借地人の協力を得て処分する
底地権の相続が発生すると、地主の変更や賃料の値上げなどで借地人にも不利益が生じかねません。とくに、相続人に相続放棄されると底地が国に物納されるリスクもあるので、借地人と話し合って処遇を決めることが大切です。相続によってデメリットが生じやすい場合、借地人も処分に協力してくれる可能性があります。
借地人の協力を得て処分する方法としては、以下の3つが検討できます。
- 借地人と共同で売却する
- 借地人に売却する
- 底地と借地権を等価交換して完全所有してから売却する
それぞれ見ていきましょう。
借地人と共同で売却する
借地人と共同で土地+建物として売却する方法です。底地と借地権のセットであれば、買主は通常の土地の所有と同じであるため買い手も付きやすく市場価格での売却が期待できるでしょう。
ただし、借地人の協力を得られない可能性もあります。仮に売却できた場合でも、売却金の分配で揉めやすいため、事前にしっかり話し合っておくことが大切です。
借地人に売却する
第三者には売りにくい底地権ですが、賃借人であれば買い取ることで完全所有できるので購入のメリットがあります。
自由に建て替えやリフォーム・売却ができ、賃料の支払いも必要なくなるのであれば、購入してくれる可能性も高いため、打診してみるとよいでしょう。
底地と借地権を等価交換して完全所有してから売却する
等価交換とは価値が等しいものを交換する方法です。底地を借地権と同等になるように分割し、地主と借主がそれぞれ完全所有するようにしてから自身が取得する分を売却します。
ただし、底地に分割する大きさがなければ完全所有できる土地も小さくなるため、売却しにくくなる点には注意しましょう。
専門の不動産買い取り業者に売却する
底地は自由に使えないため、買い手がつきにくく仲介での売却は難しくなります。また、不動産会社も取り扱ってくれないケースも珍しくありません。
底地のみで売却する場合、仲介ではなく買取を視野に入れることをおすすめします。とくに、底地などの訳あり不動産を専門に取り扱う買取業者であれば底地売却やトラブル時の対応のノウハウがあるのでスムーズに手放せられる可能性があるでしょう。
ただし、買取は仲介よりも価格が下がり、底地はより価格が下がりやすい点には注意が必要です。とはいえ、底地は仲介での売却も活用も難しいため、価格が下がってもすぐに手放したいなら現実的な選択肢といえます。
相続そのものを放棄する
底地を相続しても活用が難しいというのであれば、相続放棄をすることで相続を防げます。一度相続してしまうと手放すのは容易ではなくなりますが、相続前であれば相続放棄するだけです。相続後に手放すことを検討しているのであれば、容易に手放せる段階で対処しておくのもよいでしょう。
しかし、相続放棄はすべての財産の放棄が必要です。底地だけ放棄して現預金は相続することはできないので、本当に相続放棄してもよいかは慎重に判断する必要があります。また、相続放棄できるのは相続開始を知ってから3か月以内という期限があり、期限を超えると相続放棄は基本的にできません。
期限ぎりぎりで手続きしようとすると間に合わない恐れもあるので、早めに手続きを進めることが大切です。
相続放棄は底地の相続を回避するひとつの方法ですが、相続財産が他にある場合はデメリットもあります。他に財産がある場合は他の相続人に譲るなどの選択肢もあるので、相続放棄が妥当かは専門家に相談しながら決めることをおすすめします。
相続するのであれば単独名義で相続する
不動産の相続では相続人全員で共有名義にする方法もありますが、共有名義はおすすめできません。共有名義の不動産は、活用や売却に他の共有者の合意が必要です。
共有名義のまま次の相続が発生するとより権利関係も複雑になり、処分も活用も難しいという状況にもなりかねないでしょう。通常の不動産であっても共有名義の相続は権利関係が複雑になりがちです。
さらに権利関係の複雑な底地で共有名義にしてしまうと、問題が大きくなりかねないので注意しましょう。底地の相続が必要という場合は、基本的には単独名義での相続をおすすめします。
しかし、一般的な家庭においては相続財産に不動産があると、財産全体の内、不動産を占める割合が大きくなることが多いです。このため、単独名義で相続することで、相続人間のバランスが取りにくくなり、他の相続人とトラブルになったり、トラブルにならないよう金銭的負担をしなければならなかったりといった可能性もあります。底地の相続を含めトラブルなくスムーズに相続を進めたいなら、分割方法などを専門家へ相談することをおすすめします。
底地の相続は専門家に相談を
底地は、借りている人がいる以上、所有者は自由に活用できません。地代収入を得られ相続税評価額が下がるというメリットがあるとはいえ、借地人とのトラブルや収益性が大きくないなどのデメリットも大きくなります。
相続してしまった場合は処分の検討をおすすめしますが、複雑な権利関係も絡むので検討する場合は底地売却に詳しい専門家に相談することが大切です。また、相続前に対策しておくこともできるので、底地相続に不安があるなら早めに専門家に相談しておくとよいでしょう。


