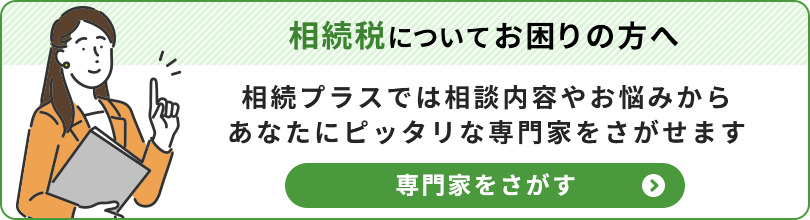特定空き家に認定されると、固定資産税の優遇措置を適用できずに6倍もの税金を納めなければならないケースがあります。空き家を相続する人の中には、特定空き家になるのではと不安を感じている人もいるでしょう。この記事では、特定空き家とは何か、また今後特定空き家同様に税金の上がる恐れのある管理不全空き家についてわかりやすく解説します。
目次開く
空き家を相続すると固定資産税が高くなる?
空き家を相続すると、固定資産税を納税する必要があります。ただし、空き家だからといって固定資産税が高くなるわけではありません。
実際に人が住んでいる・いないに関わらず居住用の建物が建っている土地であれば、固定資産税の特例措置が適用されるため、空き家でも特例適用後の税金が課税されます。しかし、同じ空き家でも「特定空き家(特定空家など)」「管理不全空き家」に認定されると、この特例措置が適用できなくなる恐れがあります。
特例が適用できないことで本来の高い税金を納める必要があることから「固定資産税が高くなる」と言われるのです。
空き家を相続したら発生する税金
空き家を相続する場合、固定資産税以外にもさまざまな税金が発生します。
主な税金は次の通りです。
- 固定資産税
- 土地計画税
- 相続税
- 登録免許税
- (売却・運用時)所得税と住民税
不動産を所有していると毎年課せられる税金が、固定資産税と都市計画税です。毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となります。
なお、都市計画税は不動産が市街化区域にある場合にのみ、固定資産税と一緒に徴収されます。
空き家を相続した際に発生する税金が、相続税と登録免許税です。相続財産に課せられる相続税は、不動産を含めた相続財産が基礎控除額を超える場合に課税されます。
不動産を相続する場合は、所有者を被相続人から相続人に変更する相続登記が必要になり、登記の際には登録免許税という税金もかかります。
相続した空き家を売却した場合、売却利益に対して所得税・住民税が譲渡所得税として発生します。また、賃貸などで運用し収入を得た場合は、所得に対して所得税・住民税がかかるのです。
住宅用地特例制度
住宅用地特例制度とは、固定資産税を軽減するための特例措置です。
この特例では、住宅やアパートなど人が居住するための建物が建っている土地は、下記のような標準課税の減額を受けられます。
<小規模住宅用地>
- 適用面積:住宅1戸につき200㎡まで
- 軽減率:評価額を6分の1
<一般住宅用地>
- 適用面積:住宅1戸につき200㎡を超える部分
- 軽減率:評価額を3分の1
宅地の面積200㎡を境に小規模住宅用地と一般住宅用地に分け、固定資産税評価額が最大6分の1に軽減されるのです。
たとえば、敷地300㎡・固定資産税評価額4500万円の場合で、固定資産税をシミュレーションしてみましょう。
固定資産税の計算は次の通りです。
固定資産税=固定資産税評価額×1.4%(標準税率)
特例を適用しない場合、固定資産税は次のようになります。
固定資産税=4500万円×1.4%=63万円
一方、特例を適用する場合を見ていきましょう。特例を適用した場合、固定資産税評価額は次のように軽減されます。
- 200㎡以下の部分=4500万円×(200㎡/300㎡)×1/6=500万円
- 200㎡超えの部分=4500万円×(100㎡/300㎡)×1/3=500万円
固定資産税評価額が500万円+500万円=1000万円となるので、固定資産税は次の通りです。
固定資産税=1000万円×1.4%=14万円
特例適用までの固定資産税が63万円に対し適用後が14万円と、大きな節税効果があるのです。
この特例は、居住用の建物が建っていれば空き家であっても適用できます。
改正空家特措法
空家特措法とは、空き家への対策を強化するために平成27年に施行された法律のことです。この法律では、空き家を次のように定義しています。
この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。※引用:空家等対策の推進に関する特別措置法|第2条(定義)
適切に管理されていない空き家は、倒壊して近隣に被害を出すリスクが高まります。また、衛生上や景観上の問題だけでなく、犯罪の温床になるなどのリスクもあります。
全国的に空き家が増え、空き家の抱える問題を解決するために施行されたのが、この空き家特措法なのです。
空家特措法では、管理の不十分な空き家を「特定空き家」に指定し、改善などの勧告・命令などができます。また、特定空き家に指定されると、先述した固定資産税の住宅用地特例制度が適用できなくなる恐れもあるのです。
しかし、空家特措法では、特定空き家に指定されない空き家への対策ができないなどの自治体が対応を苦慮するケースも多いという問題があります。
そこで、より実情に即した対応が取れるように、空家特措法は令和5年に改正され令和5年12月に改正空家特措法として施行されます。
改正空家特措法とそれまでの空家特措法との大きな違いは、下記の通りです。
- 空き家所有者の責務強化
- 管理不全空き家の新設
- 空家などの活用拡大
改正空家特措法では、空き家の所有者に対する努力義務が強化され、国・自治体の施策への協力の努力義務が加わっています。さらに、自治体への管理・活用の権限も拡充されています。
また、改正空家特措法では、特定空き家になる恐れのある空家を「管理不全空き家」に指定できるようになり、指導・勧告が可能になっているのです。なお、管理不全空き家についても、特定空き家同様に固定資産税の特例措置が適用できなくなるケースがあります。
今回の改正により空き家の所有者はよりしっかりと対策する必要がでてきました。まずは、特定空き家や管理不全空き家について理解しておくことが大切です。
特定空き家と管理不全空き家については、以下で詳しく解説していきます。
特定空き家と管理不全空き家

改正空家特措法では、新たに管理不全空き家が新設されています。ここでは、特定空家と管理不全空き家について確認していきましょう。
特定空き家
特定空き家とは、下記のような状態の空き家のことを指します。
- そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態
- 著しく衛生上有害となる恐れのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空き家を認定するのは自治体です。
各市区町村で空き家の状況を調査し、問題があるとされる空家が特定空き家に認定されるのです。
管理不全空き家
管理不全空き家とは、特定空き家の予備軍と言える空き家のことです。特定空き家になる前に、自治体で指導・勧告することで特定空き家になることを防ぐために新設されました。
現時点では明確な基準はなく今後定められていく予定ですが、草が生い茂っているなどそのまま放置すれば特定空き家になる恐れがある空き家が管理不全空き家となると予測されます。
特定空き家・管理不全空き家に認定される可能性がある家の特徴
適切に管理されている空き家であれば、特定空き家や管理不全空き家に認定されることはありません。
では、どのような状態の空き家が認定される恐れがあるのでしょうか。
特定空き家に認定される可能性がある家の特徴
特定空き家に認定される可能性がある家の特徴は、下記の通りです。
- 倒壊のリスクが高い
- 衛生上問題のある
- 著しく景観を阻害している
長期間放置されている家は、劣化や害虫などの影響で倒壊のリスクが高まります。
万が一、倒壊してしまうと近隣や通行人に被害が出る恐れがあり、特定空き家に指定される可能性が高いのです。また、衛生上問題がある家とは、異臭や害虫・害獣の発生などが問題となっている空き家です。
空き家は、管理されていないことから不法投棄の場にされているケースが少なくありません。長期間ゴミが放置されると悪臭が出るだけでなく、害獣の侵入や放火・火災などの問題も出てくる恐れがあるのです。
空き家を放置していると、雑草やゴミ・家の損壊など景観上の問題もあります。そのままの状態では、近隣住人の住環境に影響するだけでなく近隣住人が不動産を売りにくいなどの問題も出てくるのです。
管理不全空き家に認定される可能性がある家の特徴
管理不全空き家に認定される可能性がある家の特徴は、次の通りです。
- 壁や屋根が壊れていて倒壊の恐れがある
- 窓が割れて放置されている
- 雑草や樹木が生い茂っている
- ゴミが放置されている
- 害虫や害獣が発生している
管理不全空き家は特定空き家とまではいかないまでも、その一歩手前の段階であれば認定される恐れがあります。
特定空き家・管理不全空き家に認定されたらどうする?
特定空き家・管理不全空き家に認定されると、自治体から次のような順番で措置が取られます。
- 助言や指導
- 勧告
- 命令
- 戒告・代執行
なお、管理不全空き家は勧告までとなり、勧告に従わず放置していると特定空き家に指定される可能性があります。
特定空き家の場合、命令に従わない場合50万円以下の罰則が科せられ、さらに従わなければ強制的な除去処分を受ける恐れがあります。また、特定空き家・管理不全空き家ともに「勧告」を受けると固定資産税の特例を適用できなくなるので注意しましょう。
特定空き家・管理不全空き家に認定された場合、助言や指導の段階で自治体の指示に従い、空き家を適切に管理することが大切です。
適切に管理し認定された要因を改善できれば、認定は解除されます。
特定空き家・管理不全空き家に認定されないためにはどうすればよい?
認定されないためには、空き家を適切に管理することが大切です。
管理方法には次のような方法があります。
- 自分で管理する
- 管理会社に委託する
空き家が近くにある・自分で管理する時間をとれるという場合は、自分で管理するのも良いでしょう。定期的な掃除や管理・適切な管理・庭の手入れなどを行って、家の状態をきれいに保つようにします。
遠方の空き家や自分で管理の時間が取れないなら、空き家を管理してくれる業者に委託するのもおすすめです。また、空き家の状態や立地が良いのであれば、賃貸として貸し出す方法もあります。
誰かが住んでいる家であれば、入居者が管理してくれるので自分で管理する手間もないうえに家賃収入を得ることも可能です。
とはいえ、空き家は所有しているだけでも固定資産税などのコストがかかります。さらに定期的な管理となると時間も手間もかかるでしょう。賃貸にしても、立地や物件の状況によっては借り手が付かない恐れもあります。
管理や賃貸などの活用が難しい空き家であれば、売却してしまうことをおすすめします。売却してしまえば、管理の手間やコストから解放されます。
売却金というまとまった資金も手に入れられ、平等な遺産分割や相続税の原資ともなるでしょう。

相続登記後は適切な管理か売却を検討しよう
所有する空き家が特定空き家・管理不全空き家に認定されると、固定資産税の優遇措置を適用できなくなる恐れがあります。
認定されないためには、定期的な清掃や修繕などの適切な管理が必要です。遠方の空き家など管理がしきれない場合は、売却を視野に入れるとよいでしょう。
管理・売却どちらにしても、まずは相続登記することが空き家相続の第一歩です。相続後は速やかに相続登記して空き家対策を進めていきましょう。