相続税が払えないと加算税や延滞税などのペナルティが課せられるうえに、財産が差し押さえられる最悪なケースも否定できません。本記事では、相続税が払えない理由や対処法について詳しく解説します。生前から対策することで、相続税の負担軽減につなげる方法もご紹介します。相続税の納税ができるかどうか不安を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
地元の専門家をさがす
遺産を相続しているのに相続税が払えない理由
そもそも相続税は、相続財産の総額が基礎控除額を超えたときに申告が必要です。基礎控除額は法定相続人の数によって変動し、下記のように算出します。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が配偶者・長男・次男の3人だったとき、相続税の基礎控除額は4800万円です。被相続人が残した相続財産の総額が4800万円を超える場合に相続税の申告をしなければなりません。
また、相続税には基礎控除以外にもさまざまな控除や特例制度が設けられています。控除や特例の活用によって相続税が0円になったとしても、控除や特例を適用させるためには相続税の申告が必要です。
さらに、相続財産の総額が控除や特例の範囲を超えると、相続税を納税しなければなりません。相続税の申告・納税の期限は、相続発生があった事実を知った日の翌日から10か月以内です。
相続税額が遺産総額を上回るケースは少ないため、「払えないことはないのではないか」と思われる方がいるかもしれません。しかし、下記のような理由によって相続税が払えないケースもあるでしょう。
- 現金ではなく不動産や換金性の低いものなどを多く相続した
- 遺産分割協議が終わらず預金が凍結されている
それぞれの理由について、詳しく確認しましょう。
現金ではなく不動産や換金性の低いものなどを多く相続した
現金や預貯金などの金融資産よりも、不動産や自動車など換金性の低いものを多く相続した場合、遺産のなかから相続税を払うことができません。
たとえば、現金や預貯金以外でも、現金化のしやすい株式や保険などが多ければ、遺産のなかから支払いができるでしょう。しかし、遺産のほとんどが自宅の土地や建物だった場合、相続人自身が相続税を支払わなければなりません。
このように、遺産の内容が不動産や換金性の低いものばかりの場合、相続時点で相続人に預貯金がなければ相続税の支払いができずに困ってしまうでしょう。
遺産分割協議が終わらず預金が凍結されている
被相続人が亡くなると、現金や預貯金、不動産などの遺産は法定相続人全員の共有財産となります。被相続人が預貯金を多く残していたとしても、特定の法定相続人が勝手に引き出さないよう、金融機関に連絡をして口座を凍結させます。
口座凍結は相続手続きを行うまで継続され、遺言書や遺産分割協議によって「誰が相続するか」を確定しなければ口座の名義変更や解約ができず、現金を引き出せません。
誰がどの遺産をどれだけ引き継ぐかを決める遺産分割協議で法定相続人同士の意見がまとまらない場合、口座の名義変更や解約はできないままです。相続税納税の期限を迎えても遺産分割協議が終わっていなければ、相続税を遺産のなかから払うことができません。
相続税を払えないとどうなる?
相続税の申告・納税を期限までに終えられなければ、下記のようなペナルティが課されます。
- 加算税や延滞税が課される
- 財産を差し押さえられる
具体的に確認していきましょう。
加算税や延滞税が課される
相続税を期限内に申告・納税しなかった場合、下記のような税金が課されるため注意しましょう。
| 税金の種類 | 概要 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 正当な理由なく、期限までに申告をしていなかった場合に課される |
| 過少申告加算税 | 期限までに申告をしていても、自覚なしに実際よりも過少の申告をしていた場合に課される |
| 重加算税 | 自覚がありながらも、遺産の隠ぺいや虚偽の申告をした場合に課される |
| 延滞税 | 正しく申告していても、期限内に納税を行わなかった場合に課される |
申告期限までに申告と納税の両方を行っていなかった場合、無申告加算税と延滞税が両方課されるため注意しましょう。
<無申告加算税>
- 申告期限から1か月以内に自主的に申告した場合:免除
- 税務調査の事前通知前に自主的に申告した場合:5%
- 税務調査の事前通知後に申告した場合:10〜20%
<延滞税※>
- 納付期限の翌日から2か月間:2.4%
- 納付期限の翌日から2か月を経過した日以降:8.7%※
※令和6年1月1日~令和6年12月31日の延滞税の税率です。銀行の新規の短期貸出約定平均金利によって変動します。
期限までに納税しなかった場合に課される延滞税は、納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じて利息として課されるため、税額が増えていきます。
また、相続税には連帯納付義務があるため、同じ被相続人から遺産を相続した相続人全員に対して相続税を納める義務が発生します。1人でも期限内に相続税を払わなかった相続人がいると、他の相続人が立て替えなければなりません。
参照:延滞税の割合|国税庁
財産を差し押さえられる
相続税を払わないまま滞納し続けると、国税庁から財産を差し押さえられます。主に不動産が差し押さえの対象ですが、場合によっては所有する動産も差し押さえられて競売にかけられます。
財産差し押さえまでの流れは、下記の通りです。
- 滞納している納税者に督促状が届く
- 連帯納付義務にもとづいて他の相続人に督促状が届く
- 差し押さえの手続きに移行し、差押予告通知書が届く
- 差押調書が届き、差し押さえが実行される
本来の納税義務者の財産を差し押さえても納税する相続税の額に届かない場合や、不動産ばかりで換金しづらい場合は、連帯納付義務者である他の相続人の財産が差し押さえられる可能性があります。
相続税を払わないまま放置していると、他の相続人が迷惑を被ることになりかねません。次章から解説する対処法を実践し、できるだけ期限内に相続税を納めましょう。
相続税が払えない場合の対処法

相続税が払えない場合の対処法は、主に7つあります。
- 延納して分割で払う
- 不動産などを現金化して払う
- 現物で納める(物納)
- 相続放棄する
- 金融機関から借りて払う
- 一部の遺産分割協議を先に行う
- 預金の払い戻し制度を活用して払う
順番に詳細を確認し、あなたに最適な対処法を見つけましょう。
延納して分割で払う
原則、相続税は期限内に現金一括で納めなければなりません。しかし、下記の4つの要件をすべて満たせば、延納して分割で納めることが認められる場合があります。
- 相続税額が10万円以上であること
- 現金一括納付が困難であること
- 申告期限までに延納申請書などを提出すること
- 担保財産を提供すること
延納は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申請をし、認められれば年払いができます。相続人ごとに認められるかどうかが判断されます。
延納が認められれば1回あたりの税負担が軽減される一方、1.2〜6.0%の利子税が発生するため納税額は増えてしまう点に注意しましょう。
また、遺産の内訳をみたときに、不動産の割合が75%以上であれば、最長20年の延納が認められます。
不動産などを現金化して払う
遺産のなかに土地や建物などの不動産が含まれているのであれば、売却で得た売却代金から相続税を支払うことも選択肢として検討しましょう。
不動産を売却するには、相続登記を行って一度相続人の名義にしなければなりません。今後、誰かが住んだり賃貸で貸し出したりする予定がないのであれば、積極的に検討しましょう。
購入額より高い価格で売却すると譲渡所得税が発生する場合もありますが、相続開始から3年10か月以内に売却すれば譲渡所得額を減額できる特例を活用できる場合があります。相続税の支払い分を差し引いても、資金が手元に残るケースもあるでしょう。
ただし、立地や土地の大きさ、建物の築年数などによって、希望価格で希望時期までに売却できるかどうかはわかりません。さらに不動産の測量費や売買仲介手数料が発生し、思った以上の資金が手に入らない場合もあります。
不動産などを現金化して相続税を納税するのであれば、早めに準備を始めるようにしましょう。
現物で納める(物納)
現物で相続税を納める「物納」という方法もあります。物納とは、不動産や有価証券などの遺産をそのまま相続税として納める制度です。
下記の4つの要件をすべて満たせば、物納が認められる場合があります。
- 延納であっても金銭で納付することが困難であること
- 物納申請財産が日本国内にあること
- 管理処分不適格財産に該当しないものを物納すること
- 申告期限までに物納申請書などを提出すること
不動産や株式などの金銭的価値が評価され、その評価額をそのまま相続税に充てることが可能です。そのため、相続人に納税するための資金がなくても相続税を納められます。
ただし、相続した財産だけが物納対象となり、下記のように優先順位が決められています。
- 第1順位:不動産や上場株式・国債・地方債などの有価証券、船舶
- 第2順位:非上場株式など
- 第3順位:貴金属などの動産
たとえば、不動産を持っているにもかかわらず、非上場株式や貴金属を物納することはできません。そのため、「どの財産を物納するか」を選ぶことはほとんどできないと思っておきましょう。
また、相続時の時価よりも低い金額で評価されやすい点にも留意が必要です。さらに評価のために測量を行う必要があるため、測量の費用がかかる点もあらかじめ理解しておきましょう。
相続放棄する
相続放棄をすることで相続税から免れる方法もあります。相続放棄とは、プラスの遺産もマイナスの遺産もすべてを相続しないための手続きです。
相続放棄をすると「もとから法定相続人ではなかった」として扱われるため、相続税の納税義務や連帯納付義務を負う必要がありません。もちろん遺産分割協議に参加する必要もなくなり、相続トラブルの回避にもつながります。
ただし、相続放棄をするとあらゆる財産を相続する権利を失います。たとえば、被相続人の家に同居していた息子だったとしても、相続放棄をすると自宅を相続することができません。
また、相続放棄の手続きの期限は、相続が発生した事実を知ってから3か月以内です。相続が開始したらすぐに相続放棄をするかどうかの検討をしましょう。
金融機関から借りて払う
納税のために必要な資金を金融機関から借りる方法もあります。元金と利息を返済してく必要が出てくるため、延納ができない場合に検討しましょう。
ただし、相続税を納めるための借入は、担保や保証人が求められるケースがほとんどです。住宅ローンなどの一般的な融資と比べて審査が長引く場合があります。借入の審査が申告期限に間に合わない場合もあるため、早めに延納した場合と比較をして金融機関へ相談しましょう。
一部の遺産分割協議を先に行う
遺産分割協議で意見がまとまらずに相続税の支払いが難しい場合、相続税額分に対する遺産分割協議を先に行うことで解決できる可能性があります。これを一部分割といいます。
たとえば、相続税が300万円だったとき、預金口座にある300万円分だけを遺産分割することが可能です。一部分割について法定相続人全員の合意が認められれば、口座の凍結を解除して資金を引き出せるようになります。
納税に必要な資金さえ準備できれば、申告期限経過のペナルティを受けずに済みます。法定相続人全員にとってのメリットが大きいため、納得してもらいやすいでしょう。
ただし、一部分割を行ったとしても、残りの遺産に関する遺産分割協議は続けなければなりません。先に行った一部分割をどのように反映させるかについて揉める可能性もあります。
遺産分割協議がまとまらない場合、弁護士などの相続に詳しい専門家に立ち会ってもらって冷静な話し合いができる環境を整えましょう。
預金の払い戻し制度を活用して払う
遺産分割協議で意見がまとまらずに相続税の支払いが難しい場合、預金の払い戻し制度を活用する方法もあります。遺産分割協議で合意が取れない状況であっても、相続税の支払いや葬儀費用の支払いなどによって口座の凍結を解除したいシーンはたくさんあるでしょう。
そこで活用したい制度が、相続預金の払い戻し制度です。相続預金の払い戻し制度とは、遺産分割を終える前に資金が必要となった場合に一定の預金の払い戻しができる制度です。令和元年7月に施行されたばかりのため、あまり知られていないかもしれません。
民法では、以下2つの払い戻し制度が設けられています。
- 家庭裁判所の判断で払い戻しができる制度(家庭裁判所が仮取得を認めた金額まで)
- 金融機関での手続きで払い戻しができる制度(同一金融機関からの払い戻しは150万円が上限)
ただし、実際に個人が交渉することは難しいため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
地元の専門家をさがす
参照:遺産分割前の 相続預金の 払戻し制度|一般社団法人全国銀行協会
「相続税を払えない」とならないためにできること
そもそも、相続税を納税しなければならない人は少ないです。国税庁が発表している「令和4年分相続税の申告事績の概要」によると、令和4年度の相続税の課税割合は9.6%です。
つまり、被相続人100人のうち、相続税の発生するケースは10人より少ないことを示しています。
下記のようなポイントを知って、相続税を払う必要がないように対策をしましょう。
- 特例制度、各種控除を利用して相続税そのものを低くする
- 生前贈与を活用する
- 相続時精算課税制度を活用する
- 養子縁組をする
- 生命保険を活用する
順番に解説します。
特例制度、各種控除を利用して相続税そのものを低くする
相続税には特例制度や控除枠が設けられているため、積極的に活用して相続税の金額を引き下げましょう。
よく活用されている特例や控除は、下記の通りです。
| 特例制度・控除枠 | 内容 |
|---|---|
| 配偶者控除 | 1億6000万円、もしくは法定相続分の範囲までなら配偶者の相続税が非課税になる制度 |
| 未成年の控除 | 相続人が未成年の場合、(18歳-相続時の年齢)×10万円の額が相続税額から控除される制度 |
| 小規模宅地等の特例 | 被相続人が住んでいた土地や事業・貸出をしていた土地について、一定の要件を満たせば土地の評価額を最大80%減額できる制度 |
| 納税猶予の特例 (農地などの納税猶予制度) | 農地を相続したときに相続税の支払いの先延ばし、もしくは免税できる制度 |
それぞれの特例制度や控除枠を活用するには、それぞれの細かな要件を満たす必要があります。積極的に税理士などの専門家に相談しましょう。
生前贈与を活用する
生前にできる対策として、生前贈与を行う方法があります。生きているうちに贈与を行っていれば、本人が所有する財産が減って相続財産を減らすことが可能です。
贈与にも贈与税が発生しますが、年間110万円までであれば贈与税は発生しません。また、下記のような非課税枠も設けられているため、上手に活用すれば税金をかけずに次世代へ財産を移転させられます。
- おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)
- 教育資金の一括贈与の非課税枠
- 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税枠
- 住宅取得等資金の贈与の非課税枠
なかには1000万円・1500万円といった大きな非課税枠もあるため、賢く生前贈与を行って相続税の節税につなげましょう。
「生前贈与」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

相続時精算課税制度を活用する
相続時精算課税制度を活用すると、年間110万円までの基礎控除と生涯を通して贈与額2500万円までの非課税控除が受けられます。ただし2500万円を超えた贈与額に対して、一律20%の贈与税が発生します。
相続時精算課税制度を活用して贈与すると、贈与財産は相続財産に加算されて相続税が発生する点に注意が必要です。不動産の評価額は贈与をした時点での時価となります。
そのため、価値の変わらない財産を生前贈与しても節税にはなりません。土地開発によって将来の高騰が見込まれる土地や利益を産む賃貸不動産、値上がりが見込まれる有価証券などの贈与に相続時精算課税制度は有効といえるでしょう。
一方で、価値の下がる可能性のある住居不動産であれば、相続時に評価したほうが相続税の節税につながります。

養子縁組をする
養子縁組を活用すれば、相続税の基礎控除の枠が増えるため相続税を軽減できます。なぜなら、相続税の基礎控除額は下記のように算出するためです。
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
養子は実子と同様に法定相続人となるため、1人養子縁組をすると600万円分基礎控除の枠が増えます。
ただし、養子縁組によって増やせる「基礎控除額算出における法定相続人の数」には限度があるため注意しましょう。原則、実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までなら、法定相続人の数に加えることが可能です。
また、孫と養子縁組した場合、その孫が相続する遺産に対して相続税が2割加算となる点にも留意しましょう。
生命保険を活用する
生命保険の保険金も相続財産に含まれますが、以下の非課税枠が活用できます。
生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の数
課税額を計算するために、最低でも500万円を相続財産から差し引けます。そのため、現金や預貯金で財産を残すよりも、生命保険を掛けておいた方が相続税の負担を軽減することが可能です。
「相続税の特例制度や控除枠」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
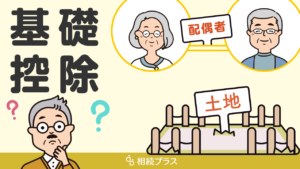
相続税が払えないと困ったら専門家に相談しよう
相続税の納付は、原則として相続発生があった事実を知った日の翌日から10か月以内に現金による一括払いをしなければなりません。そのため、遺産に現金や預金が十分に含まれていないと、相続人自らに経済的負担を強いられる場合があります。
また、相続税を支払うだけの預貯金が遺産にあったとしても、遺産分割がまとまっていないと被相続人の口座は凍結されたままです。相続税の納付期限までに遺産分割をまとめて手続きしなければ、支払いは困難となるでしょう。
このように、相続税が払えない要因はさまざまです。もし、相続税の支払いで困ったことがあるのであれば、税理士をはじめとする相続に詳しい専門家に相談しましょう。とくに、凍結されている口座からの払い戻しを希望する際には、弁護士の手を借りるとスムーズに解決できる場合があります。
積極的に専門家へ相談し、抱えている不安・困りごとを解決しましょう。
地元の専門家をさがす


