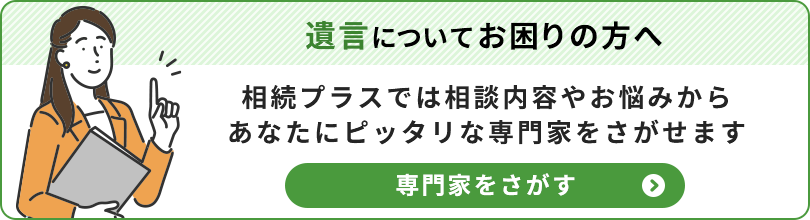遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために実務を行う人のことです。相続財産の調査から相続人の確定、財産の移転手続きまでを行います。本記事では、遺言執行者の役割や権限、選任方法について詳しく解説します。必要なケースや報酬についても解説しているため、これから遺言書を書く方や、遺言書が見つかった方の参考になれば幸いです。
目次開く
遺言執行者とは
遺言執行者とは「ゆいごんしっこうしゃ」と読み、その名の通り遺言を執行するための人です。
遺言執行者について、より理解を深めるために以下の項目ごとに解説を進めていきます。
- 遺言執行者の役割
- 遺言執行者が持つ権利義務
- 遺言執行者にできないこと
- 遺言執行者の通知義務
- 遺言執行者を選任するメリット
順番に確認しましょう。
遺言執行者の役割
遺言執行者の役割は、遺言書の内容を実現することです。遺言書は遺言を残した方が亡くなってから開封されるため、本当に遺言書の内容が実現されるかどうかを遺言者は見届けることができません。
そのため、遺言書を残した被相続人が遺言書の内容を確実に実現させるために遺言執行者を指定します。信頼できる親族や知人を指定するケースは少なくありません。
一方、相続人たちが遺言書の内容をスムーズに実現するために遺言執行者を選任するケースもあります。この場合、家庭裁判所にて遺言執行者を選出しなければなりません。
遺言執行者は、未成年や破産者でなければ誰でもなれます。相続人が遺言執行者となることも可能です。しかし、相続人のなかに遺言執行者がいると他の相続人から反発される可能性があります。
司法書士や弁護士などの専門家を選任すると、相続トラブルを回避しながら円満に相続手続きが進められます。
遺言執行者が持つ権利義務
遺言執行者が持つ権利義務は、民法第1021条によって以下のように定められています。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
※引用:民法|第1021条(遺言執行者の権利義務)
具体的に遺言執行者が行える権限は、以下の通りです。
- 相続人の調査
- 相続財産調査
- 財産目録の作成
- 子どもの認知
- 預貯金の払い戻しと分配
- 不動産の相続登記の手続き
- 貸金庫の解錠・解約・取り出し
- 株式や自動車の名義変更手続き
- 寄付行為
- 相続人の廃除とその取り消し
- 保険金受取人の変更
子どもの認知や相続人の廃除とその取り消しは遺言執行者にしか認められていない権利です。必要な際は、遺言執行者を選出すると、遺言書の内容の実現がしやすくなるでしょう。
このように、遺言執行者は相続人との間に利益相反が生じたとしても、遺言書の内容を実現するために動かなければなりません。
また、令和元年7月1日の民法改正によって、遺言執行者による単独での登記申請ができるようになりました。以前は相続・遺贈を受けた当事者にしかできませんでしたが、権限が見直されている点に注意しましょう。
遺言執行者にできないこと
遺言執行者には多くの権限が与えられている一方で、遺言執行者にできないこともあります。
遺言執行者の権限に含まれていない行為は、相続税の申告です。相続税の申告は、相続人や遺贈者に課された義務だからです。
そのため、相続人や遺贈者に代わって相続税の申告はできないため注意しましょう。
ちなみに、税務の代理や税務書類の作成は、税の専門家である税理士の独占業務です。相続税申告が必要な際は、税理士に相談しましょう。
遺言執行者の通知義務
遺言執行者には、以下のような通知義務があります。
遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
※引用:民法|第1021条(遺言執行者の権利義務)
この通知義務は、令和元年7月1日の民法改正によって加えられた義務です。従来であれば遺言執行者からの通知なしに、相続人が遺言書の内容や財産状況を知らないまま手続きが進められてしまい、トラブルに発展することが多かったためです。
任務開始時以外にも、相続人から請求があったときや遺言執行が終了したときには、遺言執行者から相続人全員に対して通知しなければならないと義務付けられています。
通知義務を果たさない場合、相続人が遺言執行者を解任させる可能性があります。
遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
※引用:民法|第1019条(遺言執行者の解任及び辞任)
解任したい場合は、家庭裁判所に対して遺言執行者解任の申し立てを行いましょう。
遺言執行者を選任するメリット
遺言執行者を選任するメリットは、大きく2つあります。
- 相続手続きがスムーズに進む
- 相続人が勝手に遺産を処分できなくなる
遺言執行者がいれば、他の相続人の同意がなくても遺言執行者がすべての相続手続きを遺言書通りに進めてくれるため、円滑に手続きを進められます。相続人自身が銀行口座や不動産などの名義変更をしなくてもよいため、相続人の負担が大幅に減るでしょう。
また、遺言執行者がいると相続人は遺言書の内容に反した行為ができなくなり、勝手に遺産を処分することができません。
このように、遺言執行者がいれば、遺言書通りの遺産分割が実現し、相続人の相続手続きの負担軽減につながります。
遺言執行者に指定・選任されたら行うこと
遺言執行者に指定・選任されたら、以下の手順で業務を遂行していきましょう。
- 遺言執行者就任の通知と遺言書の写しの送付
- 相続財産調査
- 相続人の調査・確定
- 財産目録の作成
- 預貯金口座の解約・名義変更
- 不動産の名義変更(相続登記)
- そのほかの業務
- 業務終了の通知
遺言執行者の主な業務の流れは、上記の通りです。もちろん、相続財産や相続人の状況、遺言書の内容によって業務の内容が変わる場合もあります。
ここでは、多くの遺言執行者に当てはまるケースをご紹介します。
1.遺言執行者就任の通知と遺言書の写しの送付
遺言執行者として指定・選任され、自身が承諾したら、ただちにすべての相続人に対して遺言執行者就任の通知を行いましょう。
また、あわせて遺言書の内容も通知する義務があります。就任通知と同時に、遺言書の写しも相続人に対して送付しましょう。
2.相続財産調査
被相続人が残した相続財産をすべて調査しましょう。相続財産には、以下のようなものが含まれます。
<プラスの財産>
- 現金
- 預貯金
- 不動産
- 有価証券(株式やゴルフ会員権など)
- 一般動産(自動車や骨董品、貴金属など)
<マイナスの財産>
- 借入金(住宅ローンの残高債務やクレジット残債務など)
- 未払金(水道光熱費や医療費など)
- 保証債務・連帯債務
これらは相続財産の一例です。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についてもしっかり調査をしましょう。
3.相続人の調査・確定
相続財産の調査と同時に、相続人の調査を行って相続人の確定をしましょう。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集して確認を行います。
戸籍謄本を何通も集める必要があり、相続人調査には時間と労力がかかります。また、古い戸籍だと手書きで記載されているため、判読が難しい場合もあるでしょう。
とくに、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースや代襲相続が発生しているケースにおける相続人調査は困難になりやすいです。
4.財産目録の作成
すべての相続財産が洗い出せたら、財産目録を作成しましょう。財産目録とは、すべての相続財産の内容を一覧にしたものです。
財産目録が完成したら、すべての相続人に対して送付します。送付が完了したら、遺言書に記載された通りに財産を指定の人へ引き渡すための手続きを進めます。
5.預貯金口座の解約・名義変更
つづいて、預貯金口座の解約・名義変更の手続きを行います。遺言書や被相続人・相続人の戸籍謄本などの書類が必要です。
預貯金口座の解約・名義変更は、遺言執行者単独で手続きができます。
6.不動産の名義変更(相続登記)
相続財産に不動産が含まれている場合、相続登記を行って名義変更をしましょう。遺言書や被相続人・相続人の戸籍謄本などの書類が必要です。
相続登記は、不動産を管轄する法務局で行います。手続きが煩雑になりやすいため、司法書士に依頼することも検討しましょう。
7.そのほかの業務
必要であれば、公共料金の支払いや、自動車・株式などの名義変更も行います。遺言書に書かれている内容通りに相続人や受遺者に相続財産の引き渡しができれば、遺言執行者としての業務は終了です。
8.業務終了の通知
すべての業務が終了したら、相続人に対して文書にて終了報告を行います。
遺言執行者が指定されていない遺言の場合はどうする?
遺言執行者は、被相続人の生前に遺言によって指定されるケースが多いです。しかし、なかには遺言執行者が遺言で指定されていないケースもあり、このとき相続人が遺言を執行します。
そもそも、遺言執行者は必ずしも存在しなければならないわけではありません。遺言執行者がいなくても、相続人で遺言書通りに遺産分割することが可能だからです。
しかし、遺言執行者がいると相続人は相続手続きを一任できるため、大幅な負担軽減につながります。遺言執行者が必要だと相続人らが判断した場合、遺言執行者選任の申し立てを家庭裁判所で行わなければなりません。
ここからは、相続人が遺言執行者を選任するときにどのように対応すべきかについて解説します。
- 遺言執行者の選任方法
- 遺言執行者の選任の手続き方法
順番に確認しましょう。
遺言執行者の選任方法
民法で定められているように、未成年者や破産者でなければ遺言執行者になれます。
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
※引用:民法|第1009条(遺言執行者の欠格事由)
また、1人だけでなく複数人での就任や、法人・団体を選任することもできます。
ただし、遺言執行者の行うべき業務のなかには専門性の高い業務も含まれているため、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に依頼するケースが多いです。親族や知人を選任したとしても、相続人の調査や相続登記の際には専門家に依頼することとなるでしょう。
遺言執行者の選任の手続き方法
遺言執行者の選任は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて申し立てを行います。
申し立てに必要な書類や費用は、以下の通りです。
| 必要書類 | 家事審判申立書 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本 遺言執行者候補者の住民票または戸籍附票 遺言書の写しまたは遺言書の検認調書謄本の写 利害関係を証明する資料 |
|---|---|
| 費用 | 遺言書1通につき、収入印紙800円分 連絡用の郵便切手代※家庭裁判所によって異なる |
相続人や受遺者・相続債権者などの利害関係人が申立人になれます。
参照:遺言執行者の選任|裁判所
遺言執行者を選任すべきケース・不要なケース

遺言執行者の指定のない遺言書が出てきたときに、相続人が遺言執行者を選任すべきかどうか悩むケースは少なくありません。
ここでは、以下の3つのケースをご紹介します。
- 遺言執行者を選任すべきケース
- 遺言執行者がいたほうがよいケース
- 遺言執行者がいなくてもよいケース
遺言書の内容や相続人の状況に合わせて、どのケースに当てはまるか照らし合わせましょう。
遺言執行者を選任すべきケース
遺言書で以下のような手続きをする場合、遺言執行者を選任すべきといえます。
- 非嫡出子の認知をする
- 相続人廃除・その取消をしたい
子どもの認知をするために遺言認知を行ったり、相続権を失効させる相続人排除・その取り消しを遺言で行ったりすることは可能ですが、トラブルに発展することが予想されます。
また、子どもの認知の届出や相続人排除とその取り消しの手続きについては、遺言執行者にしかできません。そのため、遺言執行者の選任が必要です。
遺言執行者がいたほうがよいケース
遺言執行者がいなくても相続手続きは進められるものの、遺言執行者がいたほうがスムーズに相続手続きを進められるケースもあります。
遺言執行者がいたほうがよいケースは、以下の通りです。
- 相続人が多忙で相続手続きに時間がかけられない
- 相続人が遠方に住んでいて相続手続きが大変
- 非協力的な相続人がいて相続トラブルに発展しそう
- 認知症の人や未成年の相続人がいる
遺言執行者がいると、相続財産の調査から相続人への財産の移転までを一任できるため、相続人の負担が大きく減ります。また、認知症の人や未成年の相続人がいる場合にも手続きが煩雑になりやすいため、円滑な相続手続きを進めるために遺言執行者がいると心強いです。
遺言執行者がいなくてもよいケース
相続人だけで円滑に相続手続きを終えられると考えられる場合、遺言執行者を選任しなくてもよいでしょう。遺言執行者なしでも相続人だけで相続手続きを進められるケースは、以下の通りです。
- 相続人の数が少ない
- 相続財産が少ない
- 生前に遺言書の内容を伝えられていて相続人が納得している
相続人の数や相続財産が少なければ、相続手続きに労力をかけなくて済むため相続人自身で手続きを完結させられる可能性が高いです。
また、遺言書の内容を伝えられていて相続人が納得しているのであれば、遺言書の内容が実行される可能性が高く、トラブルの心配もないでしょう。
遺言執行者への報酬
司法書士や弁護士、税理士などの専門家に遺言執行者を依頼したとき、報酬相場は遺産総額の1〜3%程度と考えておきましょう。
もちろん、事務所によって料金設定が異なり、最低料金を設けている事務所もあります。契約を交わすまえに見積書を提示してもらい、納得したうえで依頼しましょう。
もし、遺言書で専門家の遺言執行者が指定されているのであれば、遺言者が生前に遺言執行者と契約を交わしているはずです。金額や支払い方法について遺言書に記載されていなければ、遺言執行者に確認を取りましょう。
また、一般的に遺言執行者への報酬は相続財産のなかから相続人が支払います。
遺言執行者についてよくある質問
最後に、遺言執行者についてよくある質問をまとめてご紹介します。
- 遺言執行者に指定・選任されても辞任できる?
- 遺言執行者の解任・変更はできる?
- 遺言執行者が亡くなっていたらどうすればいい?
それぞれ回答していくため、疑問を解消しましょう。
遺言執行者に指定・選任されても辞任できる?
遺言執行者に指定・選任されたとしても、辞任することが可能です。
就任前であれば、特別な事由なしに拒否できます。しかし、就任したあとになって辞任をしたい場合には、正当な事由が求められます。引っ越しや病気などによって職務が継続できないと認められた場合にのみ辞任が認められ、職務のまっとうが難しいという理由だけでは認められません。
就任後に辞任したい場合は、家庭裁判所へ辞任の申し立てを行い、認められれば辞任が可能です。就任後に辞任することは難しいため、安易に遺言執行者を承諾しないように注意しましょう。
遺言執行者の解任・変更はできる?
遺言執行者が遺言書の内容を実行せずに業務を怠った場合や、相続人との間で揉めごとがあった場合など、相続人らは家庭裁判所において解任や変更の手続きができます。
家庭裁判所へ遺言執行者解任の申し立てを行い、認められれば解任されます。さらに、変更したい場合は新たに遺言執行者選任の申し立てを行って他の方を選任することが可能です。
解任の申し立てを行うには、利害関係者全員の同意が必要です。また、解任を認めてもらうには、以下のような解任の正当事由も欠かせません。
- 遺言執行を怠っている
- 財産の使い込みがある
- 報酬が高額すぎる
- 長期の不在がある
- 特定の相続人に偏った行為をする
遺言執行者の解任・変更は申し立てをしたあと、一定の時間がかかります。
遺言執行者が亡くなっていたらどうすればいい?
遺言書を開封したときに遺言執行者が亡くなっている場合、遺言執行者がいないものとして扱います。そのため、相続人が遺言を執行することが一般的です。遺言執行者が必要だと判断した場合、相続人が家庭裁判所に対して遺言執行者の選任と申し立てを行います。
同様に、遺言執行中に遺言執行者が亡くなった場合も、相続人らが家庭裁判所で選任の申し立てを行う必要があります。遺言執行者の立場をその子どもや配偶者などの相続人が継承することはできません。
また、遺言執行者が亡くなったとしても、遺言書自体は有効です。
遺言執行者とは遺言を実行してくれる存在
遺言執行者は必ずしも必要な存在ではありません。遺言執行者がいない場合、通常相続人が遺言を執行します。ただし、子どもの認知や相続人の排除・その取り消しが含まれているのであれば、遺言執行者を選任しなければ手続きを進められません。
また、遺言執行者がいれば相続人同士のトラブルを回避し、相続手続きにかかる負担を大幅に軽減してくれるメリットがあります。
遺言執行者になるために必要な資格はありませんが、司法書士や弁護士、税理士などの専門家に依頼すればより確実に遺言内容を実現してくれます。煩雑な手続きを代行してもらえるため、安心してお願いできるでしょう。
遺言執行者の指定がない遺言書が見つかったときは、前向きに遺言執行人を選任することを検討してください。