遺言書の内容を確認すると「内容が不自然」「筆跡が被相続人と明らかに違う」など、明らかに不自然だと気づいた時にはどうすればいいのでしょうか?
このような場合では、遺言無効確認請求訴訟によって解決できる場合があります。本記事では、遺言書が無効であると認められるケースや遺言無効確認請求訴訟の手続きの流れ、注意点について詳しく解説します。
目次開く
地元の専門家をさがす
遺言書が無効であることを認めてもらう遺言無効確認請求訴訟
遺言書の内容を確認して先述したような「被相続人がこのような遺言書を残すはずがない」と感じた場合、遺言無効確認請求訴訟を提起することで無効にできる可能性があります。
遺言無効確認請求訴訟とは、裁判所に対して遺言書が無効であることを認めてもらうための訴訟です。遺言書が無効であると認められれば、遺言通りに遺産分割をする必要がなくなります。
ただし、遺言無効確認請求訴訟を起こせば必ずしも無効になるわけではなく、一般的に訴えが認められるのが難しい訴訟だと言われています。無効性を証明するために一定の費用と時間がかかる点にも留意が必要です。当然、費用と時間がかかったとしても遺言書が有効であると結論付けられる場合もあるでしょう。
また、遺言書が有効であることを主張する遺言有効確認訴訟もあります。多数の相続人が「この遺言書は無効だ」として遺産分割協議による財産分配を行おうとする場合に、遺言有効確認訴訟を起こすことも可能です。
遺言の無効が認められるケース
遺言無効確認請求訴訟において、遺言書の無効を求める側はさまざまな要因に基づく主張を行います。遺言の無効主張が認められる主なケースは、下記の通りです。
- 遺言能力が欠如していた
- 公序良俗に違反する内容の遺言だった
- 遺言の形式に沿っていなかった
- 遺言書が偽造・変造されていた
- 錯誤・詐欺・脅迫によって遺言された
- 遺言の撤回の撤回がされた
6つのケースについて、詳しく確認しましょう。
遺言能力が欠如していた
遺言書の無効が争われる代表例が、遺言者の遺言能力の有無です。遺言能力とは、遺言の内容を理解して、遺言の結果を分かったうえで意思表示する力のことです。
たとえば、遺言者が当時認知症を発症していた場合や精神上の障害があった場合などは、遺言能力が欠如していたとして遺言書の無効が認められる可能性があります。
遺言書に効力を持たせるには、遺言者の遺言能力が欠かせません。つまり、遺言書を作成した日付における遺言者の遺言能力に欠如があれば、遺言書は無効ということです。なお、遺言能力の有無は医師の医学的判断が尊重されるものの、最終的には裁判所における法的な判断によって決められます。
公序良俗に違反する内容の遺言だった
原則として、遺言者は遺言によって所有している財産の引継ぎ先を自由に指定できます。
しかし、遺言が公序良俗に違反する内容の遺言だった場合、その内容は無効と判断される可能性があります。たとえば、遺言者と不倫関係である愛人に財産を譲る内容や、反社会的勢力へ遺贈する内容が該当し、遺言書の無効が認められる可能性があります。
遺言の形式に沿っていなかった
遺言書が効力を発揮する条件に、形式を守っていることも含まれます。そのため、民法で定められた形式に沿っていない遺言書は、遺言の方式違背として無効とされます。
特に、自筆証書遺言には書き方に細かなルールが設けられているため、無効とされるリスクが高いです。たとえば、パソコンで作成した遺言書や代筆された遺言書は無効となる代表例です。作成した日付や押印が抜けている場合や、訂正方法が間違っている場合も遺言の方式違背に該当するため無効です。
公正証書遺言であっても、証人が未成年や推定相続人などの証人の欠格事由に当てはまる場合は、無効となります。
また、2人以上の人が同一の証書で遺言書を作成する共同遺言も民法で禁止されており、共同遺言をしている場合にはその遺言書は無効であると認められます。
遺言書が偽造・変造されていた
遺言書を遺言者本人以外の者が作成した場合、偽造された遺言書そのものが無効になります。なぜなら、遺言書は遺言者本人が作成しなければ効力を発揮しないからです。
また、遺言書は本人によって正しい形式で修正・変更することは可能です。しかし、遺言書の一部が遺言者本人以外の者によって変造された場合は、変造された部分のみが無効となります。
本人による遺言の変更であっても、正しい形式でない場合は変更は無効とみなされます。
錯誤・詐欺・脅迫によって遺言された
遺言者本人が作成した遺言書であっても、錯誤・詐欺・脅迫によるものの場合、遺言書の無効が認められる可能性があります。
錯誤
錯誤とは、遺言者の大きな認識違いによって遺言書における意思表示が行われることです。ただし、小さな誤認・誤解だけでは無効にはならず、遺言者が真実を知っていればその遺言をしなかったといえると裁判所が認定しなければなりません。
詐欺
詐欺とは、他の人から騙されて遺言書における意思表示が行われることです。たとえば、長男が実際には海外で働き介護費を援助している次男について「次男が帰ってこないのは絶縁したからだ」と思い込ませ、長男に全財産を相続させると遺言させると父親に意思表示させた場合は詐欺に該当します。
脅迫
脅迫とは、被相続人やほかの親族を殺害するなどと脅迫して遺言者本人の意思とは異なる意思表示をさせられることです。脅迫で書かされた遺言書だと認められると、遺言書が無効になるだけでなく、脅迫した相続人は相続欠格事由に該当し、相続権を失う可能性があります。
このように、錯誤・詐欺・脅迫によって作成された遺言書は、遺言者本人の意思ではないと判断されるため無効と認められることがあります。
遺言の撤回の撤回がされた
民法において、本人による遺言の撤回は認められています。しかし、一度本人が撤回した事実を撤回し、遺言に効力を持たせることは原則できません。一度撤回した遺言には効力が生じないからです。
ただし、撤回行為が詐欺や脅迫によるものである場合にはその限りではありません。

遺言無効確認請求訴訟の流れ
遺言書が無効になる可能性があるのであれば、遺言無効確認請求訴訟を検討しましょう。遺言無効確認請求訴訟の流れは、下記の通りです。
- 遺言の無効を主張するための証拠を集める
- 相続人による話し合いをする
- 家庭裁判所に調停の申し立てを行う
- 遺言無効確認請求訴訟を提起する
4つのステップごとに、詳しく確認しましょう。
遺言の無効を主張するための証拠を集める
まずは、遺言書が無効であることを主張するための証拠を集めましょう。いくら主張をしても証拠がなければ客観的に「無効」だと認められず、敗訴してしまう可能性が高まります。
たとえば、遺言能力の欠如を要因に遺言書の無効を主張するのであれば、下記のようなものが証拠として提出できます。
- 遺言書を作成した時期の遺言者の病院のカルテ
- 介護事業者サービスの利用記録
有効を主張している相続人らに対する交渉材料となるため、できるだけ多くの証拠品を収集しましょう。
相続人による話し合いをする
証拠が集まった時点で、一度相続人や遺言に関係する人と話し合いをしましょう。
遺言無効確認請求訴訟には時間や費用がかかるうえに、相続人との間に大きな亀裂を生み出す恐れがあります。そのため、いきなり訴訟をするよりも、一度話し合いでの解決を目指すことをおすすめします。
直接交渉をするとお互いに負担がかかるため、代理人である弁護士に交渉してもらうことも手段の1つです。過去の事例や法的観点から判断ができるうえに、冷静な話し合いができることも期待できます。
しかし、それでも合意に至らない場合は遺言無効確認の調停の申し立てを行い、調停における法廷での話し合いで解決を目指すことになります。
一方で、遺留分を侵害する遺言書内容の場合、早期に内容証明郵便にて遺留分侵害額請求の意思表示をしておきましょう。なぜなら、遺留分侵害額請求権の時効は1年間だからです。遺言書が有効だと判断されたときに備えておくと安心です。
家庭裁判所に調停の申し立てを行う
家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
遺言無効確認は、家庭に関する事件であることから家事調停の対象です。家事調停の対象である事件について提起する場合、原則として先に家庭裁判所で家事調停を申し立てなければならないと定められています。これを調停前置主義といいます。
調停を申し立てる裁判所は、ほかの相続人のうちひとりの住所地を管轄する家庭裁判所です。
調停では、中立な立場である調停委員がそれぞれの相続人の主張の聞き取りを公平に行い、遺言無効や遺産分割について合意に至るまでをサポートします。弁護士に依頼している場合、調停にその弁護士を同席させたり、代理出席してもらったりすることが可能です。
調停で双方の当事者が合意に至らずに不成立で終わった場合、遺言無効確認請求訴訟を提起することになります。
遺言無効確認請求訴訟を提起する
調停が不成立となったら、遺言無効確認請求訴訟を提起しましょう。
遺言無効確認請求訴訟は、遺言執行者がいる場合は遺言執行者に対して、遺言執行者がいない場合は他の相続人および受遺者全員に対して提起します。
提起先は、ほかの相続人のうちのひとりの住所地、または相続開始時における被相続人の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所です。訴額が140万円以下の場合は原則簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所の管轄です。
提訴を起こしたあと、おおよそ1か月に1度のペースで原告と被告が互いの主張と立証を行う形で審理が進められ、すべて出揃った段階で判決が下されます。意思能力の有無が争点である場合は病院の診断書や介護記録を取り寄せ、自筆であるかが争点となる場合は筆跡鑑定を行うことが想定されるでしょう。
訴訟のなかで、互いが譲歩して和解という形で終了することもあります。感情的な対立が激しい遺言無効確認請求訴訟では和解で終えることは困難なものの、判決が出るまでに大きな負担がかかることから、両者が早期解決を目指すことも大事になってきます。
遺言無効確認請求訴訟の判決に不服がある場合
遺言無効確認請求訴訟の判決に不服がある場合、当事者は控訴によって上級裁判所における再判断を求めることが可能です。さらに控訴審での判決に不服がある当事者は、上告審での再判断をもとめることができます。
また、提起から判決までの期間は、第一審だけでも1〜2年程度と長いです。判決が出たあと不服がある場合は控訴・上告を行うため、さらに長期化します。
なお、必ずしも原告・被告の本人が全員出席しなければならないわけではなく、代理人として弁護士に出席してもらうことが可能です。
地元の専門家をさがす
遺言無効確認請求訴訟のあとに行うこと

遺言無効確認請求訴訟のあとに行うことは、無効と認められたか認められなかったかによって異なります。
遺言の無効が認められれば遺産分割協議
遺言書が無効だと認められれば、遺言書は存在しなかったものとして法定相続人全員による遺産分割協議を行います。もし、遺言書が有効だと判断された場合であっても、遺言書に記されていない財産の分割方法については、遺産分割協議を行わなければなりません。
遺産分割協議が法定相続人全員の合意に至らなかった場合、遺産分割調停を申し立てます。遺産分割調停が不成立となった場合は、遺産分割審判に移行し、審判が下されます。
遺産分割審判では、法定相続分通りの財産分配に落ち着くケースが多いです。
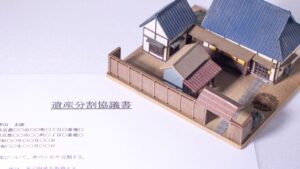
遺言の無効が認められなければ遺留分侵害額請求
提訴の結果、遺言の無効が認められなかったとしても、不公平な遺言に納得いかなければ遺留分侵害額請求ができる可能性があります。遺留分は遺言よりも優先されるからです。
遺留分侵害額請求とは、一定の範囲の法定相続人が最低限保証されている遺産の取り分を請求することです。たとえば、長男・次男の2人が法定相続人であるにもかかわらず、遺言に「長男に全財産を相続させる」と記載されていたとしましょう。このとき、次男は遺留分である4分の1に相当する金銭を長男に請求することができます。
ただし、遺留分侵害額請求の時効は1年です。遺言無効確認請求訴訟の間に1年経過することもあるので、遺留分侵害額請求は並行して行使しておくようにしましょう。

遺言無効確認請求訴訟の注意点
遺言無効確認請求訴訟を検討している場合は、下記の4つの注意点について理解しておきましょう。
- 遺言無効確認請求訴訟は認められるのが難しい訴訟である
- 遺言無効確認請求訴訟は時間がかかる
- 遺言無効確認請求訴訟に時効はないが早期提起が望ましい
- 生前のうちに遺言無効確認請求訴訟はできない
あらかじめ注意点を理解し、できるだけ当事者における交渉や調停での解決を目指すことをおすすめします。それでは、詳しく解説します。
遺言無効確認請求訴訟は認められるのが難しい訴訟である
遺言無効確認請求訴訟は、一般的に立証の難易度が高い訴訟と言われています。なぜなら、過去の事実を証明することはとても難しいからです。
とくに、公正証書遺言では形式的な間違いが少なく、無効を立証するには下記のような事実を客観的に証明する必要があります。
- 遺言書作成時、被相続人が認知症や精神病などによって遺言能力がなかった
- 欠格事由を持つ者が証人になっていた
- 公証人が遺言内容を遺言者に口授せずに、質問に頷いただけだった
一方、自筆証書遺言は形式的なミスが見つかるケースが多く、ミスが見つかれば無効になる可能性があります。
遺言無効確認請求訴訟は時間がかかる
遺言無効確認請求訴訟は長期化することが多く、精神的な負担がかかる点に注意が必要です。
それぞれの期間の目安は、訴訟提起までの準備に数か月、第一審に1〜2年程度、控訴審に半年から1年程度、上告審に半年程度と考えておきましょう。
また、遺言書の無効が認められた場合、そこから遺産分割協議を行って財産分配を行わなければなりません。法定相続人全員の合意に至らない場合には調停・審判を行う必要があり、1〜2年程度の期間がかかります。
そのため、遺言の効力の是非について争い、解決して遺産分割が終わるまでに数年はかかると考えておく必要があります。当然、遺産分割が終わらなければ、被相続人の銀行口座や不動産の名義変更はできません。
また、相続税が発生する場合は相続発生を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納税を行う必要があります。遺産分割が終わっていなくても相続税の申告・納税の期限は延期されないため注意しましょう。
遺言無効確認請求訴訟に時効はないが早期提起が望ましい
遺言書の無効を申し立てること自体には、時効や期限は設けられていません。しかし、「相続発生から時間が経つにつれ証拠収集が困難になりやすい」ことや、「遺留分侵害額請求の時効が1年のため、遺言無効確認請求訴訟の結果を待つことが難しい」ことなどから、早期に訴訟提起することが望ましいとされています。
なお、遺言無効確認請求訴訟を提起したとしても、遺留分侵害額請求の時効は中断されません。遺言無効確認請求訴訟は長期化するケースが多いため、予備的に遺留分侵害額請求をしておくようにしましょう。
生前のうちに遺言無効確認請求訴訟はできない
遺言無効確認請求訴訟は、遺言者が死亡したあとでなければ提起することができません。
そもそも、遺言書は遺言者が死亡して初めて効力を発揮します。遺言者が存命中はいつでも遺言を撤回することが可能だからです。
遺言者の生前に提起しても不適法として却下されるため注意しましょう。
遺言無効確認請求訴訟は難しいことが多いため弁護士への相談がおすすめ
遺言無効確認請求訴訟は、一般的に訴えを認められるのが難しい訴訟と言われています。形式的なミスが見つかれば無効となる可能性がありますが、遺言能力の有無や偽造・変造が争点となった場合は証明することがとても難しいからです。
また、訴訟に発展すると数年は遺産分割ができないと覚悟しておかなければなりません。そのため、早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。
冷静な交渉を行って訴訟に発展する前に解決するためのアドバイスはもちろん、同時に遺留分侵害額請求も依頼できます。
相続プラスでは、相続トラブルに強い弁護士を一覧で確認できます。エリア別・悩み別でも検索できるため、ぜひ活用してください。
地元の専門家をさがす


