法務局では所有者の変更など不動産の権利変動があった人向けに「登記案内サービス」で登記手続きに関する無料相談を実施しています。相続登記についても「申請書の書き方」や「必要書類の種類と集め方」などの案内を受けられます。ですが、時間制限がある点や、踏み込んだ内容については司法書士などへの相談を提案されることがある点には注意しましょう。
地元の専門家をさがす
法務局とは?
法務局は法務省管轄の地方機関で、私たちの財産や身分を守るための重要な役割を担う組織です。主な業務は、登記、戸籍、国籍、供託などであり、これらの業務を通じて国民生活の安全と取引の円滑化を支えています。
<法務局の主な業務>
| 業務の名称 | 概要 |
|---|---|
| 不動産登記 | 土地・建物の情報及び権利の変更に関する業務 |
| 商業登記 | 会社(法人)の設立や変更に関する業務 |
| 供託 | 権利保全などの目的で金銭・有価証券を預かる業務 |
| 遺言書保管 | 自筆証書遺言を保管し、各種証明書を交付する業務 |
| 各種証明書の交付 | 登記事項など、権利や合意事項に関する証明書を交付する業務 |
参考:法務局のご案内|法務局
法務局で無料相談できること
法務局で行う手続きは、下記のような登記のやり方や書類の書き方、諸制度に関する内容となります。
- 手続きの流れが知りたい
- 必要な申請書の様式を教えてほしい
- 申請書に添付する書類の集め方がわからない
- 申請書・添付書類の書き方、形式を教えてほしい
- 手数料(登録免許税など)の計算方法がわからない
- 関連する制度(法定相続情報証明制度)について知りたい
特に書類の書き方や様式については厳格な決まりなどがあるため、提出後に補正で差し戻しにならないよう、この無料相談にて不明事項は隅々まで確認しましょう。
法務局で相談できないこと
法務局の無料相談窓口では、手続きに至るまでの判断や、手続きの結果に関することは対応できません。特に登記については、登記官と呼ばれる担当者による厳格な審査が前提となるため、事前に「問題なく手続きできる」と保障してもらうのは不可能です。
これら以外の内容でも、手続きのやり方自体でない内容のものは、司法書士や弁護士、土地家屋調査士などへの相談を進められる場合があります。これら士業が相談先となるのは、主に「登記申請の代行依頼」や「遺言及び遺産分割協議に関する相談」、「会社法に基づく手続きの相談」などが挙げられます。
参考:登記申請を御自身ですることを検討されている方からよくある質問|法務局
法務局の利用の仕方
法務局は各地にあり、登記申請などについて相談したいときは手続きの管轄局の案内を確認する必要があります。相談の手順や方法は管轄局によって異なりますが、登記案内サービスを利用する場合、基本的には下記の手順で利用することになるでしょう。
- 手順1:管轄の法務局にて予約する
- 手順2:相談時に滞りが無いように資料や状況を整理する
- 手順3:予約時に希望した方法で相談する
登記相談ができる法務局はどこ?
相続した土地・建物の名義変更などといった不動産登記に関する相談は、申請先である「不動産の所在地を管轄する法務局」で行います。管轄がどこになるかは、法務局のWebサイトで簡単に調べられます。
相談方法は何が選べる?
法務局での相談は、電話や来庁によるもののほか、Web会議サービスを利用したオンラインでの相談も利用できます。オンライン相談は遠隔地に住む人などにとって便利ですが、管轄局によっては実施していない場合があるため、あらかじめ手続きの管轄または最寄りの法務局のWebサイトを確認するようにしましょう。
登記相談を利用した相続登記の流れ(自分でやる場合)
登記相談は、登記申請に関することであればどのような内容でも相談可能です。ここでは、相続登記を例にして利用手順を考えてみましょう。実際に、相続登記では法務局への相談を行ってから手続きに入ることが多いと考えられます。相続関係を複数の戸籍謄本で証明する必要があるなど、添付書類や登記申請書の準備が複雑になるためです。
事前に法務局で相談してから自分で登記申請するときの流れは、次のようになります。
登記相談を予約する
登記案内サービスの予約は、専用のWebサイト「法務局手続案内予約サービス」で行うのが便利です。サイト上では、まず管轄の地方局を選択し、遷移した先で利用登録を行ってから予約日時を指定して手続きを行います。
初回の登記相談に行く
登記相談の時間は1回あたり20分と限られます。初回相談では、前提となる情報をスムーズに伝えて、十分な回答のための時間を確保できるよう心がけましょう。相談前の準備では、下記のような資料をできるだけ用意しておくべきです。
- 登記事項証明書(不動産の登記情報がわかるもの)
- 登記済証、登記識別情報(不動産の権利を示すもの)
- 亡くなった人及び相続人の戸籍謄本(相続関係がわかるもの)
- 相談したい内容のメモ(自分で作成)
必要書類を収集・作成する
初回の登記相談で得た情報をもとに、必要書類の収集と作成を進めます。収集する書類の代表例は、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本や住民票、そして不動産の固定資産評価証明書などです。
自分で作成する必要があるものとして、登記申請書、遺産分割協議書、そして相続関係説明図などもあります。手続きで最も重要といえる登記申請書は、法務局のWebサイトから様式をダウンロードして作成できますが、記載内容に間違いがないよう細心の注意が必要です。
必要に応じて2回目以降の登記相談をする
すべての書類が揃い、申請書の作成が完了したら、申請前に再度、登記相談を利用することをおすすめします。この段階での相談の目的は、完成した書類一式に不備がないか最終チェックをしてもらうことです。
ここで軽微な誤りや不足書類を指摘してもらえれば、申請後の補正を防ぎ、手続きを一度で円滑に終えられる可能性が高まります。あわせて、登録免許税の正確な金額と納付方法についても最終確認しておくと安心です。
相続登記の申請をする
相談を経て、書類一式の準備が完璧に整ったら、いよいよ法務局へ相続登記の申請をします。申請方法は、法務局の窓口へ直接持参する方法、郵送する方法、そしてオンラインで申請する方法があります。
窓口申請は、もし記載内容に軽微な訂正点が見つかった場合に、その場で訂正できる可能性があるのがメリットです。そのため、申請書に押印した印鑑を持参すると、補正時にスムーズに対応できます。申請後は、登記が完了するまで数週間待ち、問題なく登記完了されれば、登記識別情報通知書などの重要書類を受け取って、手続きはすべて終了です。
自分でやる人がクリアすべき障害
相続登記を自分で行うことは可能ですが、誰でも簡単にできるわけではありません。多くの人が直面する障害は主に「時間の確保」「書類収集の手間」「専門的な書類作成の難しさ」の3つです。ほかには、遺産分割の方法など、法務局での相談だけでは解決できない問題が起こることもあるでしょう。
これらのハードルを越えられず、途中で断念して司法書士に依頼するケースも少なくありません。
時間の確保が難しい
自分で相続登記を進める上で、最初の壁となるのが時間の確保です。法務局や市区町村役場といった公的機関の窓口は、基本的に平日の日中しか開いていません。そのため、書類の収集や相談のために、仕事を休んだり、日中の予定を調整したりする必要があります。
戸籍謄本などの必要書類の収集で手間がかかる
相続登記で最も大変なのは書類収集です。特に相続に関係する人の戸籍謄本は、法定相続のルールに関する予備知識がないと収集できず、単に「数が多くややこしい」という問題もあります。
遺産分割協議書の作成方法で迷う
登記申請のときに必要となる遺産分割協議書は、相続人全員の合意を証明する重要な書類です。実印の使用・印鑑登録証明書の添付などのルールを守ることはもちろん、文面にもあいまいさが生じないよう注意しなければなりません。それにもかかわらず決まった書式・様式がないため、作成方法で迷いがちです。
法務局での相談だけでは解決できない問題が起きる
法務局に相談できる内容は手続き方法だけであり、相続登記によって土地・建物の名義変更が実現するまでのあいだに起こる問題は解決できません。すでに紹介しましたが、例として「最適な遺産分割の方法がわからない」や「自分で登記申請することが難しい」などといった問題です。これらについては、相続登記について基本的な法令の知識があり、代理での手続きに対応する司法書士などの専門家のサポートが必要です。
地元の専門家をさがす
相続登記の流れ(司法書士の場合)
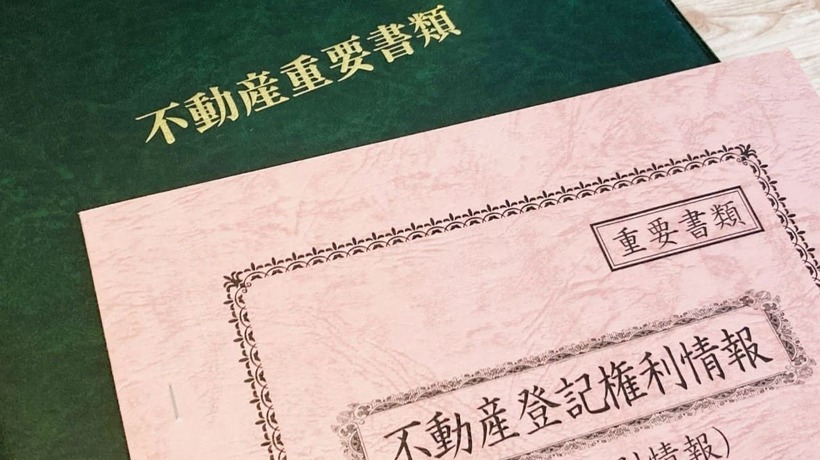
司法書士に相続登記を依頼するケースでは、多くの場合、書類の収集・作成から申請まですべて代理による手続きを行うことになります。基本的には、事前相談の段階で手続き全体の予定と必要書類の見通しを立て、後は書類作成・収集を含めて任せるだけとなります。
司法書士が相続登記を行う場合の流れは、登記申請の方法別に次の通りです。
オンライン申請の場合
オンライン申請は、司法書士が電子署名を用いてインターネット経由で登記申請を行う方法です。相談で手続きについて打ち合わせを行った後は、オンラインと郵送による書類提出を組み合わせた方法で代理による登記申請が進みます。
申請の流れは下記の通りですが、登記申請する人自身での対応は、初回相談と委任状ファイルへの電子署名までです。ここまでの対応が終われば、遠方の不動産でもスムーズかつ確実に相続登記の手続きが進みます。
窓口・郵送申請の場合
窓口・郵送申請は、司法書士が管轄法務局に直接書類を提出する従来の方法です。書類収集以下から法務局への提出まですべて司法書士が対応するため、依頼者の負担はほとんどありません。
ここでも、初回相談と委任状への署名のみが相続登記を希望する人自身での対応となります。書類収集や提出については、司法書士が確実に処理します。
司法書士に依頼した方がいいケース
相続登記は相続人が行う手続きですが、難易度が高く、失敗がつきものです。スピーディな手続きを望むなら、司法書士に相談・依頼するとよいでしょう。ここで以下に挙げるケースは、特に司法書士への依頼がおすすめできるといえます。
売却など次の予定が決まっている場合
相続した不動産を売却する、あるいは担保に入れて融資を受けるといった具体的な予定が控えている場合は、司法書士への依頼が不可欠です。
自分で手続きを進めて万が一書類に不備があると、登記完了が遅れ、売買契約の決済日に間に合わないといった重大なトラブルに発展しかねません。司法書士であれば、定められた期日までに迅速に登記を完了させることができ、買主や不動産会社、金融機関といった関係者との調整もスムーズに進みます。
不動産が遠方にある場合
相続した実家が遠方にあるなど、不動産の所在地が現在の居住地から離れている場合も、司法書士に依頼するメリットは大きいといえます。
相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局に申請する必要があるため、自分でやろうとすると、現地への移動時間や交通費が大きな負担になるでしょう。司法書士はオンライン申請などを活用して全国の不動産に対応できるため、自宅や勤務先の近くの事務所に依頼すれば、移動の手間をかけずに手続きを進めることが可能です。
疎遠な相続人がいる場合
遺産分割協議での合意は相続人全員で行わなくてはなりません。問題となるのは、交流や面識がない相続人が含まれることで協議を始められないケースです。特に、祖父母以上前の世代から登記されていない土地・建物につき、何代にも渡って相続登記する必要があるとき(数次相続)では、このような問題が起きがちです。
上記のように疎遠な相続人がいるケースでは、戸籍を辿って相続人を特定する調査から司法書士に依頼可能です。相続人の特定後は、連絡先の調査から遺産分割協議書の作成まで、双方にとって気まずい相続人同士のやりとりをサポートしてもらえます。
相続関係が複雑な場合
相続人がさらに亡くなって権利関係が複雑化する「数次相続」や、本来の相続人が先に亡くなってその子ども(孫)が相続する「代襲相続」が発生しているときは、高度な専門知識が不可欠です。相続人の中に行方不明者や認知症の方がいると、登記前に家庭裁判所での特別な手続きが必要となる点にも要注意です。
上記のようなケースでは、迷わず司法書士に相談しましょう。登記申請の方法を熟知しており、特別代理人の選任申立てなどといった家庭裁判所での手続きも担えることから、複雑なケースでは心強い味方になります。
平日に時間が取れない場合
相続登記の手続きは、戸籍謄本の収集で市区町村役場へ行ったり、法務局へ相談や申請に行ったりと、主に平日の日中に手続きを行う必要があります。仕事や家事、介護などで多忙な方にとって、これは非常に大きなハードルです。
司法書士に依頼すれば、これらすべての手続きを代行してもらえるため、自身の仕事や日常生活に大きな支障をきたすことなく登記を完了させられます。更に書類の収集や手続きの複雑さからくる精神的なストレスを軽減できる点も、大きなメリットといえるでしょう。
法務局での登記相談で不足するときは司法書士へ
相続した不動産の名義変更には、法務局での相続登記が必要です。法務局では登記手続きに関する無料相談を実施しており、申請書の書き方や必要書類の集め方について案内を受けられます。
無料で利用できる法務局での登記相談は、書類の記入方法がメインです。相続登記の難しい点は、多数の書類を集めるために時間と手間を要求される点や、土地・建物の利活用の予定があるときは確実かつスピーディな手続きが必要になる点です。なかには、高度な専門知識が求められることもあります。
時間がない、手続きが完了するか不安があるといったときは、司法書士に相談するとよいでしょう。
地元の専門家をさがす


