預金口座の名義人が亡くなった事実が金融機関に伝わって口座が凍結されてしまい、引き出しが一切できなくなってお困りではありませんか。このようなとき、相続預金の払戻し制度を活用すれば遺産分割前でも相続人が単独で一定の金額までの預金を引き出すことができます。本記事では、相続預金の払戻し制度の概要や払戻しの手続き方法、注意点について詳しく解説します。名義人の口座凍結にお困りの方は、ぜひ参考にしてください。
目次開く
地元の専門家をさがす
亡くなった人の口座は凍結される
金融機関は、口座名義人が死亡していることを把握し口座凍結の必要性があると判断すると、その口座を凍結して引き出しや振り込みをできなくします。相続人や親戚などによる引き出しを防止することで、相続トラブルを回避することが目的です。
しかし、引き出しができなくなると、葬儀やお布施、お墓などの出費を相続人が立て替えることになってしまいます。一家の大黒柱だった方が亡くなった場合、口座凍結によって配偶者や子どもが経済的に苦しい状況に陥ってしまうこともあるでしょう。
一般的に、凍結された銀行口座から預金を引き出すには、遺言書もしくは遺産分割協議書が必要です。しかし、遺言書がなく遺産分割協議書の作成中である場合は、たとえ生活を共にしていた相続人であっても、遺産分割が終わるまで(遺産分割協議がまとまり遺産分割協議書が作成されるまで)名義人の口座から預金を引き出すことができません。
このような不都合を回避するために、遺産分割が終わる前に一定額の預金を引き出すことのできる相続預金の払戻し制度が令和元年7月に施行されました。相続預金の払戻し制度を活用すれば、一定の範囲で葬儀費用や生活費の支払いに充てられる可能性があります。

相続預金の払戻し制度とは
相続預金の払戻し制度とは、遺産分割の対象となる亡くなった方の預金について、遺産分割が終わる前であっても、ほかの相続人の同意なしに、相続人が単独で一定の範囲で預金の払戻しを受けられる制度です。
相続預金の払戻し制度は、平成30年の民法改正により令和元年7月1日よりスタートした新しい制度です。制度が施行されるまでは、遺言書がある場合は遺言書通りに遺産分割を行えましたが、遺言書がない場合は遺産分割協議が終了するまでの期間、相続人が単独で亡くなった方の預貯金債権の払戻しができませんでした。
つまり、生計を共にしている家族の生活費や葬儀費用の支払い、相続財務の弁済などによって資金が必要である場合にも亡くなった方の預金払戻しができなかったのです。
民法が改正された結果、下記の2つの方法で払い戻しを受けられるようになりました。
- 預貯金債権に限り、仮払いの必要性があると認められるときには、他の相続人の利益を損なわない範囲で、家庭裁判所の判断によって仮払いが認められるようになった
- 預貯金債権の一定の金額までであれば、家庭裁判所の判断を待たずに金融機関で支払いを受けられるようになった
相続預金の払戻し制度の施行によって、一時的に相続人が葬儀代や亡くなった方の借金を肩代わりする必要がなくなり、相続財産のなかから支払えるようになりました。2つの払い戻し方法について、次の章で詳しく確認しましょう。
参照:相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について|法務省
被相続人の預貯金を払い戻す2種類の方法
亡くなった方の預貯金を払い戻す相続預金の払戻し制度には、払い戻す方法が2つ設けられています。
- 金融機関での手続き
- 家庭裁判所での手続き
詳しく確認しましょう。
金融機関での手続き
金融機関で手続きすることで、亡くなった方の預貯金を払い戻すことができます。金額の上限までであれば、家庭裁判所の判断を待たずに払戻しができる点が大きなメリットです。
相続人が単独で払戻しができる金額は、口座ごとに下記の計算式で求められる額もしくは150万円までのいずれか低い額と定められています。
払戻しできる金額=相続開始時の預金額×3分の1×払戻しを行う相続人の法定相続分
法定相続分とは、民法で定められた相続人ごとの遺産の取り分です。たとえば、相続人が母親・長男・次男の3人で、相続開始時の預金額がA銀行は1200万円、B銀行は2400万円だったときに長男が単独で払戻しできる金額は下記のように計算します。
<A銀行>
- 預金額:1200万円×3分の1×長男の法定相続分:4分の1=100万円
150万円を超えていないため、長男は50万円の払戻しを受けられる
<B銀行>
- 預貯金:2400万円×3分の1×長男の法定相続分:4分の1=200万円
150万円を超えているため、長男は上限の150万円の払戻しを受けられる
ただし、複数の支店で口座を作っていたとしても、同じ金融機関からの単独で払戻しできる上限金額は150万円です。
金融機関の手続きによって払戻しを受ける場合、下記の必要書類の提出が求められます。
- 亡くなった方の出生から死亡まで連続した除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 預金の払戻しを希望する人の印鑑証明書
- 預金の払戻しを希望する人の本人確認書類
上記以外にも、金融機関によって別の書類の提出を求められる場合があります。詳しくは、取引先の金融機関に問い合わせましょう。

家庭裁判所での手続き
家庭裁判所へ保全処分の申立てを行って、相続預金の全部または一部を仮で取得し、金融機関から払戻しを受けることも可能です。
ただし、遺産分割調停・審判の申立ても同時に行う必要があります。なぜなら、保全処分申立ては、遺産分割調停・審判で遺産分割の内容が決定するまでに相続財産の一部を相続人へ払戻しする制度だからです。
家庭裁判所が払戻しを認めるケースは、下記の2つの条件を満たすときです。
- 生活費の支弁等の事情によって相続預金の仮払いの必要性が認められる場合
- 払戻しによってほかの相続人の利益を損なわない場合
単独で払戻しができる上限金額は、申立人の事情によって家庭裁判所が個別に決定します。そのため、いかに裁判官へ詳しい事情を伝えられるかが鍵となります。
家庭裁判所での手続きによって払戻しを受ける場合、下記の書類提出が求められます。
- 家庭裁判所の審判書謄本(審判書上確定表示がない場合、審判確定証明書も必要)
- 預金の払戻しを希望する人の印鑑証明書
なお、金融機関によっては別の書類の提出を求められる場合があります。手続きを進める際に、取引先の金融機関に確認するようにしましょう。
参照:遺産分割前の相続預金の払戻し制度|一般社団法人全国銀行協会

相続預金の払戻し制度を活用すべきケース・すべきでないケース
相続預金の払戻し制度があるなら、積極的に活用した方がよいと考える方がいるかもしれません。しかし、安易に制度を活用するにはリスクがあります。
ここでは、相続預金の払戻し制度を活用すべきケース・すべきでないケースについて詳しく解説します。
相続預金の払戻し制度を活用すべきケース
相続預金の払戻し制度を活用すべきケースは、下記のような場合です。
- 葬祭費や未払いの医療費を支払いたい
- 亡くなった方の借金の返済にあてたい
- 生計をともにしていた家族の当面の生活費が足りない
上記のケースに当てはまる場合、相続預金の払戻し制度を活用すれば相続財産を支払いにあてることが可能です。相続人に資産がない場合でも亡くなった方のための費用を支払えます。
ただし、払戻し制度によって引き出した預貯金は遺産の一部です。亡くなった方名義の支払いや借金の返済にあてた分は、かならず領収書や明細を残しておきましょう。
相続預金の払戻し制度を利用すべきでないケース
相続預金の払戻し制度を利用すべきでないケースは、下記の通りです。
- 相続放棄を検討している
- 相続人のあいだでのトラブルが予想される
相続放棄とは、相続人としての立場を失い、プラスの遺産もマイナスの遺産もすべて引き継がない相続方法です。相続放棄を検討している場合、払戻したお金で亡くなった方の借金の返済や未払い料金の支払いを行うと単純承認とみなされて相続放棄できなくなる可能性があります。
相続放棄の可否については専門家であっても意見が割れるほど難しいため、自己判断することは危険です。相続預金の払戻し制度を活用する前に、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談しましょう。
また、相続人間でトラブルが予想される場合にも、単独で払戻しを行うとトラブルのきっかけになるリスクがあります。被相続人の未払金の支払いのために遺産を使ったとしても、相続人本人のために使ったのではないかと疑われるかもしれません。
遺産分割がスムーズにいかない、親族関係に亀裂が入るなどのトラブルを回避するために、相続預金の払戻し制度を活用せずに一時的に相続人が立て替えた方がよい場合があります。
相続預金の払戻し制度を利用すべきかどうかの判断に迷う際は、相続に詳しい司法書士や弁護士にアドバイスをもらうことをおすすめします。
地元の専門家をさがす


相続預金の払戻し制度に関する注意点

最後に、相続預金の払戻し制度に関する注意点を4つご紹介します。
- 金融機関で手続きする場合、上限額は金融機関ごとに設定される
- 払戻した預貯金は遺産分割で取得したものとみなされる
- 遺言があると払戻しできなくなることもある
- 相続預金の払戻し制度以外にも、預貯金を引き出す手段はある
相続預金の払戻し制度を利用する前に詳しく確認しましょう。
金融機関で手続きする場合、上限額は金融機関ごとに設定される
金融機関で相続預金の払戻しの手続きを行う場合、上限額は金融機関ごとに設定されている点に注意しましょう。1つの金融機関で相続預金の払戻しが受けられる上限額は、150万円です。
1つの金融機関に複数の口座があり、それぞれに一定の預金がされている場合でも1金融機関ごとに上限が定められています。そのため、150万円以上引き出したい場合は、複数の金融機関で手続きが必要になります。
取引金融機関ごとに手続きを行いましょう。
払戻した預貯金は遺産分割で取得したものとみなされる
金融機関から払戻しされた預金は、遺産分割で取得したものとしてみなされます。なぜなら、払戻しした預金を含めずに遺産分割をすると、他の相続人との公平性が保てないからです。
払戻しで取得した分だけ、そのあと相続する財産の総額が減る点に注意しましょう。
また、金融機関から払戻しされた預金は相続財産を取得したとみなされます。後日、亡くなった方の借金や保証人になっていたことが判明したとしても、相続放棄できなくなる可能性がある点にも注意が必要です。
遺言があると払戻しできなくなることもある
相続預貯金について記載のある遺言書がある場合、相続預金の払戻し制度が使えないケースがあります。
たとえば、「A銀行の預貯金のすべてを長男に相続させる」といった遺言書がある場合、長男に与えられた預貯金については他の相続人が払戻しを受けることはできません。
そもそも、遺言は死亡時に効力が発生するものです。そのため、払戻し制度よりも先に遺言にもとづいて遺産が引き継がれることになります。
なお、遺言で指定されていない預貯金がある場合には、相続預金の払戻し制度の対象です。
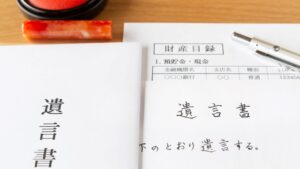
相続預金の払戻し制度以外にも、預貯金を引き出す手段はある
相続預金の払戻し制度以外にも預貯金を引き出す手段があります。
金融機関によっては、遺産分割協議書の代わりに相続同意書を提出すれば相続手続きをしてくれる場合があります。
相続同意書とは、預金を誰が受け取るのかを相続人全員で決定し、その合意について証明するための書類です。金融機関が指定する様式に従って空欄を埋め、押印するだけで相続同意書を作成できます。
ただし、相続同意書で手続きする場合にも、亡くなった方の除籍謄本や相続人全員分の戸籍謄本・印鑑証明書などが必要です。
また、遺産分割協議が成立してからの引き出しでも問題ないのであれば、相続預金の払戻し制度を活用せずに遺産分割協議書を作成してから相続手続きをしてもよいでしょう。急ぎの場合は、必要な預金分だけ先に遺産分割協議することも可能です。
当然、他の相続財産については、後日改めて遺産分割協議を行う必要があります。
相続預金の払戻し制度を活用すべきかどうかは慎重に
相続預金の払戻し制度とは、遺産分割協議が成立する前に亡くなった方名義の預金を一定金額まで引き出せる制度です。家族の生活費や未払い金の支払いに困らないように制定された新しい制度です。
とても便利な制度ではあるものの、払戻しした預金の使い方によっては相続放棄ができなくなる可能性があります。後日、亡くなった方の借金が出てきたとしても相続放棄が認められないリスクがあるため、慎重な判断が必要です。
また、相続預金の払戻し制度を活用しなくても遺産分割協議の前に金融機関からお金を引き出せる可能性があります。相続預金の払戻し制度を活用すべきか悩んでいる方や、デメリットが心配な人は専門家に相談しましょう。
相続プラスでは、預貯金の相続手続きに強い司法書士や弁護士の検索が可能です。悩みや所在地から検索できるため、ぜひ気軽に活用してくださいね。専門家に相談することで、納得のできる解決法が見つかるはずです。
地元の専門家をさがす


