婿養子なら義理の実家の財産も相続できる?婿養子は、義理の実家だけでなく自分の実家の遺産も相続できるというメリットがあります。しかし、婿養子と単なる婿は異なるなど注意しなればならない点もいくつかあるものです。この記事では、婿養子の相続について、基本から婿入りとの違いや具体的な相続割合など詳しく解説します。
目次開く
地元の専門家をさがす
婿養子の相続権
婿養子とは、妻との婚姻を結んだうえで、妻の両親とも養子縁組をしている人のことです。妻の両親と親子関係が生じるため、妻側の姓名を名乗ることになります。一般的には、妻側の家業を継ぐためや妻がひとりっ子・妻の苗字を保存するためなどで婿養子が選択されます。
また、婿養子になることで、相続時の立場も養子縁組を結んでいない夫の立場とは異なってくるのです。ここでは、婿養子の相続権について詳しくみていきましょう。
婿養子は妻の両親・実の両親の両方を相続できる
婿養子は、妻の両親との親子関係が生じるため、妻の両親の相続人になることが可能です。たとえば、被相続人Aの相続人が配偶者と子どもB・Cのときに、子どもBの配偶者DがAの婿養子になった場合、相続人は配偶者と子どもB・Cと婿養子Dとなります。
また、婿養子になることで実の両親との親子関係が断たれるわけではありません。婿養子になっても実の両親との親子関係はそのまま存続するため、実の両親で相続が発生すると婿養子になっても相続人になることができるのです。
なお、婿養子になる場合、一般的には妻の父・母両方と養子縁組を結びます。しかし、どちらか一方と養子縁組をした場合、養子縁組していない方の相続権は発生しない点には注意しましょう。仮に、妻の父だけと養子縁組している場合、妻の母の相続人にはなれないのです。
婿養子の相続分は実子と変わらない
「婿養子だから実子よりも割合が少ないのでは」と思っている方も多いでしょう。しかし、婿養子が妻の両親の相続人になる場合でも、実子と相続分が異なるということはありません。
たとえば、相続財産が1億円で、相続人が実子A・B・Cと婿養子Dの場合、均等に4等分した2500万円ずつがそれぞれの相続分となるのです。
このように、養子縁組することで婿養子は実子との兄弟姉妹の関係も生じます。ただし、養子縁組は養子になった人だけを取り込む制度です。
妻の両親の子ども(婿養子にとっての義理の兄弟姉妹)と、婿養子の実際の兄弟姉妹との間では兄弟姉妹の関係は発生しないので、実際の兄弟姉妹が妻側の相続に関係することはありません。
婿養子は遺留分請求・代襲相続もできる
遺留分とは、兄弟姉妹を除いた法定相続人に認められている最低限取得できる遺産のことです。
たとえば、遺言で相続人のうち1人にすべて相続させるとあっても、遺留分を持つ相続人は侵害された遺留分に相当する金銭を侵害した相続人に請求できます。婿養子も実子と同等の扱いとなるため、遺留分も実子同様に有します。
また、婿養子にも代襲相続で相続する権利、婿養子の子どもに代襲相続させる権利があります。仮に、妻の両親が妻の祖父母より先に亡くなり、その後祖父母がなくなれば、婿養子は代襲相続人として祖父母の遺産を相続できます。
反対に、自分がなくなった場合でも、自分の子に代襲相続させることが可能です。ただし、養子縁組で発生した相続権を代襲相続できるのは、養子縁組後に生まれた子である点には注意が必要です。連れ子のように養子縁組前の子は、妻の両親との血縁関係がないとみなされるので代襲相続できません。
相続における「婿入り」と「婿養子」には違いがある?
婿といっても「婿養子」と単なる「婿入り(婿)」では扱いが違う点には注意が必要です。
婿入りとは、妻側の姓を選んだ人のことを言います。妻の両親と養子縁組までしているわけではないので、たとえ同居していたとしても妻の両親の相続人になることはできません。
一方、婿養子は妻側の姓を名乗るだけでなく、妻の両親と養子縁組までしている人です。こちらは、たとえ別居していても妻の両親から見て子どもにあたるので、相続権を有します。
婿養子と婿入りの大まかな違いは以下の通りです。
| 婿養子 | 婿入り(婿) | |
|---|---|---|
| 姓 | 妻の姓 | 妻の姓 |
| 相続権 | ある | ない |
| 養子縁組 | している | していない |
| 相続税の2割加算 | 対象外 | 対象 |
相続税の2割加算とは、相続や遺贈で財産を受け取った人のうち特定の人は相続税が2割増しになる制度のことです。2割加算されるのは、配偶者でない人や被相続人の1親等の血族でない人(兄弟姉妹や第三者)、養子となった孫などが該当します。
婿の立場で遺言により相続した場合、2割加算の対象です。しかし、婿養子で相続した場合は2割加算の対象外となります。
婿入りする理由には、婿養子同様、妻の家業の後継者や妻がひとりっ子など、何かしら相続が絡む場合もあるでしょう。しかし、単なる婿の場合は相続権がないので、実際の相続時に婿入りした意図とは異なる相続になる可能性もあります。
婿になる理由が相続までかかわることを目的としているなら、婿養子の手続きまで必要という点は注意しましょう。
婿養子が妻の両親の遺産を相続できないケース
婿養子になれば必ずしも妻の両親の遺産を相続できるわけではありません。ここでは、婿養子が妻の両親の遺産を相続できないケースとして、以下の2つを解説します。
- 養子縁組を解消したケース
- 亡くなった人が遺言書を用意していたケース
養子縁組を解消したケース
養子縁組は、離縁することで解消します。離縁すると妻の両親との親子関係も消滅するため、妻の両親の相続が発生しても相続することはできません。離縁手続きは、妻の両親(養親)と婿養子が同意したうえで必要書類を揃えて役所に養子離縁届を提出することでできます。
反対に、もし妻と離婚した場合でも、離縁していなければ親子関係は存続するので相続人になることは可能です。とはいえ、離婚後にも親子関係のみ継続するとトラブルに発展しかねないので、離婚と同時に離縁手続きも行うのが一般的でしょう。
亡くなった人が遺言書を用意していたケース
相続では遺言書が優先されます。遺言書で婿養子に相続させない旨や特定の相続人のみに相続させる旨が記載されていれば、婿養子であっても相続できません。
ただし、婿養子であれば遺留分があります。遺留分を侵害する相続があれば、侵害分を請求できる点は覚えておきましょう。
「遺留分」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
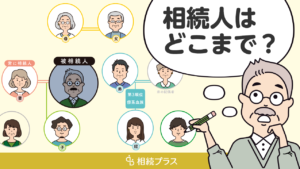
地元の専門家をさがす
婿養子が関わる相続の具体例

ここでは、婿養子が関わる相続の具体例として、妻の両親と実の両親が亡くなったパターンで相続の仕方を解説します。
妻の父親または母親が亡くなった場合
以下の条件で見てみましょう。
- 被相続人:妻の父親(養親)
- 相続財産:1億2000万円
- 相続人:配偶者・妻・妻の兄弟2人・婿養子
妻の父親が亡くなった場合、相続人となるのは配偶者とその子どもです。子どもには妻とその兄弟、婿養子の4人が該当します。
この場合の相続分は、配偶者が2分の1、子どもで残りの2分の1を均等に分けるので、婿養子を含めた子どもは8分の1ずつ相続し、以下のようになります。
- 配偶者:6000万円
- 妻:1500万円
- 妻の兄弟2人:それぞれ1500万円
- 婿養子:1500万円
一見すると、妻と婿養子の夫婦で3000万円の相続となり他の兄弟姉妹から見ると不公平なように感じます。しかし、相続は世帯単位ではなく子どもごとに発生するので、法律上問題ありません。とはいえ、妻夫婦が多く相続することに不公平感を抱く兄弟姉妹も少なくないでしょう。
また、婿養子がいなければ、妻と兄弟2人でそれぞれ2000万円ずつ相続できたことを考えると、本来の相続分よりも少なくなっているという点も、他の兄弟が不満を抱くことにつながります。
実の父親が亡くなった場合
一方、婿養子の実の親が亡くなったパターンはどうなのでしょう。以下の条件で相続分を計算します。
- 被相続人:婿養子の父親
- 相続財産:8000万円
- 相続人:配偶者・婿養子・子ども1人(婿養子の兄弟)
婿養子であっても、実の親の相続権を持つので通常の相続同様の相続割合で相続します。上記の場合、配偶者が2分の1、婿養子を含めた子ども2人で残りの2分の1を半分に分けるので、相続分は以下の通りです。
- 配偶者:4000万円
- 婿養子:2000万円
- 子ども:2000万円
婿養子になるかどうかは、実の親子関係での相続分に影響しません。しかし、妻側の両親の遺産を相続し、さらに実の両親の遺産も相続することに対して、他の相続人から不公平感を抱かれる恐れもある点は注意しましょう。
婿養子の相続に関する注意点
婿養子は、両方の相続ができるというメリットばかりではありません。婿養子の相続には、注意しなければならない点もいくつかあるので、以下のような注意点を押さえておくようにしましょう。
- 妻と離婚しても養子縁組は解消されない
- 負の財産を相続するリスクもある
- 妻の両親の扶養義務も生じる
- 実子との相続トラブルになる可能性がある
- 相続税の基礎控除に制限がある
妻と離婚しても養子縁組は解消されない
先述したように、養子縁組を解消するには離縁届が必要です。妻と離婚したからと言って自動的に養子縁組も解消されるわけではない点には注意しましょう。
負の財産を相続するリスクもある
相続財産は、必ずしもプラスの財産だけとは限りません。借金や未払金などマイナスの財産も相続の対象です。相続権を有するということは、これらのマイナスの財産を相続するリスクもある点には注意が必要です。
ただし、婿養子であっても相続放棄できます。妻の両親の遺産が明らかにマイナスが大きいといった場合は、相続放棄を検討するとよいでしょう。相続放棄は「相続開始があったことを知ったときから3か月」という手続きの期限があります。
相続放棄を検討している場合は、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
妻の両親の扶養義務も生じる
子には親を扶養する義務が法律によって定められています。扶養義務とは、経済的な支援を行う義務のことです。婿養子になり親子関係が生じれば、この扶養義務も生じます。
また、実の親の扶養義務はそのまま存続しているので、両方の親の扶養義務を負うことになるのです。両方の扶養義務を負うことで、経済的な負担が大きくなる可能性がある点は覚えておきましょう。
実子との相続トラブルになる可能性がある
婿養子の相続では、しばしば実子とのトラブルになるケースも少なくありません。先述したように、婿養子が相続人になることでその分実子が相続できる割合が少なくなります。さらに、婿養子夫婦が他の実子よりも多く相続することにもなるので、不公平感は大きくなります。
スムーズに相続するためには、養子縁組前に他の実子としっかり話し合っておくことが重要です。とはいえ、相続財産に大きな影響があるため話し合いもなかなか進まないというケースも少なくありません。そのような場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
相続税の基礎控除に制限がある
相続税の基礎控除は、以下の方法で計算されます。
相続税の基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の人数
この法定相続人の人数には養子も含まれるので、婿養子や孫を養子にするなど養子を増やして相続税の節税を検討している人もいるでしょう。
ただし、基礎控除に含められる養子の人数には、以下のような制限があります。
- 実子がいる場合:1人まで
- 実子がいない場合:2人まで
節税目的で養子縁組を利用する際には、養子の人数制限があることは覚えておきましょう。
「養子縁組の相続トラブル」や「相続問題」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。


婿養子の相続を検討しているなら弁護士に相談を
婿養子は妻の両親との親子関係が生じるため、妻の両親・実の両親の両方の相続人になれます。しかし、婿養子がいることで実子にとっては相続分が減るなど大きな影響がありトラブルに発展するケースも少なくありません。
このように婿養子の相続にはメリット・デメリットがあるので、そもそも婿養子がいいのか遺言がいいのかなど相続についてしっかり検討して進めることが大切です。
スムーズな相続を目指しているなら、他の実子とのトラブル対策や婿養子が適切かなど弁護士に相談してアドバイスをもらいながら進めるとよいでしょう。
地元の専門家をさがす


