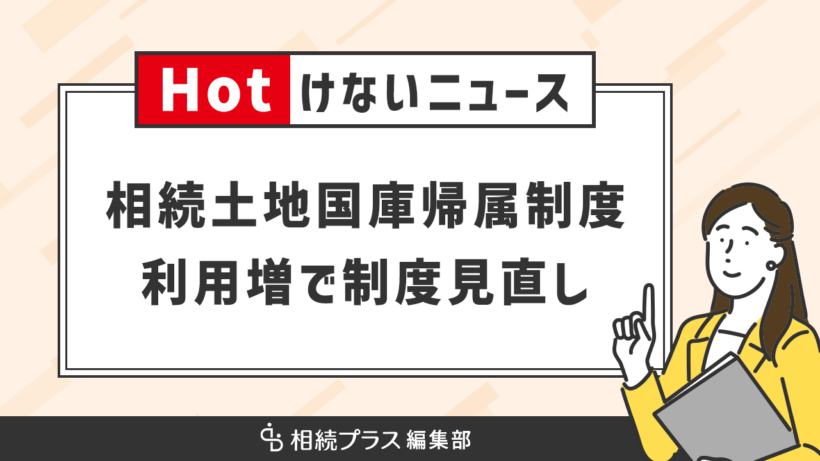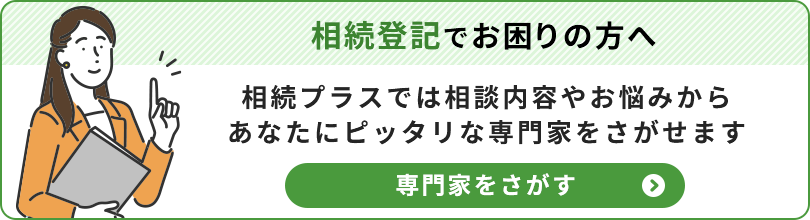相続などで取得した土地の所有権を国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」は、開始から2年が経過しました。利用件数は急増している一方で、国の管理費用の負担が深刻な課題となっています。財務省は、制度の柔軟化や見直しに向けて議論を始める方針です。
制度の利用件数が前年度比4.7倍に急増
相続した土地が遠方にある、土地の形状が悪い、あるいは売却先が見つからない、といった「管理困難土地」の問題が深刻化する中、令和5年4月に始まった「相続土地国庫帰属制度」への関心が高まっています。
この制度では、一定の条件を満たせば相続人などが不要な土地を国へ引き渡すことができ、令和5年度には258件だった利用申請件数が、令和6年度には1,229件とおよそ4.7倍に急増しました。
現場での費用・労力負担が課題となり、制度運用の見直しへ
利用件数が急増する中で、国が引き取った土地の管理コストが大きな課題として浮上しています。
国は土地を引き取る際、10年分の管理費相当として原則20万円の負担金を相続人に求めていますが、実際には草刈りや柵の設置、異物の撤去など、管理業務にかかる費用がこの負担金を上回るケースも少なくありません。
法務省によれば、負担金の金額は原則として、土地1筆につき面積に関係なく20万円とされています。そのため、例えば山林や雑種地などで管理が比較的容易な場合や、すでに整備が行き届いており、追加の管理がほとんど不要な場合でも、10年分として一律20万円の負担が求められます。こうしたケースでは、面積や実際の管理手間に対して負担金が割高となり、採算が合わないと感じる相続人も少なくないと考えられます。
財務省は「今後も引き取り件数が増加すれば、財政負担がさらに重くなる」として、土地の管理方法や売却条件の見直しを含め、制度全体の再検討を進めるとしています。
制度見直しは令和10年に本格化、今後の課題と方向性が焦点に
財務省は、令和10年の制度見直しに向け、近日中にも有識者を交えて議論を開始する予定です。議論の焦点は、管理業務の簡素化や売却時の価格設定ルールの緩和など、多岐にわたるとみられます。
特に民間への売却については、現在の基準では買い手がつかないケースも多いため、今後は市場価格に応じて柔軟に価格設定を変更できるよう、制度改正を進める方針です。
少子高齢化や都市部への人口集中により、今後も「利用予定のない土地を相続したくない」と考える人は増えていくとみられます。相続に関する制度設計は、個人の財産選択の自由と行政のコスト負担のバランスを、どのように取るかが重要な課題となっています。