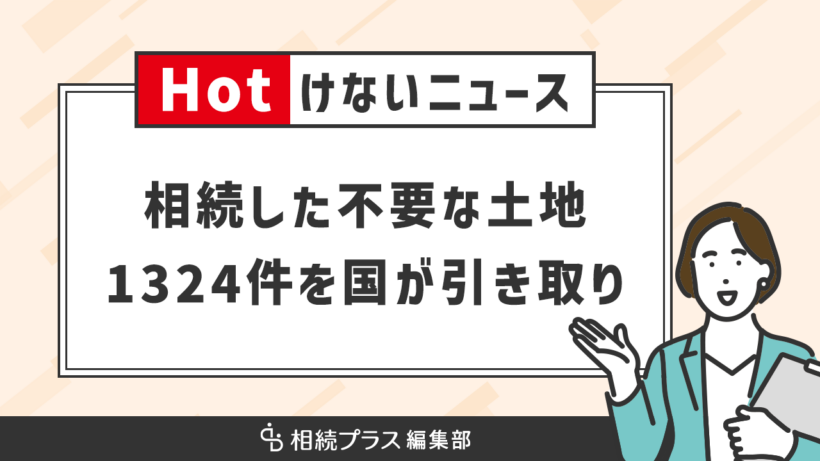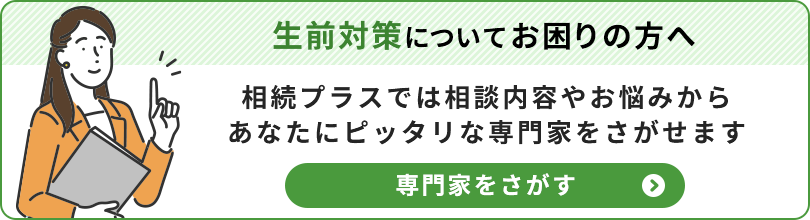相続や遺贈により取得した土地について、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらうことができる「相続土地国庫帰属制度」の利用実績に関する統計を、法務局が公開しました。令和5年4月にスタートしたばかりで利用状況がわかりにくい面もあった相続土地国庫帰属制度ですが、今回の統計では引き取り実績や却下・不承認の理由など、詳細な情報が公開されました。統計結果をもとに、相続土地国庫帰属制度の現状を読み解きます。
1324件が国に引き取り、却下・不承認の理由も公開
統計によると、制度がスタートした令和5年4月27日から令和7年1月までの間に、3343件の申請が行われました。そのうち1324件が受理され、既に国への引き取りがなされています。
申請の却下は52件・不承認は48件となっており、相続土地国庫帰属制度は申請できれば比較的承認されやすい制度と言えるでしょう。
申請が却下・不承認となった主な理由
申請が却下・不承認になったものについては、その理由も公開されています。
<却下となった主な理由>
- 添付書類の提出がなかった:32件
- 通路の用に供されている:11件
- 境界が明らかでない:7件
<不承認となった主な理由>
- 管理又は処分を阻害する工作物などがある:21件
- 国による追加の整備が必要:19件
- 国が管理に要する費用以外の金銭債務がある:6件
添付書類がなかったことを除くと、土地が制度の要件を満たしていないことが却下・不承認の原因の多くを占めていることがわかります。
相続土地国庫帰属制度は対象の土地にさまざまな要件が設定されているので、制度の活用を検討している方は事前に要件を満たしているかチェックしておきましょう。要件は法務省のホームページで公開されていますが、要件を満たしているか不安な方は司法書士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
引き取られた土地は田・畑が最多、宅地もほぼ同数の実績
統計では引き取りされた1324件について、地目別の内訳も公開されています。
<引き取られた土地の地目>
- 田・畑:1258件(38%)
- 宅地:1188件(35%)
- 山林:520件(16%)
- その他:377件(11%)
用途が限られる田・畑が38%と最多ですが、宅地も35%とほぼ同程度の引き取りがなされており、幅広い種類の土地が引き取られていることがわかります。
有効活用が決まり申請が取り下げられたケースも多数
統計では申請の取り下げ件数も公開されており、その数は511件にのぼります。取り下げの理由には以下のように、相続土地国庫帰属制度とは別の制度・利用者による有効活用も含まれており、法務省は取り下げのおよそ半数が有効活用が実現したものと公表しています。
<取り下げの主な理由>
- 自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した
- 隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった
- 農業委員会の調整などにより農地として活用される見込みとなった
- 審査の途中で却下、不承認相当であることが判明した
相続土地国庫帰属制度は、制度の運用を通じて自治体や農業委員会による有効活用を促進することも目的としています。取り下げ件数からも、有効活用の促進に一定の効果をあげていることがうかがえます。
こうした有効活用の場合、相続土地国庫帰属制度の負担金は不要になるため、利用者にとってはより効果的な活用が実現したと言えるでしょう。
相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリット
相続土地国庫帰属制度は、活用に困る土地を国に引き取ってもらうことができる便利な制度ですが、対象に要件が設けられていたり負担金が発生したりといったデメリットも存在します。
<相続土地国庫帰属制度のメリット>
- 買い手や借り手が見つかりにくい土地でも引き取ってもらえる
- 農地や山林といった用途が限られる土地も対象になる
- 維持管理の手間がかからない
<相続土地国庫帰属制度のデメリット>
- 要件を満たさなければ活用できない
- 1筆1万4000円の審査料や原則20万円の負担金が発生する
- 引き渡しまでの申請手続きが大変
また、活用に困る土地を相続しないようにすることが目的であれば、相続放棄を活用したり生前のうちに売却したりといった選択肢も検討できます。それぞれメリット・デメリットがあるため、どの方法が自分に適しているのかしっかり検討することが重要です。

活用に困る土地を相続する可能性がある方は、早い段階での対策が大事
相続土地国庫帰属制度は令和5年4月にスタートしたばかりの新しい制度ですが、今回の統計から制度が着実に活用されていることがわかりました。申請できれば受理されやすい手続きであること、申請後に他の使用者による有効活用が決まるケースもあることが読み取れるため、活用に困る土地を相続する際の対処法として、十分に検討の余地がある制度だと言えるでしょう。
活用にあたってはメリット・デメリットを整理し、相続放棄や生前の売却など他の手段も考慮することが重要になってきます。しかし、相続放棄には相続発生から3か月という期限があり、生前の売却のためには相続が発生する前から動かなければなりません。
どの方法が最も適しているのか検討するためには、できるだけ早い段階で相続対策をはじめる必要があります。活用に困る土地を相続する可能性がある方は、とれる選択肢が多いうちに相続対策をはじめることをおすすめします。